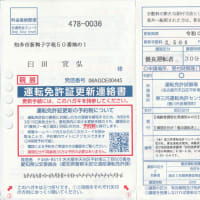教会の聖書日課に基づき、コヘレトの言葉10章を読みます。
10章10節~11章6節は災難について書かれています。ところで、災難には一般に「人災と天災」があるわけでして、コヘレトがそこまで考えていたかどうかは分かりませんが、この2つを分別して読み取っていくと分かりやすいのではないかと思います。10章10~18節は人災に関することと見て、その次の10章19節~11章6節は天災に関することと見るとよいのではないかと思います。
10 なまった斧(おの)を研いでおけば力が要らない。知恵を備えておけば利益がある。11 呪文も唱えぬ先に蛇がかみつけば、呪術師には何の利益もない。12 賢者の口の言葉は恵み。愚者の唇は彼自身を呑(の)み込む。13 愚者はたわ言をもって口を開き、うわ言をもって口を閉ざす。14 愚者は口数が多い。未来のことはだれにも分からない。死後どうなるのか、誰が教えてくれよう。15 愚者は労苦してみたところで疲れるだけだ。都に行く道さえ知らないのだから。16 いかに不幸なことか、王が召し使いのようで、役人らが朝から食い散らしている国よ。17 いかに幸いなことか、王が高貴な生まれで、役人らがしかるべきときに食事をし、決して酔わず、力に満ちている国よ。18 両手が垂れていれば家は漏り、両腕が怠惰なら梁(はり)は落ちる。
「なまった斧を研いでおけば力が要らない」(10節前半)というのは、歯車が合っているということと同じです。歯車が合っていれば力は出さずにも隣の軸は回転します。それと同じように斧も研いであるならば力を出さずに済む。「知恵を備えておけば利益がある」(10節後半)は、知恵も備えてうまく使うならば、研いである斧のようにうまく使うことができるということです。「業と道理と知識と知恵」を用いているのです。しかし「呪文も唱えぬ先に蛇がかみつけば、呪術師には何の利益もない」(11節)ということが起こります。これは10節を受けて、蛇使いの魔術師が、その技能をうまく使えずに、蛇に噛まれることを言っています。そうしますと、技能をうまく使えない蛇使いが蛇に噛まれるということは、「人災」であるということになります。
「賢者の口の言葉は恵み。愚者の唇は彼自身を呑み込む。愚者はたわ言をもって口を開き、うわ言をもって口を閉ざす。愚者は口数が多い」(12~13節)は、失言についてのことです。私もよく失言をしますが、失言は本当に損です。失言による災難はまさに「人災」です。
「愚者は口数が多い。未来のことはだれにも分からない。死後どうなるのか、誰が教えてくれよう。愚者は労苦してみたところで疲れるだけだ。都に行く道さえ知らないのだから」(14~15節)。未来のことは分からないというのは、コヘレトが繰り返して言ってきたことです。ここではそれが、愚者の言葉とされています。そして愚者の愚者は「未来が分かる」と言っているということでしょう。「未来が分かる」と発言する、愚者のその苦労は疲れるだけだと言います。これもまた「人災」の一つです。
そして次に人災の典型のようなことと、その反対のことが語られています。「いかに不幸なことか、王が召し使いのようで、役人らが朝から食い散らしている国よ。いかに幸いなことか、王が高貴な生まれで、役人らがしかるべきときに食事をし、決して酔わず、力に満ちている国よ」(17~18節)。ここでは不幸と幸いが対置されています。「王が召し使いのようで」というのは、王に統制する力がないということでしょう。だから役人が朝から食い散らかしているのです。それは昼間から酔っているということでしょう。統治の空白が起きているのです。それはまさに「人災」です。18節は逆の賢い王と役人のことが示されていて、それは力に満ちた幸いな国であるとされています。「業と道理と知識と知恵」が、適切に用いられているということでありましょう。この記述によって、17節の災難に遭っている国の人々が、対照的に浮かび上がってきます。
「両手が垂れていれば家は漏り、両腕が怠惰なら梁は落ちる」(18節)というのは、家の管理のことです。両手が垂れているように、両腕が怠惰なように、管理者が働かずにいれば、家も修理をすることができず壊れていくということです。これも「人災」です。
このように、10章10~18節は人災について記されています。聖書に「人災について」記されているのは興味深いことです。
*クリスチャントゥデイのコラム「コヘレト書を読む」をお読みいただければ幸いです。