NISAに意外な落とし穴、株高持続へ是正急務
編集委員 前田昌孝
- 2013/7/3 6:00日本経済新聞
株式を買った後に思惑が外れて値下がりしたら、塩漬けにしてしまう個人投資家も多い。何年か後に運良く買値に戻ってきたら、損得ゼロで売却するのを「やれやれの売り」と呼ぶことがある。ところが、来年から始まる少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)を活用して株式を売買すると、「やれやれの売り」で利益はゼロなのに、なぜか課税されることがある。株高を持続させるには、NISAのこんな落とし穴を埋める必要がありそうだ。
NISAはよく英国のISA(個人貯蓄口座)の日本版と呼ばれるが、似て非なるところがある。年間投資可能額が100万円と、英国の約170万円に比べて低い点は、まあいいとしよう。大きな違いは、英国ではいったん非課税口座を通じて株式や投資信託を購入すれば、売却益や配当、分配金が無期限で非課税扱いになることと、途中で別の株式や投信への乗り換えが認められていることだ。
日本では非課税扱いは買った年の5年目の年末まで。しかも、最初に買った株式や投信を売却(あるいは解約)すれば、その時点で非課税扱いは打ち切られる。買った後に株価や基準価格が下落し、塩漬けにしてしまった株式や投資信託も、5年目の年末が来たら、(1)NISAの外に出す(2)6年目のNISAの上限100万円の枠を使って非課税のまま持ち続ける――の選択をしなければならない。
問題はNISA外の特定口座や一般口座に移すにしても、6年目のNISAの枠を使うにしても、移管先の口座での取得価格が移管時の時価になることだ。この結果、投資家には、損をしているのに課税されるという理解しがたいことが起きる。過去の日経平均の値動きを使って、中長期投資を心掛けている人がおかしな状況に追い込まれないか、シミュレーションしてみた。
例えば、ドルコスト平均法という長期投資向けの方法で毎月8万円ずつ日経平均連動株を購入し、10年後にまとめて売却すると仮定する。図はバブルの崩壊が始まった90年1月からこの投資を始めた場合を示している。1年目(90年)には合計96万円(8万円×12カ月)を投資すると、約34株が取得できる。これが95年には66万円(94年末の日経平均1万9723円で評価)を取得価格として特定口座に移管される。
同様に2年目に取得した約39株は96年に78万円(95年末の日経平均1万9868円で評価)で買ったとみなされて特定口座に移る。3~5年目に取得した株式も図のように評価されて特定口座に移る。特定口座に移った合計225株の税制上の取得価格は合計390万円(66+78+102+77+67)だ。99年末に売却した場合、売却代金425万円(64+75+99+96+92)との差額35万円弱が課税対象となり、7万円強(税率は20.315%)の税金が徴収される。
投資家の現実の損益は、総取得株数499株に99年末の日経平均1万8934円を掛けた945万円の売却代金から、投資額の960万円(8万円×120カ月)を引くから、約15万円の損失だ。この投資家はバブル崩壊後という難しい局面にもかかわらず、等金額投資を続け、それでも残念ながら15万円ほどの損失が出たのに、税制上は35万円弱の利益が出たと見なされ、7万円強を徴税されてしまう。
もし14年1月から10年間の株価動向が90年1月からの10年間と同じならば、この事例と同じことが起きよう。実は似たようなことは、向こう10年間の株価動向が86~87年からの10年間をなぞった場合でも、発生する。銘柄分散、時間分散という最も健全な資産形成に取り組んでいるにもかかわらず、陥るかもしれないNISAの大きな落とし穴といえそうだ。
もっと単純に、1年目の大発会で日経平均連動株をNISA口座で100万円分購入して5年後に特定口座に移し、10年目の年末に売却した場合も想定してみよう。図に示すように、この10年間の日経平均の動きが98年1月からの10年間と同じならば、差し引きで2万3000円の利益が出る。ところが、税制上は約45万円の売却益が出たと見なされ、9万1000円を課税される。税引き後では6万8000円の赤字になってしまう。同様の不都合は向こう10年間の株価の足取りが95~98年から10年間と同じようならば、発生する。
日経平均を使って試算しても不都合が起きるくらいだから、もっと値動きが激しい個別株を使って分析すれば、「利益なき課税」が頻発するだろう。相続時も同様の扱いだから、親がNISA口座で買った株式が相続時に値下がりしていて、子が特定口座などで受け入れた場合には、親の買値よりも低い株価で売却しても、利益が出たと見なされて課税されてしまう。
こうした不都合は投資家が理解しにくいというだけでなく、所得のないところに所得税を課す点で合理的とは言えないし、憲法が保障する財産権の侵害に当たるかもしれない。不都合をなくすためには、NISAから外に出すときの移管価格は「最初の取得価格または移管時の時価の高いほう」とする必要がありそうだ。
もちろん徴税側の理屈もある。値下がりした銘柄を課税口座に移管するときに、最初の買値を取得価格にできるのならば、すぐに売却して損失を出し、他の売却益が出ている銘柄と損益を通算することで、税負担を減らせるからだ。「NISAで売却損が出ても税制上はないものと見なす」という原則が崩れるともいえる。しかし、投資家が現実に課税された場合の違和感を思えば、何らかの修正は必要だろう。
もう1つ、NISAを通じて買った株式や株式投信を換金したら、非課税扱いは終わりというルールも再考すべきではないか。英国では口座からお金を引き出さない限り、別の銘柄へのスイッチングを認めている。日本では当該年の非課税枠が残っていて、これを使って別の銘柄を買うのならばもちろんOKだが、これは新たな買い付けであって乗り換えではない。
乗り換えを認めると、証券会社が手数料稼ぎのために過当勧誘に走りがちなことを懸念しているのかもしれないが、グラフに示すように、個人投資家の株式売買の大半はインターネット経由だ。売買の頻度も個々の投資家が自らの判断で決めているのだから、税制が「望ましい株式売買のあり方」を押しつける必要はないだろう。
現行の「売却したら非課税は終わり」というルールだと、NISAで株式を買おうと思っている個人は同じ100万円を14年に1回、15年に1回、16年に1回という具合に繰り返し使うだけで、株式の保有残高を増やそうとはしないだろう。むしろ、口座からお金を引き出さない限り、乗り換えは自由というルールにしておけば、毎年新たに100万円を株式投資に振り向ける人が増える可能性がある。
先物主導で外国人投資家ばかりに振り回される状況を卒業し、業績や事業戦略の巧拙など個別銘柄のファンダメンタルズがもっと株価に反映するような躍動感のある株式市場を構築するには、個人マネーの流入が欠かせない。NISAが対象とするような若い社会人が、個別企業の投資価値の分析などに詳しくなることは、日本経済の基礎体力の強化にもつながろう。長期にわたる株高を戦略的に実現したいのならば、NISAを通じた個別株投資の利便性向上は、有効な政策だ。
振り返れば、今年も前半戦は終わった。世界の株式市場を見渡すと、株価指数の年初来上昇率が10%以上だったのはグラフに掲げた21市場だ。日本は今のところ第4位。ただ、首位のベネズエラはハイパーインフレ の抑制がきかなくなっており、ドバイやクウェートはまだバブル崩壊後の調整局面が続いている。市場の規模などを考えても、東京市場が今年前半の世界の株式相場をリードしたといっていい。
後半戦でもリードが続くかどうか。NISAへの期待だけでは当然、力不足だが、法人税 減税も含め、財務省もアベノミクスの成長戦略に足並みをそろえれば、思いのほか強い相場が実現するかもしれない。
NISA 非課税の恩恵逃さない基礎知識(30日 7:00)
- 夫婦で2倍の税制メリット NISAとは(20日 7:00)
- 豊かな老後 「確定拠出年金」フル活用(27日 7:00)
- 非課税制度「NISA」、予約150万件(19日 1:03)
- 確定拠出年金が投資に有利?(15日 3:30)
- 日本版ISA、本格普及に立ちはだかる「壁」(9日 23:00)














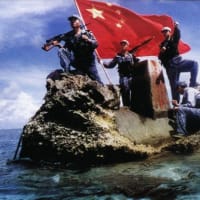
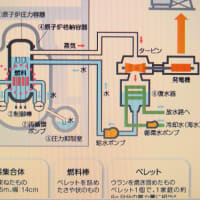
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます