経営理念の浸透段階の最後である”実践・実現”について述べる前に、その要である「事業計画書」について今日は取り上げます。
皆さんの社会福祉法人や株式会社にも事業計画書を毎年策定し、事業経営やサービスの質の向上に日々お取り組みのことと思います。
しかし、皆さんの法人や施設の事業計画書は以下のような状態になっていませんか?
・年度だけ更新し、毎年内容が同じ
・”事業”の計画書ではなく、”行事”の計画書になっている
・単年度の行動内容が中心で、中長期的な視点の行動内容が十分ではない
・達成目標や達成期日、担当責任者等が明確になっていない
・事業計画書を作成したことに満足してしまい、実際に運用できていない
・進捗管理が十分ではなく、達成目標や達成期日の概念があいまい
・経営層で作成しているため、職員が事業計画書を知らない
などなど。
挙げ始めるとキリがありませんが、1つでも該当する場合は、事業計画書をより戦略的なツールとして活用するための改善が必要です。
経営理念が法人や施設が目指す”目的地”であると例えるならば、事業計画書はそこへ向かうための”地図”といえます。
その地図が、世界地図のような全てを見渡せるような縮尺であれば、職員はあっちからも、こっちからも、そっちからも行けてしまう状態(行動の統一を図れない状態)を引き起こしかねません。
その一方、〇〇町△△番地□号のようなピンポイントの縮尺であれば、職員はその先どちらに進んでよいか、先を見据えて進むことができない状態(組織のビジョンや方向性の不透明さに対する不安・不満を抱く状態)となってしまいます。
また、古い地図ばかり見ていては、利用者ニーズに応えるサービス提供が遅れ、結果的に社会資源として地域社会から認められることはないでしょう(古い旅行雑誌を見ながら観光して、行きたいお店がなくなっていた時の気持ちはお分かり頂けると思います)。
そうならないためにも、事業計画書に経営理念を実現するための具体的な行動内容を落とし込むこと、また法人や施設の3年、5年後の”ありたい姿(あるべき姿)”を示し、それに向けて1年目、2年目、3年目・・・と取り組みを積み上げ、目的地に近づいていくことが重要となります。
そのように事業計画書を一般職員も参加しながら作成していけば、おのずと年度だけ変更したり、達成目標が欠けたり、進捗管理が不十分といった状態にはならないでしょう。
なぜならば、事業計画書はいわば法人や施設のケアプランと例えることができます。
ある利用者の抱える生活課題を多職種連携で解決できるよう取り組むための指南書(地図)がケアプランです。
定期的にカンファレンスを開いてモニタリングを行い、長期・短期目標のサービス内容をの達成状況を評価します。
”達成”であれば、新たな生活課題についてサービス内容を追加することになるでしょう。
”未達”であれば、その生活課題をクリアするために、違ったアプローチやサービス内容の見直しが必要になります。
このようなケアマネジメントサイクルは、PDCAサイクルで運用しています。
事業計画書もまたこのPDCAサイクルに沿って運用されています。
事業計画書と聞くと、馴染みのない”言葉”ということで拒否反応を起こす職員もいますが、実はすでにケアマネジメントで実践しているわけです。
法人や施設の3年後、5年後どのくらいのサービス水準を目指すか、どういった組織作りをしていきたいか、地域にはどのような存在感を示すことができるかなど、職員一人ひとりが経営理念を実現するために、社会資源の一つとして、どんな役割を果たしていく必要があるのかを考えることで(経営理念を”理解・納得”している状態が求められます)、優先順位をつけて行動内容が導き出されます。
皆さんの法人や施設の事業計画書が戦略的なツールとして使いものになる”地図”となっているか、改めて確認してみましょう。
管理人
皆さんの社会福祉法人や株式会社にも事業計画書を毎年策定し、事業経営やサービスの質の向上に日々お取り組みのことと思います。
しかし、皆さんの法人や施設の事業計画書は以下のような状態になっていませんか?
・年度だけ更新し、毎年内容が同じ
・”事業”の計画書ではなく、”行事”の計画書になっている
・単年度の行動内容が中心で、中長期的な視点の行動内容が十分ではない
・達成目標や達成期日、担当責任者等が明確になっていない
・事業計画書を作成したことに満足してしまい、実際に運用できていない
・進捗管理が十分ではなく、達成目標や達成期日の概念があいまい
・経営層で作成しているため、職員が事業計画書を知らない
などなど。
挙げ始めるとキリがありませんが、1つでも該当する場合は、事業計画書をより戦略的なツールとして活用するための改善が必要です。
経営理念が法人や施設が目指す”目的地”であると例えるならば、事業計画書はそこへ向かうための”地図”といえます。
その地図が、世界地図のような全てを見渡せるような縮尺であれば、職員はあっちからも、こっちからも、そっちからも行けてしまう状態(行動の統一を図れない状態)を引き起こしかねません。
その一方、〇〇町△△番地□号のようなピンポイントの縮尺であれば、職員はその先どちらに進んでよいか、先を見据えて進むことができない状態(組織のビジョンや方向性の不透明さに対する不安・不満を抱く状態)となってしまいます。
また、古い地図ばかり見ていては、利用者ニーズに応えるサービス提供が遅れ、結果的に社会資源として地域社会から認められることはないでしょう(古い旅行雑誌を見ながら観光して、行きたいお店がなくなっていた時の気持ちはお分かり頂けると思います)。
そうならないためにも、事業計画書に経営理念を実現するための具体的な行動内容を落とし込むこと、また法人や施設の3年、5年後の”ありたい姿(あるべき姿)”を示し、それに向けて1年目、2年目、3年目・・・と取り組みを積み上げ、目的地に近づいていくことが重要となります。
そのように事業計画書を一般職員も参加しながら作成していけば、おのずと年度だけ変更したり、達成目標が欠けたり、進捗管理が不十分といった状態にはならないでしょう。
なぜならば、事業計画書はいわば法人や施設のケアプランと例えることができます。
ある利用者の抱える生活課題を多職種連携で解決できるよう取り組むための指南書(地図)がケアプランです。
定期的にカンファレンスを開いてモニタリングを行い、長期・短期目標のサービス内容をの達成状況を評価します。
”達成”であれば、新たな生活課題についてサービス内容を追加することになるでしょう。
”未達”であれば、その生活課題をクリアするために、違ったアプローチやサービス内容の見直しが必要になります。
このようなケアマネジメントサイクルは、PDCAサイクルで運用しています。
事業計画書もまたこのPDCAサイクルに沿って運用されています。
事業計画書と聞くと、馴染みのない”言葉”ということで拒否反応を起こす職員もいますが、実はすでにケアマネジメントで実践しているわけです。
法人や施設の3年後、5年後どのくらいのサービス水準を目指すか、どういった組織作りをしていきたいか、地域にはどのような存在感を示すことができるかなど、職員一人ひとりが経営理念を実現するために、社会資源の一つとして、どんな役割を果たしていく必要があるのかを考えることで(経営理念を”理解・納得”している状態が求められます)、優先順位をつけて行動内容が導き出されます。
皆さんの法人や施設の事業計画書が戦略的なツールとして使いものになる”地図”となっているか、改めて確認してみましょう。
管理人










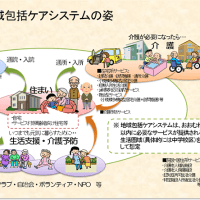
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます