
6月になると。
茶の稽古場では、主菓子として「水無月」が出てくるように。
御用達の和菓子屋のが、これまた絶品で。
社中一同、6月の巡ってくるのをお楽しみにしているくらい。
今日は、その「水無月」から、少し書いてみたい。
---
●和菓子「水無月」の由来
六月末日ともなると。
一年の半分は過ぎたことになりますね。
ひとつの節目だ。
そんなその日は、古来、「夏越の祓(なごしのはらえ)」の日。
「夏越の祓」とは、半年無事に過ごせた感謝と、盛夏を迎えて疫病災難から逃れたいと言う願いを込めた、禊(みそぎ)の行事。
各神社では、人々は、名前を書いた紙の人形を水に流したり、茅(ち)の輪をくぐったりして、穢れを祓い、身を清めた。
また、この日には、氷室から宮中に氷が献上され、その氷は、食べると夏痩せしないと言われた。
庶民はそれに倣い、氷を表す三角形の餅生地の上に、悪魔払いを表す小豆をのせた「水無月」というお菓子を食べるようになる。
それが、今に伝わる和菓子「水無月」の由来、という訳。
「水無月」は、涼を求め、無病息災を願う、盛夏の風物詩なんだなあ。
●新暦と旧暦の違い
さて。
6月末日の「夏越の祓え」は盛夏の禊ぎ、
水無月は盛夏の和菓子、
と書いたけれど。
どうも実感が湧かないひとも?
6月は入梅前後のひと月だから?
その辺を納得するには、その感じを感じ入るには。
暦の知識が不可欠。
新暦と旧暦を、上手に読むこと…。
○新暦
明治5年以降、現代に至るまで、日本でも用いられている。
正しくはグレゴリウス暦という。
中世ヨーロッパで、太陽の運行を基準に作られた太陽暦。
もともとの制定の目的は、キリスト教の神事を毎年狂いなく行うことであった。
閏年は、4年に一度、一日加えるだけ、と誤差が少なく、一年が正確に刻まれることがポイント。
○旧暦
明治初期以前に、長い間日本の暮らしの中で用いられたもの。
主に月(太陰)の運行を基準に作られた、太陰太陽暦。
中国伝来の手法を用いながら、日本で制定・改変されたもの。
新月(=朔)を1日とする。
月名と季節がずれないようにするためおよそ3年弱毎に、1年を13ヶ月にする必要がある。この余分な1月を閏月(うるうづき)と呼ぶ。
日本の風土・自然・四季と共に巡る暦といえる。
古来、日本の年中行事は、この旧暦に従って行われたもので、行事本来の意味・季節感を理解するためには、
新暦でなく、旧暦を用いて月日を捉える必要があるといえる。
●「水無月」・「夏越の祓」と、新暦・旧暦
「水無月」とは、6月だけれど。
新暦と旧暦とでは、ほぼ1ヶ月のズレがある。
そのズレをよく理解することが、日本の季節を読み解く鍵ともいえる。
「夏越の祓」は、6月の末日というけれど。
新暦の6月30日は。
梅雨の真っ最中。
それほど暑くはない。
旧暦の6月29日(太陰暦では、新月から新月の間がひと月なので、29日か30日間であることが多い)は。
新暦の7月24日に当たる。
いわゆる“梅雨明け十日”の、夏空の続く頃。
まさしく盛夏。
「夏越の祓」をするに、ふさわしい頃。
●水無月を知るのには、旧暦が必要
上記のように。
和菓子「水無月」の“水無月”とは“旧暦の水無月”だ、ということが、ここまで来るとわかるはず。
新暦ではなく、旧暦を知り、
日本古来の文化を深く知ってこそ、
日本文化が根ざしてきた、巡る季節というものを、深く感じてこそ、
和菓子「水無月」も、一層美味しく、より深く楽しめるのでは…?
これは、和菓子・茶道・伝統行事といったことに限らず、
私たち日本人の暮らし・生き方にも、多くの示唆をもつのでは…?
●まとめ:月をみよう
だから。
まずは。
月をみよう。
月の満ち欠けを気にかけてみよう。
まずは、そこからはじめること。
それは、すぐにでも出来ること。
月とつながる、ということ。
そんな簡単なことが。
私たちと日本を、
私たちと季節を、
私たちと自然を、
私たちと宇宙を、
つないでくれるのだから…。
●ちなみに…
今は、月が満ちてゆく頃。
日に日に膨らんでいくお月さまが、雨の合間に、見えるかな?
今日、新暦6月30日は、旧暦では、水無月も初めの五日…。
---
…という訳で。
今日は、「水無月」と、新暦・旧暦について、長々書きました。
ご参考になれば幸い。
ならなければ、全て忘れてください。
いずれにしても。
皆様、美しい日本の季節を存分に楽しんで、よい日日をお過ごし下さい。
kuu
追記:
茶の稽古場では。
新暦の6月が終わると、茶席に「水無月」は出てこない。
例の和菓子屋でも、“新暦の”「6月限定」で水無月を作っているから。
なので。
上記のように、本来の意味で「水無月」がふさわしい、旧暦水無月末日、“梅雨明け十日”の盛夏の頃には、「水無月」は手に入らないこともある。
なんてこった!
昨今、茶を嗜むひとや茶菓子屋さんに、旧暦に無頓着なひとがあまりに多いことは、
僕には信じがたいし、また、心底残念に思うなあ…。
僕個人は、茶道に関する行事は、全て、旧暦(と「二十四節気」、そしてその年の季節そのもの)にのっとって、期日を決めて、執り行うのがよい、と考えています。
茶人よ。
夜空をみあげ、月をさがせ!!!
関連記事:
旧暦水無月ついたち ~ 「氷の節句」
亥の月亥の日 炉開き 口切茶事 柚子の色付く頃
柚子の色付く頃 ~ 利休さんの教え (炉開き・口切・亥の子餅)
【カテゴリ】「日月(じつげつ)~旧暦・二十四節気を旅する」とは?
★美しい日本の私












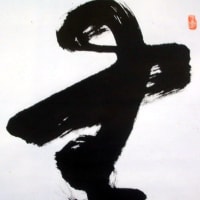







旧暦バージョン(^^)で、また来月も作ろうと思います♪
いいですねえ、水無月。
で、また。
旧暦六月末日にも水無月、ってのがいいですねえ。
きっと、今日より、美味しいのでは???
よい夏の日を。
自然のわずかな変化で季節の移ろいを感じていた子どものころが懐かしくなりました。
これからでも遅くないですよね。お月様と友達になることにします。
コメント、ありがとうございました。
>新暦と旧暦、そうだったんですか。
知って、使って、感じ入ると、面白くなってきます。
ご参考ページ:
「日月(じつげつ)~旧暦・二十四節気を旅する」とは?
http://blog.goo.ne.jp/so-kuu/e/b3488c3b16340888eb82748210b93f51
>自然のわずかな変化で季節の移ろいを感じていた子どものころが懐かしくなりました。
暦も便利ですが。
まずは、季節そのものを肌で感じることこそ大切ですね。
お茶においてもそうありたい、と常々思っています。
>これからでも遅くないですよね。
>お月様と友達になることにします。
もちろん!
お月さんは、いつも空にあります。
今夜は、見えません。。。
>月は、毎晩見上げています。
月のみえない晩も月をみあげる。
それもまた楽し、ですね。