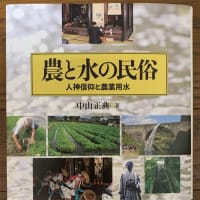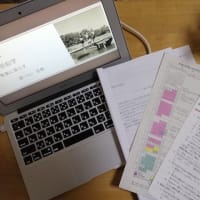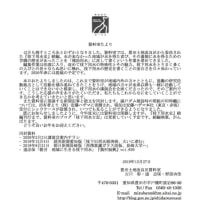今日は豊田市立西広瀬小学校にお願いしたいことがあり、初めてのことだったので、枝下町高齢者クラブ会長のKさんが連絡をとってくださり、Kさん、野原、逵で西広瀬小学校に伺いました。

西広瀬小学校は13年前、私が矢作川研究所に入ったとき、すぐに話を聞きました。高度経済成長期、矢作川白濁の時代に、毎朝矢作川・飯野川の水を汲んで、西広瀬小学校の子どもたちが水質測定を始めたのです。『枝下用水史』の年表にも1976(昭和51)年7月の項にこのことを記しています。この活動は矢作川がきれいになっても続いていて、今日は16,057日目でした。
今日が何日目か、そして今日の透視度はどれだけだったか、県道153号線を走って西広瀬小学校を通るとわかるようになっています。
これまでぜひ一度訪ねてみたいと思っていたのですが、その機会がなく、今日ようやく実限することができました。校長・Sさんは月末の矢作川水質測定16,000日達成記念式典の準備で、ちょうど小学校の紹介パワーポイントを作成しているところだったと見せてくださいました。私はこれまで西広瀬小学校が水質調査をしていることは知っていましたが、他にもそれぞれ担当学年を決めて、地域の自然から学んでいることを、今回初めて知りました。せっかくなのでその取り組みを見せていただくことにしました。
私はこの掲示板の文字が全て発泡スチロールカッターで切りぬかれていることにおどろきました。これはぜひまねしてみたいと思い、作り方をくわしく教えていただきました。

まず案内いただいたのは、ムササビの生態調査でした。今は巣立っていて見ることができなかったのですが、背の高い木にカメラを取り付け、遠隔で観察しているのでした。

校長先生が案内してくださいました。
校門の近くには矢作川のミニ水族館がありました。こちらは4年生担当です。

ウサギ小屋を改修した、丸根山ビオトープを紹介する生命館を見せていただきました。こちらは5年生担当とのこと、動物クイズが貼り出してありました。

そして矢作川の透視度を検査する「清流の塔」へ。6年生の朝の作業だそうです。


窓から今日は57センチと表示していました。
1学年わずか10人ほどの子どもたちが、4年生になったら、5年生になったら、6年生になったらと上の学年の子たちから引き継いで取り組んでいく。そんな姿があったことを初めて知りました。
今日一緒に行っていただいたKさんからは、枝下町の小学生に枝下用水の話をする日を作ってねと言われています。これまで小学生にと言われてどうしたらいいのかわかりませんでしたが、こういう取り組みをしている子どもたちなんだと知ることができて、ちょっと楽しみになってきました。