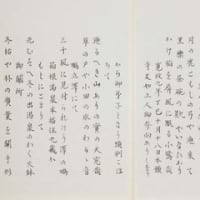(茅舎追想その二十一)茅舎と麦南そして武者小路実篤
川端茅舎の幼なじみの無二の親友に「雲母」の主要俳人の西島麦南がいる。麦南の簡単なプロフィールは次のとおりである。
西島麦南 (にしじま-ばくなん)
明治二十八年(1895)~昭和五十六年(1981) 大正-昭和時代の俳人。
明治二十八年一月十日生まれ。武者小路実篤(むしゃのこうじ-さねあつ)の「新しき村」で開拓に従事。大正十三年岩波書店に入社,「校正の神様」とよばれ、昭和四十年文化人間賞受賞。俳句は飯田蛇笏(だこつ)に師事、傾倒し、みずから「生涯山廬(さんろ)(蛇笏)門弟子」と称した。昭和五十六年十月十一日死去。八十六歳。熊本県出身。本名は九州男(くすお)。句集に「金剛纂(こんごうさん)」「人音(じんおん)」。
【代表句など】炎天や死ねば離るゝ影法師
この麦南について、飯田蛇笏の亡き後「雲母」の主宰者となった飯田龍太は次のとおり記している。
http://white.ap.teacup.com/cyamicat2/187.html
[岩波書店に永年勤め、“校正の神様”といわれた西島麥南さんが、去る十月(昭和五十六年)十一日のおひる過ぎ、鎌倉由比ヶ浜の自宅で亡くなった。行年八十六歳と九カ月。……
本名九州男。明治二十八年、田原坂の古戦場にほど近い肥後植木に生まれ、句集の自序に「生涯山盧門弟子」と記したように、俳句は蛇笏門に終始したが、岸田劉生に私淑して画家をこころざし、あるいは大正七年、武者小路実篤らの「新しき村」の創設に参加したり、ときに小説家として身をたてようと志したときもあったようだが、岩波茂雄の厚い庇護に感じて生涯を校正一筋に賭けた。……
だが、麥南さんの来訪も開戦後は途絶えた。……リベラリストで真の理想主義者、平和主義者であった麥南さんの身辺にも、いつか故なき官憲の圧力が加えられたためのようだ。(「麥南さんのこと」昭和五十七年)]
茅舎と麦南とは、茅舎が二歳年下だが、麦南の「信(のぶ)ちゃん時代」(『川端茅舎(石原八束著)』所収)を見ると、この二人は茅舎の生涯にわたっての無二の親友であったという思いを深くする。そこで、麦南は茅舎について次のとおり記している。
[生きとし生けるものに罪なきはない。けだし信ちやん(注・茅舎)は最も罪すくなき生涯を生活した人のひとりであった。妻も子も愛する女もなく童貞にして死んでいつた。この十幾年を殆ど病牀に引籠つて暮してきた。生活経験の範囲からいへば極めてせまかつたといへるが、信ちやんの生活はその中において浄く深く徹していつた。私は川端茅舎の名に於て喧伝さるゝ信ちやんを哲人と呼ぶ。]
また、麦南は、茅舎と麦南が「新しき村」の会員になるときのことを次のように記している。
[新しき村の会員にもいつしよになつた。武者小路さんに逢ふ前に、私が信ちやんと二人連名の手紙を書いた。はじめにあつた武者さんは、信ちやんが成人したやうな感じの人だつた。水にはひると自由にのうのうとくつろぐ信ちやんの、日常のあのぎこちない不器用なからだつきとそつくりのからだつきの武者さんだつた。]
麦南は、大正七年(一九一八)から三年間、九州の日向の「新しき村」に参加し、茅舎は第二種会員(村外会員)となる。後に、茅舎は、この「新しき村」の実践に参加できない頃の苦しみを「花鳥巡礼」に書き留めている。
さて、茅舎の最後の第三句集『白痴』の「もう一度後記」に、次のようなことが記されている。
[鶯の機先は自分に珍しいほどの歓喜を露はに示してゐる。抱風子の鶯団子は病床生活の自分に大きい時代の認識を深める窓の役目を果たして呉れた。]
この「鶯の機先」と「抱風子の鶯団子」は、『白痴』の最後の二章の題名で、その全文は次のとおりである。
鶯の機先
三月十二日朝篠浦一兵少佐次男旭君幼年
学校入試合格通知飛来
鶯の機先高音す今朝高音す
ひんがしに鶯機先高音して
鶯の声のおほきくひんがしに
抱風子鶯団子
三月廿九日午後三時抱風子鶯団子持参
先週以来連続して夢枕に現はれたるそ
のもの目前へ持参
抱風子鶯団子買得たり
買得たり鶯団子一人前
一人前鶯団子唯三つぶ
唯三つぶ鶯団子箱の隅
しんねりと鶯団子三つぶかな
むつつりと鶯団子三つぶかな
皆懺悔鶯団子たひらげて
この『白痴』の最後の二章は何とも不可思議な響きを有しているのだが、「鶯の機先」は、「戦争」、そして、「抱風子鶯団子」は「平和」の象徴のような、そんな雰囲気も有しているように思えるのである。
そして、間もなく戦争が始まり、その戦争が終結すると、本当の平和がやって来て、その戦後の平和は、茅舎や麦南が青春時代に希求した、武者小路実篤の「新しき村」のような、「理想的な調和社会・階級闘争の無い世界(ユートピア)」が実現するであろう・・・、というような、そんなことを暗示しているのではなかろうか・・・。
この武者小路実篤の「新しき村」の到来こそ、この『白痴』の表紙の「実篤」装幀の隠された秘密なのではなかろうか・・・、と、茅舎と麦南との交遊と実篤とその「新しき村」との出会い・・・、それらのことが、次の世代を戦後担うこととなる、「新婚の清を祝福して贈る」という、この『白痴』の「序」に隠された秘密なのではなかろうか・・・、と、さらに付け加えるならば、「白痴茅舎」の「白痴」とは、武者小路実篤の「お目出たき人」とか「馬鹿一」とか・・・、と、そんなニュアンスに近いものだと、そんな思いにも駆られるのである。
(追記)
下記のアドレスで【 近現代日本の俳人とドスト氏 】として、「西東三鬼・西島麦南・川端茅舎・中村草田男・上田五千石」が紹介されていた。この西島麦南がドストエフスキーを熟読していたということは、川端茅舎の句集『白痴』を解読するための一つのキィーとなるものと理解をいたしたい。
http://dostef.webspace.ne.jp/bbs/dostef_topic_pr_447.html
【 近現代日本の俳人とドスト氏 】
・露人ワシコフ/叫びて石榴(ざくろ)/打ち落とす 三鬼
・暗く暑く/大群衆と/花火待つ 三鬼
・倒れたる/案山子(かかし)の顔の/上に天 三鬼
・胡瓜(きゅうり)もむ/エプロン白き/妻の幸(さち) 麦南
・国狭く/銀漢流れ/わたりけり 麦南
・想念の/絶壁の如し/鉦叩(かねたたき) 茅舎
・栗の花/白痴四十の/紺絣(こんがすり) 〔句集『白痴』より〕 茅舎
・降る雪や/明治は遠く/なりにけり 草田男
・真直ぐ往(ゆ)けと/白痴が指しぬ/秋の道 〔句集『美田』より〕 草田男
・万緑や/死は一弾を/以(もっ)て足る 五千石
ページ内にすでに掲載していますが、ドストエフ好きーの俳人としては、上掲の、
・西東三鬼
(1900~1962)
・西島麦南
(1895~1979。熊本県出身。飯田蛇笏に師事。氏はドスト氏の著作に
生の救いと支えを見出した。)
が知られています。
三鬼の蔵書には岩波文庫の米川訳の『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』があり、三鬼は両小説を愛読していました。
三鬼の句「暗く暑く/大群衆と/花火待つ」の「暗く暑く」、米川訳『カラ兄弟』の大審問官の章の中の一文「一日も過ぎて、暗く暑い、死せるがごときセヴィリヤの夜が訪れた。」の「暗く暑い」を踏まえていると思われます。
三鬼は、なんと、7カ国語に精通していたとのこと。その中にロシア語も入っていたのでしょうかね。( 驚いた感じと滑稽味を含む三鬼の句は、私には、面白いです。)
麦南におけるドスト氏については、いつか、追加の情報や気付き等をまとめてみたいと思います。(麦南は、師の蛇笏の作風の良き一面を受け継いでいて、清新で風格のある佳句も多くて私の好きな俳人の一人です。)
ほかに、
・川端茅舎(1897~1941)へのドスト氏の影響の指摘あり。
( 茅舎は虚子に入門し麦南は虚子の弟子で蛇笏に師事していたと
いうこともあって、茅舎と麦南は交友関係があった。)
・中村草田男(1901~1983)に、ドスト氏に関して触れている文章あり。
( 上掲の「白痴」という語を含めている茅舎の句・草田男の句は、
ともに、ドスト氏の『白痴』の主人公の人物像を踏まえている
のではないかという指摘があるようです。
年下の草田男が同門として茅舎に兄事していたので、草田男と
茅舎は親交がありました。麦南・茅舎・草田男は、薦め合った
関係はわかりませんが、ホトトギス派の俳人として、東京の地
でお互いにドスト氏の作品を読み合い、語り合った仲だったの
でしょう。)
上掲の上田五千石(1933~1997)の絶唱には、私には、『悪霊』のキリーロフの自然讃美の人生観とその人生観の中での彼のピストル自殺の行為のことが感じられました。どういう時にこの句を作ったのかわかりませんが、氏の念頭に『悪霊』のキリーロフのことがあったのではないかという気がします。
川端茅舎の幼なじみの無二の親友に「雲母」の主要俳人の西島麦南がいる。麦南の簡単なプロフィールは次のとおりである。
西島麦南 (にしじま-ばくなん)
明治二十八年(1895)~昭和五十六年(1981) 大正-昭和時代の俳人。
明治二十八年一月十日生まれ。武者小路実篤(むしゃのこうじ-さねあつ)の「新しき村」で開拓に従事。大正十三年岩波書店に入社,「校正の神様」とよばれ、昭和四十年文化人間賞受賞。俳句は飯田蛇笏(だこつ)に師事、傾倒し、みずから「生涯山廬(さんろ)(蛇笏)門弟子」と称した。昭和五十六年十月十一日死去。八十六歳。熊本県出身。本名は九州男(くすお)。句集に「金剛纂(こんごうさん)」「人音(じんおん)」。
【代表句など】炎天や死ねば離るゝ影法師
この麦南について、飯田蛇笏の亡き後「雲母」の主宰者となった飯田龍太は次のとおり記している。
http://white.ap.teacup.com/cyamicat2/187.html
[岩波書店に永年勤め、“校正の神様”といわれた西島麥南さんが、去る十月(昭和五十六年)十一日のおひる過ぎ、鎌倉由比ヶ浜の自宅で亡くなった。行年八十六歳と九カ月。……
本名九州男。明治二十八年、田原坂の古戦場にほど近い肥後植木に生まれ、句集の自序に「生涯山盧門弟子」と記したように、俳句は蛇笏門に終始したが、岸田劉生に私淑して画家をこころざし、あるいは大正七年、武者小路実篤らの「新しき村」の創設に参加したり、ときに小説家として身をたてようと志したときもあったようだが、岩波茂雄の厚い庇護に感じて生涯を校正一筋に賭けた。……
だが、麥南さんの来訪も開戦後は途絶えた。……リベラリストで真の理想主義者、平和主義者であった麥南さんの身辺にも、いつか故なき官憲の圧力が加えられたためのようだ。(「麥南さんのこと」昭和五十七年)]
茅舎と麦南とは、茅舎が二歳年下だが、麦南の「信(のぶ)ちゃん時代」(『川端茅舎(石原八束著)』所収)を見ると、この二人は茅舎の生涯にわたっての無二の親友であったという思いを深くする。そこで、麦南は茅舎について次のとおり記している。
[生きとし生けるものに罪なきはない。けだし信ちやん(注・茅舎)は最も罪すくなき生涯を生活した人のひとりであった。妻も子も愛する女もなく童貞にして死んでいつた。この十幾年を殆ど病牀に引籠つて暮してきた。生活経験の範囲からいへば極めてせまかつたといへるが、信ちやんの生活はその中において浄く深く徹していつた。私は川端茅舎の名に於て喧伝さるゝ信ちやんを哲人と呼ぶ。]
また、麦南は、茅舎と麦南が「新しき村」の会員になるときのことを次のように記している。
[新しき村の会員にもいつしよになつた。武者小路さんに逢ふ前に、私が信ちやんと二人連名の手紙を書いた。はじめにあつた武者さんは、信ちやんが成人したやうな感じの人だつた。水にはひると自由にのうのうとくつろぐ信ちやんの、日常のあのぎこちない不器用なからだつきとそつくりのからだつきの武者さんだつた。]
麦南は、大正七年(一九一八)から三年間、九州の日向の「新しき村」に参加し、茅舎は第二種会員(村外会員)となる。後に、茅舎は、この「新しき村」の実践に参加できない頃の苦しみを「花鳥巡礼」に書き留めている。
さて、茅舎の最後の第三句集『白痴』の「もう一度後記」に、次のようなことが記されている。
[鶯の機先は自分に珍しいほどの歓喜を露はに示してゐる。抱風子の鶯団子は病床生活の自分に大きい時代の認識を深める窓の役目を果たして呉れた。]
この「鶯の機先」と「抱風子の鶯団子」は、『白痴』の最後の二章の題名で、その全文は次のとおりである。
鶯の機先
三月十二日朝篠浦一兵少佐次男旭君幼年
学校入試合格通知飛来
鶯の機先高音す今朝高音す
ひんがしに鶯機先高音して
鶯の声のおほきくひんがしに
抱風子鶯団子
三月廿九日午後三時抱風子鶯団子持参
先週以来連続して夢枕に現はれたるそ
のもの目前へ持参
抱風子鶯団子買得たり
買得たり鶯団子一人前
一人前鶯団子唯三つぶ
唯三つぶ鶯団子箱の隅
しんねりと鶯団子三つぶかな
むつつりと鶯団子三つぶかな
皆懺悔鶯団子たひらげて
この『白痴』の最後の二章は何とも不可思議な響きを有しているのだが、「鶯の機先」は、「戦争」、そして、「抱風子鶯団子」は「平和」の象徴のような、そんな雰囲気も有しているように思えるのである。
そして、間もなく戦争が始まり、その戦争が終結すると、本当の平和がやって来て、その戦後の平和は、茅舎や麦南が青春時代に希求した、武者小路実篤の「新しき村」のような、「理想的な調和社会・階級闘争の無い世界(ユートピア)」が実現するであろう・・・、というような、そんなことを暗示しているのではなかろうか・・・。
この武者小路実篤の「新しき村」の到来こそ、この『白痴』の表紙の「実篤」装幀の隠された秘密なのではなかろうか・・・、と、茅舎と麦南との交遊と実篤とその「新しき村」との出会い・・・、それらのことが、次の世代を戦後担うこととなる、「新婚の清を祝福して贈る」という、この『白痴』の「序」に隠された秘密なのではなかろうか・・・、と、さらに付け加えるならば、「白痴茅舎」の「白痴」とは、武者小路実篤の「お目出たき人」とか「馬鹿一」とか・・・、と、そんなニュアンスに近いものだと、そんな思いにも駆られるのである。
(追記)
下記のアドレスで【 近現代日本の俳人とドスト氏 】として、「西東三鬼・西島麦南・川端茅舎・中村草田男・上田五千石」が紹介されていた。この西島麦南がドストエフスキーを熟読していたということは、川端茅舎の句集『白痴』を解読するための一つのキィーとなるものと理解をいたしたい。
http://dostef.webspace.ne.jp/bbs/dostef_topic_pr_447.html
【 近現代日本の俳人とドスト氏 】
・露人ワシコフ/叫びて石榴(ざくろ)/打ち落とす 三鬼
・暗く暑く/大群衆と/花火待つ 三鬼
・倒れたる/案山子(かかし)の顔の/上に天 三鬼
・胡瓜(きゅうり)もむ/エプロン白き/妻の幸(さち) 麦南
・国狭く/銀漢流れ/わたりけり 麦南
・想念の/絶壁の如し/鉦叩(かねたたき) 茅舎
・栗の花/白痴四十の/紺絣(こんがすり) 〔句集『白痴』より〕 茅舎
・降る雪や/明治は遠く/なりにけり 草田男
・真直ぐ往(ゆ)けと/白痴が指しぬ/秋の道 〔句集『美田』より〕 草田男
・万緑や/死は一弾を/以(もっ)て足る 五千石
ページ内にすでに掲載していますが、ドストエフ好きーの俳人としては、上掲の、
・西東三鬼
(1900~1962)
・西島麦南
(1895~1979。熊本県出身。飯田蛇笏に師事。氏はドスト氏の著作に
生の救いと支えを見出した。)
が知られています。
三鬼の蔵書には岩波文庫の米川訳の『カラマーゾフの兄弟』『悪霊』があり、三鬼は両小説を愛読していました。
三鬼の句「暗く暑く/大群衆と/花火待つ」の「暗く暑く」、米川訳『カラ兄弟』の大審問官の章の中の一文「一日も過ぎて、暗く暑い、死せるがごときセヴィリヤの夜が訪れた。」の「暗く暑い」を踏まえていると思われます。
三鬼は、なんと、7カ国語に精通していたとのこと。その中にロシア語も入っていたのでしょうかね。( 驚いた感じと滑稽味を含む三鬼の句は、私には、面白いです。)
麦南におけるドスト氏については、いつか、追加の情報や気付き等をまとめてみたいと思います。(麦南は、師の蛇笏の作風の良き一面を受け継いでいて、清新で風格のある佳句も多くて私の好きな俳人の一人です。)
ほかに、
・川端茅舎(1897~1941)へのドスト氏の影響の指摘あり。
( 茅舎は虚子に入門し麦南は虚子の弟子で蛇笏に師事していたと
いうこともあって、茅舎と麦南は交友関係があった。)
・中村草田男(1901~1983)に、ドスト氏に関して触れている文章あり。
( 上掲の「白痴」という語を含めている茅舎の句・草田男の句は、
ともに、ドスト氏の『白痴』の主人公の人物像を踏まえている
のではないかという指摘があるようです。
年下の草田男が同門として茅舎に兄事していたので、草田男と
茅舎は親交がありました。麦南・茅舎・草田男は、薦め合った
関係はわかりませんが、ホトトギス派の俳人として、東京の地
でお互いにドスト氏の作品を読み合い、語り合った仲だったの
でしょう。)
上掲の上田五千石(1933~1997)の絶唱には、私には、『悪霊』のキリーロフの自然讃美の人生観とその人生観の中での彼のピストル自殺の行為のことが感じられました。どういう時にこの句を作ったのかわかりませんが、氏の念頭に『悪霊』のキリーロフのことがあったのではないかという気がします。