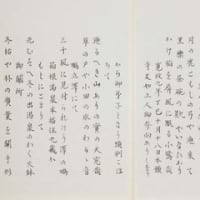二
以上で大体抄出を了ったわけであるが、本書を通覧して先ず注意されることは、前年のに比して編纂上にかなりの変貌が認められる事実である。即ち元文三年のは何と言っても東帰後日も浅い撰集のこととて、量的にも僅か数葉の貧弱なものにすぎないが、巴人自身としては江戸俳壇返り咲きの記念すべき第一集として、粗末ながらも相応に対外的な効果を願慮し、集中的に超波・平砂・祇丞・有佐・渭北・青峨・沾洲等江戸座知名の顔触れを網羅するなど、かなりはでやかな編纂ぶりが見られるのであるが、それに比して本書は殆ど他門の吟を交えず終始一門で固めて、前年とは見違える程の堅実な編纂振りを示している。即ち膝元の東都社中を始めとして、近くは関宿・下館・結城・烏山から遠くは京都に至るまで、全面的に一門の出吟で埋め、量的にも略々前年に倍する二十葉に近い紙幅を擁している。東帰後足かけ三年の歳月を経て、巴人を中心とする江戸夜半亭が内外共に漸く充実の趨勢を示し始めた状が明らかに看取されよう。
集中、巴人の句としては、歳旦三つ物の附句類を除いて左の三句を挙げることができる。
已(ママ)未歳旦 古郷に三とセ住ゐして
世中又新らしきやうに
おほえ侍りけれハ
我としの寄もしらて花の春 宋阿
大尾
馬車さハらぬ江戸の師走哉 宋阿
年内立春
枝川へ盗まれけりな雪の山 宋阿
三句何れも後年の『夜半亭発句帖』(宝暦五年刊、雁宕・阿誰・大済共編)に採録を見ている。第一句の前書に「古郷に三とセ住ゐして」とあるが、巴人の東帰は元文二年四月のことであるから、この春で足かけ三年の江戸住まいとなるわけである。この句『発句帖』には前書を脱し、中七は「寄をしらず」とあり、第三句も同じく中七「盗まれにけり」とあって、何れも句形に若干の異同が見られる。もとより型通りの歳旦・歳暮吟で別にとり立てて言うべきことではないが、最後の一句の如きやゝ奇想を弄しすぎて却って江戸座の遺臭すら感ぜられよう。
それはともかく本書を通じて最も注意すべきは、集中より次の如き蕪村の逸句一を拾い得る事実であろう。
不二を見て通る人有年の市 宰町
宰町が蕪村の前身であることは、従来諸家の推定によって略々誤りない事実とされて来たのであるが、潁原先生の紹介された元文三年の『卯月庭訓』(露月撰)に見える。
鎌倉誂物
尼寺や十夜に届く鬢葛 宰町
の一句が、蕪村後年の「落日菴句集」(乾猷平氏『未刊蕪村句集』所収)に収載されている一事よりすれば(註②)、もはや動かし難い事実と称してよい。それにしても宰町時代の作品としては、今までのところ元文三年の初頭から翌四年の春にかけて、僅かに発句五句とその他若干の付合が知られているにすぎず、ここに宰町資料として新たにこの一句を加え得たことを喜びとしたい。
その他前年に準じて、東湖・我兄・解糸・巨川・少我・芝光・赤鯉・佳交等の東都社中を始め、雁宕・風篁・丈羽・田洪・巴牛・巴甃・高峨等の野総常連、更には富鈴・我笑・千虎・可焉・畦石・郢里・盛澄等の京都社中に至るまで、遠近を問わず句を寄せて居り、これらの賑やかな顔触れを通して当時の夜半亭の雰囲気は十分に察することができよう。
なお、関宿境歳旦中に見える蛙吹は、蕪村の青年時代を通じて、かの雁宕と共に特に因みの深かった阿誰(註③)の前号ではないかと思われる節がある(所書と音の相似に注意)。しかも私見によれば阿誰は蛙吹--阿推--阿誰と順次改号したらしく、その時期に関しては必ずしも詳らかではないが、巴人の十三回忌に宋屋の撰んだ追善集『明の蓮』(宝暦四年刊)に、撰者自ら「東奥さかいの何がしハ亡師にゆかり淺からず、過し桃櫻の追善にありし懐舊を聊五文字を置かへて、十三回に猶するも佛縁歟」として、
六月や春ふることの名ハ枯ず 箱嶌氏 阿誰
の一句を掲げている。宋屋の言をこのまゝ信ずるとすれば、元文四年の十一月に成った『桃桜』には既に阿推の号で一句を投じていたことが知られ(註④)、蛙吹より阿推への改号は、元文四年正月以後十一月以前のことと推定される。その後寛保元年の『夜半亭歳旦帖』にも「関宿さか井」として依然阿推号で見えて居り、阿誰の号は管見の範囲ではやゝ後れて寛保四年(延享元年)の『蕪村歳旦帖』を以て初出とされる様であるから、阿推から阿誰への改号(むしろ改字)は、略々寛保の末頃と考えられる。
以上で新たに発見された元文四年の夜半亭歳旦帖に関し、注意すべき諸点には一応触れ得たつもりであるが、なお巴人関係の新資料としては、この他に同じく中村家で発見された『誹諧連歌五十韻』と題する句巻があり、元文三年五月十日及び十二日に高峨邸で催された二巻の俳諧が収めてある。前会の連衆には風篁・高峩・月下・醉月・宋阿・貞府・巴舟・嶌竃・路文(以下得点順)等の名が見え、後会には高峩・宋阿・醉月・巴舟・嶌竃・風篁・貞府等が一座している。内容の詳しい紹介は別の機械に譲ることとして、ここでは序ながら巴人の改号をめぐる問題について一言して結びとしたい。
三
巴人の改号が竹雨--巴人--宋阿の順序で行われたことは周知の如くであり、夙に潁原先生の指摘された如く、元禄十四年刊の『杜撰集』(嵐雪撰)まではなお竹雨と号し、翌十五年春の烏山天満宮奉納句(宋屋撰『杖の土』所載)からは巴人号が用いられている事実よりして、巴人への改号は元禄十五年に入ってからのこととされている(註⑤)。この点に関しては従来とも異論はないのであるが、次の巴人から宋阿への改号をめぐっては、必ずしも問題がないわけではない。
先ず『西の奥』(寛保三年刊)に富鈴が「いつのころ歟一夜松編集の後宋阿と變名して云々」と述べていることからすれば、宋阿への改号は一応享保の末頃(因みに『一夜松』の編集は享保十八年)と考えられるわけであるが、この点について潁原先生は、『一夜松』撰集後なる享保十九・二十年の諸集にもすべてやはり巴人号で出ている事実から、『西の奥』の富鈴の言もそのまゝに信じ難いとされて、宋阿への改号は元文期に入ってからのことであろうとされている(註⑥)。その後故志田博士は、元文元年首夏の雁宕餞別一枚摺に初めて宗阿の号が見えるところから、改号の時期を略々その頃と推定された(註⑦)。しかしかく定めることによって、博士の言われた如く前後の資料とも抵触せず(註⑧)、その限りでは問題は一応解決されたかの如くに見えるが、なお疑点を挟むべき余地が全くないわけではない。と言うのは、富鈴の『梅鏡』(元文四年刊)を見ると、「享保寅(十九年)秋予文臺の主と成日、馬老の賀章すこし匣底に有しを、拾ひて爰にのす」として、その後に、
ことば草花咲實なるはじめ哉 郢月泉 宗阿
の一句を掲げて居り、もしその言をそのまゝ信ずるとすれば、享保十九年秋の富鈴の文台開きの頃には、既に宗阿の号で賀句を寄せていたことが知られる。してみると従来誤伝かとされて来た『西の奥』の富鈴の言が、新たな信憑性をもって想起され、改号の時期も、元文元年より更に享保十八・十九年の交まで遡り得る可能性がかなり濃厚となって来る。
それにしても前に触れた如く、享保十九年・二十年頃の諸集に以前巴人号で出ていると言う事実は、一体どう解釈さるべきであろうか。無論中には前述の『此長月』の場合の様に、巴人時代の旧集からそのまゝ転載したものもあったろうし、或いは又撰者の不注意から、改号の事実を知らずに旧号のまゝで採録した様の場合も考えられないではない。しかし事実上それだけでは解釈のつかない場合がむしろ多いのであって、例えば享保二十年成の『籬下』(隆志撰)などには、自ら興行した一座の俳諧に明瞭に巴人の名で出座しているのである。してみると改めて別な理由の介在することが考えられなければならない。もともと改号後に於ける巴人号の使用は、単にこの時期のみに限らず、元文期に入ってからも時折は見られる事柄であって、例えば元文三年の三月に興行された風篁と貞府の戦句の判に、「巴人菴」の署名が見え(中村家蔵)、翌四年の三月に成った『梅鏡』(富鈴撰)の中の一句に、
元日 名の高き遊女聞えず御代の春 巴人庵 宋阿
とあり、同じ春の頃午寂から寄せられた『桃桜』の序文中にも、やはり「巴人菴宋阿」と称されている。これらの事例から、巴人の号は改号後もかなり遅くまで軒号として時たま併用されていたことが知られ、この号には後々まで何か特別な愛着を感じていたらしく想像されるのである。してみると改号の当座即ち享保十九年から二十年にかけて、特に巴人号の頻用が見られたと言うことも、必ずしも説明のつかないことではなくなって来る。つまり巴人自身にしてみれば何と言っても永年使い馴れた俳号ではあり、いわば長い過去の俳歴の象徴として一方ならぬ愛着を感じてもいたであろうから、一応改号はしてみたもののそうむげに捨て去ることもならず、当座はともすれば旧号の使用に心惹かれることが多かったであろうし、又場合によっては、自他共に耳馴れぬ新号よりは世間的も通りの良い旧号を用いる方が便利なことも少なくなかったに相違ない。こう考えて来ると、上述の問題も或る程度解釈がつきそうに思われるが、無論これで悉く疑点が解消したとは言い得ない。何れにしてもこの問題に関してはなお後考を俟つべきであろう。
それはともかくとしてこゝに注意すべきは、前述の如く享保十九年の秋の富鈴の立机の賀句に宗阿とあり、次いで元文元年夏の雁宕餞別一枚摺にも、更に元文三年の歳旦帖にもやはり宗阿とある事実である。このことから、宋阿と号する前に一時的ではあるが、宗阿と称した時期があったのではないかと言う疑いが生じて来る。即ちその後の改号は、巴人--宗阿--宋阿の順序を経て行われたのではなかろうか。従来宗阿は宋阿の誤記であろうとして簡単に片付けられ来たのであるが、後述する如く富鈴の『梅鏡』などを見ても、集中に掲げられた巴人の句が、その制作年時によって明瞭に宗阿と宋阿の二様に書き分けられて居り、以下の推定が無稽の説でないことを物語っている。もしそうだとすると、次の宗阿から宋阿への改号は何時頃であったろうか。元文三年の歳旦帖までは宗阿の号で見えていることは前にも述べたが、宋阿の号は管見の範囲では同年五月十日及び十二日の高峨亭会の句巻(前述)を以てその初見とされる様である(註⑧)。してみるとその改号(むしろ改字)は元文三年正月以後五月以前と言うことになる。爾後同年七月九日の夜半亭会句巻(中村家蔵)を始め、その後の諸集すべて宋阿の号で出ていることは周知の如くである。ただ翌年三月に成った富鈴の『梅鏡』に、宋阿号と宗阿号とが混在することが一応問題になるが、それとても仔細に検討してみると、在洛中の旧作と思われる連句や発句には、例えば、
住吉難波屋の笠松を題して
時知らぬ河内の雲の松の雪 宗阿
の如く宗阿の号が付されてあり、東武より寄せられた近作には、
初雪や雪にもならで星月夜 東武 宋阿
の如く宋阿とあって、その間明瞭な区別が施されて居り、前術の推定に齟齬を来す虞れはない。なお同じくこの年に成った寥和の『風の末』にも、
埋火や老てしたがふかたつぶり 宗阿
の一句が見えているが、この句は実は夙に正徳三年刊の『きくいたゞき』に見える旧作であって、この宗阿も撰者の不用意から出た誤りと見てよかろう。ともあれこゝに紹介した元文四年の歳旦帖を始め、同年十一月に撰んだ『桃桜』更には寛保元年の歳旦帖に至るまで、この間に成った自家の撰集にはすべて宋阿と出ている以上、もはや多くを疑う必要もなかろうかと思う。
以上、巴人並びに蕪村関係の新資料として元文四年の夜半亭歳旦帖を紹介し、併せて巴人の改号をめぐる諸問題について二三私見を述べてみたのであるが、なお未解決のまゝに残された点も少なくない。それらについては暫く後考を俟つこととして、ひと先ず小稿のの筆をおきたいと思うが、終わりに快く珍襲の発表を許された中村氏の御厚情に改めて深謝申し上げたい。
(註①)両書に関しては夙に潁原先生によってその大要が紹介されている。(同氏著『俳諧史論考』所収「夜半亭巴人」の項二九九--三〇七頁参照)
(註②)但し『落日菴句集』には前書を脱し、下五仮名書きにて「さねかつら」とあり。
(註③)姓箱島、名善兵衛、下総関宿堺の人。安永元年十二月十五日没、享年六十二。
(註④)『桃桜』は周知の如く左右両巻あるが、左巻には阿誰の句は見えない。恐らく右巻の方に収 載を見ているかと思われるが、未見。
(註⑤)潁原退蔵氏『俳諧史論考』所収「夜半亭巴人」の項、二八〇--二八一頁参照。
(註⑥)前同書、二九七--二九八頁参照。
(註⑦)志田博士『奥の細道・芭蕉・蕪村』所収「蕪村の宰町資料附巴人・太祇資料」の項、三四四 頁参照。
(註⑧)元文元年九月成の『此長月』(永我撰)に依然巴人の号で一句が見え、一応問題になるが、 この句は博士によれば夙に享保十五年刊の『〓之笛』(淡々撰)に見えている由で、同書よりの 転載と見れば齟齬を来さない。
(註⑨)潁原先生の御指摘によれば、元文二年六月九日羅人の主催で一万六千七百韻を興行し、同十 六日東山で竟宴五百韻を催して、その賀集として出した『一日萬句嘉定蒲簀』の中に「東武宋阿」として一句が見えている由で、これによれば元文二年六月には既に宋阿と号していたと思われる が、先生も言われる如くる『嘉定蒲簀』の出板は無論万句興行の当時よりは後のことと思われる から、確実な文献上の初見としては、やはり元文三年五月の高峨亭会句巻とすべきであろう。
〔転載上の付記:①引用句文などは旧字体・旧仮名遣い。但し、二倍送り記号は*印を付して平仮名の 表記。②本文は新字体・新仮名遣いに改定。③ルビの位置・記述記号などは一部改定。〕
以上で大体抄出を了ったわけであるが、本書を通覧して先ず注意されることは、前年のに比して編纂上にかなりの変貌が認められる事実である。即ち元文三年のは何と言っても東帰後日も浅い撰集のこととて、量的にも僅か数葉の貧弱なものにすぎないが、巴人自身としては江戸俳壇返り咲きの記念すべき第一集として、粗末ながらも相応に対外的な効果を願慮し、集中的に超波・平砂・祇丞・有佐・渭北・青峨・沾洲等江戸座知名の顔触れを網羅するなど、かなりはでやかな編纂ぶりが見られるのであるが、それに比して本書は殆ど他門の吟を交えず終始一門で固めて、前年とは見違える程の堅実な編纂振りを示している。即ち膝元の東都社中を始めとして、近くは関宿・下館・結城・烏山から遠くは京都に至るまで、全面的に一門の出吟で埋め、量的にも略々前年に倍する二十葉に近い紙幅を擁している。東帰後足かけ三年の歳月を経て、巴人を中心とする江戸夜半亭が内外共に漸く充実の趨勢を示し始めた状が明らかに看取されよう。
集中、巴人の句としては、歳旦三つ物の附句類を除いて左の三句を挙げることができる。
已(ママ)未歳旦 古郷に三とセ住ゐして
世中又新らしきやうに
おほえ侍りけれハ
我としの寄もしらて花の春 宋阿
大尾
馬車さハらぬ江戸の師走哉 宋阿
年内立春
枝川へ盗まれけりな雪の山 宋阿
三句何れも後年の『夜半亭発句帖』(宝暦五年刊、雁宕・阿誰・大済共編)に採録を見ている。第一句の前書に「古郷に三とセ住ゐして」とあるが、巴人の東帰は元文二年四月のことであるから、この春で足かけ三年の江戸住まいとなるわけである。この句『発句帖』には前書を脱し、中七は「寄をしらず」とあり、第三句も同じく中七「盗まれにけり」とあって、何れも句形に若干の異同が見られる。もとより型通りの歳旦・歳暮吟で別にとり立てて言うべきことではないが、最後の一句の如きやゝ奇想を弄しすぎて却って江戸座の遺臭すら感ぜられよう。
それはともかく本書を通じて最も注意すべきは、集中より次の如き蕪村の逸句一を拾い得る事実であろう。
不二を見て通る人有年の市 宰町
宰町が蕪村の前身であることは、従来諸家の推定によって略々誤りない事実とされて来たのであるが、潁原先生の紹介された元文三年の『卯月庭訓』(露月撰)に見える。
鎌倉誂物
尼寺や十夜に届く鬢葛 宰町
の一句が、蕪村後年の「落日菴句集」(乾猷平氏『未刊蕪村句集』所収)に収載されている一事よりすれば(註②)、もはや動かし難い事実と称してよい。それにしても宰町時代の作品としては、今までのところ元文三年の初頭から翌四年の春にかけて、僅かに発句五句とその他若干の付合が知られているにすぎず、ここに宰町資料として新たにこの一句を加え得たことを喜びとしたい。
その他前年に準じて、東湖・我兄・解糸・巨川・少我・芝光・赤鯉・佳交等の東都社中を始め、雁宕・風篁・丈羽・田洪・巴牛・巴甃・高峨等の野総常連、更には富鈴・我笑・千虎・可焉・畦石・郢里・盛澄等の京都社中に至るまで、遠近を問わず句を寄せて居り、これらの賑やかな顔触れを通して当時の夜半亭の雰囲気は十分に察することができよう。
なお、関宿境歳旦中に見える蛙吹は、蕪村の青年時代を通じて、かの雁宕と共に特に因みの深かった阿誰(註③)の前号ではないかと思われる節がある(所書と音の相似に注意)。しかも私見によれば阿誰は蛙吹--阿推--阿誰と順次改号したらしく、その時期に関しては必ずしも詳らかではないが、巴人の十三回忌に宋屋の撰んだ追善集『明の蓮』(宝暦四年刊)に、撰者自ら「東奥さかいの何がしハ亡師にゆかり淺からず、過し桃櫻の追善にありし懐舊を聊五文字を置かへて、十三回に猶するも佛縁歟」として、
六月や春ふることの名ハ枯ず 箱嶌氏 阿誰
の一句を掲げている。宋屋の言をこのまゝ信ずるとすれば、元文四年の十一月に成った『桃桜』には既に阿推の号で一句を投じていたことが知られ(註④)、蛙吹より阿推への改号は、元文四年正月以後十一月以前のことと推定される。その後寛保元年の『夜半亭歳旦帖』にも「関宿さか井」として依然阿推号で見えて居り、阿誰の号は管見の範囲ではやゝ後れて寛保四年(延享元年)の『蕪村歳旦帖』を以て初出とされる様であるから、阿推から阿誰への改号(むしろ改字)は、略々寛保の末頃と考えられる。
以上で新たに発見された元文四年の夜半亭歳旦帖に関し、注意すべき諸点には一応触れ得たつもりであるが、なお巴人関係の新資料としては、この他に同じく中村家で発見された『誹諧連歌五十韻』と題する句巻があり、元文三年五月十日及び十二日に高峨邸で催された二巻の俳諧が収めてある。前会の連衆には風篁・高峩・月下・醉月・宋阿・貞府・巴舟・嶌竃・路文(以下得点順)等の名が見え、後会には高峩・宋阿・醉月・巴舟・嶌竃・風篁・貞府等が一座している。内容の詳しい紹介は別の機械に譲ることとして、ここでは序ながら巴人の改号をめぐる問題について一言して結びとしたい。
三
巴人の改号が竹雨--巴人--宋阿の順序で行われたことは周知の如くであり、夙に潁原先生の指摘された如く、元禄十四年刊の『杜撰集』(嵐雪撰)まではなお竹雨と号し、翌十五年春の烏山天満宮奉納句(宋屋撰『杖の土』所載)からは巴人号が用いられている事実よりして、巴人への改号は元禄十五年に入ってからのこととされている(註⑤)。この点に関しては従来とも異論はないのであるが、次の巴人から宋阿への改号をめぐっては、必ずしも問題がないわけではない。
先ず『西の奥』(寛保三年刊)に富鈴が「いつのころ歟一夜松編集の後宋阿と變名して云々」と述べていることからすれば、宋阿への改号は一応享保の末頃(因みに『一夜松』の編集は享保十八年)と考えられるわけであるが、この点について潁原先生は、『一夜松』撰集後なる享保十九・二十年の諸集にもすべてやはり巴人号で出ている事実から、『西の奥』の富鈴の言もそのまゝに信じ難いとされて、宋阿への改号は元文期に入ってからのことであろうとされている(註⑥)。その後故志田博士は、元文元年首夏の雁宕餞別一枚摺に初めて宗阿の号が見えるところから、改号の時期を略々その頃と推定された(註⑦)。しかしかく定めることによって、博士の言われた如く前後の資料とも抵触せず(註⑧)、その限りでは問題は一応解決されたかの如くに見えるが、なお疑点を挟むべき余地が全くないわけではない。と言うのは、富鈴の『梅鏡』(元文四年刊)を見ると、「享保寅(十九年)秋予文臺の主と成日、馬老の賀章すこし匣底に有しを、拾ひて爰にのす」として、その後に、
ことば草花咲實なるはじめ哉 郢月泉 宗阿
の一句を掲げて居り、もしその言をそのまゝ信ずるとすれば、享保十九年秋の富鈴の文台開きの頃には、既に宗阿の号で賀句を寄せていたことが知られる。してみると従来誤伝かとされて来た『西の奥』の富鈴の言が、新たな信憑性をもって想起され、改号の時期も、元文元年より更に享保十八・十九年の交まで遡り得る可能性がかなり濃厚となって来る。
それにしても前に触れた如く、享保十九年・二十年頃の諸集に以前巴人号で出ていると言う事実は、一体どう解釈さるべきであろうか。無論中には前述の『此長月』の場合の様に、巴人時代の旧集からそのまゝ転載したものもあったろうし、或いは又撰者の不注意から、改号の事実を知らずに旧号のまゝで採録した様の場合も考えられないではない。しかし事実上それだけでは解釈のつかない場合がむしろ多いのであって、例えば享保二十年成の『籬下』(隆志撰)などには、自ら興行した一座の俳諧に明瞭に巴人の名で出座しているのである。してみると改めて別な理由の介在することが考えられなければならない。もともと改号後に於ける巴人号の使用は、単にこの時期のみに限らず、元文期に入ってからも時折は見られる事柄であって、例えば元文三年の三月に興行された風篁と貞府の戦句の判に、「巴人菴」の署名が見え(中村家蔵)、翌四年の三月に成った『梅鏡』(富鈴撰)の中の一句に、
元日 名の高き遊女聞えず御代の春 巴人庵 宋阿
とあり、同じ春の頃午寂から寄せられた『桃桜』の序文中にも、やはり「巴人菴宋阿」と称されている。これらの事例から、巴人の号は改号後もかなり遅くまで軒号として時たま併用されていたことが知られ、この号には後々まで何か特別な愛着を感じていたらしく想像されるのである。してみると改号の当座即ち享保十九年から二十年にかけて、特に巴人号の頻用が見られたと言うことも、必ずしも説明のつかないことではなくなって来る。つまり巴人自身にしてみれば何と言っても永年使い馴れた俳号ではあり、いわば長い過去の俳歴の象徴として一方ならぬ愛着を感じてもいたであろうから、一応改号はしてみたもののそうむげに捨て去ることもならず、当座はともすれば旧号の使用に心惹かれることが多かったであろうし、又場合によっては、自他共に耳馴れぬ新号よりは世間的も通りの良い旧号を用いる方が便利なことも少なくなかったに相違ない。こう考えて来ると、上述の問題も或る程度解釈がつきそうに思われるが、無論これで悉く疑点が解消したとは言い得ない。何れにしてもこの問題に関してはなお後考を俟つべきであろう。
それはともかくとしてこゝに注意すべきは、前述の如く享保十九年の秋の富鈴の立机の賀句に宗阿とあり、次いで元文元年夏の雁宕餞別一枚摺にも、更に元文三年の歳旦帖にもやはり宗阿とある事実である。このことから、宋阿と号する前に一時的ではあるが、宗阿と称した時期があったのではないかと言う疑いが生じて来る。即ちその後の改号は、巴人--宗阿--宋阿の順序を経て行われたのではなかろうか。従来宗阿は宋阿の誤記であろうとして簡単に片付けられ来たのであるが、後述する如く富鈴の『梅鏡』などを見ても、集中に掲げられた巴人の句が、その制作年時によって明瞭に宗阿と宋阿の二様に書き分けられて居り、以下の推定が無稽の説でないことを物語っている。もしそうだとすると、次の宗阿から宋阿への改号は何時頃であったろうか。元文三年の歳旦帖までは宗阿の号で見えていることは前にも述べたが、宋阿の号は管見の範囲では同年五月十日及び十二日の高峨亭会の句巻(前述)を以てその初見とされる様である(註⑧)。してみるとその改号(むしろ改字)は元文三年正月以後五月以前と言うことになる。爾後同年七月九日の夜半亭会句巻(中村家蔵)を始め、その後の諸集すべて宋阿の号で出ていることは周知の如くである。ただ翌年三月に成った富鈴の『梅鏡』に、宋阿号と宗阿号とが混在することが一応問題になるが、それとても仔細に検討してみると、在洛中の旧作と思われる連句や発句には、例えば、
住吉難波屋の笠松を題して
時知らぬ河内の雲の松の雪 宗阿
の如く宗阿の号が付されてあり、東武より寄せられた近作には、
初雪や雪にもならで星月夜 東武 宋阿
の如く宋阿とあって、その間明瞭な区別が施されて居り、前術の推定に齟齬を来す虞れはない。なお同じくこの年に成った寥和の『風の末』にも、
埋火や老てしたがふかたつぶり 宗阿
の一句が見えているが、この句は実は夙に正徳三年刊の『きくいたゞき』に見える旧作であって、この宗阿も撰者の不用意から出た誤りと見てよかろう。ともあれこゝに紹介した元文四年の歳旦帖を始め、同年十一月に撰んだ『桃桜』更には寛保元年の歳旦帖に至るまで、この間に成った自家の撰集にはすべて宋阿と出ている以上、もはや多くを疑う必要もなかろうかと思う。
以上、巴人並びに蕪村関係の新資料として元文四年の夜半亭歳旦帖を紹介し、併せて巴人の改号をめぐる諸問題について二三私見を述べてみたのであるが、なお未解決のまゝに残された点も少なくない。それらについては暫く後考を俟つこととして、ひと先ず小稿のの筆をおきたいと思うが、終わりに快く珍襲の発表を許された中村氏の御厚情に改めて深謝申し上げたい。
(註①)両書に関しては夙に潁原先生によってその大要が紹介されている。(同氏著『俳諧史論考』所収「夜半亭巴人」の項二九九--三〇七頁参照)
(註②)但し『落日菴句集』には前書を脱し、下五仮名書きにて「さねかつら」とあり。
(註③)姓箱島、名善兵衛、下総関宿堺の人。安永元年十二月十五日没、享年六十二。
(註④)『桃桜』は周知の如く左右両巻あるが、左巻には阿誰の句は見えない。恐らく右巻の方に収 載を見ているかと思われるが、未見。
(註⑤)潁原退蔵氏『俳諧史論考』所収「夜半亭巴人」の項、二八〇--二八一頁参照。
(註⑥)前同書、二九七--二九八頁参照。
(註⑦)志田博士『奥の細道・芭蕉・蕪村』所収「蕪村の宰町資料附巴人・太祇資料」の項、三四四 頁参照。
(註⑧)元文元年九月成の『此長月』(永我撰)に依然巴人の号で一句が見え、一応問題になるが、 この句は博士によれば夙に享保十五年刊の『〓之笛』(淡々撰)に見えている由で、同書よりの 転載と見れば齟齬を来さない。
(註⑨)潁原先生の御指摘によれば、元文二年六月九日羅人の主催で一万六千七百韻を興行し、同十 六日東山で竟宴五百韻を催して、その賀集として出した『一日萬句嘉定蒲簀』の中に「東武宋阿」として一句が見えている由で、これによれば元文二年六月には既に宋阿と号していたと思われる が、先生も言われる如くる『嘉定蒲簀』の出板は無論万句興行の当時よりは後のことと思われる から、確実な文献上の初見としては、やはり元文三年五月の高峨亭会句巻とすべきであろう。
〔転載上の付記:①引用句文などは旧字体・旧仮名遣い。但し、二倍送り記号は*印を付して平仮名の 表記。②本文は新字体・新仮名遣いに改定。③ルビの位置・記述記号などは一部改定。〕