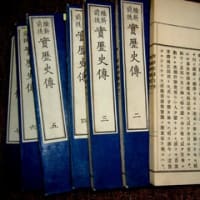吉田松陰、 田中河内介、 真木和泉守
すごい先生たち-50
田中河内介・その49 (寺田屋事件ー38)
外史氏曰
【 生麦事件ー6 】
【 海江田武次と奈良原喜左衛門のこと 】
海江田武次( 信義 )
もともと海江田(かえだ)武次は 有村俊斎(しゅんさい)と言い、雄助、治左衛門、如水( 後の国彦 )の四兄弟の長男であった。
有村俊斎(しゅんさい)の父は 仁左衛門兼善(かねよし) と云い、薩摩では極小身の人であったが、同藩の医師森氏の女(むすめ) 連(れん) を迎えて 男女数人の子を挙げた。 即ち 男子は長男有村俊斎( 後に子爵 海江田信義(かえだのぶよし) )、次男雄助(ゆうすけ)兼武(かねたけ)、三男治左衛門(じざえもん)兼清(かねきよ)、四男如水( 後の国彦 )の四人、女子二人であった。 ( この他に夭折した女子一名 )
兄弟の内、雄助、治左衛門は江戸に出府し、江戸屋敷詰めになった。
長兄の俊斎は世才に長け、家計を助けるために十一歳で茶坊主、十三歳で数寄屋坊主になり、西郷隆盛、大久保利通に相知り会う中にあり、三人は藩主島津斎彬に愛された。
安政六年、俊斎は 京都藩邸に居て、「 井伊斬奸(ざんかん)計画 」の京都工作に奔走する。 「 斬奸計画 」 は水戸有志と密会を重ね、井伊を誅殺し薩摩藩壮士三千人を擁して大挙京に上り、朝廷を守護して幕府に対し朝命によって幕政の改革を迫るものであった。
しかし、この計画は事前に藩主父子に漏れ、同時に呼応して起つ予定であった薩摩の有志四十九名は藩公の切なる鎮撫に心を動かされ、東上を思い止まったので 大事の手筈は悉く狂ってしまった。
江戸の薩摩藩邸では国元のこの急変を知らされず、斬奸を進めていた同士が召還され、残ったのは有村兄弟だけになった。
有村兄弟は進んで水戸藩有志と事を共にせんか、それとも退いて藩公の指揮に従わんか悩む。 そして、二人の悲壮なる決心は、寧(むし) ろ藩公にそむくとも、水藩の有志と事を共にして天下の公議に殉じることであった。
二人は水戸藩と綿密な計画のもと、弟治左衛門は大老井伊の襲撃に加わり、兄雄助は桜田門外での井伊大老の襲撃には参加せず、その結果を見届けた上で京坂に走り、薩摩藩邸で天朝を擁して幕政改革役を担うことになった。
万延元年三月三日、弟 有村治左衛門は 水戸脱藩浪士十七名と共に桜田門外で井伊大老を討ち、その首級を取るが、引き上げの途次、追ってきた彦根藩 供目付助役 小河原秀之丞に背後から斬りつけられ、深傷を負い、辰の口の若年寄遠藤但馬守屋敷の門前にいたりて自刃した。 二十三歳。
兄有村雄助は 薩摩藩壮士三千人をもってする京坂挙兵のため、桜田門外での井伊大老襲撃の結果を見届けるや、即日 水戸脱藩浪士金子孫二郎、佐藤寛と大坂に向かった。 三月九日夜、金子、佐藤、有村の一行は、伊勢の四日市に到着したが、その宿を襲ったのが薩摩藩の捕吏であった。 其れと言うのも、三日の事件後、幕府は犯行者の探索に血眼となり、全国に手配を進めた為、薩摩藩は有村が幕府の役人に捕われる前に、これを捕えて鹿児島へ護送しようとしたのであった。 不幸にして、金子、佐藤も同時に捕えられ、二人は京都伏見の薩摩藩邸から伏見奉行に引き渡され、暫く拘囚されたのち、三月二十四日、江戸に護送された。 金子は処刑され、佐藤は明治まで生きた。
一方、鹿児島に護送された有村雄助は 幕府の追及を恐れる藩庁命で 三月二十三日、桜田事件の関係者として切腹を命ぜられ、母、長兄( 俊斎のちの信義 )、弟( 国彦 ) が見守る中で自刃した。 二十八歳であった。
この有村兄弟の壮烈な働きは、幕末の列女として有名な母 有村連壽尼(れんじゅに) の平素の訓育にあるといわれている。 また連は和歌に巧みであった。
弓張りの月も時雨に曇るかな
思ひ放たば隅なからまし
という激励の歌と
雄々しくも君につかふるますらをの
母てふものはかなしかりけり
という兄弟の死を悼む歌は、薩摩婦人の心根を歌っている。 なお、連は明治二十八年十月二日没、八十八歳。
長男俊斎( 海江田(かえだ)武次・信義 ) は 天保三年二月十一日生れ。 国元では 示現流(じげんりゅう) の名人と言われる薬丸半左衛に学んだ。
嘉永五年、江戸に出仕して水戸藩の藤田東湖らと交わり、その後、薩摩藩の下級武士であった大久保利通・西郷隆盛・伊地知正治・吉井友実らと結束して精忠組を組織した。 信義はその中で尊攘派として活躍した。
桜田事変後、故 日下部伊三次の未亡人がその一女子( 日下部伊三治の死後、妻の静子と一人娘の松子が残された ) と共に鹿児島に来住し、深く俊斎に頼った。蓋し、弟 次左衛門が桜田の一挙前に 日下部家の婿養子たる約束があったためであろう。 遂に俊斎は、文久元年十二月、有村家を弟 如水( 後の国彦 ) に譲って 安政の大獄の犠牲者 日下部伊三次の婿養子となり、日下部の原姓である海江田を名乗り、海江田武次( 諱は信義 )と称する。
その後、戊辰戦争のとき、東海道先鋒総督参謀として江戸開城に功績があった。
風雲の幕末の中で大きな事件に巻き込まれた兄弟。 機運の大きな違いで二人の兄弟 雄助、治左衛門は若くして、桜田門外の変に関連して華々しく散ったが、長兄の俊斎であった海江田武次は明治維新迄生き延び、明治二年 京都で刑法官判事につき、翌年 奈良県知事、明治二十年子爵、同二十三年貴族院議員、翌年枢密顧問官となる。 明治三十九年十月二十七日病没、七十五歳。
四男・有村如水( 後の国彦 ) は、明治以後、島津家家扶、第五国立銀行頭取を務めた。
また、二女が 東郷平八郎元帥の兄四郎兵衛に嫁ぎ、 長男信義の長女が 東郷平八郎元帥に嫁いだ。

海江田信義
奈良原喜左衛門
天保二年六月二十三日生まれ。 寺田屋事件、生麦事件、薩英戦争と活躍した喜左衛門は、慶応元年閏五月十八日に 京都二本松の薩摩藩邸で亡くなり、遺体は東山即宗院に埋葬された。 三十五歳。
但し、以下のような説もある。
【 奈良原喜左衛門は生麦事件後、京摂間にあって国事に奔走し、京都二本松の薩摩藩邸で客死したことになっているが、孫の山口政雄氏が執筆した 『 奈良原喜左衛門伝 』 ( 私家本 ) によると、実は東京品川の海晏寺近くのある寺で、由あって奈良原喜左衛門は切腹を命じられたのが真相のようである。 介錯は喜八郎が願い出た。 その理由は家族にも分からない。 知っているのは 久光と喜八郎、岩下方平(まさひら)の三人のみである。 】 ( 幕末異人殺傷録 宮永 孝著 )
弟・奈良原喜八郎( 繁・幸五郎 )
天保五年五月二十三日生れ。 寺田屋へ鎮撫使として派遣された奈良原喜八郎は喜左衛門の弟である。 寺田屋事件、生麦事件、薩英戦争などで活躍する。
喜八郎( 幸五郎・繁 )も兄と同格の御供目付の地位に就いていたことは、大久保利通の日記の中の五月二十日( 二日後には、久光らは江戸に出発する ) の条に役替(やくがえ) の記述があるが、喜八郎はじめ、海江田武次、大山格之助( 綱良 )、江夏仲左衛門らは、「 寺田屋事件 」 の論功行賞として、御供目付に任命されていた。
静岡県令、日本鉄道会社初代社長、 明治二十五年七月に第8代沖縄県知事に任命され、以来、十五年十ヶ月にわたって県政を占め 「 琉球王 」 といわれた。 明治二十九年男爵。 大正七年八月十三日没。 八十五歳。

奈良原 繁
つづく 次回
すごい先生たち-50
田中河内介・その49 (寺田屋事件ー38)
外史氏曰
【 生麦事件ー6 】
【 海江田武次と奈良原喜左衛門のこと 】
海江田武次( 信義 )
もともと海江田(かえだ)武次は 有村俊斎(しゅんさい)と言い、雄助、治左衛門、如水( 後の国彦 )の四兄弟の長男であった。
有村俊斎(しゅんさい)の父は 仁左衛門兼善(かねよし) と云い、薩摩では極小身の人であったが、同藩の医師森氏の女(むすめ) 連(れん) を迎えて 男女数人の子を挙げた。 即ち 男子は長男有村俊斎( 後に子爵 海江田信義(かえだのぶよし) )、次男雄助(ゆうすけ)兼武(かねたけ)、三男治左衛門(じざえもん)兼清(かねきよ)、四男如水( 後の国彦 )の四人、女子二人であった。 ( この他に夭折した女子一名 )
兄弟の内、雄助、治左衛門は江戸に出府し、江戸屋敷詰めになった。
長兄の俊斎は世才に長け、家計を助けるために十一歳で茶坊主、十三歳で数寄屋坊主になり、西郷隆盛、大久保利通に相知り会う中にあり、三人は藩主島津斎彬に愛された。
安政六年、俊斎は 京都藩邸に居て、「 井伊斬奸(ざんかん)計画 」の京都工作に奔走する。 「 斬奸計画 」 は水戸有志と密会を重ね、井伊を誅殺し薩摩藩壮士三千人を擁して大挙京に上り、朝廷を守護して幕府に対し朝命によって幕政の改革を迫るものであった。
しかし、この計画は事前に藩主父子に漏れ、同時に呼応して起つ予定であった薩摩の有志四十九名は藩公の切なる鎮撫に心を動かされ、東上を思い止まったので 大事の手筈は悉く狂ってしまった。
江戸の薩摩藩邸では国元のこの急変を知らされず、斬奸を進めていた同士が召還され、残ったのは有村兄弟だけになった。
有村兄弟は進んで水戸藩有志と事を共にせんか、それとも退いて藩公の指揮に従わんか悩む。 そして、二人の悲壮なる決心は、寧(むし) ろ藩公にそむくとも、水藩の有志と事を共にして天下の公議に殉じることであった。
二人は水戸藩と綿密な計画のもと、弟治左衛門は大老井伊の襲撃に加わり、兄雄助は桜田門外での井伊大老の襲撃には参加せず、その結果を見届けた上で京坂に走り、薩摩藩邸で天朝を擁して幕政改革役を担うことになった。
万延元年三月三日、弟 有村治左衛門は 水戸脱藩浪士十七名と共に桜田門外で井伊大老を討ち、その首級を取るが、引き上げの途次、追ってきた彦根藩 供目付助役 小河原秀之丞に背後から斬りつけられ、深傷を負い、辰の口の若年寄遠藤但馬守屋敷の門前にいたりて自刃した。 二十三歳。
兄有村雄助は 薩摩藩壮士三千人をもってする京坂挙兵のため、桜田門外での井伊大老襲撃の結果を見届けるや、即日 水戸脱藩浪士金子孫二郎、佐藤寛と大坂に向かった。 三月九日夜、金子、佐藤、有村の一行は、伊勢の四日市に到着したが、その宿を襲ったのが薩摩藩の捕吏であった。 其れと言うのも、三日の事件後、幕府は犯行者の探索に血眼となり、全国に手配を進めた為、薩摩藩は有村が幕府の役人に捕われる前に、これを捕えて鹿児島へ護送しようとしたのであった。 不幸にして、金子、佐藤も同時に捕えられ、二人は京都伏見の薩摩藩邸から伏見奉行に引き渡され、暫く拘囚されたのち、三月二十四日、江戸に護送された。 金子は処刑され、佐藤は明治まで生きた。
一方、鹿児島に護送された有村雄助は 幕府の追及を恐れる藩庁命で 三月二十三日、桜田事件の関係者として切腹を命ぜられ、母、長兄( 俊斎のちの信義 )、弟( 国彦 ) が見守る中で自刃した。 二十八歳であった。
この有村兄弟の壮烈な働きは、幕末の列女として有名な母 有村連壽尼(れんじゅに) の平素の訓育にあるといわれている。 また連は和歌に巧みであった。
弓張りの月も時雨に曇るかな
思ひ放たば隅なからまし
という激励の歌と
雄々しくも君につかふるますらをの
母てふものはかなしかりけり
という兄弟の死を悼む歌は、薩摩婦人の心根を歌っている。 なお、連は明治二十八年十月二日没、八十八歳。
長男俊斎( 海江田(かえだ)武次・信義 ) は 天保三年二月十一日生れ。 国元では 示現流(じげんりゅう) の名人と言われる薬丸半左衛に学んだ。
嘉永五年、江戸に出仕して水戸藩の藤田東湖らと交わり、その後、薩摩藩の下級武士であった大久保利通・西郷隆盛・伊地知正治・吉井友実らと結束して精忠組を組織した。 信義はその中で尊攘派として活躍した。
桜田事変後、故 日下部伊三次の未亡人がその一女子( 日下部伊三治の死後、妻の静子と一人娘の松子が残された ) と共に鹿児島に来住し、深く俊斎に頼った。蓋し、弟 次左衛門が桜田の一挙前に 日下部家の婿養子たる約束があったためであろう。 遂に俊斎は、文久元年十二月、有村家を弟 如水( 後の国彦 ) に譲って 安政の大獄の犠牲者 日下部伊三次の婿養子となり、日下部の原姓である海江田を名乗り、海江田武次( 諱は信義 )と称する。
その後、戊辰戦争のとき、東海道先鋒総督参謀として江戸開城に功績があった。
風雲の幕末の中で大きな事件に巻き込まれた兄弟。 機運の大きな違いで二人の兄弟 雄助、治左衛門は若くして、桜田門外の変に関連して華々しく散ったが、長兄の俊斎であった海江田武次は明治維新迄生き延び、明治二年 京都で刑法官判事につき、翌年 奈良県知事、明治二十年子爵、同二十三年貴族院議員、翌年枢密顧問官となる。 明治三十九年十月二十七日病没、七十五歳。
四男・有村如水( 後の国彦 ) は、明治以後、島津家家扶、第五国立銀行頭取を務めた。
また、二女が 東郷平八郎元帥の兄四郎兵衛に嫁ぎ、 長男信義の長女が 東郷平八郎元帥に嫁いだ。

海江田信義
奈良原喜左衛門
天保二年六月二十三日生まれ。 寺田屋事件、生麦事件、薩英戦争と活躍した喜左衛門は、慶応元年閏五月十八日に 京都二本松の薩摩藩邸で亡くなり、遺体は東山即宗院に埋葬された。 三十五歳。
但し、以下のような説もある。
【 奈良原喜左衛門は生麦事件後、京摂間にあって国事に奔走し、京都二本松の薩摩藩邸で客死したことになっているが、孫の山口政雄氏が執筆した 『 奈良原喜左衛門伝 』 ( 私家本 ) によると、実は東京品川の海晏寺近くのある寺で、由あって奈良原喜左衛門は切腹を命じられたのが真相のようである。 介錯は喜八郎が願い出た。 その理由は家族にも分からない。 知っているのは 久光と喜八郎、岩下方平(まさひら)の三人のみである。 】 ( 幕末異人殺傷録 宮永 孝著 )
弟・奈良原喜八郎( 繁・幸五郎 )
天保五年五月二十三日生れ。 寺田屋へ鎮撫使として派遣された奈良原喜八郎は喜左衛門の弟である。 寺田屋事件、生麦事件、薩英戦争などで活躍する。
喜八郎( 幸五郎・繁 )も兄と同格の御供目付の地位に就いていたことは、大久保利通の日記の中の五月二十日( 二日後には、久光らは江戸に出発する ) の条に役替(やくがえ) の記述があるが、喜八郎はじめ、海江田武次、大山格之助( 綱良 )、江夏仲左衛門らは、「 寺田屋事件 」 の論功行賞として、御供目付に任命されていた。
静岡県令、日本鉄道会社初代社長、 明治二十五年七月に第8代沖縄県知事に任命され、以来、十五年十ヶ月にわたって県政を占め 「 琉球王 」 といわれた。 明治二十九年男爵。 大正七年八月十三日没。 八十五歳。

奈良原 繁
つづく 次回