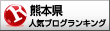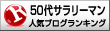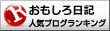いよいよ最終日、今日で組み立てを完成し、全機エンジンがかからなければ終われない授業です!
前回、ピストンの取り付けも終わっていますので、シリンダーヘッドを取り付けますが、その前に、ガスケットパッキン・吸排気弁・弁ばね等も綺麗に洗浄し、綺麗な布で拭きあげておきます。
トルクレンチを使い、規定の25N・mで締め付けます。
次は、ロッカーアームアセンブリの組みたてです。
シリンダーヘッドの内側から、吸排気弁の弁棒を通し弁ばねをはめ、表から写真のように弁ばねをリテーナーで押さえ止めます。
この機種の場合リテーナーは、雪だるまみたいな大小の穴が繋がった穴が開いており、先ず大きな穴に弁棒の尻(くびれ)を通して、親指で押さえ小さな穴の方にずらしながら、くびれをかけロックします。
また、この機種の場合弁棒2本は斜めに傾斜し開いており、そのため弁ばねを止めるリテーナーも斜めに傾斜しますが、低い方に雪だるまみたいな穴の大が来るようにネジって定位置とします。(逆だと、振動で外れる恐れ有り)
2本のプッシュロッドを差込みますが、吸気と排気のプッシュロッドを間違わないように差込みます。
新しいうちは左右に違いはないものの、長く使っているとクセが出来るそうです。
2本のプッシュロッドの差込みにはテクニックがあります。
吸気弁と排気弁を動かすプッシュロッドなので、高さが違うとロッカーアームの取り付けがしにくいことから、フライホイルを回しながら両方同じ高さの位置になるのように調整して、プッシュロッドを挿入します。
ロッカーアーム乗せてロックナットとピボットナットで6N・mで締め付けます。
次に行うのは、バルブクリアランス(弁すき間)の調整です。
弁ばねの復元力によって弁棒とタペットが離れた時、その間にわずかなすき間が出来るようになっています。
これは、弁棒が高熱によって膨張しても、弁が完全に閉じるように空けたすき間で、この機種では0.06~0.08mmとなっています。
すき間ゲージを使い0.07mmで調整しました。
具体的には、フライホイルを回しながら圧縮トップ位置に持って来て、すき間ゲージを弁棒とロッカーアームの接点に挟み込み(写真)、アジャストスクリュのナットをメガネレンチで固定し、マイナスドライバーでアジャストスクリュを調整し、緩くもきつくも無い感触で止めます。
ロッカーアーム(揺れ腕)の取り付けとアジャストスクリュ調整が終わったら、弁椀室カバーをはめます。
ダイナモからの高圧コード(写真:黒いキャップ)を点火プラグの端子にカチ音を確かめながら押し込みます。
この場合1気筒エンジンですが、車のエンジンなど複数気筒:4気筒等の場合は、ディストロビュータの回転子から各4個の点火プラグに順次電流が送られることになります。
また、点火プラグは爆発燃焼によって付着する煤(炭素)を焼き捨てるに必要な温度(自己清浄温度約500℃)を保つ必要があり、その熱はねじ込んだシリンダヘッドに移り、冷却フィンによって放熱されます。
大事なのは点火プラグには熱が逃げやすい【コールド型:高速機関】と、逃げにくい【ホット型:低速機関】があるので、適正な規格を使うことです。
この熱を逃がす度合いを≪熱価(ヒートバリュウー)≫と言います。

この後は、1日目にやった分解と逆の組みたてです。
リコイルスタータをカバーするファンカバーを取りつけます。
コントロールパネルアセンブリの、スロットルレバー、ロッドスプリング、ガバナロッド、ガバナスプリングを元のように取り付けますが、中2日空けると記憶は飛んでしまいます。
特殊なテンションスプリングが複数の穴にはめてあるので、スケッチやデジカメ画像を頼りに取り付けていました。 
空気清浄器(エアクリーナー)の清掃は、実際場面では最も身近な清掃ですが、今回は頻繁に分解組み立てする練習機で綺麗ですので、省略しました。
一般的には、乾式空気清浄器で、濾紙や不織布、スポンジ等の濾材がはめてあります。汚れている場合は、洗浄スプレー等で綺麗にします。
トラクター等の濾材には円筒形のフィルターがあり、コンプレッサーの空気で汚れを吹き飛ばしますが、その場合は必ず筒の内側から外に向かって吹くことが大事です。
外から吹くと、埃をフィルターの奥に押し込んでしまいます。
また、気化器(キャブレタ)の清掃も実際場面では最も身近な清掃ですが、同様に省略しました。
気化の原理は、吸入行程でシリンダ内が負圧になると、空気清浄器を通った空気が気化器に吸入されます。気化器の中は流路を急にベンチョリ部で、さらに流速が増し負圧になるので、主ニードル弁から燃料が吸い上げられます。
この時、空気流と吸い上げられた燃料が霧状の混合気になります。
チョークを引く始動時混合比は、1対8~10。
高・低速時の混合比は、1対13。
経済混合比は、1対17~18 とされ、1対20以上では薄すぎて点火しなくなり、1対8以下では濃すぎて点火しません。
空気清浄器と、気化器を取り付けます。
ガソリンタンクとフューエルコック部分を取り付けたら、ガソリンを入れます。 
さて、うまく起動するでしょうか?
いろいろ不調機もありましたが、全機無事に動きました。
めでたしめでたし!
さて、この日も道具の最終チェックです。
58品の全部の確認が出来て、3日間(延べ9時間)にわたったガソリンエンジン分解・組み立てが完了しました。
エンジンを分解するなんて、卒業したらなかなか一人では出来ません。
今回の体験が、我が家の農機のメンテナンスにも役立つことでしょう。
また、外部に修理依頼する時も、ズブの素人では無い知識人の依頼をして、より経済的に修理が出来ると期待します。
熊本県立農業大学校2年機械応用・ガソリンエンジン分解組み立て!1日目
ガソリンエンジン分解組み立て!2日目
~ お願い
お願い イイネなら、『熊本県人気ブログランキング』をクリックして、投票して下さい。
イイネなら、『熊本県人気ブログランキング』をクリックして、投票して下さい。

ランキングに参加中です。現在、熊本県内 26位 クリックして応援お願いします!