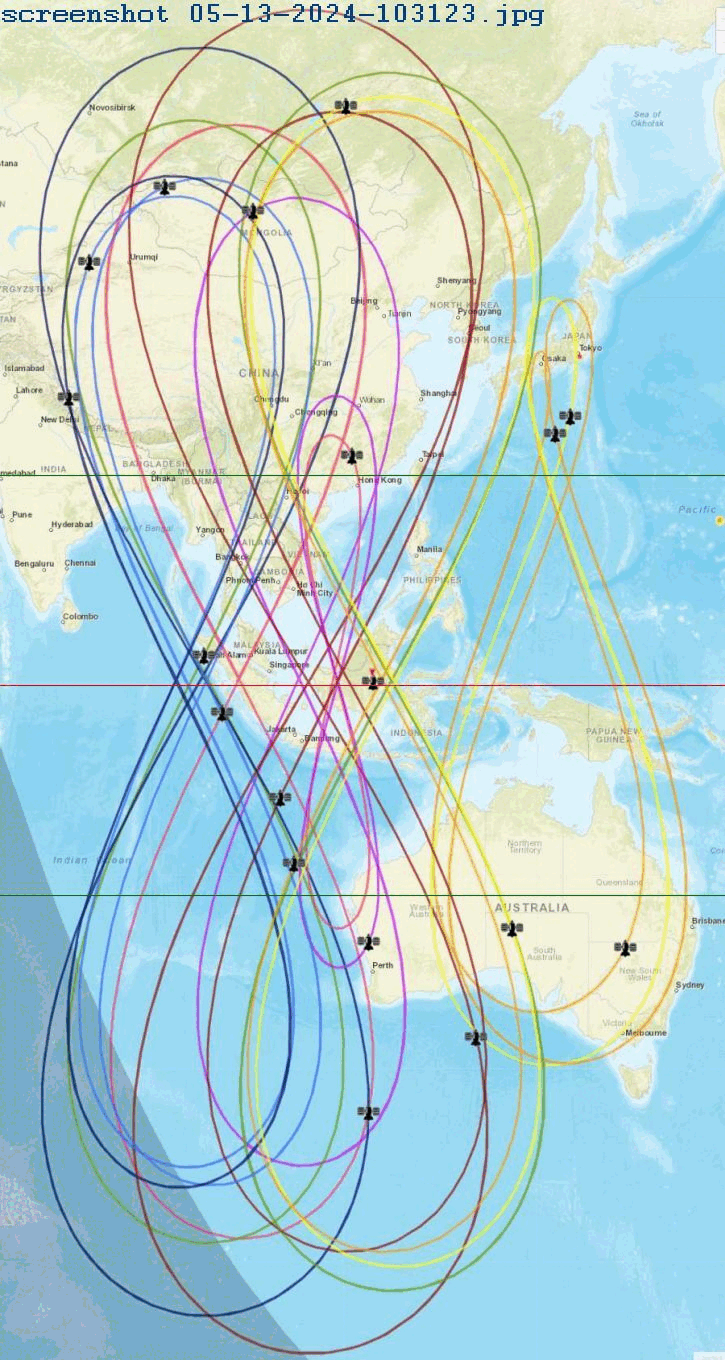24.5.13 今回の強烈な太陽フレア活動を受けて,前世紀まで太陽黒点11年周期と呼ばれることが多かったソーラサイクル太陽活動周期について復習しておくことが重要です.

歴史的経緯から現在のサーラサイクルは約11年ごとの周期で第25期とカウントされています.以下の図からも判りますように,第23期以降の太陽活動は低迷をしてきましたので,第25期の今回のソーラサイクルがこれほど激烈な活動サイクルになるとは予想されていませんでした.来年はソーラサイクルピークを迎えますから,IGSO/QZS GPSなど地球衛星測位系にとって正念場となるかもしれません.またソーラサイクルピークと磁気圏の無い月面探査とが絡み合うことは,まさに宇宙開発の醍醐味となってくるでしょう.
当方は大学院時代を1970年代初頭に東北大学の女川地磁気観測所の地磁気測定データと南極昭和基地から持ち帰られた地磁気記録データの比較の研究に打ち込んでいました.つまり第20ソーラサイクル期の地磁気データを主に扱っていたことになります.その後の時期もソーラサイクルの活動性については継続して関心をもっていましたが,全般的には太陽活動が低迷することが多く,太陽の無黒点時期が来るのではとの説すらも流れました.しかし,今回激烈な活動サイクルに入って,低緯度オーロラまでが日本各地で観測されて国民的な関心が大いに高まったのは大変結構なことだと考えています.
南下中のQZS-2が太陽合ピークに到達しました.今週一杯かけてQZS-2太陽合とIG三座クロス太陽合が黄道上で重なり合うダブルクロスイベントの生起が控えています.QZS-2とIG三座,そしてQZS-4とIG四座は半年ごとに黄道上での太陽合が重なり合うダブルクロスイベントを引き起こすように軌道配置がされているようです.詳細は省きますが,グローカル・イーストIG座系として,有効な活用を検討しうる関係にあると言えるでしょう.



β角プロットを用いてQZSとIGSOのクロス太陽合の前倒し現象を年単位の時空間現象として確認しようとしているところが本ブログの重要な出発点でした.
QZS/IGSO座群はグローカル・イーストが達成した21世紀の現時点にけるにおける衛星軌道技術の到達点のひとつでしょう.欧米先進地域でもQZS/IGSO座構築に挑戦し実現しているところはありません.QZS/IGSO座軌道群のデータリダクションを継続して,記録してゆく意義は大きいと考えます.その応用技術として月面測位技術への応用に未来を見たいと思います.
当面は以下のN2YOのURLを使用するようにします(アンカーKOREASAT-7).
https://www.n2yo.com/?s=42691|36828|37256|37384|37763|37948|41434|42738|42965|40547|41241|43539|44204|40938|40549|44709|44337|49336
N2YOサービスの画面コピーを利用したIGSO/QZS衛星軌道群の地表への射影の16時間分のIGSO/QZS群衛星軌道アニメGIFを記録します.
(1) IGSO/QZSS射影軌道の16時間分の10分毎のアニメGIF
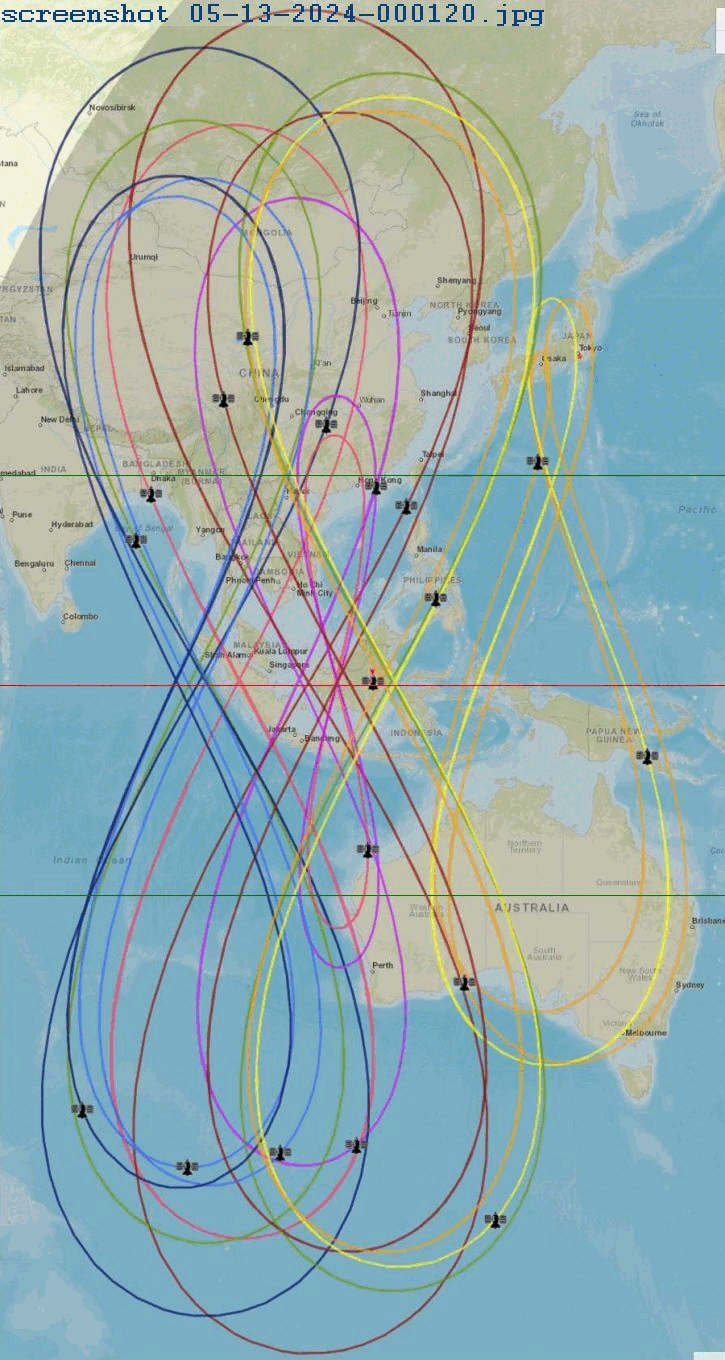
(2) IGSO/QZSS射影軌道の昼間6時間分の2分毎のアニメGIF
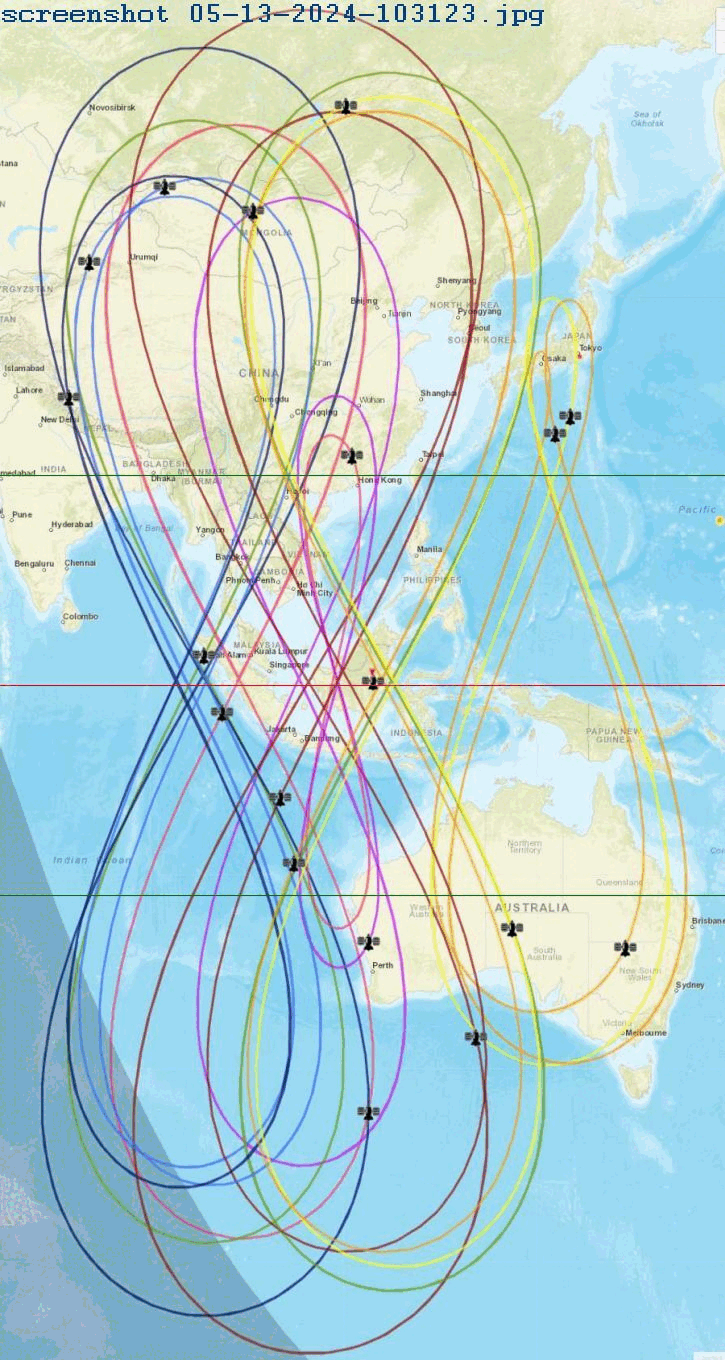

歴史的経緯から現在のサーラサイクルは約11年ごとの周期で第25期とカウントされています.以下の図からも判りますように,第23期以降の太陽活動は低迷をしてきましたので,第25期の今回のソーラサイクルがこれほど激烈な活動サイクルになるとは予想されていませんでした.来年はソーラサイクルピークを迎えますから,IGSO/QZS GPSなど地球衛星測位系にとって正念場となるかもしれません.またソーラサイクルピークと磁気圏の無い月面探査とが絡み合うことは,まさに宇宙開発の醍醐味となってくるでしょう.
当方は大学院時代を1970年代初頭に東北大学の女川地磁気観測所の地磁気測定データと南極昭和基地から持ち帰られた地磁気記録データの比較の研究に打ち込んでいました.つまり第20ソーラサイクル期の地磁気データを主に扱っていたことになります.その後の時期もソーラサイクルの活動性については継続して関心をもっていましたが,全般的には太陽活動が低迷することが多く,太陽の無黒点時期が来るのではとの説すらも流れました.しかし,今回激烈な活動サイクルに入って,低緯度オーロラまでが日本各地で観測されて国民的な関心が大いに高まったのは大変結構なことだと考えています.
南下中のQZS-2が太陽合ピークに到達しました.今週一杯かけてQZS-2太陽合とIG三座クロス太陽合が黄道上で重なり合うダブルクロスイベントの生起が控えています.QZS-2とIG三座,そしてQZS-4とIG四座は半年ごとに黄道上での太陽合が重なり合うダブルクロスイベントを引き起こすように軌道配置がされているようです.詳細は省きますが,グローカル・イーストIG座系として,有効な活用を検討しうる関係にあると言えるでしょう.



β角プロットを用いてQZSとIGSOのクロス太陽合の前倒し現象を年単位の時空間現象として確認しようとしているところが本ブログの重要な出発点でした.
QZS/IGSO座群はグローカル・イーストが達成した21世紀の現時点にけるにおける衛星軌道技術の到達点のひとつでしょう.欧米先進地域でもQZS/IGSO座構築に挑戦し実現しているところはありません.QZS/IGSO座軌道群のデータリダクションを継続して,記録してゆく意義は大きいと考えます.その応用技術として月面測位技術への応用に未来を見たいと思います.
当面は以下のN2YOのURLを使用するようにします(アンカーKOREASAT-7).
https://www.n2yo.com/?s=42691|36828|37256|37384|37763|37948|41434|42738|42965|40547|41241|43539|44204|40938|40549|44709|44337|49336
N2YOサービスの画面コピーを利用したIGSO/QZS衛星軌道群の地表への射影の16時間分のIGSO/QZS群衛星軌道アニメGIFを記録します.
(1) IGSO/QZSS射影軌道の16時間分の10分毎のアニメGIF
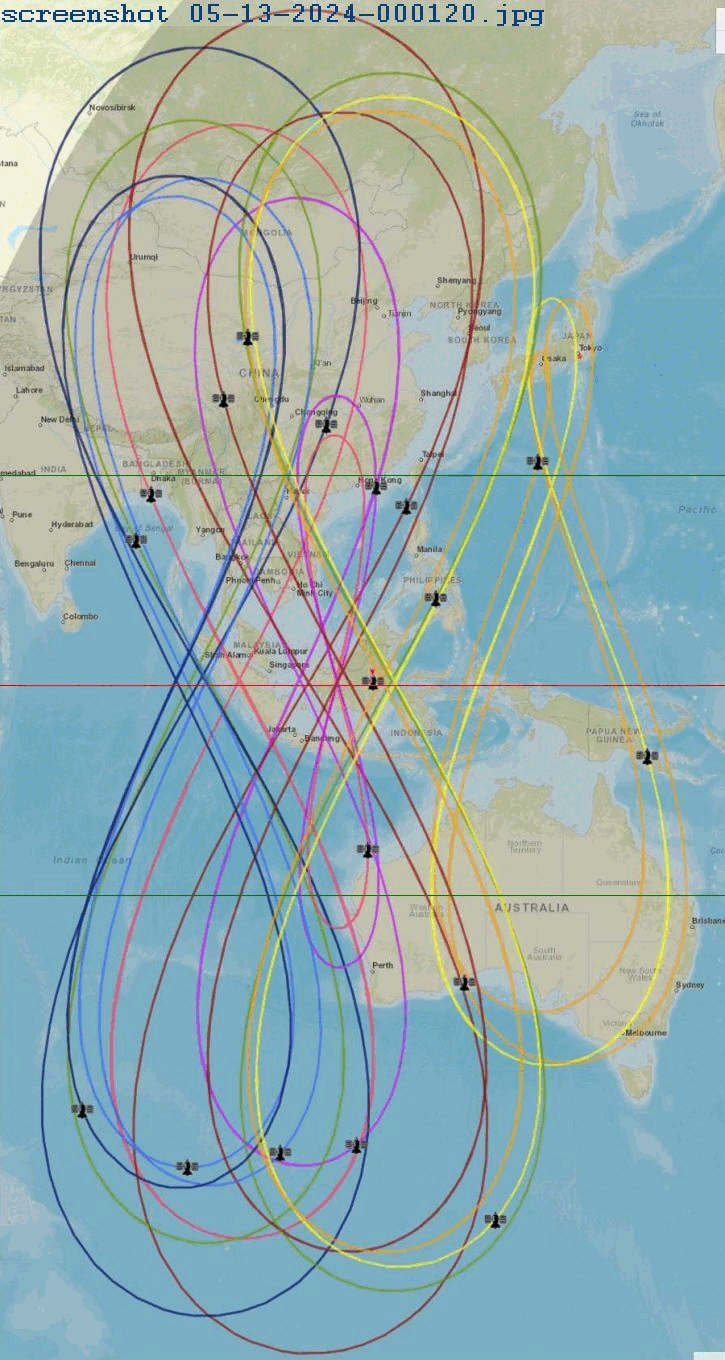
(2) IGSO/QZSS射影軌道の昼間6時間分の2分毎のアニメGIF