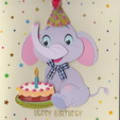2011年9月29日(木)、一関市東山町「唐梅館公園」に行きました。西本町地区と北磐井里地区を結ぶ車道が通じており、峠付近の道路沿いに生えているクサギ(臭木)が、真っ赤な萼にのった藍色に熟した実を沢山つけていました。
峠からは、東側の遥か遠くに室根山(標高895m)が見えました。






クサギ(臭木) クマツヅラ科 クサギ属 Clerodendron trichotomum
山野の林縁や川岸などの日当たりの良い所に普通に生える落葉小高木。高さは3~5m、時に9mになる。樹皮は灰色で丸い皮目が多く、老木では縦に浅い割れ目ができる。葉は対生し、長さ8~20㎝の三角状心形または広卵形で、先は尖り、基部は円形。縁にはまばらに浅い鋸歯があるか、ほとんど全縁。脈上に軟毛が散生することがある。葉柄は2~10㎝と長い。若葉は食べられる。枝や葉を切ると独特の臭気(強い悪臭)があるのでこの和名がある。
8~9月、枝先の葉腋から長い柄のある集散花序を出して、香りの良い直径2~2.5㎝の白い花をつける。花冠は長さ2~2.5㎝の細長い筒状で、先は5裂して平開する。雄しべ4個と雌しべ1個は花冠の外に長く突き出て、先端は上向きに曲がる。葯は黒紫色で丁字形に付き、花粉は花の匂いに誘われて集まるガ(蛾)やチョウ(蝶)の体に付いて運ばれる。萼片は長さ約1㎝の卵形で、果期には平開して美しい紅色になる。
果実は、直径6~7㎜の球形で、光沢のある藍色に熟す。果実をワラ(藁)の灰汁で煮出した液で布を染めるとあさぎ(浅黄)色になる。根は薬用にされる。材は下駄、薪炭に利用される。分布:北海道、本州、四国、九州、沖縄、朝鮮、中国、台湾。
[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・日本の樹木」より