
図版は「母の肖像3」(2015年制作・和紙に墨とアクリル絵具・59.4×42.0㎝)である。「愛」という文字がかかれている。
私にとって母の死は、衝撃であった。すべての愛が無くなったと感じた。
この作品は母の死後1年ほど経ってからかかれたものである。母の肖像を「愛」と墨でかいた後、ただ白いだけのまぶし過ぎる余白に、母に対する私の憶(おも)いと感情を、色彩を使って塗り重ねていったのである。母と対話していたと言った方が適切かもしれない。何層にも塗り重ねた結果、はじめ青かったものが次第に黒に近いものに変化していった。母の肖像が黒い闇の中に消え
てしまわないように文字の点画の周囲だけを塗り残さねばならなかった。不思議な青白い光りが文字の縁(へり)から立ち現れた。これは何なのだろうか。これが余白というものなのだろうか。これが彼岸の色なのだろうか。私は何をかこうとしているのだろうか。ただ出来るだけ永く、できれば永遠に母と一緒にいたいという願いだけで塗りつづけただけのことに過ぎない。芸術などという高尚なものではない、徹底的に個人的な、私だけの世界である。また、これは伝統的な詩書画一致の作品でもある。絵が花や風景ではなく、抽象的な色彩だけの表現になっているのである。上代の唐紙にあるような装飾的な料紙の色とは本質的に異なっている。
書の歴史の重畳だの、書法だ技法だ理論だといった理屈など、書をかき続ける動機にはならない。私は書を探求して、練習を重ね、書に上達して、人間や社会について理解を深め、人間性に磨きをかけて、私を愛してくれた母の愛に報いるために、母の喜ぶ顔を見たいがために、身を削るような事でも苦にせずに作品をかきつづけてきたのだった。母の死によって私は今までかいてきたすべての作品が空しいものに思われた。それらは、母がいなくなれば何の価値もない紙屑みたいなものである。
芸術作品に普遍的なものなどないのである。良寛は立派な人らしいが、私には関係のない事である。井上有一は型破りで魅力的な人間で、その作品には芸術的価値があり、世界が認めているというが、彼が世界的であろうがなかろうが私と何の関係があろうか。井上有一が有名になっても世界は変わらない。良寛が死んでも悲しむ人は一握りの人で、世界は微動だにしない。
このように個人的で他人には関係のない作品を公開することには躊躇する。私は今まで母を喜ばせたい一心で作品を発表してきたが、母がいなくなった今、発表する動機が希薄になってしまった。このような個人的な意味しかない作品をかき続ける意味も、発表する意義も分からないまま、私は、かき続け発表もしているのである。非常に危うい、今にもちぎれそうな、細い綱の上をフラフラしながら私は歩いているようなものだ。

図版は「母の肖像10」(2016年制作・紙に墨とアクリル絵具・103×72.8㎝)である。「根源」と墨でかかれている。
私は、亡き母との対話を続けながら作品をかき続けた。これは絶対的に個人的なことであり、ただ母と過ごしたい一念でかいているに過ぎないのだが、また別に、文字の周縁に現れた細い余白が何なのか、単なる強調のための輪郭線ではない、その正体をつきとめたいという欲求のために、私は、かきつづけ作品を発表した。
この周縁の余白は、墨でかいた母の肖像の背景がまぶし過ぎるので、母と対話をしながら、何層も絵具を塗り重ねた結果出現したもので、文字が背景の闇の中に消えてしまわないように文字の周縁にかき残されたものである。このように実際的な必要から生まれた輪郭線ではあるが、はじめ、私には、どうしても越えられない生と死の境界線のようにも感じられた。生者と死者は決して交わることは出来ないのかも知れないが、私は何とかして此岸を乗り越えて死者の住む世界へ行こうと試みたのである。今では、この周縁にある余白は此岸と彼岸を隔てながら、それらを結びつけているものであることが分かっているが、書をはじめてから昨日まで、私には余白の真の意味が分かっていなかったのである。


図版は「家族の肖像」(2016年制作・紙に墨とアクリル絵具・103×72.8㎝)とその部分の拡大である。「星・月・太陽・地球」とかかれている。母は十代の頃、朝鮮半島から引き揚げてきた。その母の父母や兄弟姉妹が半島を着の身着のままで逃亡し帰国する途中の孤立した家族の肖像を墨でかいた後に、何層にも絵具を塗り重ねたものである。亡き母と対話するなかで、母の父母や姉妹たちの思い出ばなしになった。それで、母の父母や姉や弟の肖像書をかいたのである。
文字の周縁の余白には、白の中に虹のような色がちらちらしている。これは、塗り重ねた時間の名残である。喜びや苦しみや悲しみや寂しさを含んだ色が何層にも塗り重ねられているのである。虹色を描こうと企んだのではなく、母や母の父母姉妹たちと共に感じた哀しみが結果として複雑な色になったのに過ぎない。
私は、母の死に導かれて「母の肖像」をかくなかで、私の四半世紀の書活動の途中で、私の作品に時おり現れた不思議な余白の意味と、小川芋銭の絵画に描かれていた余白や良寛の書の余白の意味に気づいた。余白から書芸術を鑑賞してみると、余りにも深さの無い作品が多いのに驚く。ほとんどの書家の書の余白は、ただの白か、装飾的な造形空間に過ぎなかった。良寛や芋銭の余白からは、彼等の思想や理想が読み取られ、正直で純粋な人間性が感じられたが、彼等は書芸術史上稀有な存在であった。文字の書きぶりから過去の書作品を見ると、変化に富んだ多様な書芸術作品が存在しているかのように見えるが、しかし、そこには真の余白のあるものは少ない。特に、20世紀後半からの書家の書には、彼岸を引き寄せるだけの力のある余白を持った書は皆無に等しいといえるだろう。このような書に魅力があるはずがない。書の魅力は造形的な美にあるのではなく、古来から言われているように、書人の思想や理想やものの感じ方といった人間性にあり、それが余白に顕現したとき、見る者は、はじめて玄妙なる感動を味わうことが出来るのである。
私は思わぬ偶然から余白の重要性に気づいたが、余白がなんであるのか分かったわけではない。何かとんでもないものが余白には潜んでいるに違いないと直観しただけである。私は長い時間をかけて余白と格闘してきたようにも感じているが、なぜだか分からない。私は、かき続けられる限り、私が見つけた細い周縁を通って、さらに余白の実態を明確にしたいと思っている。そして、母の住んでいるであろう、生死を越えた世界への隘路を見つけたいと思っている。また、余白は窓枠の様なものである。その窓を開けて、余白の向こうにあるであろう夢の世界を書画に造形したいとも考えている。
書壇というものを私はよく知らない。書壇に関係なく私は字をかいてきた。仮に書壇がなくなったとしても、日本がなくならない限り、書芸術は永遠に続いてゆくであろう。書芸術は昔から書壇の独占物ではない。良寛の周縁にいた多くの庶民が良寛の作品を大事にしたように、こころある誠実な庶民がいる限り、人間性の象徴である書芸術が人びとに愛されないはずがない。書を学び表現しようとする者は、自己の思想や理想や物の見方、感じ方を磨き、人間らしさの根源を見極めなければならないだろう。書の技術は自己を磨くためにあるのだ。作品はその上に実る花実である。常に余白を見つめ、余白に何ものかが現れるまでかき続ける事である、と私は思う。(完)


















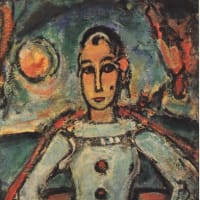


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます