
妖艶なエコノミスト・浜矩子は2月18日の講演会で、
『私は「一人は皆のため 皆は一人のため」という言葉が今ほど、人類の生存のために、重要になったときはないと思います。
一人が一人のためだけを考えているとき、我々は「合成の誤謬」の罠から身を守ることは出来ませんし、絶対に「自分さえ良ければ病」に罹らずにいるわけにはゆきません。
一人が一人のためだけを考えていればいるほど、恐慌深まりし中で、我々は一蓮托生で奈落のそこに逝ってしまう訳なので、「一人は皆のため 皆は一人のため」という心意気に形を与えられるか?
そういうところが、ついこの間(2月13日、14日)のG7の会合とか、4月に開かれますG20の会合に集まる人たちに求められる心意気だと思います。
その辺のところを共通認識として持たずして、いくら小手先的な生命維持装置を生み出しても、この難局を乗り越えることは出来ないのです』
と、ヒューマンジャングルでの心意気を説いている。
「浜矩子は、エコノミストではなく宗教伝道師か?」と疑われるような発言を繰り返しているのだ。
しかし、浜矩子が3月29日付毎日新聞“時代の風”欄に寄稿した、「君の内需は私の外需――ロンドン会議再び」を読むことで、すべてが氷解するのである。
浜矩子は、その文末で「2009年のロンドン会議において、発想の転換をリードする賢者は果たして出現するか?」と結んでいるが、小欄は、「浜矩子こそ、その賢者である」と讃えたい。
以下、「君の内需は私の外需」より抜粋
●ロンドン会議再び
4月2日のG20サミットが近づくにつれて、1933年の「世界経済会議」との対比に関する論考が目につく。
1933年の6月12日に開かれた世界経済会議はロンドンで開かれた。
今回のG20サミットも開催地はロンドンである。
そしていずれのロンドン会議も、世界中を震撼させる大不況の中での開催である。
大不況の深化を食い止めるに当たっての課題も両者に共通している。
端的にいって、それは保護主義の蔓延を回避するという命題である。
これだけ共通点が揃えば、誰でも、二つのロンドン会議を比べてみたくなる。そこで言えることは何か。第一に、21世紀のロンドン会議は決して20世紀のロンドン会議の二の舞を演じてはならない。
そして第二に、重要なのは発想の転換である。
●33年ロンドン会議の失敗
33年のロンドン会議に先立って、その準備委員会保護主義回避の重要性を強調したメモを作成していたにもかかわらず、会議は経済的国家主義を排除することに完全に失敗した。
会議に参集した国々は第一に、この場が交渉の場であると誤解した。第二に、この誤解に基づいて、彼らはその場に「相互主義」の構えをもって臨んだ。
会議は交渉の場であってはいけなかった。大不況の底なしのクレパスから、世界経済を引き上げるための知恵と力の出し合いの場であるはずだった。
相互主義とは要するに、相手より決して自分が損しないことを旨とする行動原理だ。相手が譲歩した以上には、こちらも決して譲歩はしない。
(こうして、33年ロンドン会議は)世界的な危急存亡のときに全く埒が明かず失敗に終わった。
●アメリカ発の互恵主義
だが、アメリカが画期的な新通商政策を打ち出した。1934年互恵通商協定法である。
ここで、通商の世界に「相互」に代わる「互恵」の概念が始めて登場した。この違いは大きい。互恵とはすなわち「進んでお互いに恩恵を施しあう」という考え方だ。
絶対に相手より損はしないぞ、という相互主義のケチくささとは対照的だ。発想が逆転している。
互恵の精神にのっとり、当時のアメリカは大統領に関税一律50%引き下げ権限を付与した。アメリカ大統領は、相互的に制約されることなく、世界に向かってアメリカ市場を開放する権利を手にした。アメリカにもこんな時代があったのである。
●ニューディール政策失敗の苦肉の策
ただし、この時点でアメリカが互恵主義に転じたのは、何も、突如として博愛の精神に目覚めたからではない。当時のアメリカは要するに生産力をもて余していた。
ニューディール政策でいくら内需拡大を図っても、やはり、それだけではそれ以前のバブル期に膨らんだ供給力を吸収できない。どうしても外需が必要だった。
だが、アメリカが世界に対して市場の門戸を閉ざしている限り、世界もアメリカに市場を提供してくれない。相互主義でお互いにやり合っている限り、この袋小路から抜け出すことは不可能だ。
互恵主義への転換は、そこに気づいての転換だった。
かくして残念ながらアメリカの互恵主義への転換も、別段高邁な精神の表れではなかった。だが、逆に言えば、何も人々の精神性が高まらずとも、保護主義合戦の泥沼から脱却することは出来るというわけだ。
さらにいえば、あのときのアメリカのいわば捨身の変身は、内需がだめなら外需で行こう、という発想の限界を良く示している。30年代においてさえそうだったのである。いわんや、グローバル時代の今日において、各国が外需の落ち込みを内需転換で補えると思うのは愚かだ。しかも、その内需をお互いに開放し合わず抱え込むというようなことで、何とかなるはずはない。みんなの内需がみんなの外需なのである。
2009年のロンドン会議において、発想の転換をリードする賢者は果たして出現するか。
浜矩子(はまのりこ)語録 目次へ
『私は「一人は皆のため 皆は一人のため」という言葉が今ほど、人類の生存のために、重要になったときはないと思います。
一人が一人のためだけを考えているとき、我々は「合成の誤謬」の罠から身を守ることは出来ませんし、絶対に「自分さえ良ければ病」に罹らずにいるわけにはゆきません。
一人が一人のためだけを考えていればいるほど、恐慌深まりし中で、我々は一蓮托生で奈落のそこに逝ってしまう訳なので、「一人は皆のため 皆は一人のため」という心意気に形を与えられるか?
そういうところが、ついこの間(2月13日、14日)のG7の会合とか、4月に開かれますG20の会合に集まる人たちに求められる心意気だと思います。
その辺のところを共通認識として持たずして、いくら小手先的な生命維持装置を生み出しても、この難局を乗り越えることは出来ないのです』
と、ヒューマンジャングルでの心意気を説いている。
「浜矩子は、エコノミストではなく宗教伝道師か?」と疑われるような発言を繰り返しているのだ。
しかし、浜矩子が3月29日付毎日新聞“時代の風”欄に寄稿した、「君の内需は私の外需――ロンドン会議再び」を読むことで、すべてが氷解するのである。
浜矩子は、その文末で「2009年のロンドン会議において、発想の転換をリードする賢者は果たして出現するか?」と結んでいるが、小欄は、「浜矩子こそ、その賢者である」と讃えたい。
以下、「君の内需は私の外需」より抜粋
●ロンドン会議再び
4月2日のG20サミットが近づくにつれて、1933年の「世界経済会議」との対比に関する論考が目につく。
1933年の6月12日に開かれた世界経済会議はロンドンで開かれた。
今回のG20サミットも開催地はロンドンである。
そしていずれのロンドン会議も、世界中を震撼させる大不況の中での開催である。
大不況の深化を食い止めるに当たっての課題も両者に共通している。
端的にいって、それは保護主義の蔓延を回避するという命題である。
これだけ共通点が揃えば、誰でも、二つのロンドン会議を比べてみたくなる。そこで言えることは何か。第一に、21世紀のロンドン会議は決して20世紀のロンドン会議の二の舞を演じてはならない。
そして第二に、重要なのは発想の転換である。
●33年ロンドン会議の失敗
33年のロンドン会議に先立って、その準備委員会保護主義回避の重要性を強調したメモを作成していたにもかかわらず、会議は経済的国家主義を排除することに完全に失敗した。
会議に参集した国々は第一に、この場が交渉の場であると誤解した。第二に、この誤解に基づいて、彼らはその場に「相互主義」の構えをもって臨んだ。
会議は交渉の場であってはいけなかった。大不況の底なしのクレパスから、世界経済を引き上げるための知恵と力の出し合いの場であるはずだった。
相互主義とは要するに、相手より決して自分が損しないことを旨とする行動原理だ。相手が譲歩した以上には、こちらも決して譲歩はしない。
(こうして、33年ロンドン会議は)世界的な危急存亡のときに全く埒が明かず失敗に終わった。
●アメリカ発の互恵主義
だが、アメリカが画期的な新通商政策を打ち出した。1934年互恵通商協定法である。
ここで、通商の世界に「相互」に代わる「互恵」の概念が始めて登場した。この違いは大きい。互恵とはすなわち「進んでお互いに恩恵を施しあう」という考え方だ。
絶対に相手より損はしないぞ、という相互主義のケチくささとは対照的だ。発想が逆転している。
互恵の精神にのっとり、当時のアメリカは大統領に関税一律50%引き下げ権限を付与した。アメリカ大統領は、相互的に制約されることなく、世界に向かってアメリカ市場を開放する権利を手にした。アメリカにもこんな時代があったのである。
●ニューディール政策失敗の苦肉の策
ただし、この時点でアメリカが互恵主義に転じたのは、何も、突如として博愛の精神に目覚めたからではない。当時のアメリカは要するに生産力をもて余していた。
ニューディール政策でいくら内需拡大を図っても、やはり、それだけではそれ以前のバブル期に膨らんだ供給力を吸収できない。どうしても外需が必要だった。
だが、アメリカが世界に対して市場の門戸を閉ざしている限り、世界もアメリカに市場を提供してくれない。相互主義でお互いにやり合っている限り、この袋小路から抜け出すことは不可能だ。
互恵主義への転換は、そこに気づいての転換だった。
かくして残念ながらアメリカの互恵主義への転換も、別段高邁な精神の表れではなかった。だが、逆に言えば、何も人々の精神性が高まらずとも、保護主義合戦の泥沼から脱却することは出来るというわけだ。
さらにいえば、あのときのアメリカのいわば捨身の変身は、内需がだめなら外需で行こう、という発想の限界を良く示している。30年代においてさえそうだったのである。いわんや、グローバル時代の今日において、各国が外需の落ち込みを内需転換で補えると思うのは愚かだ。しかも、その内需をお互いに開放し合わず抱え込むというようなことで、何とかなるはずはない。みんなの内需がみんなの外需なのである。
2009年のロンドン会議において、発想の転換をリードする賢者は果たして出現するか。
浜矩子(はまのりこ)語録 目次へ










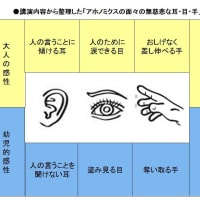

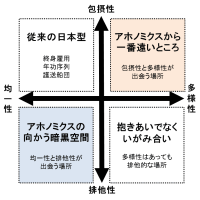













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます