会社の民事再生事件では,ほとんどの場合,別除権協定が必須となる。別除権協定とは,再生債務者(会社)所有の不動産に,抵当権(根抵当権)を有している再生債権者がいる場合で,その不動産が会社の継続上必須のものである場合には,その不動産上の抵当権を実行されると,会社の継続が不可能になるので,その再生債権者と交渉して,不動産によって担保されている部分については,期限の利益を付与してもらって分割弁済とし,その弁済が済めば担保を抹消することにし,その抵当権によって担保されている債権が不動産価格(根抵当権の極度額)を上回るときは,その担保されない部分を一般再生債権として再生計画に従って弁済するという協定をすることをいっている。
この別除権協定がないと,再生債務者の立場では,いつ抵当権を実行されるかもしれず,事業の継続が他人(金融機関等)の胸先三寸で決まる,というか,まっとうな債権者なら当然実行してくるということで,再生計画の認可が危うくなるし,仮に再生計画の認可が得られたとしても,再生計画の遂行ができなくなってしまう。
そうであるから,この別除権協定の締結は,民事再生事件の申立人(代理人)としては,結構大変な仕事になる。要は,担保不動産の価値をいくらに評価するかにかかっているのだが,債権者の方は,担保価値をできるだけ高くみて,回収率を上げようとする一方で,別除権協定がまとまらなかったために,会社の存続を諦められて,破産ともなると,自分が真っ先に悪者にされるというリスクを負っていて,なかなか微妙な立場に立たされることになる。
再生債務者としても,担保価値を高くみると,話はまとまりやすいが,後の弁済の負担が増えて,きつい思いをしなければならないし,担保価値を不当に高くみつもると,監督委員が同意してくれなかったり,裁判所から,「それって一般再生債権を再生計画によらずに弁済することになりません?」とか,「別除権者も再生債権者ですからねー。再生計画による権利の変更の平等に反しません?」などと嫌味を言われて,最終的には,再生計画不認可などという憂き目に逢わされることになる。
*****
まあ,それはともかくとして,この別除権協定は,民事再生法のどこに根拠があるのだろうか。民事再生法に,「別除権協定」という言葉は出てこないし,担保権消滅制度という強制的な制度はあるけれども,話し合いで担保権の実行を止める方法があるとは,どこにも書いていない。立法当初に出たコンメンタール(花村良一・民事再生法要説)をみても,「別除権については話し合いで実行を止める方法があります」等という解説はどこにもない。
しかし,その道の専門家達は,別除権協定を当然のことと理解してやっている。別除権協定を「民事再生法の影の主役」という人もいる(三上徹)くらいである。
そんな方に直接聞くわけにもいかず,あれこれ調べて(今手元にないが,最近出た新しいコンメンタールにちょっと出てきた。),やっと辿り着いたのが,民事再生法88条である。
別除権者は、当該別除権に係る第五十三条第一項に
規定する担保権によって担保される債権については、
その別除権の行使によって弁済を受けることができ
ない債権の部分についてのみ、再生債権者として、
その権利を行うことができる。ただし、当該担保権
によって担保される債権の全部又は一部が再生手続
開始後に担保されないこととなった場合には、その
債権の当該全部又は一部について、再生債権者とし
て、その権利を行うことを妨げない。
ぱっと見ただけでは,この条文のどこが別除権協定なのか,ということになるが,この「当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合」の中に,担保権者との話し合いで債権の一部を担保から除外することができる,という趣旨が含まれているということのようである。
すなわち,別除権協定で,一般再生債権として支払う部分を協定することが,ここにいう「被担保債権の一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合」に当たるということなのである。
で,もう一度立法当初の本をひもといてみると,確かに,別除権予定不足額の確定の方法には,合意による方法がある,という解説が出ている(才口ほか編・民事再生法の理論と実務(下)74頁・森恵一執筆部分)。しかし,解説があるといっても,たったの10行ちょっとでしかない。
☆☆☆☆☆
これくらいのことで,調べものにずいぶんな時間を取るのは,自分自身の不勉強の結果であることは認めざるを得ないし,こんな文章を書くのも,自分の恥曝しなのだが,それはそれとして,やっぱり「何かねぇ~」という心境から抜けきれない。
大体,民事再生に,別除権協定といっているものが必須であることくらい,立法者だって分かっていることなのだから,それらしい条文を置いてくれてもいいではないか。立法技術上,こうしか仕方がなかったというなら,少なくとも,立法当初に出す解説本には,それなりの扱いで(ここが大事だよ,と)書いてもらいたい。
法律が平仮名になって,ようやく分かりやすくなったとはいえ,やっぱり日本の法律は分かりにくい。不勉強は自分の責任なのだけれども・・・

この別除権協定がないと,再生債務者の立場では,いつ抵当権を実行されるかもしれず,事業の継続が他人(金融機関等)の胸先三寸で決まる,というか,まっとうな債権者なら当然実行してくるということで,再生計画の認可が危うくなるし,仮に再生計画の認可が得られたとしても,再生計画の遂行ができなくなってしまう。
そうであるから,この別除権協定の締結は,民事再生事件の申立人(代理人)としては,結構大変な仕事になる。要は,担保不動産の価値をいくらに評価するかにかかっているのだが,債権者の方は,担保価値をできるだけ高くみて,回収率を上げようとする一方で,別除権協定がまとまらなかったために,会社の存続を諦められて,破産ともなると,自分が真っ先に悪者にされるというリスクを負っていて,なかなか微妙な立場に立たされることになる。
再生債務者としても,担保価値を高くみると,話はまとまりやすいが,後の弁済の負担が増えて,きつい思いをしなければならないし,担保価値を不当に高くみつもると,監督委員が同意してくれなかったり,裁判所から,「それって一般再生債権を再生計画によらずに弁済することになりません?」とか,「別除権者も再生債権者ですからねー。再生計画による権利の変更の平等に反しません?」などと嫌味を言われて,最終的には,再生計画不認可などという憂き目に逢わされることになる。
*****
まあ,それはともかくとして,この別除権協定は,民事再生法のどこに根拠があるのだろうか。民事再生法に,「別除権協定」という言葉は出てこないし,担保権消滅制度という強制的な制度はあるけれども,話し合いで担保権の実行を止める方法があるとは,どこにも書いていない。立法当初に出たコンメンタール(花村良一・民事再生法要説)をみても,「別除権については話し合いで実行を止める方法があります」等という解説はどこにもない。
しかし,その道の専門家達は,別除権協定を当然のことと理解してやっている。別除権協定を「民事再生法の影の主役」という人もいる(三上徹)くらいである。
そんな方に直接聞くわけにもいかず,あれこれ調べて(今手元にないが,最近出た新しいコンメンタールにちょっと出てきた。),やっと辿り着いたのが,民事再生法88条である。
別除権者は、当該別除権に係る第五十三条第一項に
規定する担保権によって担保される債権については、
その別除権の行使によって弁済を受けることができ
ない債権の部分についてのみ、再生債権者として、
その権利を行うことができる。ただし、当該担保権
によって担保される債権の全部又は一部が再生手続
開始後に担保されないこととなった場合には、その
債権の当該全部又は一部について、再生債権者とし
て、その権利を行うことを妨げない。
ぱっと見ただけでは,この条文のどこが別除権協定なのか,ということになるが,この「当該担保権によって担保される債権の全部又は一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合」の中に,担保権者との話し合いで債権の一部を担保から除外することができる,という趣旨が含まれているということのようである。
すなわち,別除権協定で,一般再生債権として支払う部分を協定することが,ここにいう「被担保債権の一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合」に当たるということなのである。
で,もう一度立法当初の本をひもといてみると,確かに,別除権予定不足額の確定の方法には,合意による方法がある,という解説が出ている(才口ほか編・民事再生法の理論と実務(下)74頁・森恵一執筆部分)。しかし,解説があるといっても,たったの10行ちょっとでしかない。
☆☆☆☆☆
これくらいのことで,調べものにずいぶんな時間を取るのは,自分自身の不勉強の結果であることは認めざるを得ないし,こんな文章を書くのも,自分の恥曝しなのだが,それはそれとして,やっぱり「何かねぇ~」という心境から抜けきれない。
大体,民事再生に,別除権協定といっているものが必須であることくらい,立法者だって分かっていることなのだから,それらしい条文を置いてくれてもいいではないか。立法技術上,こうしか仕方がなかったというなら,少なくとも,立法当初に出す解説本には,それなりの扱いで(ここが大事だよ,と)書いてもらいたい。
法律が平仮名になって,ようやく分かりやすくなったとはいえ,やっぱり日本の法律は分かりにくい。不勉強は自分の責任なのだけれども・・・











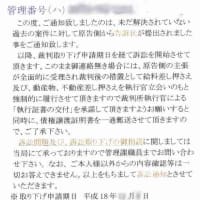
民事再生の場合の別除権協定、ひとつ失敗するとややこしくなりますよね。
私の勤めている法人が(いわゆる商法上の会社ではありません)RCCによる債権者破産を申し立てられ、一旦地裁では「破産宣告決定」となったものを経営体力あるものですから、理事長が高裁に「民事再生の申し立て」として控訴に出る際に、弁護士とともに会計士も立てたというのも文章を読ましていただいているとなんとなく。
巷の素人向けの民事再生の本では「別除権」については当然のように書かれていますが「民事再生法88条」で上記のように触れられているだけなのですか。
素人にとってはいい勉強になります。また今後ともよろしくお願いいたします。
RCCも,債権者破産の申立てをするというのは,なかなか厳しいですね。半ばお役所みたいなところなので,一旦こうと決められると,その後の交渉が難しいなどという話もちらりと聞きます。
昔は,対抗的和議などと称していたのですが,今は対抗的再生になるんですね。ここでRCCを納得させながらの再生というのは,本当に大変だったことと思います。