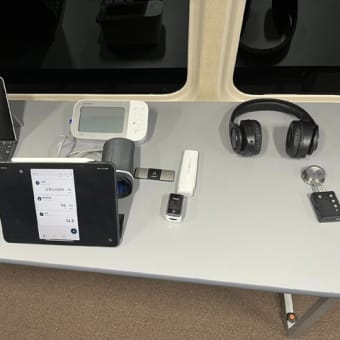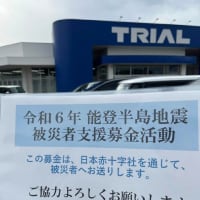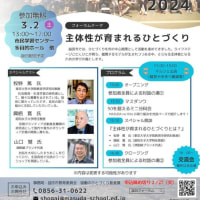内閣府の地方分権改革推進委員会は5月28日に第1次勧告を提出し、更なる分権推進に向けての道筋が示されました。国の直轄国道の整備・管理権限を15%以上都道府県に移譲すること(高津川の整備管理の県への権限移譲を含む)や、都道府県が許認可権限を持つ64本の法律の359事務を市町村に移すことなどが柱となっています。
今後の地方分権改革推進委員会のスケジュールでは、今年度から来年度にかけて第2次勧告、第3次勧告を出し、委員会の設置期限である来年度の3月までには新分権一括法案を国会に提出するという予定となっています。
また、今年3月に出された政府の道州制ビジョン懇談会の中間取りまとめによると2018年には道州制に完全移行すべきとの見解も出されています。
2018年と言えばあと10年後です。益田市の人口はここ3年で既に1,100名あまり減少していることを考えてみても、人口減少と高齢者の割合の増加は、今以上の税収の減少と民生費の増加をもたらすことが予測されています。その時には行政組織も必然的にスリムになっていくでしょう。行政サービスもスリム化し、市民や市民団体、NPOなどがそれを補完していかなければ、国や県から下りてくる膨大な事務事業、そして広い市域を維持することができない時代はすぐそこまで来ています。
そうした地方分権の大きな流れを見据えた市民と行政との関係のあり方について、まちづくりのための『わが町の憲法』と呼ばれるルールとして自治基本条例を定める自治体が増えています。
議会が主体となって自治基本条例を定めた長野県飯田市では、市民がこの自治基本条例づくりに積極的にかかわり、条例策定までの間に、「わがまちの憲法を考える市民会議」として、全体会議を14回、分科会を6回、その他に運営委員会を15回開催するなど、条例を制定するという目標はありますが、それ以上に市民と共に条例を作り上げるというプロセスを大切にして、わが町のあり方、を市民自らが問い続けたといいます。
つまり、市民一人ひとりに、「自分達の町は自分達の手で何とかしよう!」という思考や行動力が今求められています。
もちろん、地方分権が進んでも十分な財源が移譲されていないという問題も抱えています。道州制についてはこれから本格的に議論されていきます。国・県の果たすべき役割としてまだまだしっかりと果たしてもらわなければならないことも多くあります。
大切なのはそうした動きの中で、『益田市としてどういう準備をしていくのか』ということです。
自治基本条例の制定に向けての問いに対し、市長からは「自治基本条例制定に向けた動きを早いうちにしていきたい」という明確な答弁がありましたので、この益田市のあり方を考える機会として条例策定に向けて多くの市民が参画できるような取り組みになっていくよう支援していきたいと思います。
最新の画像もっと見る
最近の「活動報告」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事