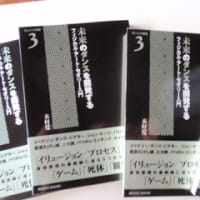宝泉薫+ファッシネイション編『歌謡曲という快楽』(彩流社、2002年)という本が昨日届く。
これは、七〇年代末から九〇年代の初頭まで刊行されていた雑誌『よい子の歌謡曲』のアンソロジー。『よい子』とは、いわゆる「ミニコミ誌」「投稿誌」で、最大部数は六千部。ぼくは、恥ずかしながら最近になって知った。
「もう黙っちゃいられない。歌謡曲を語るのは、本来歌謡曲が大好きな僕たち歌謡曲ファンがやるべきことだ。さあ、場所は出来た。後は君が集まってくるだけだ」(p. 10)
というのが創刊の辞。ファンが書き手となって誌面を構成する批評誌というのが『よい子』ということらしい。一般的に見て、まさに歌謡曲全盛の時代に、歌謡曲が好きな自分っていったい何だろうことを、フォークやニューミュージックを仮想敵としながら展開した文章が目立つ。例えば、
「とにかく、メジャー志向のフォーク歌手は「やさしさ」とか「思いやり」とか、自分をさらけださない抽象的な言葉を、小市民的な中流意識をくすぐるように、実にうまく使うんだよね。まったく生理的な嫌悪感すら感じますね。
僕は、最終的にメジャーな産業であるところの歌謡曲を断固支持します。なんといっても、郷ひろみや石野真子などの無意識過剰型スターは、日本の歌謡界が生みだした根無し草的芸能人の代表ですからね。彼らの軽さ、スピード感は、パンクなんかよりよっぽど日本の現実状況を反映していると思えるものね。」(p. 12)
一発で「歌謡曲」の存在価値を言い当てたなかなか秀逸な文章。メジャーのなかの「過剰」が歌謡曲の魅力だと。
本書には、クロニクルに二十本ほどの文章が並んでいる。興味深かったのは、「アイドル・ポップスはしんだのか?」(晄晏隆幸)というタイトルの原稿が90年12月号に掲載されていることと、その1年後の最終号では「バカとマシンガン・パート2」(渋谷義人)というフリッパーズギター論が載っていて、しかも表紙も彼らのアップなのだ。90年に入ってアイドルは死を意識され、その代わりになったのがフリッパーズだったというのは、なんだか興味深い。その真意はと思って読みはじめると、これがとても素晴らしい論考なのだ。フリッパーズがそれまでの音楽と決定的に違うポイントが、単に音楽の系統を語ることによってではなく、いわばその思想を語ることによって説明されている。といっても、浅田が云々などと言う手法ではなく(この点がすでに90年代に入ったことを告げている気がする)、ごくごく平明な自分の言葉でつづられているのだ。
◎「距離感覚」の表現こそ本当のリアルなロック 「「僕」と「あなた」のあいだにある距離をナイモノとしちゃう、またはそのあいだにある壁を暴力衝動によってぶち壊せ!っていうのが今までのロックだったりしたのかもしれない。僕もそんな直接的なコミュニケーションには憧れないこともないけれども、いや逆にそういうのに憧れれば憧れるほど、実際にはそうなれない「僕」と「あなた」というものに自覚的にならざるを得ない。そういう「ドアの向こう気づかないで恋をしていた夢ばかり見てたそして僕は喋りすぎた」みたいな距離感覚をちゃんと意識した表現こそが、今の僕にとっての本当のリアルなロックなんじゃないか、と思う。」(91年11月48号 p. 182)
◎「ポスト・アイドル」としてのフリッパーズギター 「たぶん「絶対的な自分」というものを信じたいのだと思う。「あなた」に向けてなんらかの形で「自分」を表現した時、その表現された自分というものがとてももどかしくて、だから小出しにしか出してゆけない時にそこから落ちこぼれてしまっていった自分、表現した時にそこから落ちこぼれてしまった自分、が、とても大事なものに思えて、それが絶対的なもののように思えた。本当はそれは、表現されていないということによって未だ枠づけされたり相対化されずにすんでいる、というだけであって、それが「絶対」であるという訳ではないのかもしれないのだけれど。でも、そんな「あいまいな」ままでいられる段階の自分がやっぱりあきらめられなくて、そういうあいまいな、でも本質的な部分で、あなたと「関係」してゆきたかった。」(p. 184)
ないことのわかっている、けど信じたい「絶対的な自分」を求めてさまようのが90年代なのだった。「絶対的」なものといっても、それは「表現されていないということによって未だ枠づけされたり相対化されずにすんでいる」ものかもしないなんて、とても秀逸な議論。メタのレベル(相対化のレベル)とベタのレベル(絶対的なもののレベル)がせめぎ合っている。けれども、この時点では、ベタのレベルはメタの視点にさらされていないだけで存続しているものという認識だったのだ。ベタなものをベタに存在していると思いこむ時代の手前のテクスト。
これは、七〇年代末から九〇年代の初頭まで刊行されていた雑誌『よい子の歌謡曲』のアンソロジー。『よい子』とは、いわゆる「ミニコミ誌」「投稿誌」で、最大部数は六千部。ぼくは、恥ずかしながら最近になって知った。
「もう黙っちゃいられない。歌謡曲を語るのは、本来歌謡曲が大好きな僕たち歌謡曲ファンがやるべきことだ。さあ、場所は出来た。後は君が集まってくるだけだ」(p. 10)
というのが創刊の辞。ファンが書き手となって誌面を構成する批評誌というのが『よい子』ということらしい。一般的に見て、まさに歌謡曲全盛の時代に、歌謡曲が好きな自分っていったい何だろうことを、フォークやニューミュージックを仮想敵としながら展開した文章が目立つ。例えば、
「とにかく、メジャー志向のフォーク歌手は「やさしさ」とか「思いやり」とか、自分をさらけださない抽象的な言葉を、小市民的な中流意識をくすぐるように、実にうまく使うんだよね。まったく生理的な嫌悪感すら感じますね。
僕は、最終的にメジャーな産業であるところの歌謡曲を断固支持します。なんといっても、郷ひろみや石野真子などの無意識過剰型スターは、日本の歌謡界が生みだした根無し草的芸能人の代表ですからね。彼らの軽さ、スピード感は、パンクなんかよりよっぽど日本の現実状況を反映していると思えるものね。」(p. 12)
一発で「歌謡曲」の存在価値を言い当てたなかなか秀逸な文章。メジャーのなかの「過剰」が歌謡曲の魅力だと。
本書には、クロニクルに二十本ほどの文章が並んでいる。興味深かったのは、「アイドル・ポップスはしんだのか?」(晄晏隆幸)というタイトルの原稿が90年12月号に掲載されていることと、その1年後の最終号では「バカとマシンガン・パート2」(渋谷義人)というフリッパーズギター論が載っていて、しかも表紙も彼らのアップなのだ。90年に入ってアイドルは死を意識され、その代わりになったのがフリッパーズだったというのは、なんだか興味深い。その真意はと思って読みはじめると、これがとても素晴らしい論考なのだ。フリッパーズがそれまでの音楽と決定的に違うポイントが、単に音楽の系統を語ることによってではなく、いわばその思想を語ることによって説明されている。といっても、浅田が云々などと言う手法ではなく(この点がすでに90年代に入ったことを告げている気がする)、ごくごく平明な自分の言葉でつづられているのだ。
◎「距離感覚」の表現こそ本当のリアルなロック 「「僕」と「あなた」のあいだにある距離をナイモノとしちゃう、またはそのあいだにある壁を暴力衝動によってぶち壊せ!っていうのが今までのロックだったりしたのかもしれない。僕もそんな直接的なコミュニケーションには憧れないこともないけれども、いや逆にそういうのに憧れれば憧れるほど、実際にはそうなれない「僕」と「あなた」というものに自覚的にならざるを得ない。そういう「ドアの向こう気づかないで恋をしていた夢ばかり見てたそして僕は喋りすぎた」みたいな距離感覚をちゃんと意識した表現こそが、今の僕にとっての本当のリアルなロックなんじゃないか、と思う。」(91年11月48号 p. 182)
◎「ポスト・アイドル」としてのフリッパーズギター 「たぶん「絶対的な自分」というものを信じたいのだと思う。「あなた」に向けてなんらかの形で「自分」を表現した時、その表現された自分というものがとてももどかしくて、だから小出しにしか出してゆけない時にそこから落ちこぼれてしまっていった自分、表現した時にそこから落ちこぼれてしまった自分、が、とても大事なものに思えて、それが絶対的なもののように思えた。本当はそれは、表現されていないということによって未だ枠づけされたり相対化されずにすんでいる、というだけであって、それが「絶対」であるという訳ではないのかもしれないのだけれど。でも、そんな「あいまいな」ままでいられる段階の自分がやっぱりあきらめられなくて、そういうあいまいな、でも本質的な部分で、あなたと「関係」してゆきたかった。」(p. 184)
ないことのわかっている、けど信じたい「絶対的な自分」を求めてさまようのが90年代なのだった。「絶対的」なものといっても、それは「表現されていないということによって未だ枠づけされたり相対化されずにすんでいる」ものかもしないなんて、とても秀逸な議論。メタのレベル(相対化のレベル)とベタのレベル(絶対的なもののレベル)がせめぎ合っている。けれども、この時点では、ベタのレベルはメタの視点にさらされていないだけで存続しているものという認識だったのだ。ベタなものをベタに存在していると思いこむ時代の手前のテクスト。