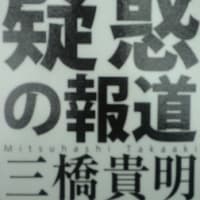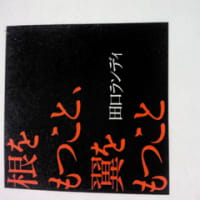前回、かいた第10回「子どもの心」研修会について、ですがいろいろ皆さんにもしってもらいたいことが多いので、自分のノートをもとに解説していければと思います.
1.発達障害の早期発見と早期介入の実際
横浜市総合リハビリテーションセンター発達精神科 清水康夫
そもそも「発達障害」ってどんな病気をさすのでしょう?
実は統一されていないのが実情です.
この「発達障害」という言葉を世の中に産み出した、米国の精神医学会が出版した「精神障害の診断と統計のためのマニュアル第3版」(以下、DSM-IIIと略)
では、「広汎性発達障害」と「特異性発達障害」というふたつに分類しています.
「広汎性発達障害」ということばは自閉症を中心とした意味であり、
「得意性発達障害」ということばは学習障害を中心とした意味です.
そもそも、このふたつに分類することにも疑問の声があります.
日本の発達障害者支援法(2005年4月施行)という法律では発達障害を自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(=ADHD)など、としています.
DSMでは対応していないADHDも含んでいる一面、臨床現場で発達障害として対応している精神遅滞は含まれていません.
もっとも、この法律はこれまでの支援から漏れていた人たちを助けるために作られており、精神遅滞に対してはすでに知的障害者福祉法があるので、対象外とされた、という経緯もあります.
とにかく、「発達障害」という言葉をひとつとっても、さまざまな意味、解釈がありますので要注意です.
さらに、診断となるとやっかいです.
知的な遅れのないタイプの発達障害(高機能自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、ADHDなど)は、必要十分な検査方法があるかというと、これがありません.
もっぱら、行動的な症候による診断となります.
自閉症やアスペルガー症候群は広汎性発達障害とか、最近では「自閉症スペクトル(スペクトル=連続体)」、「自閉症スペクトル障害」などと総称されるようになってきましたが、
これらに特徴的な行動的症候というものを説明すると
1.社会的相互交渉の質的障害
2.コミュニケーションの質的障害
3.関心の著しい限局化・常同行為
というわかりにくい説明になってしまいます.
解説するならば、
1.社会的相互交渉の質的障害
とは、共感をまじえながら、人と交渉することの質的な障害です.
「質的」という言葉の意味を伝えるのに、苦労してしまうのですが
たんなる自分勝手とか、強い引っ込み思案とはぜんぜん違うんだよ、という概念です.普通の心理行動の延長線上ではないんだ、というニュアンスを伝えたいがための表現です.
2.コミュニケーションの質的障害
も、同じでたんにコミュニケーションが上手、下手という性質のものとは違うんですよ、という意味です.
3.関心の著しい限局化・常同行為
は、1,2の結果として生じる行動傾向です.治療や教育によってもかなり変化します.
一方で、ADHDになると
「多動」;活動量のわりになにも生産されない
「衝動」;計画性なし、自己帰還性なし
「不注意」;
の3つが特徴とされます.
しかし、この3つは普通の人でも疲労、寝不足、酔っぱらいなどで同じような症状が出現してきます.ここが自閉症スペクトルの特徴とちがう点です.
そのためかDSM-IVの診断基準では、この3つの特徴があって、しかもそのために社会生活上の困難が生じているという条件下で診断される、と書かれています.
自閉症の診断基準には、この社会生活上の困難について記載はないのですが
アスペルガー症候群の診断基準には、社会生活上の困難について記載があります.
自閉症がアスペルガー症候群も含めた、自閉症スペクトル(連続体)としてとらえられるようになったいま、知的障害もなく、特徴的な行動も薄いという非典型例をどこまで診断するのか、困っているのが臨床の現場です.
普通の発達をしている人々の間にある個人差の問題と連続的なつながりをもっているだけなのか、それとも発達障害は何かが根本的に違うのか、まだわからないことばかりです.
1.発達障害の早期発見と早期介入の実際
横浜市総合リハビリテーションセンター発達精神科 清水康夫
そもそも「発達障害」ってどんな病気をさすのでしょう?
実は統一されていないのが実情です.
この「発達障害」という言葉を世の中に産み出した、米国の精神医学会が出版した「精神障害の診断と統計のためのマニュアル第3版」(以下、DSM-IIIと略)
では、「広汎性発達障害」と「特異性発達障害」というふたつに分類しています.
「広汎性発達障害」ということばは自閉症を中心とした意味であり、
「得意性発達障害」ということばは学習障害を中心とした意味です.
そもそも、このふたつに分類することにも疑問の声があります.
日本の発達障害者支援法(2005年4月施行)という法律では発達障害を自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、注意欠陥多動性障害(=ADHD)など、としています.
DSMでは対応していないADHDも含んでいる一面、臨床現場で発達障害として対応している精神遅滞は含まれていません.
もっとも、この法律はこれまでの支援から漏れていた人たちを助けるために作られており、精神遅滞に対してはすでに知的障害者福祉法があるので、対象外とされた、という経緯もあります.
とにかく、「発達障害」という言葉をひとつとっても、さまざまな意味、解釈がありますので要注意です.
さらに、診断となるとやっかいです.
知的な遅れのないタイプの発達障害(高機能自閉症、アスペルガー症候群、学習障害、ADHDなど)は、必要十分な検査方法があるかというと、これがありません.
もっぱら、行動的な症候による診断となります.
自閉症やアスペルガー症候群は広汎性発達障害とか、最近では「自閉症スペクトル(スペクトル=連続体)」、「自閉症スペクトル障害」などと総称されるようになってきましたが、
これらに特徴的な行動的症候というものを説明すると
1.社会的相互交渉の質的障害
2.コミュニケーションの質的障害
3.関心の著しい限局化・常同行為
というわかりにくい説明になってしまいます.
解説するならば、
1.社会的相互交渉の質的障害
とは、共感をまじえながら、人と交渉することの質的な障害です.
「質的」という言葉の意味を伝えるのに、苦労してしまうのですが
たんなる自分勝手とか、強い引っ込み思案とはぜんぜん違うんだよ、という概念です.普通の心理行動の延長線上ではないんだ、というニュアンスを伝えたいがための表現です.
2.コミュニケーションの質的障害
も、同じでたんにコミュニケーションが上手、下手という性質のものとは違うんですよ、という意味です.
3.関心の著しい限局化・常同行為
は、1,2の結果として生じる行動傾向です.治療や教育によってもかなり変化します.
一方で、ADHDになると
「多動」;活動量のわりになにも生産されない
「衝動」;計画性なし、自己帰還性なし
「不注意」;
の3つが特徴とされます.
しかし、この3つは普通の人でも疲労、寝不足、酔っぱらいなどで同じような症状が出現してきます.ここが自閉症スペクトルの特徴とちがう点です.
そのためかDSM-IVの診断基準では、この3つの特徴があって、しかもそのために社会生活上の困難が生じているという条件下で診断される、と書かれています.
自閉症の診断基準には、この社会生活上の困難について記載はないのですが
アスペルガー症候群の診断基準には、社会生活上の困難について記載があります.
自閉症がアスペルガー症候群も含めた、自閉症スペクトル(連続体)としてとらえられるようになったいま、知的障害もなく、特徴的な行動も薄いという非典型例をどこまで診断するのか、困っているのが臨床の現場です.
普通の発達をしている人々の間にある個人差の問題と連続的なつながりをもっているだけなのか、それとも発達障害は何かが根本的に違うのか、まだわからないことばかりです.