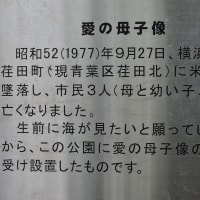変革より内輪の論理、農業委の正体
ドリルを手にとれ(1) (1/2ページ) 2014/2/11 2:00
政府がコメの生産調整を廃止すると表明した。農業改革は進むのか。政府関係者がささやく。「農業委員会が変わらないと、新たな担い手は増えないよ」
自由な農業参入を阻む正体とは・・・
画像の拡大
自由な農業参入を阻む正体とは・・・
名前は聞くけど、よく知らない。どうやら農地の売買や貸借を許可したり、農地転用で知事に意見したりして農地の取引に大きな力を持つらしい。「新規参入者には冷たい」。そんな噂も聞いた。原則、市町村ごとにあるようだ。早速、農業委を回ってみた。
■地域の名誉職
どこも事務局は役所の一角。職員は3~4人で兼務も多い。委員の大半は地域の農家から3年に1度、農家による選挙で選ぶ。ところが「前回の改選時に選挙になったのは全国1700の農業委の1割」(農林水産省)という。千葉県内のある農業委では各地区の農家の男性が持ち回りで就く。事務局職員が明かす。「地域の農家のいわば名誉職。なれ合いになっている面は否めない」
「耕作放棄地の指導など、やるべきことができていない」。同県内で農業を営む下山久信さん(68)は不満を抱き、7月の成田市農業委の選挙に出馬を決めた。慌てたのは事務局。1996年以来の選挙になるかもしれないからだ。
農業生産法人、越後ファーム社長の近正宏光さん(42)は設立時を振り返る。2006年、新潟県阿賀町。「よぐわがんね。県に聞いてくれ」。農地取得を申し入れたところ、農業委の事務局でこう言われた。
県庁では「農政局に聞いてくれ」。農水省の出先である農政局では「それは農業委で」。業を煮やし、3者を集めて問い詰めると、県の担当がようやく「農業委がOKなら」。すると農業委の担当も「県がいいと言うなら」。準備開始から半年以上たっていた。
農業委が11年に許可した有償での農地の所有権移転は5年前から3割減った。09年の法改正で農地調査も仕事になり、役割は増すばかり。「委員はあまり動かない。職員は足りない」(農業委関係者)。総務省は昨年、農水省に農業委への指導強化を勧告した。
■大きな転用収入
進まない農地の集約。「農家が農地を手放さないのは転用を待っているから」。こんな指摘も多い。放棄地のまま待ち、商業用などに転用して売れれば、大きな収入が手に入る。明治学院大教授の神門善久教授は「00~05年には全国で年平均4.6兆円の転用収入が出ていた」とはじく。
農業委は転用手続きでも力を持つ。せっかくの農地を「転用待ち」という内輪の論理で塩漬けにしていないか。全国の農業委を束ねる全国農業会議所の柚木茂夫事務局長は「基準に沿って判断しており、恣意的な運用はできない」と否定する。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「農家同士のなれ合いの関係では公平な判断は下せない」と懐疑的だ。
開かれた農業委に。なれ合いに強く「NO」と言えるのなら、いつか日本に「強い農」と言える日が来るのではないだろうか――。
◇
アベノミクスの成否は規制改革など第3の矢にかかってくる。「いかなる既得権益も私のドリルから無傷ではいられない」と安倍晋三首相。農業、雇用、医療。ドリルで突き崩すべき岩盤はたくさんある。