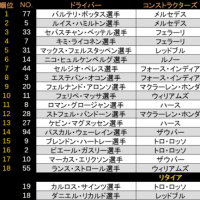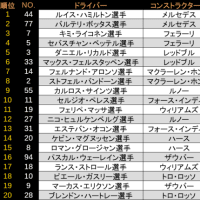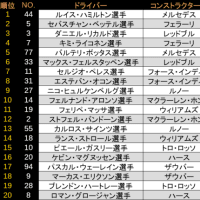PCの進歩でアナログでできる事もデジタルでできるようになり利便
性が高くなったなぁと言うのを感じるのですが、デジタルで行うにし
ても実はセオリーと言うのは全く同じものがあります。
例えば、透視図法や黄金比なんかがデジタルになったから
【 ザクレロにシャアが乗るような間違いでも起きたかのよ
うな変化 】
は発生しません。(と言うか、違う意味でこれもシャアザクと呼ば
れるのか???)
ある意味、デジタルへの変化と言うのは、絵筆の変化なので手法
が少し違う感じになっているモノのイラストはイラストですから、
【 人類が麺類になるような変化 】
はそこにはない訳です。ある意味、アナログでも水彩絵の具を使っ
て描くのとコピック使うんじゃ違うと思いますし、このカラーの表
現とデッサンって違いますよね。
実際その手の違いはある訳ですが、技法については変化はないと
思います。
例えば、デッサンを描きましょうで、 【 印象派 】 みたい
なのを描かれたら、絶命してしまいそうになりますし、それはあり
えないですよね。
つまり、デッサンだとやっぱり画法がある訳ですからそれを使う
事になります。ホームセンターに行ってDIYで何かを作るにしても
【 歴史上の剣豪すら腰を抜かす、金槌で板を居合切りの
ような切れ味で真っ二つにする 】
【 一子相伝の謎の暗殺拳の継承者であるかのように、キ
リでクギの芯を捉え、ミスなく一撃で打ち込む 】
と言う事はしませんよね。(と言うか、できるかぁ~ッ!!)
やっぱり、刃物で切り、リーマーで穴を開け、釘がずれないよう
にキリで辺りを付け、クギをハンマーで打ち付け、クギの頭が出な
い様にリーマーで開けた穴に木工ボンドを流し込み、ダボ打ちし、
最後にかんなでフライスをとる感じになると思います。
つまり、工程と機材ってセットなんで、その機材にあった用法が
ある訳です。
では、2Dで変わらないモノは何かと言うと、 【 絵の技法 】
です。これは新しい技法を使う場合は別ですが、既存の技法におい
て(つまり奥行き感を見せるとかですね。と言うか、北斗の拳では
ミノワマン VS チェ・ホンマン戦のように奥行き感をあえて変え
て迫力を出すと言う手法を取ってあったので漫画やアニメーション
のようなアンリアルな世界だと手法の自由度が高いのかも知れませ
んね。ただ、あの試合は遠近法間違っているかのようにしか見えま
せんでしたが...。)は変わらない部分が多い訳です。
では、3Dとかだとどうかと言うと、
■ 照明
■ 構図
■ カメラの基礎
は全く同じです。ただ、カメラについては、3DCGの場合ステノペ(
つまり原理的にはカメラオブスキュラと同じです。)ですから、レ
ンズのような光学系はありません(ただ、レンズフレアを持つ製品
だとレンズの構成を持たせることでその光学系にあったゴーストな
んかが入る状況を作ってくれます。)から少し違うのですが、カメ
ラの基本的な事は変わりありません。
光学系のシミュレートだと 【 MAXWELLレンダラー 】 がフ
ツーにカメラの振る舞いに近いですから(ただ、13万位しますが...。)
ソレを使うとすると、結果的に
【 カメラが何でどんな振る舞いをする機材なのか 】
が解っていないと意図したものは出来ません。また、照明はリアル
な光学シミュレートではないのでどちらかと言うと
【 センス 】
になるのですが、そうは言ってもライティングで非屋台の印象は相
当変わるので少なくともその辺りを知っておく必要があります。
3Dと2Dの違いは
【 2Dは光学系をデタラメにできる 】
と言う点で、始点誘導の為に本来だと光が入らないような位置に明
かりを入れたりするなんて手法もあったりします。フェルメールの
作品では、3Dや実際のセットでやってみるとそうならないモノがある
んですが、同じフレームに入れてみると、フェルメールの作品のほう
が印象深く感じます。
アンリアルの世界だからできるモノってこの辺でこの辺りが写真と
絵画の違いなのかも知れませんね。
実写と言うのは非現実的な現実とみえるような同じ場所の風景があ
るとその現実が凄く感じるのかも知れませんが、絵画はきっと写真以
上に主観をフレーム内に閉じ込める事ができるのかも知れませんね。
デジタルになると絵筆が違うのでレイヤーを多く使い面白い効果や
コンポジットで実写ではムリなモノまで可能にできる訳ですが、基礎
的な事はアナログにあり、そこを飛ばすと結構遠回りをする事になっ
たりもします。
例えば、3Dをやるとして、デッサンを描いた事がない人間だと、形
状を3Dに起こすと言う時に結構苦労すると思います。これは、形状把
握の能力の違いがあるからですね。
また、シーン構築やライティングについてもある程度の基礎知識が
ないとレンダリングの手法を変えても意図したものにはならなかった
りします。
これも、結果的にはアナログで行うことがベースにあってそれが理
解できているからできる内容かも知れません。
動画編集やるのにフィルムカッターとフィルムの撮影機材を買って
きて練習しろとまでは言いませんが、実際に多くのリテラシーは存在
しているので、そこをすっ飛ばすと作る上での苦労は数倍になると言
う訳です。
例えば、コミックスタジオを使うと仮定して....。線の効果とか全
く解ってなかったら、あのソフトよりもIllustratorとかのほうがラク
になってしまいます。ただ、漫画に特化した機能が満載なのでコミッ
クスタジオのほうがラクなんですよね。(と言うか物理的にトーンを
貼らなくてもいいので個人が低コストで漫画をガンガン描く上ではア
レは相当重宝します。)
つまり、デジタルは絵筆であり、機材なので、違う作法があるので
すが、共通するセオリーやリテラシーは当然存在しているのでその部
分は省くことは出来ない訳です。