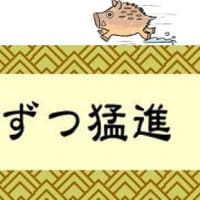前回に続いて小学生時代の話。
学校の休み時間や放課後に「鬼ごっこ」をした時期もあったが、これは単に足の速さを競い合うフィジカルな遊びで、どうも苦手だった。その点「かくれんぼ」は、鬼ごっこほどに疲れないし、遊びの過程にメンタルな要素があり、当然僕はこちらの方が好きだった。昔から、しんどいことを避ける子供だったのである。
思えば、かくれんぼというのは理不尽な遊びだ。すぐに見つかってはつまらないし、逆にいつまでも見つからなかったら退屈なものである。かくれんぼをしている子供たちの心の中では、見つかることを恐れる気持ちと見つけに来てくれることを期待する気持ちとが複雑に交錯し、その結果、たいていの子供は適度に見つかりにくく、また適度に見つけやすい隠れ場所を選ぶのである。こうして子供たちの間には暗黙の協定が成立し、ちょうどよいくらいの間隔で鬼の交代が行なわれることになる。
なかには誰にも見つからないような場所に隠れ潜む子供もいるが、最後には他のメンバーから忘れ去られ、知らないうちに鬼が代わっていたり、ゲームが終わってみんな家へ帰っていたりする。子供の世界は無情なものなのである。
鬼ごっこやかくれんぼを発展させたような遊びで「どろじゅん」というのがあった。全国的には「どろぼうと刑事」で「どろけい」または「けいどろ」などと呼ばれているようだが、僕の地方では「どろぼうと巡査」で「どろじゅん」だった。
鬼ごっこやかくれんぼが多対一の遊びであるのに対して、こちらの方は多対多のチームプレーである。巡査に捕まった泥棒は刑務所と呼ばれるスペースに拘束されるが、泥棒の仲間が助けに来てタッチを交わすと、脱走して再び逃げ回ることができる。巡査側のチームは、遠くに逃げた泥棒を探し回る者や刑務所付近で監視する者などそれぞれ役割を分担し、捜査や警備に努めた。
やり始めるとなかなか面白く、日が暮れるまで夢中で遊んだものだった。遊び方にも人それぞれの性格が出るもので、自らの危険を冒してでも仲間を助けようとする正義漢がいるかと思えば、仲間などそっちのけで自分が隠れることに専念している者もいた。
僕の場合は、子供の頃から戦略家で、チームの作戦参謀を務めることが多かった。オトリを使って看守を混乱させたり、サインプレーで各方向から一斉に突撃したり、さまざまな戦術を試みる、言わば、どろじゅん界の諸葛孔明のような存在であった。おかげで、ガキ大将タイプのチームリーダーからも厚い信頼を寄せられ、彼らが中学生になって不良グループを結成した後も、僕は彼らとうまく付き合っていくことができた。
かくれんぼやどろじゅんでは、鬼(巡査)になった者が目を閉じて数を数えるとき、数字の代わりに10文字または20文字の言葉を唱えることが普通だった。例えば「ぼんさんが、屁をこいた。においだら、くさかった」これで20文字である。「インディアンのふんどし」というのもあった。「インディアンのふんどし、インディアンのふんどし、インディアンのふんどし・・・」と十回数えても、実際には十秒ほどで済んでしまう。これで百数えたことになるのだから、子供の考えることはやっぱりすごい。
「ぼんさんが、屁をこいた」というのはユーモラスで、それになんと言っても京都らしくていいね。全国的には「だるまさんがころんだ」がポピュラーだと思うが、横浜育ちの妻は「のぎさんは、えらい人」と言ってたらしい。「のぎさん」とは日露戦争で活躍した乃木希典大将のことで、こりゃまたえらく古い話だ。
ところで「インディアンのふんどし」って、いったい何なのだろう? インディアンがふんどしを締めているのか、あるいはインディアンの図柄が入ったふんどしなのか、どちらにしても想像すると笑いがこみ上げて来る。
どろじゅんは、もうやってみたいとは思わないなぁ。無理に走ってアキレス腱を切ってしまうか、心臓発作でぶっ倒れるか、身体的リスクが非常に高い。運動量の少ないかくれんぼならやってみたい気もする。しかし、オッサンが大勢で物陰に隠れ潜んでたりすると、本物の警察に捕まってしまいそうだ。(^^;
大人になって得たものもあれば、失ったものもある。もうあの頃の自分には戻れないけど、過去は戻れないからステキなのだ。懐かしい思い出を大切にしつつ、今という現実をしっかり生きていきたいと思う。
学校の休み時間や放課後に「鬼ごっこ」をした時期もあったが、これは単に足の速さを競い合うフィジカルな遊びで、どうも苦手だった。その点「かくれんぼ」は、鬼ごっこほどに疲れないし、遊びの過程にメンタルな要素があり、当然僕はこちらの方が好きだった。昔から、しんどいことを避ける子供だったのである。
思えば、かくれんぼというのは理不尽な遊びだ。すぐに見つかってはつまらないし、逆にいつまでも見つからなかったら退屈なものである。かくれんぼをしている子供たちの心の中では、見つかることを恐れる気持ちと見つけに来てくれることを期待する気持ちとが複雑に交錯し、その結果、たいていの子供は適度に見つかりにくく、また適度に見つけやすい隠れ場所を選ぶのである。こうして子供たちの間には暗黙の協定が成立し、ちょうどよいくらいの間隔で鬼の交代が行なわれることになる。
なかには誰にも見つからないような場所に隠れ潜む子供もいるが、最後には他のメンバーから忘れ去られ、知らないうちに鬼が代わっていたり、ゲームが終わってみんな家へ帰っていたりする。子供の世界は無情なものなのである。
鬼ごっこやかくれんぼを発展させたような遊びで「どろじゅん」というのがあった。全国的には「どろぼうと刑事」で「どろけい」または「けいどろ」などと呼ばれているようだが、僕の地方では「どろぼうと巡査」で「どろじゅん」だった。
鬼ごっこやかくれんぼが多対一の遊びであるのに対して、こちらの方は多対多のチームプレーである。巡査に捕まった泥棒は刑務所と呼ばれるスペースに拘束されるが、泥棒の仲間が助けに来てタッチを交わすと、脱走して再び逃げ回ることができる。巡査側のチームは、遠くに逃げた泥棒を探し回る者や刑務所付近で監視する者などそれぞれ役割を分担し、捜査や警備に努めた。
やり始めるとなかなか面白く、日が暮れるまで夢中で遊んだものだった。遊び方にも人それぞれの性格が出るもので、自らの危険を冒してでも仲間を助けようとする正義漢がいるかと思えば、仲間などそっちのけで自分が隠れることに専念している者もいた。
僕の場合は、子供の頃から戦略家で、チームの作戦参謀を務めることが多かった。オトリを使って看守を混乱させたり、サインプレーで各方向から一斉に突撃したり、さまざまな戦術を試みる、言わば、どろじゅん界の諸葛孔明のような存在であった。おかげで、ガキ大将タイプのチームリーダーからも厚い信頼を寄せられ、彼らが中学生になって不良グループを結成した後も、僕は彼らとうまく付き合っていくことができた。
かくれんぼやどろじゅんでは、鬼(巡査)になった者が目を閉じて数を数えるとき、数字の代わりに10文字または20文字の言葉を唱えることが普通だった。例えば「ぼんさんが、屁をこいた。においだら、くさかった」これで20文字である。「インディアンのふんどし」というのもあった。「インディアンのふんどし、インディアンのふんどし、インディアンのふんどし・・・」と十回数えても、実際には十秒ほどで済んでしまう。これで百数えたことになるのだから、子供の考えることはやっぱりすごい。
「ぼんさんが、屁をこいた」というのはユーモラスで、それになんと言っても京都らしくていいね。全国的には「だるまさんがころんだ」がポピュラーだと思うが、横浜育ちの妻は「のぎさんは、えらい人」と言ってたらしい。「のぎさん」とは日露戦争で活躍した乃木希典大将のことで、こりゃまたえらく古い話だ。
ところで「インディアンのふんどし」って、いったい何なのだろう? インディアンがふんどしを締めているのか、あるいはインディアンの図柄が入ったふんどしなのか、どちらにしても想像すると笑いがこみ上げて来る。
どろじゅんは、もうやってみたいとは思わないなぁ。無理に走ってアキレス腱を切ってしまうか、心臓発作でぶっ倒れるか、身体的リスクが非常に高い。運動量の少ないかくれんぼならやってみたい気もする。しかし、オッサンが大勢で物陰に隠れ潜んでたりすると、本物の警察に捕まってしまいそうだ。(^^;
大人になって得たものもあれば、失ったものもある。もうあの頃の自分には戻れないけど、過去は戻れないからステキなのだ。懐かしい思い出を大切にしつつ、今という現実をしっかり生きていきたいと思う。