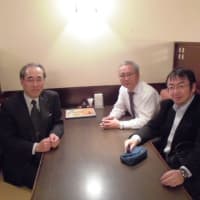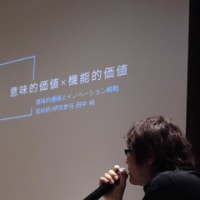ポーターらの「外的環境から導き出されたポジションに戦略的強みを求める理論」に対し、「企業の内部資源で競争優位性をはかる戦略」を提唱するのが「リソース・ベースド・ビュー」すなわち「経営資源にもとづく企業観」である。
その代表的なものが「経済価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)」の4つの視点から差別化を図ろうとする「VRIOフレームワーク」を提唱するジェイ.B.バーニーの理論である。事業体をこれら4つの切り口で比較・分析してその充実度を診断し、整備・強化することで競争優位性を築こうとするものである。
しかし、実務的な感覚で考えてみるとわかるが、3つの問題点がすぐに浮かぶ。
1つ目は、「比較対象をどう定義し分析を行うのか」、という問題である。これは、さらに比較対象の範囲をどう決めるのかという問題と、どの程度の粒度(りゅうど。細かさの度合)で分析を行うのかという2種類の問題に分かれる。
まず「範囲」の問題である。一口に「経済性」や「模倣困難性」といっても、比較の対象となる競合事業や市場セグメントごとに相対的に優位性が違ってくる。ゆえに、実際に比較するとなれば、それらをすべて網羅する形で分析を実施しなければならない。
次に「粒度」、すなわち、VRIOを使って分析する単位の大きさも問題である。単位を組織とするのか、組織の機能(R&D、生産、販売、チャネルなど)ごとに細かく見ていくのか、あるいはサプライチェーンのどこまでの範囲を対象とするのか、等々を決めなければならない。さらに、これらを決めたうえで、あらためて前述した組み合わせを掛け合わせてすべてを分析しなければならない。
変化が激しい環境下において、多くの企業はリソースも時間も限られている。現実的にはこうした分析が難しいことは論をまたないであろう。
2つめの問題は時間軸が考慮されていないことである。これ自身に2つの問題を含んでいる。1つ目は、この分析には膨大な手間ヒマがかかるため、結果が判明する頃には、分析対象がすでに変化している可能性が高くなるということである。2つ目は、仮に分析結果が確定したとしても、変化のスピートが速い昨今の経営環境下では、その「有効期限」はきわめて短くなってしまう点である。
3つめは、真に有用な情報が収集可能か、という問題である。企業の強みがソフトな領域(インタンジブル・アセット=目に見えない資産)へと移行しているいま、情報収集段階で分析の壁に当たってしまう可能性が高い。
たとえば、トヨタ自動車の強さである。あらゆる専門家や研究者たちがそれを解明し、ほかで再現が試みられたわけだが、トヨタと同程度の強さを再現した会社は皆無、といった結果も報告されている(※)。そのくらい、企業の真の強さを抽出することは困難なのである。
上記3つに加えて、あと1つ、経営者の視点から重要な点を指摘したい。
ポーター理論をはじめとする、分析偏重型の戦略構築スタイルは、組織に「分析症候群」や「石橋を叩かないと渡れない(分析結果が出ないと仕事が進められない)体質」をはびこらせ、チャレンジ精神を阻害する要因となる。すなわち、「チャレンジングな燃える集団を作る」というリーダーの重要な使命とは真っ向から対立するのである。
とどのつまり、このような戦略理論の前提には、「事前にすべてを予測できる」「ハード情報を分析することですべてがわかる」という(机上の理論家ならではの)思い込みがある。実務者の感触からすると、「予測」や「目に見える情報のみの分析結果」に会社の命運を賭けることはまさにバクチであるが、それが、このたぐいの理論を考えつく人たちには理解できないのである。
一方で、ユニクロの柳井氏、マクドナルドの原田氏、日産自動車のゴーン氏、元GEのウェルチ氏など多くの実績ある経営者が、
・「走りながら修正しろ(原田氏)」
・「実行がいちばん大切だ(ゴーン氏)」
・「1にも2にもスピードが大事だ(柳井氏、ウェルチ氏)」
などと口をすっぱくしていうのは、そのような悪しき体質が組織をダメにすることをよく知っているからである。さらには、走りながらビジネスの基本サイクルを回転させることにより、早めにリスクの芽を感知し、摘み取りながら前進することの利点を熟知しているからである。
彼らすぐれた実務者が身をもって証明してきたこと、すなわち、「自分の知恵を絞ってチャレンジする→結果を真摯に受け止める→しっかりと修正・改善を行って次につなげる」という基本を積み重ねていけば、自社の強さがいちばん着実に、しかも最短で磨かれていくのである。
結論。ポーター理論と同様、「すべてが予測・分析でき、把握が可能」という幻想のうえに組み立てられた理論、それが「バーニーのVRIOフレームワーク理論」である。
※ トヨタ生産方式が世界中の企業でどのように取り入れられたかについて、ハーバード・ビジネス・スクールが4 年間にわたって行った調査研究の結果が1999 年の『Harvard Business Review』で報告されている。
タイトルは『'Decoding the DNA of the Toyota Production System'』(邦題:『トヨタ生産方式の“遺伝子”を探る』2000 年3 月号)。この中で、報告者たちは、『トヨタは驚くほどオープンにそのノウハウを披露してきた。しかし不思議なことに、上手に再現できたメーカーは皆無である』と述べている。

↓よろしければクリックをお願いします。
ビジネスブログ100選ランキング
■ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所■
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2010 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆
その代表的なものが「経済価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)」の4つの視点から差別化を図ろうとする「VRIOフレームワーク」を提唱するジェイ.B.バーニーの理論である。事業体をこれら4つの切り口で比較・分析してその充実度を診断し、整備・強化することで競争優位性を築こうとするものである。
しかし、実務的な感覚で考えてみるとわかるが、3つの問題点がすぐに浮かぶ。
1つ目は、「比較対象をどう定義し分析を行うのか」、という問題である。これは、さらに比較対象の範囲をどう決めるのかという問題と、どの程度の粒度(りゅうど。細かさの度合)で分析を行うのかという2種類の問題に分かれる。
まず「範囲」の問題である。一口に「経済性」や「模倣困難性」といっても、比較の対象となる競合事業や市場セグメントごとに相対的に優位性が違ってくる。ゆえに、実際に比較するとなれば、それらをすべて網羅する形で分析を実施しなければならない。
次に「粒度」、すなわち、VRIOを使って分析する単位の大きさも問題である。単位を組織とするのか、組織の機能(R&D、生産、販売、チャネルなど)ごとに細かく見ていくのか、あるいはサプライチェーンのどこまでの範囲を対象とするのか、等々を決めなければならない。さらに、これらを決めたうえで、あらためて前述した組み合わせを掛け合わせてすべてを分析しなければならない。
変化が激しい環境下において、多くの企業はリソースも時間も限られている。現実的にはこうした分析が難しいことは論をまたないであろう。
2つめの問題は時間軸が考慮されていないことである。これ自身に2つの問題を含んでいる。1つ目は、この分析には膨大な手間ヒマがかかるため、結果が判明する頃には、分析対象がすでに変化している可能性が高くなるということである。2つ目は、仮に分析結果が確定したとしても、変化のスピートが速い昨今の経営環境下では、その「有効期限」はきわめて短くなってしまう点である。
3つめは、真に有用な情報が収集可能か、という問題である。企業の強みがソフトな領域(インタンジブル・アセット=目に見えない資産)へと移行しているいま、情報収集段階で分析の壁に当たってしまう可能性が高い。
たとえば、トヨタ自動車の強さである。あらゆる専門家や研究者たちがそれを解明し、ほかで再現が試みられたわけだが、トヨタと同程度の強さを再現した会社は皆無、といった結果も報告されている(※)。そのくらい、企業の真の強さを抽出することは困難なのである。
上記3つに加えて、あと1つ、経営者の視点から重要な点を指摘したい。
ポーター理論をはじめとする、分析偏重型の戦略構築スタイルは、組織に「分析症候群」や「石橋を叩かないと渡れない(分析結果が出ないと仕事が進められない)体質」をはびこらせ、チャレンジ精神を阻害する要因となる。すなわち、「チャレンジングな燃える集団を作る」というリーダーの重要な使命とは真っ向から対立するのである。
とどのつまり、このような戦略理論の前提には、「事前にすべてを予測できる」「ハード情報を分析することですべてがわかる」という(机上の理論家ならではの)思い込みがある。実務者の感触からすると、「予測」や「目に見える情報のみの分析結果」に会社の命運を賭けることはまさにバクチであるが、それが、このたぐいの理論を考えつく人たちには理解できないのである。
一方で、ユニクロの柳井氏、マクドナルドの原田氏、日産自動車のゴーン氏、元GEのウェルチ氏など多くの実績ある経営者が、
・「走りながら修正しろ(原田氏)」
・「実行がいちばん大切だ(ゴーン氏)」
・「1にも2にもスピードが大事だ(柳井氏、ウェルチ氏)」
などと口をすっぱくしていうのは、そのような悪しき体質が組織をダメにすることをよく知っているからである。さらには、走りながらビジネスの基本サイクルを回転させることにより、早めにリスクの芽を感知し、摘み取りながら前進することの利点を熟知しているからである。
彼らすぐれた実務者が身をもって証明してきたこと、すなわち、「自分の知恵を絞ってチャレンジする→結果を真摯に受け止める→しっかりと修正・改善を行って次につなげる」という基本を積み重ねていけば、自社の強さがいちばん着実に、しかも最短で磨かれていくのである。
結論。ポーター理論と同様、「すべてが予測・分析でき、把握が可能」という幻想のうえに組み立てられた理論、それが「バーニーのVRIOフレームワーク理論」である。
※ トヨタ生産方式が世界中の企業でどのように取り入れられたかについて、ハーバード・ビジネス・スクールが4 年間にわたって行った調査研究の結果が1999 年の『Harvard Business Review』で報告されている。
タイトルは『'Decoding the DNA of the Toyota Production System'』(邦題:『トヨタ生産方式の“遺伝子”を探る』2000 年3 月号)。この中で、報告者たちは、『トヨタは驚くほどオープンにそのノウハウを披露してきた。しかし不思議なことに、上手に再現できたメーカーは皆無である』と述べている。

↓よろしければクリックをお願いします。
ビジネスブログ100選ランキング
■ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所■
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2010 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆