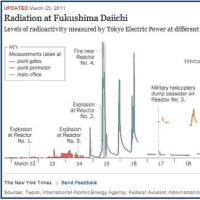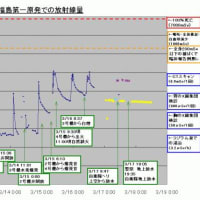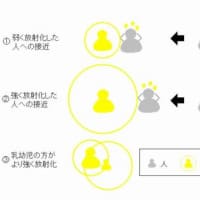東京電力の点検データ改ざん事件(3)隠蔽を暴く
2.原発の経済性追求が招いたJCO事故と点検データ改ざん
年末1973 の第1次石油ショック以降、1979年の第2次石油ショックを経て、1986年までは石油価格
の高騰に助けられ、原発の経済性は石油火力に対して相対的な優位さを保ち続けたが、1986年2月に
サウジアラビアがアジア向けネットパック価格による販売を開始して原油の公式価格が実質廃止され、
原油価格が一挙に3分の1へ暴落した。それ以降、原発の経済的優位さは完全に失われた。電力会社の
有価証券報告書における営業費ベース発電単価でみても、1986年以降、原発は輸入炭火力やLNG火力
と発電単価で競合状態にある。しかも、これは原発の設備利用率を80%に上げる一方、火力の設備利
用率を40%弱に押さえてはじめて達成される発電単価にすぎない。1994年電気事業審議会需給部会で
の耐用年発電単価試算でみても原発はLNG火力と同じ9円/kWh程度になり、1999年度の総合エネルギ
ー調査会原子力部会の試算では、耐用年発電単価(原発16年、火力15年)や運転年数27年以下の発電単
価ではLNG火力より高くなる。そのため、実際のキャッシュフロートとはかけ離れた運転年数40年の
発電単価にならして無理矢理「他の電源と遜色ない」と結論付けている。しかも、原発の設備利用率を
80%に想定しての試算であり、設備利用率が落ちれば、40年の運転年数発電原価でも競争力はない。
原発の経済性を追求するための当時の手段は、第1に、定期検査期間を短縮し修理費を削減すること、
第2に、高燃焼度化により連続運転期間をのばすことの二つである。折しも、東京電力では原発の設備
利用率が1950年代の50~60%から1988年には76.3%へ上がったものの、1989年1月に福島第二原発3
号炉で再循環ポンプ破損事故を起こして63.2%へ低落、全国平均でも70.0%へ落ち込んだ。東京電力が
自主検査データを改ざんして炉内構造物の損傷を隠し、修理を先延ばししたのは、東電の社内聞き取り
調査によれば、1986年の福島第一原発2号炉の定期検査からであり(9/2福井新聞)、丁度この頃である。
運転開始5年目の新鋭原発である福島第二原発3号炉で再循環ポンプ事故が起きたこと自体が、連続運
転による経済性追求のあまり、予兆事故を軽視し、警報を無視して運転を強行した結果であった。この
福島第二原発3号炉事故と美浜2号炉での1991年の蒸気発生器細管破断事故を経験しながら、その舌
の根が乾いた頃から、13ヶ月(400日)連続運転と定期点検期間の1ヶ月化が電力会社間で競われ始めた。
原発の経済性が失われた環境下で余儀なくされた競争でもある。そして、1998年にはほかならぬ福島
第二原発3号炉で定期点検のための停止期間36日化を達成し、翌年には関西電力の大飯3号でも36日
間の国内最短記録が達成された。こうして、1990年代後半に原発の設備利用率が80%台に乗ったので
ある。その陰では、東京電力による自主検査データ隠しが行われていたのである。これを隠さずに正直
に公表し、その都度修理しておれば、このような最短記録は達成できなかったであろうし、400日の連
続運転記録も達成できなかったであろう。その意味で、原発の経済性追求は事故・損傷隠しと表裏一体
の関係にある。この深刻な関係を無視して、検査体制や技術者の意識の問題だけに事柄をすり替えて議
論することは何ら根本的な解決にはならない。高い設備利用率の下でしか経済性の成り立たない原発で
経済性を追求する限り、事故隠しはなくならない。電力自由化で原発を競争下に置くことは重大事故を
引き寄せるようなものである。この現実を直視して、原発を競争市場から退場させる以外に解決の道は
ない。重大事故を起こす前に、原発は即座に全面停止すべきである。
南社長は9月3日、1980年代末から1990年にかけての「バブル景気が原因。受給の心配があった」
とし、原発のコスト削減が原因だとの説を否定した。しかし、これは原発の定期点検時期として夏場を
避ければ済む話であり、1986年以降の原油大幅値下げで遊休状態の火力を動かせば済む。それほど
LNG火力の発電単価は下がっていた。むしろ、1989年には福島第二原発3号炉の事故で稼働率が大幅
に低下し、原発の発電単価が毎年の営業費ベースでもLNG火力に負けていた時期である。原発の経済性を維持するため稼働率引き上げに躍起となっていたのは間違いない。現に、点検データ改ざんが始ま
ったと言われる1986年頃は、日本原電や電源開発等からの他社受電分10%強を加算するまでもなく東
電の発電設備だけで最大電力需要を十分賄えた。量的な不足が原因でデータ改ざんに走ったというのは
原発の経済性喪失を表面化させないための新たな大嘘である。もしも、1989年1月の福島第二原発3
号炉事故で110万kWの巨大原発が長期間停止したため、他の原発を一層強行運転し続けなければなら
ず、データ改ざんに走ったというのであれば、もってのほかであろう。また、当の福島第二原発3号炉
でもデータ改ざんが行われたのであるから、始末に負えない。
定期検査間隔を18ヶ月にすれば、検査が手抜きできるだけではなく、18ヶ月の連続運転をするため
に必要な高燃焼度燃料の装荷が不可欠となり、長期連続運転をしなければペイしない運転構造がより一
層強まる。高燃焼度用の濃縮度アップ燃料は高価なため、長期連続運転して初めて安くなる。そのため、
コスト削減のための連続運転に一層拍車がかかるのである。もし、設備利用率が低下すれば、固定資本
の減価償却ができなくなるだけでなく、高燃焼度化による高価な核燃料費を回収できないことになる。
電力会社は電力独占市場にあぐらをかき、電力自由化の下でも、送電網所有・支配という権益を維持
して原発を推進しようとしている。それでも、分散型電源の普及と電力自由化の下では高燃焼度化によ
る長期連続運転と定期検査や自主検査の手抜き以外に競争力を確保できない状況に置かれている。検査
におけるデータ改ざんの「原子力安全文化」と検査制度の緩和は、それなしにはやっていけなくなった
原発の現在の姿を象徴的に現している。そうである以上、重大事故を起こす前に、原発には電力市場か
ら退場していただく以外にない。
英は2001.3に新電力取引制度NETAへ移行、スポット取引価格の低下に引っ張られて相対契約価格も
下落、原発が市場で逆ざやを抱え、ブリティッシュ・エナジーの経営不振が深刻化、英政府が4.1億ポ
ンド(約760億円)の緊急運転資金支援を決定(電気新聞2002/9/12)。
原発は稼働率が70~80%と高く維持され、火力発電は
30~40%の稼働率で低い。これを逆転させれば原発の発電単価はかなり高くなる。
3.東電首脳陣=財界首脳陣の退陣がもたらす原発推進政策等への影響
東京電力は、管内居住人口4316万人(33.9%)、販売電力量2755億kWh(33.4%)、総収入5兆1560億円(33.3%)、総資産14兆1748億円(33.2%)で、日本最大の独占的電力会社(いずれも2002.3末現在、%は10電力に占める割合)。国税庁の大企業申告所得でトヨタ自動車、NTTドコモにつぐ第3位。スタンダード&プアーズの長期会社格付はAA-。電力自由化の下で、有利子負債約9.4兆円(2002.3末)、自己資本比率約15%で、設備投資を抑えて有利子負債を減らし、自己資本比率を高めようとしていた。
経団連(現、日本経団連)会長は鉄鋼、電機、化学メーカーの指定席だったが、1980年代からの円高などで後退、電力の地位が上がり、1990.12に平岩東電相談役が12年間の経団連副会長職を経て電力業界から初めて会長へ就任。在任中の3年間、「経済優先」から「企業と社会、自然との共生」へ舵取り、企業倫理、環境問題への取り組み強化、政治献金斡旋を廃止。その後も、那須相談役、荒木会長が統合後の日本経団連を含めて経団連の副会長をつとめている。政治献金廃止後、低下した政治への影響力を巨額の設備投資や原発を通じた地域とのつながりから政・官界とのパイプを強化・維持してきた。
今回の事件は、日本最大の電力会社による一大事件であるというだけでなく、日本経済界を代表する首脳陣が引き起こした一大事件として位置づける必要がある。荒木会長は日本経団連副会長で、企業倫理を担当する企業行動委員会の委員長を務め、日ハム問題などを通じて「企業行動憲章」を厳しく見直す責任者。さらに憲章は、平岩外四相談役が経団連会長時代に作ったもので、東電は組織をあげて企業倫理の守護役を務めなくてはいけない立場だった。原子力安全・保安院の調べで、東電の虚偽記載の期間は1987~1995年で、那須社長、荒木社長時代にまたがり、1990年21月にスタートした平岩経団連会
長時代とも重なる。
現職(年齢) 現職辞任時期東電社長在任期間社会的な現役職
平岩外四相談役(88) 9/30で辞任1976年10月~84年6月日本経団連名誉会長
那須翔相談役(77) 9/30で辞任1984年6月~93年6月日本経団連評議員会議長
荒木浩会長(71) 9/30で辞任1993年6月~99年6月日本経団連副会長、企業行動委員長南直哉社長(66) 10月中旬で辞任1999年6月~現在経済同友会副代表幹事
榎本聰明副社長(63) 9/30で辞任
・日本経団連は9日の会長・副会長会議で、平岩外四名誉会長(東電相談役)、那須翔評議員会議長(東電相談役)、荒木浩副会長・企業行動委員会委員長(東電会長)、上島重二副会長(三井物産会長)の退任を了承。奥田碩会長(トヨタ自動車会長)が企業行動委員会委員長を兼務、不祥事を起こした企業の「活動自粛規定の厳格化」など規定を厳格化する「企業行動憲章」の改定作業を急ぐ。評議員会議長は、伊藤助成副議長(日本生命会長)が2003.5改選時期まで代行。副会長職当面補充せず、13人体制でいく方針。
・総合資源エネルギー調査会の電気事業審議会は、9月中にまとめる予定だった中間報告を断念、9.18の会合で電力自由化論議の論点整理をし、送電料金体系の見直しや電力市場の環境整備を議論する2作業部会の設置を決めた後、12月まで議論を「凍結」することになった。自由化の中での原発の位置づけ、とくに電力の求める「バックエンドへの公的関与」が検討不十分なままであり、来春の通常国会で電気事業法改正を目指す経済産業省の筋書きが崩れる。エネ庁は「総括原価方式でありながら、さらに無税積み立ての引当金制度適用を認めてきた。TRUなども処分方法の検討はこれから進む。これ以上
の政策的措置となれば、国が事業を引き取ることになる」との態度。
次回、『東京電力の点検データ改ざん事件(4)隠蔽を暴く』記事に
続きを・・まだまだつづきます。