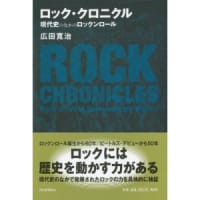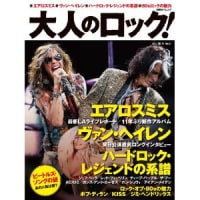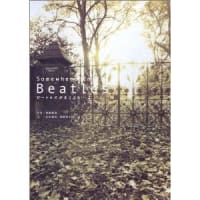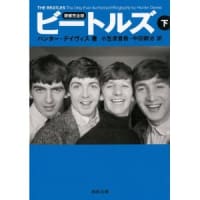さて、昨日に続いて、歌謡曲の誕生について、だらだらと考えてみる。歌謡曲の厳密な定義というのはとってもめんどくさいけど、ここではおおまかに、西洋音楽(西洋音階)と日本の音曲(日本的音階)が融合して生まれた新しい流行歌、としておく。
流行歌としての歌謡曲には「演歌」も含まれていたように思うのだけれど、歌謡曲が「ニュー・ミュージック」とか「Jポップ」とか呼ばれるようになると、「演歌」は仲間はずれにされてしまったような気がしている。
西洋音楽が日本に流入したのは、早くはキリスト教伝来時のこと。最近の研究では、このときもかなりの影響を受けていたことがあきらかになってるけど、本格的には、幕末に黒船がやってきてから。それ以前の江戸時代の音楽に影響を与えた外来音楽は、中国から沖縄経由で伝来した三味線や長崎経由の明清楽だ。
江戸時代のはやり唄の大半は伴奏楽器のない「アカペラ」だった。幕末頃には、三味線を伴奏にする「端唄」が大流行。明清楽の月琴なども伴奏に使われるようになっていた。そういう意味では、江戸時代音曲は日本独自のものではなく、中国・アジア圏の音楽の日本的展開だったと考えた方が自然だと思う。
で、明治維新以降、西洋の物質文明に圧倒された日本の権力者たちは、文明開化を旗印に今日まで突っ走ってきた。それが無意味だったとは言わないけど、日本の文化を否定してしまったことはさびしい。日本の音曲・歌謡も、低俗で卑猥なものとして全否定され、今日の音楽状況につながっている。
ちょっと話がずれてしまったけど、そういうことで、明治時代に入ると、外国のメロディに日本語の詞をつけて歌わせるという唱歌教育が始まる。でも、音階が違うから日本人はみんな音痴~みたいな劣等感を植え付けられてしまう。日本には西洋音楽が分かる先生もいないからそれはそれはたいへん。
日本に唱歌が定着しはじめたのは、1900年頃。「鉄道唱歌」が日本中で大ヒット。その頃には大人たちもようやく唱歌を口づさめるようになっていたようだ。1902年には唱歌「美しき天然」が大ヒット、メロディを借りた替え歌が広まり、それが演歌師らによって歌い広げられ、「金色夜叉」などの大ヒットにつながっていく。(8月31日のツイートより・つづく)
♪「美しき天然」 http://www.youtube.com/watch?v=Ke7GUntVooQ …
流行歌としての歌謡曲には「演歌」も含まれていたように思うのだけれど、歌謡曲が「ニュー・ミュージック」とか「Jポップ」とか呼ばれるようになると、「演歌」は仲間はずれにされてしまったような気がしている。
西洋音楽が日本に流入したのは、早くはキリスト教伝来時のこと。最近の研究では、このときもかなりの影響を受けていたことがあきらかになってるけど、本格的には、幕末に黒船がやってきてから。それ以前の江戸時代の音楽に影響を与えた外来音楽は、中国から沖縄経由で伝来した三味線や長崎経由の明清楽だ。
江戸時代のはやり唄の大半は伴奏楽器のない「アカペラ」だった。幕末頃には、三味線を伴奏にする「端唄」が大流行。明清楽の月琴なども伴奏に使われるようになっていた。そういう意味では、江戸時代音曲は日本独自のものではなく、中国・アジア圏の音楽の日本的展開だったと考えた方が自然だと思う。
で、明治維新以降、西洋の物質文明に圧倒された日本の権力者たちは、文明開化を旗印に今日まで突っ走ってきた。それが無意味だったとは言わないけど、日本の文化を否定してしまったことはさびしい。日本の音曲・歌謡も、低俗で卑猥なものとして全否定され、今日の音楽状況につながっている。
ちょっと話がずれてしまったけど、そういうことで、明治時代に入ると、外国のメロディに日本語の詞をつけて歌わせるという唱歌教育が始まる。でも、音階が違うから日本人はみんな音痴~みたいな劣等感を植え付けられてしまう。日本には西洋音楽が分かる先生もいないからそれはそれはたいへん。
日本に唱歌が定着しはじめたのは、1900年頃。「鉄道唱歌」が日本中で大ヒット。その頃には大人たちもようやく唱歌を口づさめるようになっていたようだ。1902年には唱歌「美しき天然」が大ヒット、メロディを借りた替え歌が広まり、それが演歌師らによって歌い広げられ、「金色夜叉」などの大ヒットにつながっていく。(8月31日のツイートより・つづく)
♪「美しき天然」 http://www.youtube.com/watch?v=Ke7GUntVooQ …