

役に立ちそうなら是非読んでみて下さい!!!
特集・カラダ!!!
http://diamond.jp/subcategory/sp-healthylife
日々の仕事・生活の中で、知らぬ間に健康が蝕まれているビジネスマンたち。重大な病に陥れば、最悪の場合、死を招く恐れもあります。そんな病気のサインを見逃さず、健康で過ごす秘訣をお伝えします。加齢に伴う身体の変化、職場や 家庭でのストレスなど様々な角度から、ビジネスマンの健康を考えた特集をお届けします。
知っておきたい「がん」と最新医薬品の話(第1回)
がん細胞を狙い打ちする抗体医薬
http://diamond.jp/articles/-/8612
40歳を過ぎた頃から、友人知人ががんになって闘病中という話が聞こえてくるようになる。がんは生活習慣病とも、老年病の1つでもあるともいわれる。ビジネスマンとして長年酷使してきたこの体。がんに不安を抱かない人などいないだろう。健康問題として最も関心の高いがんを克服するにはどうしたらよいだろうか。この先の体のために、いま知っておくべき予防と期待の医薬品の最先端を紹介する。
そもそもがんは、私たちの体を構成する細胞のもつ遺伝子の変化(突然変異)から始まる。遺伝子を傷つけ細胞をがん化させた後、その細胞が増殖してがんになるが、細胞を傷つける物質がわずかならがんは発生しない。仮に細胞が傷ついても、ほとんどの傷は修復機能をもつ酵素によって元通りになる。しかし、大量かつ長期間にわたって暴露されるとがんが発症する。
では、何が細胞の遺伝子を傷つけるのだろうか。生活環境のなかで、がんと関連のある因子として知られているのは食事、タバコ、ウイルス、性習慣、職業、アルコール、公害、食品添加物などがあるが、食品の中には細胞を傷つけるわけではないが、発がんを促進するものが多く含まれ、その代表が食塩や脂肪、アルコールだ。
人間には、これら環境因子によって細胞が傷はついても元通りに復元するシステムが備わっているが、問題は発がん物質の量が多すぎて修復が間に合わなかったり間違った修復がされたとき。40歳をすぎてがんの死亡率が高くなるのは、修復しきれなかった遺伝子の変化が蓄積されて、年月とともにがんへの段階を進むからだと考えられている。
がんは予防できるのか
がんの予防には1次予防と2次予防がある。1次予防はがんにならないようにすること。2次予防はがんになっても再発させないことだ。
国立がん研究センターは「がんを防ぐための12ヵ条」を提唱し、がんの原因をできるだけ避けることが大切だとしている。その気になれば誰にでもできる現代の養生訓として覚えておいて損のない12か条だ。
しかし、残念ながらこれさえ注意すればがんにならないという絶対的なゴールキーパーは存在しない。厚労省の人口動態統計によれば、2005年のがん死亡者数は32万5885人。1990年代から減少傾向に転じているが、罹患数は1975年以降、増加し続け、毎年60万人以上の新たながん患者が診断されている。
副作用の少ない期待の先端医薬品
ライフスタイルとくに食習慣の改善である程度がんを防ぐことはできそうだが、それでも高齢人口の増加とともにがんになる人は多くなるのが現実。だからこそ、早期発見、早期治療が重要な意味をもつ。がんの初期症状には、まさかと思うような症状が多いから40歳を過ぎたら毎年のがん検診を欠かさないことだ。その結果、がんが発見されても早期なら治る確率は高い。たとえば、胃がんや大腸がんの早期なら開腹せずに内視鏡で切除することも可能だ。
今、がんの手術はできるだけ機能を温存する縮小手術が主流になってきている。薬物療法でも優れた抗がん剤が登場して副作用が少なく治療効果の高い治療計画が立てられるようになった。
協和発酵キリン 研究本部研究企画部森下芳和マネジャー
薬物療法の進歩の一翼を担っているのが抗体医薬と呼ばれる分野。抗体医薬品とは何か。「最大の特徴は標的に対する特異性が高いために、副作用が少ないことです」と、抗体医薬品の研究を進める協和発酵キリン・研究本部研究企画部マネジャーの森下芳和氏は説明する。つまりがん細胞を標的とし、それ以外の部位には作用が及びにくいことが期待できるということだ。
従来の抗がん剤は、がん細胞を殺すことはできるが、他の正常細胞にもダメージを与えてしまう。それが副作用であり、副作用のために使用を断念しなければならないこともあった。これに対して抗体医薬品は、がん細胞に特異的に作用し、狙った効果を確実なものにできる。
なぜそんなことができるのか。それを説明するためには、生体がもつ免疫システムのメカニズムを知ることが必要だ。生体に進入し悪さを起こす異物(抗原)に対し、その異物から体を守るために働くタンパク質を抗体という。1つの標的(抗原)にのみ抗体が結合するという抗原抗体反応が免疫システムの特徴だ。抗体医薬品はこの特徴を利用した医薬品である。
ゲノム解析が抗体医薬品への道を拓いた
「抗体医薬品の大きさ(分子量)は従来の低分子医薬品のおよそ300倍。クジラとマグロほど違います。だから標的以外の生体に対し悪影響を及ぼす可能性が低いのです」(森下氏)。
抗体医薬品はバイオテクノロジーを駆使した創薬研究の輝かしい成果であり、がん化学療法の新たな可能性を示す医薬品なのである。
こうした薬が開発できるようになったのは、ゲノム解析により標的となる抗原分子が特定されるようになったことがあげられる。たとえば、乳がん患者ではHER2タンパクの発現が認められることがわかっていた。そこでHER2タンパクに特異的に結合する抗体医薬品が開発されている。
森下氏によれば現在、開発中のものも含めて抗体医薬品は300種類もある。その市場規模は年々成長しており、がんでは乳がんや大腸がん、急性骨髄性白血病などに対する抗体医薬品がすでに臨床で利用されている。また、がん以外にも、アレルギー免疫疾患である関節リウマチや喘息、クローン病などにも使われ、感染症分野での臨床応用も期待されている。2008年度の世界の医薬品売上高ランキングをみると、トップスリーこそ高脂血症治療薬、抗血小板薬、抗喘息薬だが、上位15位までをみると抗体医薬品が5品目もランキング入りしている。
抗体医薬品が広く利用されているのは、従来の低分子医薬品を上回る治療効果を示し、かつ副作用が少ないためだ。協和発酵キリンでは、抗体医薬品の効果をさらに高める画期的技術を開発し、通常の抗体に比べて効果を100倍も高めた医薬品の開発を行っているという。
次回・第2回では抗体医薬品という期待の新薬の特徴についてさらに詳しく紹介する。
制作/ダイヤモンド社 企画制作チーム













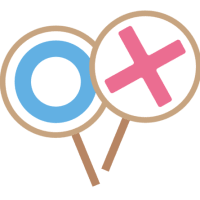






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます