
突然ですが、現在日本で国宝に指定されている茶室は3つあります。先日、そのうちの一つ、京都・山崎にある待庵(妙喜庵)に行ってきました 【事前申し込み制】
【事前申し込み制】
こちらは現存するなかで千利休の作と言われる唯一確かな茶室で、戦の最中に秀吉の命により作られたものがその後、妙喜庵に移築されたそうです(諸説あります)。
現在、待庵を含め妙喜庵全体が撮影禁止なので残念ながら写真はありません。ただ、以前は茶室の内部以外はOKだったらしくネットで検索するとけっこう出てきます。が、個人的には二次元で観ても意味がないと思うので、興味ある方は実物の見学をお勧めします。
まず妙喜庵の内部を見せていただいた後に茶室を見学するのですが、正直言って第一印象は「地味」。まず狭い(2畳)し、想像していた何倍もうす暗い。窓から覗き込んでの見学ですが、目を凝らさないと見えない箇所も多いです。これは窓の位置によって、茶を点てる手元など必要なところだけ明るくし、それ以外は暗いまま残して置くという利休の意図的な光の調節なのです。塗りっぱなしの壁から顔をのぞかせる藁くずや、壁の下地を残したままの窓など、荒っぽさすら感じる簡素さの中に、絶妙な配置で見える床の間の台の木の節や高く見せるため斜めに配置された天井、そこに渡された竹など、間違いなく美が存在する。こうした隔絶された場所で、パーソナルスペースぎりぎりの距離間で2人の人間が対峙する時、それはもうお互いむき身で魂をさらけ出して向かい合うしかないですよね。そのそぎ落とし加減に、利休の気概と権力への強烈なアンチを感じます。
私の推測も含めてですが、という前置きと共にお寺の方が話してくださったのですが、秀吉は自分の指図がすぐに実行されないと気がすまない人物で、たとえば茶室を作れと言ったら3日ぐらいで完成しないと大層ご立腹だったらしい。早く作るためには簡素な作りにせざるを得ず、2畳という狭さも、竹など自然のものをそのまま生かしたのも、そうせざるを得なかったという実際的な事情がある(そのためか、角の柱を塗りこめて丸くするなど部屋を広く見せる工夫もされています)。同時に、その限られた状況で茶の湯の世界観を表現しようとした時に、わびの精神がどんどん洗練されて具体的な形になっていったのではないか、ということでした。たとえば簡素なので通常の桧皮葺では壁が荷重に耐えられないらしく、従来より薄い屋根板になっていますが、その危うさになんとも味わい深い風情があります。
茶の湯と言うと、つい観念的なものを想像しがちですが、こうして具体的に形となった茶室を見ていると、実は利休は身体感覚が優れていたのかも、と思います。下地窓が作り出す不規則な光と影とか、近い距離で感じる人の肌身や呼吸の気配に五感が感応しなければ、自分自身の深い精神世界には降りていけない気がするからです。
ITの普及後、一人でいる時もネットやメールで常に世界と繋がることができるようになりました。常に世界と繋がっている感覚は時に救いですが、けれど、そうやって首から上、いや目から上だけで生活を続けることによって、どんどん身体感覚が衰えてきている気がします。自分自身を深めるためには、時に待庵のような空間に身を置くことも大事なのかもしれません










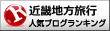

















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます