市原礼子『フラクタル』、小笠原新『ハーネス物語』、相川良彦『漱石文学の虚実』、小笠原新『シーギリヤの雨』、文学街『文学街精選作品集』 、小林弘子『室生犀星と表棹影』、おしだとしこ詩集『鳥たちのように』
2017-02-05 | 日記

市原礼子『フラクタル』
本書は、45篇の詩を収めた詩集である。第一詩集『愛の谷』が自己の半生を呻吟しながら紡いだのに対し、本詩集は老境に達した自己を振り返り、素直に、静かに、日々の思いを詩に託している。そこに流れる空気は穏やかで、また誰でもそうした自己表現の欲求を多少とも持つのではなかろうか。「帯」に青木はるみ氏は、次のように本詩集を紹介している。
「話しておきたい」ということは、
同時に「聞いておきたい」ことでもある。
「書いておきたい」にも、つながる。
その熱望が詩作と同時に評論にも及ぶ。
その姿勢は実に健気であるといえよう。
「話しておきたい」より以下抜粋
わたしは石の中にすべり込む
誰かが帰って来るのを待つ
気がつくだろうか
遠くから白い石を見る
やっぱりなにか言いたげな白い顔
親しい人のように浮かんでいる
いつかみんなに話しておきたい
本詩集のタイトル「フラクタル fractal」とは、「どこまで拡大しても内部に自己と相似な図形が無限に組み込まれた複雑な図形」という意味である。そして、冒頭の詩「フラクタル」が、この詩集のテーマを端的に示しているだろう。
「フラクタル」
フラクタルを探しなさい!
詩の女神の啓示
フラクタルって何?
みんなが持っている
心のギザギザ
ずっと
目を背けてきた
怖くて
見ることができない
弱い心のしでかしたこと
均(なら)して
可もなく
不可もなしの
毎日を生きる
不規則な感情
予測できない後悔
詩の女神は核心を迫って
されにいばらの道を進む
その後ろ姿こそ
フラクタルそのもの
いつのまにか
あとを追っている
【プロフィール】愛媛県生まれ、現在は大阪在住。北里大学薬学部卒。著書に詩集『愛の谷』詩画工房、詩文集『すべては一匹の猫からはじまった』双陽社、詩集『母の二重奏』(共著)JUNPA BOOKS

小笠原新『ハーネス物語』
評者 相川良彦
本書の短篇作品はみな、読み易くて、明快である。それは、文章が簡潔で、主人公もスマート、そしてストーリー構成がまとまっているためである。読者は作品世界へ思わず知れず惹き込まれることだろう。各作品のテーマははっきりしていて、ストーリーの展開も直線的である。テンポ良くストーリーを進めようとして、随所に偶然の出来事も組み込まれている。それは不自然な感じをもたらすのだが、反面で意外な感じを与えてアクセントにもなりうる。だから、その功罪はあい半ばする、と云って良いだろう。
情景描写の技法はリアリズムで手ざわり(生活)感を感じさせつつも、描写する世界はロマンチシズム(情と愛)の異空間である。この描く技法と求める世界のミスマッチが小笠原作品に特有の長所であり、同時に欠陥である。以下、5つの短篇の中から2作品を取り出して、その要旨と長・短所を具体的に解説しよう。
◆「マハーリア伝」の人公マハーリアは、村の大工の娘である。居酒屋を手伝うフリーターで男達の人気者、夜毎寝る相手を替える。この性に奔放で気ままな娘が父親の分からない赤子を納屋で産む。その時、居合わせた隊商の長老3人が赤子を取上げ、その子の将来(不幸な最期を遂げるが、人類の父となる)を予言する。作風は明るくて、異国情緒にあふれている。
本作品が同人誌『文学街』に載った時、同人の評判は良かった。「歴史的事実である聖母マリアを新しい視点からとらえ直しているのがとても良い」といった類の読者感想文が幾つも寄せられ、当年の同誌読者賞にも選ばれている。本作の主人公マハーリアがイエスの母マリアを連想させ、読者へ聖書の真相を覗き見たような気にさせたからである。
このように本作は、性におおらかな女性の生きざまを謳いあげている。現代日本の何処かでしばしば見られる社会現象を、古代中東に舞台を移し替えて描いた風俗小説と言えるだろう。歴史ロマン小説として良い出来映えである。
だが、事実の復元を旨とする歴史小説としてみると、本作は事実とかけ離れている。戒律の厳しい紀元前後のユダヤ社会――例えば、性への禁欲的な戒律、娼婦の蔑視、異民族への差別、こうした窮屈な戒律社会の背後にあるローマ帝国の抑圧と鬱積するユダヤ民族のストレス、ヨゼフとマリアの住んだガリラヤは大きな淡水湖を囲む農業地帯とその後背の丘陵地帯で隊商の往来する砂漠地ではない等――を全く描けていない。往時のユダヤの一少女マリアに起きた出来事とするならば、ありえない背景の設定と言わなければならない。
また、聖書についての理解も弱い。
山口里子『いのちの糧の分かち合い:いま、教会の原点から学ぶ』(新教出版社2013)によれば、(周知のように)マリアが婚外妊娠であったことは、聖書に書かれている。婚約者ヨセフは彼女の妊娠を知り「ひそかに離縁を決心」(マタイ1:19)したし、マリアも「戸惑い……考え込んだ」(マタイ1:29)ように、二人が苦悩したからである。また、マリアの歌う賛歌の歌詞「(はしための)辱めを顧みて下さいまし」(ルカ1:48)は、この妊娠が強姦によるものであったことを暗示する【拙稿「「マリアの処女懐胎」考」(『文学街』330号2015・5)】。
では、マリアの処女懐胎という聖書のありえないエピソードを、科学知識の普及した現代において、なお数多のクリスチャンが何故に信じているのだろうか?これについて筆者は次のように憶測している。
聖書は、知識の木の実を食べたアダムとエバが楽園を追われるという神話を冒頭(創世記2)に載せ、繰り返し人間の(知識の)奢りを戒めている。この世には不条理(=道理では納得しがたいよう)な出来事が多い。この不条理な出来事からの救いを、人間は神に求める。その手立てとして、この世に条理を回復するという願望と同時に、条理を超えても救われたいという、人間の希望が含まれていよう。神はそうした希望の権化として創生される。だから、宗教の教義やエピソード(特に奇跡)を知識の道理だけで納得しようとするなら、そこに信仰は生まれない。聖書が人間の(知識の)奢りを戒める――人間の知識により納得できる森羅万象はほんの僅かにすぎないのだから、知識を超えて神に救いを求める――所以である。聖書のマリアの処女懐胎に話を戻せば、それは史実であるか否かが問題なのではなく、知識を超える神の御技の象徴として捉えられているのである。
宗教問題は、日本人作家に敬遠されるテーマである。著者も、本作に賛辞を送った文学街同人諸氏もキリスト教を殆んど知らない人達だと筆者は思うが、それでも敢えて、聖書への率直な疑問を小説化してぶつけた著者の心構えは評価して良い。大きなテーマに単刀直入に斬り込む冴えが、小笠原新の本領である。
◆「ハーネス物語」の主人公・正人は、戦後の食糧難期に育っている。子沢山の貧乏世帯で、兄弟たちが戦死や栄養失調で次々に死んでゆく中、近所の沼で食材の魚を獲って母に喜ばれた。父は中学生の時に病死した。喧嘩にはめっぽう強く、顔にヤケド跡の残るライオンと綽名されて苛められていた同級生を助けたこともあった。だが、喧嘩で殴られたのがもとで、視力を徐々に失った。
優しかった母が、主人公を苛めはじめた。隣家の大学生が「これは虐待だ」と中に割って入った時、母は「この子は……ない。強く……と、この……ゆけない」と狂ったように叫び、大学生が引き下がった。聞き取れなかったが、鬼に変わったかのような母の変貌に、主人公は言いようのない悲哀を感じた。
兄の支援で高校を卒業し、針灸を5年修行した。その間に、気丈な母が亡くなった。兄たちの支援を受けて、診療所を開設した。そして、盲導犬ハーレイを飼った。或る日、散歩で主人公は転倒し、気絶した。ハーレイが裾を噛んで連れてきて若い女性に助けられた。動物好きのその女性・真弓と雑談する中で、彼女がライオン君の妹であることが分かり、やがて二人は親しくなった。
親しくなった真弓に、主人公は母のいじめを話すまでになった。黙って聞いていた真弓がしんみりと言った。「私がおかあさんなら、あなたが一番心配だ」。この時、心中に深くわだかまっていた黒雲に、一条の光がさして、聞き取れなかった母の叫びの言葉が明瞭に脳裏にたち現われた。母はこう言ったのだ、「この子は、眼が、見えない。強く、育てないと、この先、生きて、ゆけない」、と。母から捨てられたと思い恨んだ自分の愚かしさに、母の愛に、主人公は泣いた。
主人公は真弓と結婚し娘も生まれた。ハーレイは主人公の盲動役だけでなく、娘の子守り役もこなして、幸せな時が十年続いた。或る日、散歩に出た主人公へ乗用車が縁石を越えて突っ込んできた。ハーレーは体当たりで主人公を倒し、自らは車に轢かれて死んだ。主人のために己の命をささげたのであった。心温まる犬との交流を主人公が思い浮かべる夢の中で、ハーレーが訴えていた、「あなたが モウモク だったから わたしは あなたに アエタ ……」、と。
本作のテーマの一つは、障碍児の教育のあり方である。主人公の母のように、愛のムチによって鍛えるという論理も確かにありえるだろう。母ならばこその重い言葉だと思う。ただ、筆者個人は中高校時代に村田校長が言った次の言葉も気にかかる。当時、新進の進学校をめざしていた母校は、生徒に勉強のハッパをかける方針であった。ただ、それと合わないのだが、障害児の学校も併設していて、村田先生はその両校の校長を兼任していた。その校長が我々生徒に言った、「君たちは競争によって強くなる。だが、障害児はその存在を無条件に認められることで強くなる」、と。愛のムチか、愛か、筆者自身は判断がつかない。或は、軸足をどちらに置くかだけの、微妙なかねあいの問題なのかもしれない。
テーマの二つは、人間と犬の交流とは何かである。本来集団的な動物である犬は、ボス(主人)に従順という本性や仲間とのコミュニケーション能力の高さ(賢さ)を持っている。盲導犬として訓練された犬は、そうした犬本来の能力を徹底的に磨かれているのだろう。だから、主人公とハーレーとの心温まる交流が実現し、犬があたかも無二の親友のように描くことも不自然ではないのである。
だが、著者も注意書きするように、ハーレーも(他のペット犬同様に)訓練では削ぎ落されない野性を残している筈である。それを描かなければ、ハーレーの全体像は(シートン動物記のように)人間に引き寄せた犬像であって、客観性に劣るのではないか?
ここで余談じみるが、個人的な思い出話を一つさせてもらおう。十年ほど前に、或る会合で作家の伊藤桂一さんの茶飲み話を聞く機会があった。当時、八十歳代半ばであったろうが、かくしゃくとしておられた。氏、曰く、
自分(伊藤)は若い頃、学校は出たものの就職先がなかった。それで母と二人で、当時デパートに勤めていた妹に扶養されていた。その妹が夜に渋谷駅へ戻ってくるのを見計らって、出迎えるのが自分の日課だった。渋谷駅には当時忠犬ハチ公がすわっていた。それで自分はハチ公の頭をなでて、「お前は仕事があって偉いねえ」と言ったもんだ、と。
思うに、ハチ公は仕事のつもりで渋谷駅にすわっていた訳ではなかろう。伊藤さんが自分に引きつけて、ハチ公を解釈しているだけである。ただ、氏が素朴で茫洋とした雰囲気の人だから、聞く方もそこにそこはかとない犬と人間の心の交流を感じて、心温まる思いがしたのだった。
小笠原作品の主人公は、みな個性的で、スマートで、好感の持てる人間である。ストーリーは波乱万丈だが、ハッピーエンドである。だから、読後感は屈託がなく、快い。小笠原新の紡ぐ作品は、そうした主人公のカラーとストーリーの直線とが織りなす、原色の世界である。
【著者プロフィール】横須賀市生まれ、酒田市で長く高校国語教師だった。短篇小説集『エアーズロック』(日本図書館協会推薦図書)、長編歴史小説『シーギリヤの雨』(日本図書流通センター優秀図書)、高山樗牛賞受賞

【書評】 傑作あるいは奇書(?)
相川良彦『漱石文学の虚実』
― 子孫に伝わる『坊っちゃん』と『草枕』の背景 ―
評者:澤田繁晴
本書で扱われているのはモデル問題である。漱石作品のモデル問題なぞは、既に出尽くしていると思っていたのであるが、それがどうもそうではないようなのである。次から次へと薯蔓式に新事実が出て来る。それを口から出まかせではなく、理工系出身の小うるさいと思われるくらいの緻密な頭でするのであるから、読む方も真剣にならざるを得ない。手に汗を握ってしまう。良質のスリラー小説を読むような気になってしまう。著者は「俗」に徹して「俗」を出でよ、とでも言うかのように筆を進める。著者の祖母に当たる山形ナツさんの言葉を追う著者は、とかく様々なことを言われている漱石夫人・鏡子の密通問題にまで言及するのであるから恐れ入る。読者としては、「こんなことが今時出て来てよいのであろうか」といった狐に包まれたような気になってしまう。著者がいかに篤実なお人であろうと、書かれていることの七割が正しければ、上出来だと思ってしまうような代物(?)なのである。
漱石と言えば、日本文学における並外れた巨砲で、作家にして学者、我々の容易に近づけるような対象ではないようにとさえ思っていたのであるが、著者はそんな漱石の性癖と言ってもよいようなところにまで言い及ぶ。漱石とて無から有を生み出す手妻師ではなかったのである。かかる芸術作品を生み出すに当たっては、人一倍骨を折っただけではなく、使えるものは何でも使った気配である。それも巧妙にである。漱石の特質に触れた箇所は圧巻である。曰く「漱石は、登上人物のキャラクターを類型化するために、有用なエピソードを誰彼となくかき集めて、よりそれらしく装わせたからである」。漱石は複数の人物を繋げたり一人の人物を分解したりデフォルメ、変形して登場人物を創造した。漱石と読者との間には、「知的ゲーム」といったものも存在するように思う。良い小説作者は、ある意味では犯罪者のようなものであるのだろう。作者は、「ほくそ笑み」ながら犯罪に取り掛かった気配だ。読者の共感といっても、共犯者様のものであったろう。楽しみは寄席で聞かれる言葉遊び以上のものであったろう。
著者の方法は、確度の高そうな特殊例から出発して、それを一般例へと拡大して行くといったものだ。『坊ちゃん』の「うらなり」のモデル中堀貞五郎氏がその一例だ。この人物は、モデルとされることに気乗りがしないようだ。その利害とは関係なく、モデルとされることに一貫して否定的なのだ。このような人は確かにこの世に存在する。モデル問題を扱った本書に取り上げらている中堀氏のような例は、本書の誠実さを計るバロメーターにもなると思われる。またこの章には、我々に親近感さえも抱かせる正岡子規、高浜虚子といった人物も登場する。サービスとしてではなくてもちろん必要性があった上でのことである。
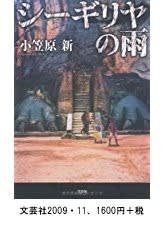
小笠原新『シーギリヤの雨』
本書は、5世紀のスリランカ、シーギリヤロックを造営した悲劇の王カーシャパにまつわるストーリーである。シーギリヤロックは現在、世界遺産になっており、スリランカ観光の最高の訪問地として世界中から人々が訪れる所となった。
5世紀のスリランカにダートゥセーナという名君が出る。王にはカーシャパとモッガラーナという二人の王子がいた。兄のカーシャパは父王を弑逆し、王位に就く。 スリランカは厳格な仏教国であり、父殺しは罪の最たるものである。以後、良心の呵責に苦悩する彼はひたすら善政を行う。更にモッガラーナ対策として、シーギリヤロックの山頂に「梯子の家」と呼ばれるほどの難攻不落の要塞宮殿を造る。
モッガラーナはインドに逃げ、タミル王朝の援助を受けて11年後、カーシャパに逆襲する。戦いの最中に、勝利を決定づけるアクシデントが起こり、モッガラーナが勝利、以後王位に就き、シンハラ朝は近世まで続く。
かつてスリランカを訪れ、シーギリヤロックを現前に見た。シーギリヤレディと呼ばれる岸壁に描かれた美女たち、中腹に厳然として残る「獅子の前足」、更に山頂に残る宮殿跡等、心打たれるものがあった。暴虐な王カーシャパとするガイドの説明に対して、私は違うと反論した。「性悪なる者に美は創造できない」、「王族には王族の運命があり、それから逃れることは出来ない」と。帰国後、まるで霊感に打たれたように執筆、「人間の原点」を描きたいと思った。本書は、スリランカのシーギリヤロックを小説化した世界最初の作品と言って良い。
【プロフィール】横須賀市生まれ、酒田市で長く高校国語教師だった。短篇小説集『エアーズロック』(日本図書館協会推薦図書)、長編歴史小説『シーギリヤの雨』(日本図書流通センター優秀図書)、高山樗牛賞受賞

『文学街 精選作品集』
210ページ、1000円+税、郁朋社2016.11
文学街刊行会編『文学街 精選作品集』評
川合 悠
文学街」同人18名の作品集である。小説が11編、童話・俳句・評論が各1編、詩が4編の構成である。作品の寄せ集めなので、玉石混淆と言える。その欠点は統一性がなくて畳みかける迫力を欠くところだが、見方を変えれば何処から読んでも良く、作品も多彩で短かくて読みやすい。その中から、筆者の目に留まった作品3点をピックアップして、本書の作風の一端を示そう。
(1) 片山龍三「フリー・エアー」は、サスペンス調の小説である。主人公は会社を休み、20年前に失踪した高校時代の女友達・絵梨子捜索の旅に出ようと決心する。というのは、最近になって彼はある夢を見るようになった、絵梨子が舎利仏になって御堂に納まっている夢をである。二人は同じ考古学サークルに属する、とくに親しいというほどでもない友人であった。その絵梨子が部活として見に行った舎利仏のある寺院で卒然と消えたのだ、「舎利仏に永遠の命を感じる」という言葉を残して。この失踪事件は、当時の警察が色々調べたが、けっきょく迷宮入りとなった。
だが、夢に触発された主人公は、20年前に訪れた寺院へ行き、舎利仏を見ないと気持ちが納まらなくなった。汽車を降りて、駅員に寺院までの道筋を尋ねた。遅いから、もうミイラは見られないという返答に、主人公は戸惑う――ミイラではない、(木か金属で作った)舎利仏の筈だと。タクシーを降りて、舎利仏の納まる御堂までの道すがら、失踪当日の出来事が次々と記憶に蘇える。そして、ついに御堂の前に立って……。
――→ 短篇だから複雑なトリックを組み込んではいないが、淡々としたストーリー構成と手際のよい情況描写で読者を惹きつける作品である。
(2) 上遠野秀治「壁」は気の利いた心理小説である。死刑囚の男が独房に放り込まれた。独房は2メートル四方、窓はなく、廊下の片側に横一列に並び、囚人同士が顔を見合せられない作りである。ただ、夜中に看守の耳を逃れて話をする事くらいは可能だった。或る晩、隣の独房にいる老人が男に話しかける――この刑務所が建てられた時、ゴミを詰め込み上辺をコンクリで塗り固めるという手抜き工事があったという噂がある。その箇所が偶々自分の独房だったなら、そこの壁はもろいから抜け穴がほれて脱獄できる、と。そりゃ、どこにあるんだ、と男。そこまでは知らん、と老人。やっぱり、作り話だ、と男はもうその話に乗らなかった。
或る日、突然看守が老人の房の前に来て、死刑執行の通知をする。独房棟は異様な興奮状態になり、老人は歯を食いしばり腕を振り回して最後のあがきを試みるが、糸の切れた操り人形のように足腰が立たなくて抱えられながら廊下の奥へと消え去り、二度と戻ってこなかった。男は死の恐怖に身がすくみ、一つの思いが浮上する。たとえ僅かな希望でもいい。冗談のような噂話にでも縋っていなければ、自分は絶望の中で死ぬだろう。抜け穴を探すのだ。男は暗い瞳で目の前の壁を凝視し始めた。
懸命に探してみたが、とうとう抜け穴は見つからなかった。やはりあの老人の話は嘘だった。男は絶望感で打ちひしがれる。思い返せば、自分はいつも壁と対峙してきた。人の、社会の、心の壁に阻まれ、囚われ、絶望の煮え湯を幾度飲んだことだろう。もう疲れた、あとは刑の執行まで静かに過ごそう。と思った矢先、隣の房に新しい囚人が入って来た。大声でわめき、自分の大物ぶりを吹聴する。哀れだと思った。そして、その新入りが「すぐに脱獄してやる」とわめいた時、この一ゕ月の徒労の末に味わった絶望と後悔が男の心底に疼く。残酷で冷酷な憎しみが湧き、男は隣の房の新入りに話しかける――あんた、脱獄したいんだろう。なら、こんな話を知っているか……、と。それは語り継がれる、壁の中のフォークロア。
――→ストーリーは空想的な場での異常な男たちの人間模様であるが、メリハリがあって面白い。テーマも人間心理の暗部を鋭く衝いている。短編小説を書く作者の技量は確かである。
(3) みずしな さえこ「詩=三篇 1 喪失の午後に」
初めて髪に白いひとすじを発見した時 気になっていた眼尻の小皺が定着した時
初めてシニアグラシィズを必要とした時 不本意にもヒールの靴が履けなくなった時
初めて己の乳房 尻の弛みに気がついた時 いよいよの女の証、月のものが無くなった時
女は女を失ったというのか 飛び行く残酷な時間の行進の中で
女は自ら女を剥脱したというのか あきらめと歎きとおののきの中で
それで
女は果して得るものはあったのか それとひきかえに女は何を得たというのか
考えるには及びますまい 人をいきるということはそういうこと
そういうことだから
今や男も女もない 恐れるものは何もない
ただ
人を生かされているだけのこと だけのこと
もはや失うものは何もない
ますます人間になっていくだけのこと ますますの人間になっていくだけのこと
――→ 女の美への執念と老の悲哀を、艶やかに、そして、あけすけに詠った詩である。シナをつくらず、女の生態を良くも悪くもさらけ出す作者の詩人魂と度胸にエールを送りたい。なお、この詩は、みずしな作の詩集からピックアップした幾つかの詩と併せて、ユーチューブ動画としてネット上にアップされている。タイトルは「みずしなさえこ処女詩集「faces」の詩と朗読」で、作者自身が朗読している。

能登印刷出版部2016.8,2000円+税
幼少期の厳しい環境をバネに、ひたすら自己を鍛えた室生犀星と、文選工として働きながら犀星と競い合った夭折の詩人表棹影。作品とともに二人の青春の軌跡をたどる論考随筆。
能登印刷出版部の紹介文
新たなる出発を喚起:小林弘子『室生犀星と表悼影』評
澤田繁晴
私は最近次のような文章を書いた。
私はかつて室生犀星の一連の小説を「教養小説」と呼んだことがある・・・・この種の小説の肯定的な側面を記述したのであろう。もちろんもうひとつの側面もあると思う。「成り上がりの文学」といった側面である。「文学界の秀吉」とでもいった側面である。犀星その人には感覚的に鋭敏なところはあったが、立身出世主義の臭みは如何ともし難いであろう。 (「木山捷平と室生犀星」)
自分で自分の書いたものを評するのもおかしなものであるが、これなどは「奇矯の言」に類するものであるのかも知れない。その点小林さんの本書は安心して読むことができる良書であると思う。全体としてこの本に異論を挟む人はないであろう。しかし、本書にはもうひとつの側面もあるようには思う。本書の圧巻とも言える「室生犀星と『女ひと』」の章についてである。そこには我々に喚起をうながす次のような言葉がある。
たくさんの名もない女、無学の女、社会の片隅に人知れず消えていった「馬鹿みたいな」女たちこそ、犀星は自分のいとしい分身だったと述懐し、そんな彼女たちの上に、学問や恵智とは無関係な、生の女の美しさ、「女ひと」の魅力を見出したという。
かつて「人生に索めるものはただ一つ、汝また復讐せよ」と己に命じた若き日の犀星にとって、おそらく何にもまして、求めて叶わなかった生母のイメージと深く重なるように「女のあはれ」が、つねに彼を突き動かしてやまなかったであろう。
よく言われていることなのであるが、犀星は女性からの人気が高い。犀星は役者ではないのだから、あの「ごり」のような容貌の故とは到底言えないであろう。そのきちんとした理由をそろそろ探求しておく頃合いではないかと思う。女性には何らかの形で思い当たる「節」があるはずである。犀星を総括しておく、というのは次のような意味である。犀星は、自分の置かれた境遇を考えながら「復讐の文学」に言及した。ところがこれが、「封建的遺制の犠牲者」たる女性の思いと合致したのではないかと思う。犀星人気の秘密である。広い意味での「復讐の文学」といった側面である。この章に取り上げられている一連の女性作家(円地文子、森茉莉、佐多稲子、林芙美子、野上弥生子、幸田文)の文学(もちろん、これだけに止まらないであろう)を「復讐の文学」という大枠の下に収めることも不可能ではあるまい。
犀星が取り上げた女性(母)の系譜はこれである程度の推測ができるであろう。父の系譜(小畠家の父子・吉種・生種のいずれであろうとも)の「封建的遺制の利得者」としての顔は、いかがなものであろうか。これにより教養小説家たる犀星の一族の「半面教師」ではない「反面教師」の顔も明らかになるはずである。このことにより、「復讐の文学」の従来のような半面ではなく全面が明らかになるはずである。一つの社会システムが、300年も存続するのには、それなりの理由がある。一部の人の利得だけで、そんなに長い間存続することなどあり得ない。だが、このことを言い始めると、この文章の範囲を大きく逸脱することになるであろうから、文学面にだけ限定しておく。犀星文学は「母の無念と父の悔恨」の二つに帰結するのではなかろうか、と思う。犀星は、「母の無念」には深く入り込んだが、「父の悔恨」には自身の出世にかまけていたために触れる時間がなかった。
犀星の「冬の蝶」(大正2・1)という作品には次のようにある。
唯、脇本自身は栄達や名誉の外に、さういふ栄達や 名誉をさえ軽蔑できるだけの生活がしたかったからであった。
本書は犀星文学についての過去のさまざまな人たちの評価も客観的な視点から公平に満遍なく取り入れられ、さながら犀星文学評解説の決定版の感がする。犀星文学にこれまで係られてきた人には頭の整理のために、犀星文学にこれから取り組もうとされている人には過去の成果を概観するためにも必読の書である。
表悼影関連では、犀星の生母問題についての先鞭をつけられただけで、その内容に関しては現在評価されることのない新保千代子さんであるが、悼影を「金沢のラディゲ」としてとらえられていたことを知り、文学に対する「眼差し」には掬すべきところがあると思って面白く読ませていただいた。
(「群系」第37号2016年10月、所収)

土曜美術社、2012.9
2100円+税、108頁
おしだ としこ詩集『鳥たちのように』
冒頭の詩「たんねんに」の一部抜粋
作物を上手に育てる人は
たんねんに 土作りから始めるのだと
冬の間に凍てついて硬くなった土を
天と地を入れ替えるように
深く掘り起こすのを「天地返し」と言うらしい
たんねんに耕された土は団粒をつくり
蒔いた種をよく発芽させて
しっかりと根をはり 葉をしげらせ
みずみずしい実りを恵むのだと
おしだとしこさんの詩はしっかりと土に根を張り、花を咲かせ、豊かな実りを迎えた畑の作物のようだ。一つ一つに手塩にかけて育てた詩人の労苦と誇りが息づいている。少し苦くて純朴だが、まぎれもない本物の大地の味がする。
一色真理
「本書のおび」より
【プロフィール】1933名古屋市、個人誌「翔」発行。近著に小説『蝶のことづて』2010私家版、詩集『白い道』2010私家版、評論『正宗白鳥ー死を超えるもの』2008、詩集『流れのきりぎしで』2007

とがりまさみ/吉野さくら/みりゅうせい『gift~言葉の、贈り物~』
3人の詩人の詩の作品集、20余の詩で編集されている。
読者の皆様こんにちわ
秋風に誘われて詩心が疼いた私達三人です。
相談してこんな詩集を発行してみました。
私達の詩をお読みになって下さってありがとう。
私たちは『相模文芸クラブ』の会員仲間です。
同人雑誌『相模文芸』に作品を発表してきました。
このたび自分の作品集を残したいと決心しました。
とりあえずはこうしてアンソロジイとなりました。
次回にはそれぞれの個人詩集を完成させます。
そのときにまた皆様とお会いしたいと思います。
どうぞいつまでもよろしく。 - 十一月 -
序
幸せになるための、言葉。
泣きそうな時、勇気をくれる、言葉。
不安な時、未来へ向かわせてくれる、言葉
”詩”(ことば) には、力が、ある。
51ページ、印刷:(株)コーエー、2011年11月
作品の紹介:詩の朗読ユーチューブ動画「みりうせい自作詩朗読poems MIRIU]」
本冊の頒価500円:購入希望は、〒252-0235 相模原市中央区相生2-6-15 外狩雅巳へ連絡のこと。

みずしなさえこ詩集『Facesー顔の中の顔ー』
R.M.Y.企画、87頁、2010.6、1200円
〈解説〉人の世 そして魂の旅 尾関 忠雄
人生を人の世と謳う
ほんのちょっぴり、洒落て、人間の味を醸し出す。とりわけ、男と女、もしくは女と男の情欲と情感が絡む。その時、人生に深いブルーとピンクが色づく。詩人、みずしなさえこの感性が妖しく華ひらき、厳しい人生を不思議なほど華やかに、人の世へと変貌せしめる。この稀有なる才能を秘めながら、さらに詩的なる世界から、演劇的世界へと誘う。
みずしなさえこの独特な、ややハスキー・ヴォイスが人生そのものの不条理さを、人の世の広さと深さへと変声させながら謳う。ゆっくりと、ゆったりと、じっくりと我が胸の底へ響くことに恐らく、疑う余地はない。
「或る女の…」「Facesー顔の中の顔」の詩篇に満ち溢れた男と女の情念とある種の機微に、ロマンチシズムの儚ささえ感ずる。否、角度を変えて解読すれば、人の世に生きんがための、愛と憎しみのパラドックスの美学さえもまた、強く意識せざるを得ない。みずしなさえこのエロスに注がれる、エクスタシーの愛液の一滴を飲み干す。
「Hホテルのロビーでは」の詩、これひとえに人の世の男と女の出会いと、人間模様が謳われている。いささかシニカルに、幾分コミカルに。これらの詩情はまたしても、散文「お見合立会人」「シルバーダンスクラブ」に色濃く流れている。恋愛は感性の芸術であり、とりわけ演劇的ですらある。みずしなさえこの独特なハスキー・ヴォイスは人の世の恋情を詠う。
我らの人の世の来し方はいったい、どのようなものなのか。ふと、そのありようを眺め、黙して語る時、詩人、みずしなさえこの魂の旅のいくばくかを聴くことができる。それを語るのもまた、演劇人としてのみずしなさえこであることを実感させられる。
実存主義の哲学者、マルチン・ハイデッカーは、人間は死を避けることができない有限的な存在者であると、いっている。しごく、当たりまえのことであるがゆえに、みずしなさえこは死と対面し、それを直視しながら魂との対話さえ充全にして試みる。
「もしもママが死んだら」の詩には、詩の重さ、暗さを不思議なくらい明るく、ある種の諦念と達観した心境で綴っている。また、散文「母の戒名」には、みずしなさえこの胸のなかの慟哭が響きわたって、悲痛でさえ、ある。人の世に、まさしく幕を降ろす瞬間がこのうえもない厳粛さを漂わせることに対して、奇妙なほど後悔の念を抱く。
詩「その歩み 止めないで」は、人の世のなかで無力な自己をさらけ出しながら、なおかつ孤独と無情な時を生き延びてきた有限的な存在者を謳う。これはまたしても、魂の旅の賛歌なのであろうか。
かけがえのない、この詩集『みずしなさえこの世界・Faces―顔の中の顔』に込められた、みずしなさえこのミューズに私の詩魂を捧ぐ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます