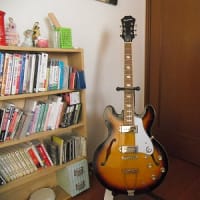「四十五年後へのメッセージ」 作 大山哲生
一
今から四十五年前の大学三年の時のことである。
私は史跡同好会というサークルで大山グループのリーダーをしていた。グループ員は十八名。私の研究テーマに共感して集まってくれた仲間である。
その年の五月、グループで恒例の春合宿をすることになった。場所は、京都のあるお寺の宿坊である。
到着すると一通り全員で見学した。夕食後は恒例の肝試しである。この寺は山の奥深くにあるから、真っ暗という表現がぴったりである。
ルールは、二人で境内の階段の一番上まで登って帰ってくるというものであった。
それぞれ大騒ぎしながらも全員無事に肝試しを終え、男子六名は部屋に集まり世間話に花を咲かせていた。
そのとき一年の八重樫亜弥が袋をもって入ってきた。
「すみません。お邪魔します。あの。私占いに凝っていて皆さんにラッキーカラーのぬいぐるみをプレゼントします」そういうと、色とりどりのクマのぬいぐるみを六つだして男子全員に渡した。私のラッキーカラーは緑色ということで緑色のぬいぐるみを渡された。
「交換とかしたら運気が落ちますからだめですよ」と言うと、八重樫亜弥はえくぼを見せて笑い、部屋から出て行った。
男子はあっけにとられていたが、他の女子に見つかったら申し訳ないような気がして、皆そそくさとカバンに入れた。
こうして春合宿は無事におわり、大山グループの一体感はさらに深まったように思われた。
私は、家に帰ってクマのぬいぐるみを出したが、ぬいぐるみなどというものが自分の部屋にあることに何とも言えない違和感を感じた。特に母親や姉に見られると恥ずかしいので、がらくた箱の中に入れて、その後出してみることはなかった。
二
九月になると、八重樫亜弥はサークル活動を休むようになった。友人の話だとかなり落ち込んでいるらしい。友人も八重樫にサークルに参加するように声をかけたが、その後参加することはなかった。十一月には退部届けがだされ、八重樫亜弥は正式に史跡同好会をやめた。
春合宿では一番楽しそうにしていたのにどうして退部したのか、私にはさっぱりわからなかった。
その後、私は二十五歳で結婚したが、六十五歳の現在に至るまでクマのぬいぐるみは妻にも見せていないし話してもいない。
三
退職すると時間もある。一度部屋の大掃除をしようと思い立った。押し入れを整理しているとあのがらくた箱が出てきた。
がらくた箱の中には、昔真空管ラジオを作ったときの部品や、高校入試合格の日の新聞が入っていた。そして、すみにはビニールに包まれたあの緑色のクマのぬいぐるみがあったのである。
そのぬいぐるみを出してみると四十五年経ったと思えないほど新しく見える。私も、やっとあのときの思い出と向かい合える心境になった。
手にとって見るとふわふわして実に気持ちがいい。昔犬を飼っていた時があったが、あのときの犬の手触りと似ている。
四
私は、そのときぬいぐるみの腹の中になにやらごつっとしたものが入っているのに気がついた。
腹の部分のチャックをあけるとピンクのメモ用紙が折りたたんで入れてあった。私は、どきどきしながらメモを広げた。
『先輩、好きです。大好きです。 八重樫亜弥』
私は、唖然とした。一瞬、この文言をどうとらえていいのかわからなかった。
しばらくすると、これがラブレターだということはわかった。でも、これは本当に私宛のものなのだろうか。
遠い記憶をたどると、あのとき八重樫亜弥はひとりひとりに別の色のぬいぐるみをわたし、交換しないように念を押した。そうすると、このメモは私宛と考えて間違いなさそうである。
つまり八重樫亜弥があのとき私に告白したのである。私は、はっと気がついた。八重樫亜弥は九月からサークルに来なくなって十一月には退部した。このメモと考え合わせると、彼女は私に振られたと思ったのかもしれない。
四十五年経って、あのとき八重樫亜弥が退部した気持ちが少し理解できた気がした。私は、久しぶりに八重樫亜弥の面影や声を思い出していた。そして、あのときの八重樫亜弥がとてもいとおしく思えたのであった。青春は傷つきやすかったけれどきらきらと輝いていたなと懐かしく思い返していた。この思い出がある限り、六十五歳であってももう一度輝いていけるのではないかと思うようになった。
八重樫亜弥の四十五年後へのメッセージであった。