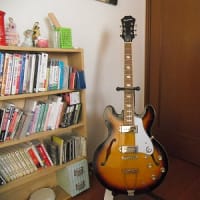~メインサイト「古都旅歩き」~
「心の帰るところ」 作 大山哲生
一
私は中小路宗則という者で、菅家の道真様(菅原道真)にお仕えしておりました。
道真様は、頭脳明晰で詩歌や漢文の才にあふれ、政(まつりごと:政治)についても常に先を見通して政策を進めていかれる。お仕えする者としてはなんとも頼もしいお方でした。
遣唐使の廃止を進言なされた時も、廃止に反対する者もおりました。しかし程なくして唐が滅びてしまい、道真様の先見の明が証明されたのでした。
このため、藤原氏の政界進出を快く思わない宇多天皇にかわいがられ、要職を歴任されたのです。
二
宇多天皇が、醍醐天皇に譲位されたあとも道真様は重用され出世されました。
昌泰(しょうたい)二年(899年)道真様は右大臣になられました。右大臣とは左大臣に次ぐ重職で、道真様は異例の出世をされたのでした。
だから、道真様の出世を妬む者も多かったのです。ある貴族などは道真様に露骨に引退をすすめたほどです。もちろん道真様はこれを一蹴されました。
道真様は、藤原氏が権力を握るのを快くは思っておられませんでした。
ある日のこと、道真様は醍醐天皇に、天皇の元に権力を集中すべしと進言されました。帝もこの意見には大層乗り気なのでした。
この進言に驚いたのが左大臣・藤原時平様です。それもそのはず、道真様の意見は藤原氏を権力の座から追い落とすことを意味したのですから。
三
藤原時平様は、ある策を講じました。醍醐天皇に拝謁すると、
「お上、実は折り入って耳にいれたい話がございます。右大臣の道真めは、ひそかにお上を廃位させるつもりらしゅうございます」
「なに、それは誠か」
「私の部下が直接聞きましたから、間違いのあろうはずはございません。お上を廃位させて道真の娘婿に皇位を継がせるつもりのようです。こうなった上からは、道真を早めに処分なさるのがよろしいかと」
藤原時平様の言葉に動揺した醍醐天皇は、道真に九州太宰府の役人をお命じになりました。
これは謀反を企てたことによる左遷でした。
道真様をかわいがっていた宇多上皇は驚き、醍醐天皇と道真様の間をとりなそうとされましたが、醍醐帝は決して道真様と会おうとはされませんでした。
四
いよいよ、太宰府へ赴く日がやってきました。道真様は途中、長岡に立ち寄られました。ここは昔、在原業平様たちと詩歌管弦の遊びをされたこともある場所なのでした。
深い緑の木々を見上げながら
「ここも見納めだな。私の心は長くここにとどまっていることだろうよ」と寂しそうにつぶやかれました。いよいよ京都を離れるとき、道真様は何度も何度も京都の町を振り返られたのでした。そして、「いよいよ、これが最後か」と辛そうに私に言われました。
太宰府に向かう道中も、京都ではあんなこともあった、こんなこともあったと一人語りをされていました。私は涙を流しながら相づちを打つのが精一杯なのでした。
五
太宰府についてからも、道真様はどことなく寂しそうでした。表面上は太宰府の役人として赴任したのですから、仕事には精をだされました。
梅の咲く季節がくると「のう宗則、京都の梅も咲き始めただろうか」とお聞きになる。
桜が咲くと「京都の桜もさぞかし美しく咲いていることだろうよ」とおっしゃる。
道真様にとっては季節の移り変わりが、全部京都を思い出させるのだろうと思われたのでした。
太宰府の生活にも慣れると、道真様は木材を削り像を彫り始められました。それからは毎日暇さえあれば像にかかられるのでした。
六
長い年月が経ち、道真様は病の床に臥せられました。
ある日、私を枕元に呼び、
「宗則、私はこの太宰府に左遷されたが心はいつも京都にあった。頼みがあるのだが、私は自分で自分の分身となるべき像を彫り上げた。この身は京都に帰ることがかなわなかったけれど、私の死後せめてこの像を京都に持ち帰り祭ってほしい」とおっしゃいました。
程なくして道真様は、あの世に旅立たれたのでした。
私は道真様の法要をすませると、道真様が彫られた像を持って京都を目指しました。
しかし、この像を京都のどこに祭ればよいのかわからずいろいろと思案していました。
そのとき、道真様が最後に長岡で言われた言葉が頭をよぎったのでした。
「私の心は長くここにとどまっていることだろうよ」
私は、京都長岡に行き緑豊かな森の中に祠をつくり、その中に道真様の像をお祭りいたしました。
道真様は、京都に戻ることはかなわなかったけれど、道真様の言葉通り魂だけは永遠に京都長岡の地にとどまることになったのでした。
その後、この祠をだれいうともなく長岡天満宮と呼ぶようになりました。