本書よりーーーほとんどの国民は、もし異なったニュース源から出た情報の内容が同じであれば、それは真実だと考えてしまうだろう。
彼らは、すっかりだまされているということに気がついていないだけなのである。
part5 大いなる洗脳(世界医薬産業の犯罪より)ーその1のつづきです
一流と言われる医学者まで洗脳されている・・・としたら・・・
一般人など
part5 大いなる洗脳 (世界医薬産業の犯罪)音声読み上げmp3です。
Web魚拓より転載 (Ctrlボタンを押しながらクリックする)
以下転載ーーーーーーーーーーーー
誤情報宣伝局
↑
●一九六七年
一九六〇年代に入り、アメリカでは動物実験反対派の動きが再び活発になり、上院での公聴会なども開かれていた。医学・製薬・動物実験コンビナートにとって、この動きは目障りきわまりなく、この辺りで、全国で最高の権威を誇る新聞誌上で――すなわち『ニューヨーク.タイムズ』のことだが――この件に関する大々的な宣伝をする時が来たと判断した。国中の大新聞が『ニューヨーク・タイムズ』に歩調をあわせるのが慣例になっているからである。
この時、全国医学研究協会(NSMR)の指図を受けて、宣伝用の記事を書いたのは、ローレンス・ガルトンというフリーランスの科学記者だった。『ニューヨーク・タイムズ』は彼の記事を日曜版に載せるという特別待遇を与えた。記事の信頼度が強調されたと大喜びしたNSMRは、後日、これを引き伸ばし光沢紙に刷って、イラスト入りの小冊子に仕立て、無料で各方面に配布した。その冊子の表紙には「『ニューヨーク・タイムズ』一九六七年二月二十六日付日曜版より」と大きな文字で麗々しく印刷されていた。
ガルトンの使ったテクニックは当時よく使われた手法で、実験動物は決して苦痛を与えられていないし、むしろ一般の動物たちより苦痛の少ない死を迎えている、と強調して、読者を安心させるというものだった。
研究目的で解剖される動物には深い麻酔がかけられ、観察が終了すると意識が戻らないうちに死に至らしめられる。手術後も生かしておく必要がある場合の手順は、人間の手術の場合と同様である。すなわち、無菌状態での手術、術後回復の監視、可能な限りの痛みの除去。
もしこれが本当なら、動物実験反対論者どもは、いったい何を騒ぎ立てているのだということになるではないか。二一年にもわたり、アメリカ中の動物実験研究室に足繁く通ったと公言しているガルトン氏に、今さらこんな質問をするのも野暮かとは思うが、あえて聞かせてもらおう。
あなたは、電気ショックで実験動物――それも予算さえ許せば霊長類を使うのだが――の心身を完全に破壊するまで行なわれるおびただしい数の神経生理学実験について、本当に聞いたり見たりしたことがないのか。
また、「ネコの性行動」調査の実験について本当に聞いたり見たりしたことがないのか。この実験は、一九六七年時点で、全米二〇以上の大学で実施されていたもので、ネコのペニスの神経を外科的に露出させ(簡単に言うとナイフで切り開く)、ネコが終末(すなわち死)に至るまで、絶え間なく電気ショックを与え続けるというものなのだが。
お決まりの「無痛実験」宣伝の後に、ガルトンは、さらにもうひとつのよく使われる手法を出してくる――動物虐待に非難の声を上げているのは誰か?誰って、動物愛護団体に決まっているではないか。それならば、とガルトンは言う。
「昨年中にマサチューセッツ州で医学校や病院研究所で、実験に使われたイヌは一万頭にも満たない。ところが、動物愛護協会によって三万五〇〇〇頭ものイヌが殺されたと発表されている」。ここでのガルトンの絶妙な言葉の使い分けに御注意願いたい。実験には「使われた」、愛護協会には「殺された」と言っている。愛護協会は、病犬、野良犬、捨て犬などの無用の苦痛を長びかせないよう殺したのである。このような数字と言葉のごまかしで読者を完全に混乱に陥れておいて、最後のとどめを刺す。
病気とは残酷なものだ。重度の火傷、重い外傷、激しいショック、手術、予防接種、糖尿病や高血圧など慢性病の薬、心臓ペースメーカー――これらの研究は動物実験に負うところが大きい。
ガルトンは臓器移植を入れ忘れているようだ。それにしても、ここでの彼のすべての主張は証拠を欠いている。従って容易に完全な反論が可能である。最初の火傷を例にとって反論してみよう。
火傷に対し、動物の皮膚とヒトの皮膚とは反応の仕方が異なる。動物は浮腫を生じ、ヒトは火ぶくれをおこす。そして動物実験に負うところあってか、一〇〇年前と変わらず、ある割合以上に皮膚に火傷を負うとヒトは死ぬ。一九八〇年、イタリアのソレントで開かれた医学会で、人工臓器の生みの親の一人で、パリのデュボス教授の長年の協力者でもあるルイジ・スプロヴィエリ教授が、一〇カ国から集まった数百人の医師たちを前に語った言葉に注目したい。「生物医学研究は今や、動物に頼る必要はありません。コンピュータを使うべきです。伝統的手法に頼るのは有害無益です。
というのは、人と動物の違いが、私たちをほとんどの場合、間違った結論へと導くからです。私たちは人工臓器が動物実験で試されずとも、直接、人間に使って大丈夫だということにすでに気づいております。たとえば、心臓の弁、そしてベースメーカーです。これらは、まず人間で完全に機能するということが分かってから、動物でもうまくゆく、ということが追認されたのです」(『ラ・ナツィオーネ』フィレンツェ、一九八〇年十月五日)。
一九世紀末に、今日でも使われている外科手術テクニックの大部分を考案したローソン・テイトから、バリバリの現役R・J・ベルチャー教授に至るまで多くの外科医たちが、前述のガルトンの記事で外科手術についての部分はまったくのでたらめだと非難した。外科手術だけではない。彼の書いたことすべてが非難の的になった。ところが『ニューヨーク・タイムズ』は、押し寄せる抗議をまったく取り上げなかったのである。
↑
●一九七八年
一九七八年三月二十七日『ニューズ・ウィーク』に「実験室の動物たち」というタイトルの長文の記事が載った。執筆者はピーター・グウィンとシャロン・ベグレイ。二人は相当な無理をして、動物実験という弁解不可能な行為の新しい逃げ道を捜し出している。
科学者にとって、実験に動物を使用することは、自然の秩序の一部だと考えられるのである。
「神が人間に動物の支配権をお与えになったという、旧約時代の伝統にまでさかのぼる」とNSMRのサーマン・グラフトン博士が語っている。
生物医学者たちも、彼らの扱う動物たちが虐待を受けているという批判に対しては、きっぱりとこれを否定する。「ニューヨーク中のネコの半分は、我々の実験用ネコほどに人道的な扱いを受けていないだろう」とコーネル大学医学部のブルース・エワルド博士は言う。
ほとんどの動物実験は有益であり、注意深く実行されている――厳しい規制の結果、動物の苦痛はかなり軽減されている……。
費用の増大、保護法の強化(そんな法は存在しないか、たとえあったにせよ実施はされていない――著者)、そして、実験非難の声、という三重の脅威にさらされて、研究者たちは、研究が有効で人道的であるよう細心の注意を払っている。
↑
●一九八〇年
一九七八年までは、誤情報宣伝局は世論をリードするマスメディアのトップに次のように働きかけていた――「すべての動物実験は人類の幸福にとって必要不可欠である。しかも実験者に自然に備わった慈悲心によって動物は十分に保護され、事実上何の不利益もこうむっていない」。ところが、権力側のこの言い分に対し、一九七八年に『罪なきものの虐殺』が実例をもって、完全な反証を提出した。
彼らは『罪なきものの虐殺』をすぐ絶版に追い込むのには成功した。しかし動物実験反対派は、反対闘争の拠り所としてこれまでの倫理的道徳的論拠に加えて、堅固な科学的根拠を見出したのである。
そこで、再び、NSMRの指令によって、長文の動物実験擁護記事が新聞に出されることになった。今回ももちろん『ニューヨーク・タイムズ』である。反対派の亡霊を払拭するためには、動物実験のもたらす恩恵の素晴らしさを伝えるメッセージを完壁なものに手直しする必要がある。これは難しい仕事である。
さて七八年十二月三十「日付『ニューヨーク・タイムズ』の付録に、バトリシャ・カーティス署名の記事が出た。記事のタイトルは、体制側の姿勢が、六七年頃のそれとはすっかり変わっているということを印象づけるよう工夫されていた。
いわく、「動物実験反対論」。もっとも、「反対」はタイトルだけで終わりだったが。NSMRの編集者たちは実に巧妙だ。反対運動の高まりの機先を制するために、世論の変化を、他でもない実験業界自身の変化の影響だとしてしまったのである。
「多くの科学者の間にも高まっているこの危惧の発端は、科学者自身の発見の中にある」とカーティスはぬけぬけと言う。こんな白々しい文句を聞かされた後は、どのような文が続こうと驚きもしなくなる。
「ポリオワクチンから刺激反応生理学まで、数多くの重要な医学上の発見が、動物実験の成果であるという事実には疑いの余地がない」。このいつもの擁護派の決まり文句『罪なきものの虐殺』にその多くを引用したように、その虚偽性は医学の権威者たちによって明らかにされてきたのだがを述べた後、カーティスは次のようなことまで書くことを許されている。ただしほんのわずかでも否定的ニュアンスはにおわせないよう注意した上でのことだが。
今日、よく行なわれる心理学実験に「学習させられた諦め」(learned helplessness)と呼ばれる状態がある。檻に閉じ込めた動物にさまざまな電気ショックを与え、その動物がショックを回避する方法を次々と学習するようしむける。最終的には動物は床に横たわって、ショックを受身的に受け入れるようになる。研究者はこの「学習させられた諦め」の状態と、ヒトの響状態との間に何らかの同一性を見出そうとしている。
この非人格的な冷たい書き方は、自称「研究者」たちの研究論文に相通じるものではないだろうか。
例によって、この記事のどこにも製薬業界の私利私欲や、動物実験は必然的に人体実験につながるという恐るべき事実などについてはまったく触れられていない。人体実験は現実に、主に公的施設に収容されている孤児や貧しい老人たちを対象に行なわれているのである。この種の実験を資金的にバックアップしているのはロックフェラー関連団体である。
この記事は、『リーダーズ・ダイジェスト』に転載された。『リーダーズ・ダイジェスト』は毎月の発行部数が全世界で二〇〇〇万部、読者数一億人と豪語しているロックフェラーの息のかかった雑誌である。
このカーティスの動物実験の記事の掲載された国際版一九八〇年三月号(アメリカ版では二月号)を検討してみると、非常に興味ある事実に気づく。
『リーダーズ・ダイジェスト』を開いてみると、まず特等席の第一ページを占領しているのは、ロックフェラー傘下のブリストルマイヤーズ社の感冒薬コムトレックスの広告。
そしてそれに続く最初の六ページ全部が、薬と化粧品の広告で埋まっている。七ページ目にはドライヤーの広告があり、その後、ようやく本文が始まる。これがニページ分の記事で、タイトルが「医薬界だより」、内容は医薬研究や新薬、新しい治療法などの称賛に終始する。
この号に関して言えば、前述の六ページに加え、さらにあと二七ページ分が化学工業関連製品(石油化学、農業化学関係が少々あるがほとんどは薬と化粧品)の全ページ広告に当てられ、これらで雑誌全体の広告の大部分を占める。化学工業に無関係の広告ぺージもあるにはあるが、後ろの方に追いやられている。
さらに、前の方の一ページは、かの誤情報宣伝の大本山、ブリタニカ大百科事典のための指定席になっている。
この百科事典は近年、ロックフェラー傘下に入ったが、それ以来、医学関係項目を、医薬品取引に有利な方向へと全面改訂を行なった。
↑
世論の買収
マスメディアによる虚偽、歪曲、弾圧といった周到で組織的な情報操作は、独裁政権下においてよりも、いわゆる民主的といわれる社会においての方がはるかにたちが悪い。独裁制社会では、国民は、マスメディアに表現の自由がないということを知っているために、政府発表のニュースはすべて割り引いて受け取るべきものと承知している。それに対し、民主社会では、ほとんどの国民は、もし異なったニュース源から出た情報の内容が同じであれば、それは真実だと考えてしまうだろう。
彼らは、すっかりだまされているということに気がついていないだけなのである。
『ニューヨーク・タイムズ』や『リーダーズ・ダイジェスト』のようなマスコミ界のメジャーが、動物実験の必要性に反駁を加えるような情報は流さない、というのは何もアメリカに限ったことではない。国全体が化学・医学権力の支配下におかれている国ではどこでも同じような状況だと言えよう。
〔南アの例〕南ア『ケープ・タイムズ』一九七七年六月二十八日付紙上で、クリスチアン・バーナード博士は、動物実験反対論者に挑戦を試みた。医学が実験動物を使用することなしに、これまでいかにして進歩してきたか、また将来どのようにして進歩できるかを証明せよ、と迫ったのである。この挑戦を、南アの動物実験反対同盟、SAAAPEAが受けて立ち、回答を送った。しかし、バーナード博士の原稿は検閲しなかった『ケープ・タイムズ』が、回答の方は入念に検閲し、核心となる部分をほとんどカットして骨抜きにしてしまったのである。
ヨーロッパ中の体制派の新聞は、『ケープ・タイムズ』と同様の編集方針をとっている。反対派側が流したいと思う重要な情報は、大抵、検閲の網にひっかかってしまう。
〔フランスの例〕一九七七年七月二十九日、パリの日刊紙『ル・フィガロ』にJ・P・カケラ教授の署名入りで「モルモットか人間か」という記事が載った。これはタイトルを見ただけでもお分かりの通り、嘘情報と決まり文句の羅列に終始した動物実験賛歌であり、現代医学の最大の誤謬が最高の成功のごとくに紹介されている文である。動物実験のお陰で人類が救われたという、いつものあれである。
『ル・フィガロ』には反論の投書が殺到したらしい。しかし紙上に取り上げられたのはそのうちたったの二通、それもズタズタにカットしての採用だった。一通はフランスの動物実験反対同盟の会長からのもの、そしてもう一通は私のものだった。私自身かなり努力して簡潔に書いた文だったにもかかわらず、主要な部分はほとんど削られていた。たとえば、ごく最近フランス語で出版した「動物実験に関するテクニカル・リポート」を希望者に無料で送るという申し出を書き添えておいたのだが、もちろん削除された。このリポートには、他のさまざまな情報とともに、動物実験を科学の失策だとして糾弾した各国の一五〇名に上る医学界権威者の言葉を引用してある。
他の欧米諸国の主要新聞も、これまでのところ、反対運動に対する扱いは、上記二例とほぼ同様だろう。
しかし、何と言っても、政府と化学・医学コンビナートとの馴れ合いがもっとも露骨に出ているのは、フランス、ドイツそれにイタリアだろう。フランスとドイツでは、もっとも有力な宣伝媒体であるテレビが、国家の独占事業であり、イタリアも、テレビ事業に対し、政府が主導権を握っているからである。
これらの国のテレビで放映される討論会まがいの番組で動物実験がテーマになったことがある。編集部によって多少手が加えられたなどという程度のものではない、完全な事実の歪曲になってしまっていた。
一九八一年五月、フランスで大々的な討論番組が放映された。出演者の顔ぶれを見ると、実験支持派にはそうそうたる「科学者」を揃えた。
一方、反対派の方は、「科学者」を向うにまわして堂堂とわたり合える人材が注意深く排除されていた。反対派代表として選ばれたのは、ブリジッド・バルドー、新聞記者、映画製作者、それに、サリドマイド悲劇に関しては何も知らない(さもなくば知りたくない)ため討論会の間中ほとんど無言を通したホメオパシーの医者、といった顔ぶれだった。そこで、動物実験者たちは、思うがままにあらゆるにせ情報を一六〇〇万人の視聴者に伝えることができたという次第である。
↑
誤情報宣伝局
↑
●一九六七年
一九六〇年代に入り、アメリカでは動物実験反対派の動きが再び活発になり、上院での公聴会なども開かれていた。医学・製薬・動物実験コンビナートにとって、この動きは目障りきわまりなく、この辺りで、全国で最高の権威を誇る新聞誌上で――すなわち『ニューヨーク.タイムズ』のことだが――この件に関する大々的な宣伝をする時が来たと判断した。国中の大新聞が『ニューヨーク・タイムズ』に歩調をあわせるのが慣例になっているからである。
この時、全国医学研究協会(NSMR)の指図を受けて、宣伝用の記事を書いたのは、ローレンス・ガルトンというフリーランスの科学記者だった。『ニューヨーク・タイムズ』は彼の記事を日曜版に載せるという特別待遇を与えた。記事の信頼度が強調されたと大喜びしたNSMRは、後日、これを引き伸ばし光沢紙に刷って、イラスト入りの小冊子に仕立て、無料で各方面に配布した。その冊子の表紙には「『ニューヨーク・タイムズ』一九六七年二月二十六日付日曜版より」と大きな文字で麗々しく印刷されていた。
ガルトンの使ったテクニックは当時よく使われた手法で、実験動物は決して苦痛を与えられていないし、むしろ一般の動物たちより苦痛の少ない死を迎えている、と強調して、読者を安心させるというものだった。
研究目的で解剖される動物には深い麻酔がかけられ、観察が終了すると意識が戻らないうちに死に至らしめられる。手術後も生かしておく必要がある場合の手順は、人間の手術の場合と同様である。すなわち、無菌状態での手術、術後回復の監視、可能な限りの痛みの除去。
もしこれが本当なら、動物実験反対論者どもは、いったい何を騒ぎ立てているのだということになるではないか。二一年にもわたり、アメリカ中の動物実験研究室に足繁く通ったと公言しているガルトン氏に、今さらこんな質問をするのも野暮かとは思うが、あえて聞かせてもらおう。
あなたは、電気ショックで実験動物――それも予算さえ許せば霊長類を使うのだが――の心身を完全に破壊するまで行なわれるおびただしい数の神経生理学実験について、本当に聞いたり見たりしたことがないのか。
また、「ネコの性行動」調査の実験について本当に聞いたり見たりしたことがないのか。この実験は、一九六七年時点で、全米二〇以上の大学で実施されていたもので、ネコのペニスの神経を外科的に露出させ(簡単に言うとナイフで切り開く)、ネコが終末(すなわち死)に至るまで、絶え間なく電気ショックを与え続けるというものなのだが。
お決まりの「無痛実験」宣伝の後に、ガルトンは、さらにもうひとつのよく使われる手法を出してくる――動物虐待に非難の声を上げているのは誰か?誰って、動物愛護団体に決まっているではないか。それならば、とガルトンは言う。
「昨年中にマサチューセッツ州で医学校や病院研究所で、実験に使われたイヌは一万頭にも満たない。ところが、動物愛護協会によって三万五〇〇〇頭ものイヌが殺されたと発表されている」。ここでのガルトンの絶妙な言葉の使い分けに御注意願いたい。実験には「使われた」、愛護協会には「殺された」と言っている。愛護協会は、病犬、野良犬、捨て犬などの無用の苦痛を長びかせないよう殺したのである。このような数字と言葉のごまかしで読者を完全に混乱に陥れておいて、最後のとどめを刺す。
病気とは残酷なものだ。重度の火傷、重い外傷、激しいショック、手術、予防接種、糖尿病や高血圧など慢性病の薬、心臓ペースメーカー――これらの研究は動物実験に負うところが大きい。
ガルトンは臓器移植を入れ忘れているようだ。それにしても、ここでの彼のすべての主張は証拠を欠いている。従って容易に完全な反論が可能である。最初の火傷を例にとって反論してみよう。
火傷に対し、動物の皮膚とヒトの皮膚とは反応の仕方が異なる。動物は浮腫を生じ、ヒトは火ぶくれをおこす。そして動物実験に負うところあってか、一〇〇年前と変わらず、ある割合以上に皮膚に火傷を負うとヒトは死ぬ。一九八〇年、イタリアのソレントで開かれた医学会で、人工臓器の生みの親の一人で、パリのデュボス教授の長年の協力者でもあるルイジ・スプロヴィエリ教授が、一〇カ国から集まった数百人の医師たちを前に語った言葉に注目したい。「生物医学研究は今や、動物に頼る必要はありません。コンピュータを使うべきです。伝統的手法に頼るのは有害無益です。
というのは、人と動物の違いが、私たちをほとんどの場合、間違った結論へと導くからです。私たちは人工臓器が動物実験で試されずとも、直接、人間に使って大丈夫だということにすでに気づいております。たとえば、心臓の弁、そしてベースメーカーです。これらは、まず人間で完全に機能するということが分かってから、動物でもうまくゆく、ということが追認されたのです」(『ラ・ナツィオーネ』フィレンツェ、一九八〇年十月五日)。
一九世紀末に、今日でも使われている外科手術テクニックの大部分を考案したローソン・テイトから、バリバリの現役R・J・ベルチャー教授に至るまで多くの外科医たちが、前述のガルトンの記事で外科手術についての部分はまったくのでたらめだと非難した。外科手術だけではない。彼の書いたことすべてが非難の的になった。ところが『ニューヨーク・タイムズ』は、押し寄せる抗議をまったく取り上げなかったのである。
↑
●一九七八年
一九七八年三月二十七日『ニューズ・ウィーク』に「実験室の動物たち」というタイトルの長文の記事が載った。執筆者はピーター・グウィンとシャロン・ベグレイ。二人は相当な無理をして、動物実験という弁解不可能な行為の新しい逃げ道を捜し出している。
科学者にとって、実験に動物を使用することは、自然の秩序の一部だと考えられるのである。
「神が人間に動物の支配権をお与えになったという、旧約時代の伝統にまでさかのぼる」とNSMRのサーマン・グラフトン博士が語っている。
生物医学者たちも、彼らの扱う動物たちが虐待を受けているという批判に対しては、きっぱりとこれを否定する。「ニューヨーク中のネコの半分は、我々の実験用ネコほどに人道的な扱いを受けていないだろう」とコーネル大学医学部のブルース・エワルド博士は言う。
ほとんどの動物実験は有益であり、注意深く実行されている――厳しい規制の結果、動物の苦痛はかなり軽減されている……。
費用の増大、保護法の強化(そんな法は存在しないか、たとえあったにせよ実施はされていない――著者)、そして、実験非難の声、という三重の脅威にさらされて、研究者たちは、研究が有効で人道的であるよう細心の注意を払っている。
↑
●一九八〇年
一九七八年までは、誤情報宣伝局は世論をリードするマスメディアのトップに次のように働きかけていた――「すべての動物実験は人類の幸福にとって必要不可欠である。しかも実験者に自然に備わった慈悲心によって動物は十分に保護され、事実上何の不利益もこうむっていない」。ところが、権力側のこの言い分に対し、一九七八年に『罪なきものの虐殺』が実例をもって、完全な反証を提出した。
彼らは『罪なきものの虐殺』をすぐ絶版に追い込むのには成功した。しかし動物実験反対派は、反対闘争の拠り所としてこれまでの倫理的道徳的論拠に加えて、堅固な科学的根拠を見出したのである。
そこで、再び、NSMRの指令によって、長文の動物実験擁護記事が新聞に出されることになった。今回ももちろん『ニューヨーク・タイムズ』である。反対派の亡霊を払拭するためには、動物実験のもたらす恩恵の素晴らしさを伝えるメッセージを完壁なものに手直しする必要がある。これは難しい仕事である。
さて七八年十二月三十「日付『ニューヨーク・タイムズ』の付録に、バトリシャ・カーティス署名の記事が出た。記事のタイトルは、体制側の姿勢が、六七年頃のそれとはすっかり変わっているということを印象づけるよう工夫されていた。
いわく、「動物実験反対論」。もっとも、「反対」はタイトルだけで終わりだったが。NSMRの編集者たちは実に巧妙だ。反対運動の高まりの機先を制するために、世論の変化を、他でもない実験業界自身の変化の影響だとしてしまったのである。
「多くの科学者の間にも高まっているこの危惧の発端は、科学者自身の発見の中にある」とカーティスはぬけぬけと言う。こんな白々しい文句を聞かされた後は、どのような文が続こうと驚きもしなくなる。
「ポリオワクチンから刺激反応生理学まで、数多くの重要な医学上の発見が、動物実験の成果であるという事実には疑いの余地がない」。このいつもの擁護派の決まり文句『罪なきものの虐殺』にその多くを引用したように、その虚偽性は医学の権威者たちによって明らかにされてきたのだがを述べた後、カーティスは次のようなことまで書くことを許されている。ただしほんのわずかでも否定的ニュアンスはにおわせないよう注意した上でのことだが。
今日、よく行なわれる心理学実験に「学習させられた諦め」(learned helplessness)と呼ばれる状態がある。檻に閉じ込めた動物にさまざまな電気ショックを与え、その動物がショックを回避する方法を次々と学習するようしむける。最終的には動物は床に横たわって、ショックを受身的に受け入れるようになる。研究者はこの「学習させられた諦め」の状態と、ヒトの響状態との間に何らかの同一性を見出そうとしている。
この非人格的な冷たい書き方は、自称「研究者」たちの研究論文に相通じるものではないだろうか。
例によって、この記事のどこにも製薬業界の私利私欲や、動物実験は必然的に人体実験につながるという恐るべき事実などについてはまったく触れられていない。人体実験は現実に、主に公的施設に収容されている孤児や貧しい老人たちを対象に行なわれているのである。この種の実験を資金的にバックアップしているのはロックフェラー関連団体である。
この記事は、『リーダーズ・ダイジェスト』に転載された。『リーダーズ・ダイジェスト』は毎月の発行部数が全世界で二〇〇〇万部、読者数一億人と豪語しているロックフェラーの息のかかった雑誌である。
このカーティスの動物実験の記事の掲載された国際版一九八〇年三月号(アメリカ版では二月号)を検討してみると、非常に興味ある事実に気づく。
『リーダーズ・ダイジェスト』を開いてみると、まず特等席の第一ページを占領しているのは、ロックフェラー傘下のブリストルマイヤーズ社の感冒薬コムトレックスの広告。
そしてそれに続く最初の六ページ全部が、薬と化粧品の広告で埋まっている。七ページ目にはドライヤーの広告があり、その後、ようやく本文が始まる。これがニページ分の記事で、タイトルが「医薬界だより」、内容は医薬研究や新薬、新しい治療法などの称賛に終始する。
この号に関して言えば、前述の六ページに加え、さらにあと二七ページ分が化学工業関連製品(石油化学、農業化学関係が少々あるがほとんどは薬と化粧品)の全ページ広告に当てられ、これらで雑誌全体の広告の大部分を占める。化学工業に無関係の広告ぺージもあるにはあるが、後ろの方に追いやられている。
さらに、前の方の一ページは、かの誤情報宣伝の大本山、ブリタニカ大百科事典のための指定席になっている。
この百科事典は近年、ロックフェラー傘下に入ったが、それ以来、医学関係項目を、医薬品取引に有利な方向へと全面改訂を行なった。
↑
世論の買収
マスメディアによる虚偽、歪曲、弾圧といった周到で組織的な情報操作は、独裁政権下においてよりも、いわゆる民主的といわれる社会においての方がはるかにたちが悪い。独裁制社会では、国民は、マスメディアに表現の自由がないということを知っているために、政府発表のニュースはすべて割り引いて受け取るべきものと承知している。それに対し、民主社会では、ほとんどの国民は、もし異なったニュース源から出た情報の内容が同じであれば、それは真実だと考えてしまうだろう。
彼らは、すっかりだまされているということに気がついていないだけなのである。
『ニューヨーク・タイムズ』や『リーダーズ・ダイジェスト』のようなマスコミ界のメジャーが、動物実験の必要性に反駁を加えるような情報は流さない、というのは何もアメリカに限ったことではない。国全体が化学・医学権力の支配下におかれている国ではどこでも同じような状況だと言えよう。
〔南アの例〕南ア『ケープ・タイムズ』一九七七年六月二十八日付紙上で、クリスチアン・バーナード博士は、動物実験反対論者に挑戦を試みた。医学が実験動物を使用することなしに、これまでいかにして進歩してきたか、また将来どのようにして進歩できるかを証明せよ、と迫ったのである。この挑戦を、南アの動物実験反対同盟、SAAAPEAが受けて立ち、回答を送った。しかし、バーナード博士の原稿は検閲しなかった『ケープ・タイムズ』が、回答の方は入念に検閲し、核心となる部分をほとんどカットして骨抜きにしてしまったのである。
ヨーロッパ中の体制派の新聞は、『ケープ・タイムズ』と同様の編集方針をとっている。反対派側が流したいと思う重要な情報は、大抵、検閲の網にひっかかってしまう。
〔フランスの例〕一九七七年七月二十九日、パリの日刊紙『ル・フィガロ』にJ・P・カケラ教授の署名入りで「モルモットか人間か」という記事が載った。これはタイトルを見ただけでもお分かりの通り、嘘情報と決まり文句の羅列に終始した動物実験賛歌であり、現代医学の最大の誤謬が最高の成功のごとくに紹介されている文である。動物実験のお陰で人類が救われたという、いつものあれである。
『ル・フィガロ』には反論の投書が殺到したらしい。しかし紙上に取り上げられたのはそのうちたったの二通、それもズタズタにカットしての採用だった。一通はフランスの動物実験反対同盟の会長からのもの、そしてもう一通は私のものだった。私自身かなり努力して簡潔に書いた文だったにもかかわらず、主要な部分はほとんど削られていた。たとえば、ごく最近フランス語で出版した「動物実験に関するテクニカル・リポート」を希望者に無料で送るという申し出を書き添えておいたのだが、もちろん削除された。このリポートには、他のさまざまな情報とともに、動物実験を科学の失策だとして糾弾した各国の一五〇名に上る医学界権威者の言葉を引用してある。
他の欧米諸国の主要新聞も、これまでのところ、反対運動に対する扱いは、上記二例とほぼ同様だろう。
しかし、何と言っても、政府と化学・医学コンビナートとの馴れ合いがもっとも露骨に出ているのは、フランス、ドイツそれにイタリアだろう。フランスとドイツでは、もっとも有力な宣伝媒体であるテレビが、国家の独占事業であり、イタリアも、テレビ事業に対し、政府が主導権を握っているからである。
これらの国のテレビで放映される討論会まがいの番組で動物実験がテーマになったことがある。編集部によって多少手が加えられたなどという程度のものではない、完全な事実の歪曲になってしまっていた。
一九八一年五月、フランスで大々的な討論番組が放映された。出演者の顔ぶれを見ると、実験支持派にはそうそうたる「科学者」を揃えた。
一方、反対派の方は、「科学者」を向うにまわして堂堂とわたり合える人材が注意深く排除されていた。反対派代表として選ばれたのは、ブリジッド・バルドー、新聞記者、映画製作者、それに、サリドマイド悲劇に関しては何も知らない(さもなくば知りたくない)ため討論会の間中ほとんど無言を通したホメオパシーの医者、といった顔ぶれだった。そこで、動物実験者たちは、思うがままにあらゆるにせ情報を一六〇〇万人の視聴者に伝えることができたという次第である。
↑
PART6 無用の惨劇 へ続く
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー
世の中、有識者とか学者とか言っても、簡単にだまされている・・
まして一般大衆は
スライヴ 医療
スライブ金融










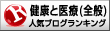



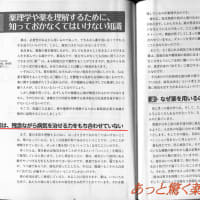

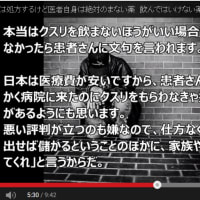


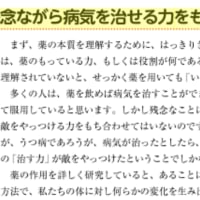







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます