ニーマンフェローが交代で自らを語る、私の履歴書の講演版というべき「サウンディング」。今日は、ニーマン・コミュニティジャーナリズムフェロー(5万部以下の新聞で働くジャーナリスト)Davidが担当。アメリカの新聞は日本とは大きく異なり、全国紙がUSA Today, Wall Street Journalくらいしかなく(New York Timesは広く読まれてはいるが、あくまでもニューヨークの新聞)、新聞と言えば小さいコミュニティを対象としたものがほとんどだ。
彼のトークでは、ワシントンDCでのインターンに始まり、ローカルニュースを点々をし、その後は、マネジメントにも関わるようになり、新聞ビジネスの悪化がコミュニティの弱体に繋がるのではないかと危惧する。ローカル新聞が、どんどん消えて行く米国。自分の町で何が起こっているのかを知ることなしに、コミュニティはどう存続するのか。ジャーナリズムはコミュニティのソーシャルキャピタルを強化する、というのが彼の論点で、わりとオーソドックスな意見だと思う。
このテーマについては、最近全く調査をしていないので、的外れのところも多々あるかもしれないが、以下は、今後、調べてみるための論点と、いうことで、いくつか思いついたことをまとめて見たい。
ージャーナリズム衰退の議論が起こる時には、いつもビジネスモデルが問題にされ、肝心の市民が何故新聞を読まないのか、について多くは語られない。新聞はいい子ちゃんなのに、メディア環境が変わって被害者になってしまったというノリである。
ーインターネットの登場で、他の選択肢が出来てそちらに読者が流れているとすれば、新聞はそもそも他に読むものがなかったから読まれていただけであって、メディア環境が変る中で、読者が本当に必要なものを提供できているのか、ということと、そもそもジャーナリストが考える程の、役割を果たしてきたのか、という、根本的な問いかけが必要だと思う。
ーあるいは、読者が同じ新聞の無料オンライン版に流れているものの、オンラインではなかなか広告収入を得ることができず、特に小さいコミュニティでは、さらに、ビジネスモデルが成り立たないからゆえの衰退なのか。つまり新聞は必要とされてはいるものの、ビジネスモデルが確立していないために、撤退せざるを得ないからなのか。
ーそれ以前に、新聞が語られる際には、新聞なしでは、市議会、消防、警察、学校、教会などで何が起こっていることがわからなくなり、それが、市民の政治社会への関与に影響すると言われる。この辺りは、単に街で起こっていることだけでなく、「腐敗」を暴く米国の新聞らしいことで、ある程度、納得もいくことだ。
ーただ、肝心な点は、そもそも市民が、地域の「政治」にどれくらい関心を持っているのか、そのコミットメントがどれほどのものなのか、ということだと思う。例えば、市民はジャーナリストが思うほど、こうした情報を本当に必要としているのか。ジャーナリストは自分の役割、そして、市民の政治コミットメントを過大評価していないだろうか。本当に、市民が新聞を必要としているのなら、さらに数十セント余計に払っても、存続させるような動きはなかったのか。(まぁ、この点は難しいことではあるけれど)
とまぁ、彼の話しを聞きながら、このようなことがランダムに頭に浮かんだ。
さて、トークの後は、バッフェスタイルのディナーで、フェロー同士が食事とおしゃべりを楽しむ。今日のテーブルの隣は、2年前にピューリッツアーを受賞した調査報道記者Rと、米国が好きになれず、大学卒業後ヨーロッパを転々とし、その後、ロンドンに住み、タイム・ヨーロッパ版編集長をつとめたJで、あれこれ語り合う。
Rによると、彼女の新聞は部数も安定していて、30人の記者のうち何と8人が調査報道記者。コミュニティの政治意識が高く、また、この新聞自体も独自の調査報道で全米でも一目置かれる存在だ。調査報道は資金食いなので減少傾向にあるが、彼女の新聞ではその心配もないとのこと。新聞がコミュニティを強くするのではなく、強いコミュニティに良い新聞が存続するということか。(余談だが、Rは調査報道で数々の賞を受賞している花形記者だが、息子二人との子育の両立のために、週三日出勤のパートタイム記者である)
また、Jには、久しぶりにアメリカに住んでみて、米国の良さ悪さを改めてどう思うのか聞いてみた。
米国の良さは、新しいアイディアを受け入れてもらえるオープンさ。ヨーロッパなら、アイディアよりも、階級、出身大学などが問われ、アイディアそのものを評価してもらることは、難しい。また、イノベーションを推奨するカルチャーは断然アメリカ。また、外国出身者を受け入れる懐の広さ。ヨーロッパの人種問題は根強く、人種差別は深刻であるとのこと。まさに彼が言う点こそが、アメリカが世界の優秀な人材を引きつける理由だろう。(私が住むHarvardとMITを擁するケンブリッジも、まさに、世界の知を受け入れる国際学術都市と言える)
一方、アメリカの課題については、レベルの低いポピュラーカルチャーの蔓延。人々は本当にものを考えなくなっている。メディアもくだらないものが多すぎる。そしてさらに残念なことは、こうしたアメリカンカルチャーが、世界に影響を与えて広がっている。また、ヨーロッパには、一般的なレベルで「インテリ」が多数存在していて、物事を真剣に深く考える知的文化がある。(食べ物へのこだわりや生活を楽しむことも興味深かったが、話しがそれるので泣く泣くカット)
...ということを話しつつ、私は別のことを考えていた。
アメリカは、収入、教育レベル等においても、天国と地獄、世界最強国と発展途上国など両極が同居しているような複雑な国だ。人々の価値観、宗教観も、日本では信じられないようなレンジがある。それに加えて、複雑な人種問題がある。Rがジャーナリズムのカルチャーの違いについて、北部はものを突っこんで報道するが、南部は誰もが知っている不正事件があっても、あえて報道しないような、ぬるいカルチャーがあると言っていたが、中立を謳うジャーナリズムが、どれだけ人々の多様な「本音」を伝えられるのだろうか。それならむしろ、ソーシャルメディアなどで、自分の価値観に近い人同士が繋がって、情報交換するほうが、より魅力的ではないだろうか。
新聞がコミュニティの「政治」のことを伝えて成り立っていたのも、他にローカル情報の選択肢がなく、新聞が描くコミュニテぃというのは、ある意味でお行儀のよい「幻想」だったのではないか。そして「幸い」なことに、それが成り立つ平和な環境が長く続いていたのではないか。
今はよかれあしかれ、様々な情報が入り乱れ、ネットの情報空間もよりリアル社会が反映しているものになっている。そう考えると、実は、多様な価値観を持つ米国で、地域に根ざした新聞が存在していたこと自体が、奇跡にも思えるというのは、言い過ぎだろうか。私の中にもまだ答えはないが、ともかく色々なことを考えさせられた。
そして、日本のことを考えてみると、実は評価しなければ行けない点も多々あることに気がついた。
ー日本は人口あたりにおいて、世界で最も新聞購読数が多い国だ。
ー新聞購読は減少が続いているし、若者の新聞離れも深刻ではるが、それでも多くの人にとって、新聞が生活の一部に溶け込んでいる。それは、社会で起こっていることへの関心の高さとも言える。
ー新聞を読む理由に「職場などで共通の話題を持ちたいから」という答えも、調査などで一定数あるが、多くの人が同じ話題を共有し、それを語り合えうために「準備」をしていることは貴重だと思う。
ー教育も様々な問題を抱えつつ、識字率の高さ(日本では当たり前に感じるが...)、人々の知的なことへの関心への高さも評価出来る。途中から話しに参入してきた、米ジャーナリズムスクール出身で、読売新聞インターン経験もある中国出身フェローも、日本に来て驚いたのは、皆が物を良く知り、社会問題に関心が高いことだと言い、他のフェローも同意(日本に行ったり住んだことがあるフェローは、何と半分近く!)。
また、昨日、たまたまお茶をした米国人雑誌編集長に、私が出版した本について話すと、そんなテーマなら(メディアや図書館)、米国なら大学出版から数千册しか出ないのに、と驚いていた。岩波新書のようなものが成り立つのも、こうした読者層が存在するからだ。(ありがとうございますw)とはいえ、日本でも知的なものへの関心が薄れていると言われているものの、それでもまだ評価できるレベルだと思う。
しかし、それでも課題は多々ある。
ー言うまでもなく、日本の新聞のクオリティ。何よりも「権力」を監視する力。そして、市民が考えるべき問題を噛み砕いて説明する力、時々に可能となる新しいメディアの活用、文章のスタイルなどをみても、この数十年にわたり、劇的な進化は起こっていない。「安泰」なジャーナリズムが逆に進化を阻んでいないだろうか。
ー読者の側も、メディア批判は盛んではあるが、文句はいいつつ、惰性で新聞を購読していないだろうか。
ーそれぞれの記事を単に読んで消化するのではなく、メディアリテラシー的に、深く読み込んでいるだろうか。
記事が書かれた目的、書かれてあることを裏付けする情報源やデータ。どんな立場の人の意見を取り入れていて、それはなぜだろうか。どんな情報が語られていないのか(これは意外と一番大事な点)。様々な角度からチェックしつつ読み込むことは大事だ。
ーそして何より、日本でも人々の価値観は多様化している。これまでのような、巨大発行部数を持つ、単一な価値観を前提とした新聞社のアプローチでは、成り立たなくなるだろう。
ー今後は、オンラインメディアの可能性も含めて、市民のジャーナリズムを、確立していく必要がある。ご興味おありの方は「米国で進むジャーナリズムのイノベーション」をご欄下さい。米国の面白いところは、衰退しているところがあるかと思えば、未来がはっきり見えなくても、意思をもって新しいことに挑戦する人たちも一定数存在することだろう。
というわけで、ジャーナリズムを新聞としていたり、考えも多々まとまりのないブログになってしまいましたが、引続き、カオスながらもジャーナリズムについて、色々と考えて行きたいと思います。
彼のトークでは、ワシントンDCでのインターンに始まり、ローカルニュースを点々をし、その後は、マネジメントにも関わるようになり、新聞ビジネスの悪化がコミュニティの弱体に繋がるのではないかと危惧する。ローカル新聞が、どんどん消えて行く米国。自分の町で何が起こっているのかを知ることなしに、コミュニティはどう存続するのか。ジャーナリズムはコミュニティのソーシャルキャピタルを強化する、というのが彼の論点で、わりとオーソドックスな意見だと思う。
このテーマについては、最近全く調査をしていないので、的外れのところも多々あるかもしれないが、以下は、今後、調べてみるための論点と、いうことで、いくつか思いついたことをまとめて見たい。
ージャーナリズム衰退の議論が起こる時には、いつもビジネスモデルが問題にされ、肝心の市民が何故新聞を読まないのか、について多くは語られない。新聞はいい子ちゃんなのに、メディア環境が変わって被害者になってしまったというノリである。
ーインターネットの登場で、他の選択肢が出来てそちらに読者が流れているとすれば、新聞はそもそも他に読むものがなかったから読まれていただけであって、メディア環境が変る中で、読者が本当に必要なものを提供できているのか、ということと、そもそもジャーナリストが考える程の、役割を果たしてきたのか、という、根本的な問いかけが必要だと思う。
ーあるいは、読者が同じ新聞の無料オンライン版に流れているものの、オンラインではなかなか広告収入を得ることができず、特に小さいコミュニティでは、さらに、ビジネスモデルが成り立たないからゆえの衰退なのか。つまり新聞は必要とされてはいるものの、ビジネスモデルが確立していないために、撤退せざるを得ないからなのか。
ーそれ以前に、新聞が語られる際には、新聞なしでは、市議会、消防、警察、学校、教会などで何が起こっていることがわからなくなり、それが、市民の政治社会への関与に影響すると言われる。この辺りは、単に街で起こっていることだけでなく、「腐敗」を暴く米国の新聞らしいことで、ある程度、納得もいくことだ。
ーただ、肝心な点は、そもそも市民が、地域の「政治」にどれくらい関心を持っているのか、そのコミットメントがどれほどのものなのか、ということだと思う。例えば、市民はジャーナリストが思うほど、こうした情報を本当に必要としているのか。ジャーナリストは自分の役割、そして、市民の政治コミットメントを過大評価していないだろうか。本当に、市民が新聞を必要としているのなら、さらに数十セント余計に払っても、存続させるような動きはなかったのか。(まぁ、この点は難しいことではあるけれど)
とまぁ、彼の話しを聞きながら、このようなことがランダムに頭に浮かんだ。
さて、トークの後は、バッフェスタイルのディナーで、フェロー同士が食事とおしゃべりを楽しむ。今日のテーブルの隣は、2年前にピューリッツアーを受賞した調査報道記者Rと、米国が好きになれず、大学卒業後ヨーロッパを転々とし、その後、ロンドンに住み、タイム・ヨーロッパ版編集長をつとめたJで、あれこれ語り合う。
Rによると、彼女の新聞は部数も安定していて、30人の記者のうち何と8人が調査報道記者。コミュニティの政治意識が高く、また、この新聞自体も独自の調査報道で全米でも一目置かれる存在だ。調査報道は資金食いなので減少傾向にあるが、彼女の新聞ではその心配もないとのこと。新聞がコミュニティを強くするのではなく、強いコミュニティに良い新聞が存続するということか。(余談だが、Rは調査報道で数々の賞を受賞している花形記者だが、息子二人との子育の両立のために、週三日出勤のパートタイム記者である)
また、Jには、久しぶりにアメリカに住んでみて、米国の良さ悪さを改めてどう思うのか聞いてみた。
米国の良さは、新しいアイディアを受け入れてもらえるオープンさ。ヨーロッパなら、アイディアよりも、階級、出身大学などが問われ、アイディアそのものを評価してもらることは、難しい。また、イノベーションを推奨するカルチャーは断然アメリカ。また、外国出身者を受け入れる懐の広さ。ヨーロッパの人種問題は根強く、人種差別は深刻であるとのこと。まさに彼が言う点こそが、アメリカが世界の優秀な人材を引きつける理由だろう。(私が住むHarvardとMITを擁するケンブリッジも、まさに、世界の知を受け入れる国際学術都市と言える)
一方、アメリカの課題については、レベルの低いポピュラーカルチャーの蔓延。人々は本当にものを考えなくなっている。メディアもくだらないものが多すぎる。そしてさらに残念なことは、こうしたアメリカンカルチャーが、世界に影響を与えて広がっている。また、ヨーロッパには、一般的なレベルで「インテリ」が多数存在していて、物事を真剣に深く考える知的文化がある。(食べ物へのこだわりや生活を楽しむことも興味深かったが、話しがそれるので泣く泣くカット)
...ということを話しつつ、私は別のことを考えていた。
アメリカは、収入、教育レベル等においても、天国と地獄、世界最強国と発展途上国など両極が同居しているような複雑な国だ。人々の価値観、宗教観も、日本では信じられないようなレンジがある。それに加えて、複雑な人種問題がある。Rがジャーナリズムのカルチャーの違いについて、北部はものを突っこんで報道するが、南部は誰もが知っている不正事件があっても、あえて報道しないような、ぬるいカルチャーがあると言っていたが、中立を謳うジャーナリズムが、どれだけ人々の多様な「本音」を伝えられるのだろうか。それならむしろ、ソーシャルメディアなどで、自分の価値観に近い人同士が繋がって、情報交換するほうが、より魅力的ではないだろうか。
新聞がコミュニティの「政治」のことを伝えて成り立っていたのも、他にローカル情報の選択肢がなく、新聞が描くコミュニテぃというのは、ある意味でお行儀のよい「幻想」だったのではないか。そして「幸い」なことに、それが成り立つ平和な環境が長く続いていたのではないか。
今はよかれあしかれ、様々な情報が入り乱れ、ネットの情報空間もよりリアル社会が反映しているものになっている。そう考えると、実は、多様な価値観を持つ米国で、地域に根ざした新聞が存在していたこと自体が、奇跡にも思えるというのは、言い過ぎだろうか。私の中にもまだ答えはないが、ともかく色々なことを考えさせられた。
そして、日本のことを考えてみると、実は評価しなければ行けない点も多々あることに気がついた。
ー日本は人口あたりにおいて、世界で最も新聞購読数が多い国だ。
ー新聞購読は減少が続いているし、若者の新聞離れも深刻ではるが、それでも多くの人にとって、新聞が生活の一部に溶け込んでいる。それは、社会で起こっていることへの関心の高さとも言える。
ー新聞を読む理由に「職場などで共通の話題を持ちたいから」という答えも、調査などで一定数あるが、多くの人が同じ話題を共有し、それを語り合えうために「準備」をしていることは貴重だと思う。
ー教育も様々な問題を抱えつつ、識字率の高さ(日本では当たり前に感じるが...)、人々の知的なことへの関心への高さも評価出来る。途中から話しに参入してきた、米ジャーナリズムスクール出身で、読売新聞インターン経験もある中国出身フェローも、日本に来て驚いたのは、皆が物を良く知り、社会問題に関心が高いことだと言い、他のフェローも同意(日本に行ったり住んだことがあるフェローは、何と半分近く!)。
また、昨日、たまたまお茶をした米国人雑誌編集長に、私が出版した本について話すと、そんなテーマなら(メディアや図書館)、米国なら大学出版から数千册しか出ないのに、と驚いていた。岩波新書のようなものが成り立つのも、こうした読者層が存在するからだ。(ありがとうございますw)とはいえ、日本でも知的なものへの関心が薄れていると言われているものの、それでもまだ評価できるレベルだと思う。
しかし、それでも課題は多々ある。
ー言うまでもなく、日本の新聞のクオリティ。何よりも「権力」を監視する力。そして、市民が考えるべき問題を噛み砕いて説明する力、時々に可能となる新しいメディアの活用、文章のスタイルなどをみても、この数十年にわたり、劇的な進化は起こっていない。「安泰」なジャーナリズムが逆に進化を阻んでいないだろうか。
ー読者の側も、メディア批判は盛んではあるが、文句はいいつつ、惰性で新聞を購読していないだろうか。
ーそれぞれの記事を単に読んで消化するのではなく、メディアリテラシー的に、深く読み込んでいるだろうか。
記事が書かれた目的、書かれてあることを裏付けする情報源やデータ。どんな立場の人の意見を取り入れていて、それはなぜだろうか。どんな情報が語られていないのか(これは意外と一番大事な点)。様々な角度からチェックしつつ読み込むことは大事だ。
ーそして何より、日本でも人々の価値観は多様化している。これまでのような、巨大発行部数を持つ、単一な価値観を前提とした新聞社のアプローチでは、成り立たなくなるだろう。
ー今後は、オンラインメディアの可能性も含めて、市民のジャーナリズムを、確立していく必要がある。ご興味おありの方は「米国で進むジャーナリズムのイノベーション」をご欄下さい。米国の面白いところは、衰退しているところがあるかと思えば、未来がはっきり見えなくても、意思をもって新しいことに挑戦する人たちも一定数存在することだろう。
というわけで、ジャーナリズムを新聞としていたり、考えも多々まとまりのないブログになってしまいましたが、引続き、カオスながらもジャーナリズムについて、色々と考えて行きたいと思います。














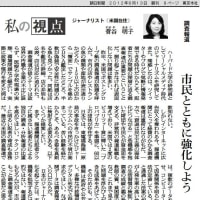
でも、ぜひ、お聞きしたい事があります。
日本のジャーナリズムを考えるときに、記者クラブというものの存在も、かなり大きいと思うのですが、いかがでしょうか?特に311の際の報道で、ジャーナリズムが、本来果たすべき役割を果たせずに、大本営発表を流す、安全デマを流す、ことに終始してしまったのも、記者クラブ制による、弊害ではないかと考えています。指摘されている、権力を監視する力、これはかなり失われていると感じています。
一部、自由報道協会のような団体に所属するフリーの記者さんや、ツイッター、YouTubeなどによる、会見の24時間放映などで、一般の新聞にはのらなかった、質疑応答などの、生の情報にも、一般市民がアクセスできた事は、よい変化だと思います。ただ、その場合、受け手のメヂアリテラシーがさらに重要になってきますね。
日米のジャーナリズムの比較というブログ記事から、ずれてしまいましたが、お時間のある時に、ご意見お聞かせ戴けれると嬉しいです。
http://www.hayashik.iii.u-tokyo.ac.jp/jp_news/jp_events/tsudoi_hyper_local_report/
小さな地域のジャーナリズムも単に衰退してるというのではなく様々に試行錯誤している印象を受けましたがいかがでしょうか??