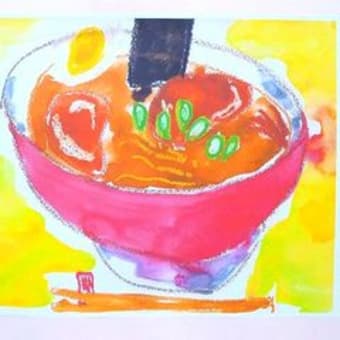73.楽しく宿題!(1)
「知的障害児者、発達障害児者 個性と可能性を伸ばす!」
造形リトミック教育研究所
*楽しいからのパートナー
*新しく知るからのパートナー
*ちょっと簡単からのパートナー
 おはようございます。
おはようございます。宿題を片付けることが、毎日、叱られることの種になっていることがあります。それでは、本末転倒です。宿題が、元凶となってマイナスの循環を生んでしまいます。学習嫌いになってしまいます。
個別に出される宿題でない以上、宿題が実力よりもハードであることは当然あります。それならば、実力に合うようにアレンジして取り組みましょう。宿題には、復習や学習の定着という意味がありますが、それよりも何よりも、アレンジしてでも無理のないように取り組み、「先生との約束をきちんと果たす」という習慣を身につけることを一義としましょう。
1日のスケージュールの中でほぼ決められた時間に宿題を行い、ほぼ決められた時間に翌日の準備をしましょう。自分のやるべきことは「ちゃんとやったよ」という責任感と満足感、「翌日」を楽しみにするという期待感を、宿題を通して大切に育てていきましょう。
では、宿題を楽しくこなすのにはどうしたらよいでしょうか。具体的な課題を想定して、気楽に考えていきましょう。
はじめは、「漢字の学習」
1)漢字の大きさは、お子さんの実力に合っていますか。
指先の巧緻性に合わせて、大きさをアレンジしましょう。
・大きなマスのノートを使用する。
・ワークやプリントに記入する形であれば、別紙に大き目のマスを用意してそこに書き込む。それを、プリントにホチキスでとめて提出する。
・お子さんが別紙では満足しない場合は、別紙に練習させ、プリントには手を添えて書き込む。
2)漢字の量は、お子さんの実力に合っていますか。
・自力で行う量を決めてあげる。「ここまでは、ひとりでがんばろうね」と。
・その他は、手を添えて書き込む。
・宿題を2つに分けて行い、間に5分でも休憩をとる。
3)自力で書くのが難しい場合は、水性ペン(黄色など)で書いてあげ、その上をトレースさせましょう。「それだけで、ずい分楽になりました。これで、いいんですね」と言われたケースもありました。それでいいのです。
4)漢字の構造がわからない場合
・部首の構成がわからない場合は、少なくとも5cm×5cm位の大きさのマスに色分けしながら書くなどの、工夫した学習が必要となります。部首ごとに切って、再構成させるのも効果的です。
・たて、よこ、ななめの方向性がわからない場合は、やはり描画の基礎の学習を充分に行いましょう。少なくとも10cm×10cm位の大きさのマスに、たて、よこ、ななめ、十字形、放射状線を描く練習を行いましょう。教室では、「リズム造形」として基礎機能の習得を行っています。
・しかしこれらは宿題とは別に行うものです。お子さんが良ければ、それを宿題として提出してももちろん構いません。しかし、それでは「ダメ!」というようでしたら、宿題は宿題で、手を添えてさらっと行いましょう。
こんなふうに、宿題はスイスイ、さらっと行いましょう。少し考え、少し努力することを毎日積み重ねていきましょう。楽しく・・・。そうすれば、やがてしっかり考え、じっくり努力することも可能となります
造形リトミック教育研究所
>>ホームページ http://www.zoukei-rythmique.jp/
>>お問い合せメール info@zoukei-rythmique.jp