いま話題の「さおだけ屋はなぜ潰れないのか」という本。タイトルをつけた時点で勝負あった感もあるが、実際よく売れているようだ。誰もが一度は疑問に思うことを題材に会計を優しく学ぶという企画はやはり秀逸だと思う。
本屋で目を通したので、表題に対する答えはある程度知っているけれど、他人の「商売」を邪魔するわけにもいかないので、興味ある方は直接本を手にとってみてください。
(もっとも明確な解答というほどのことは書いてはいないけれど…)
さおだけ屋に限らない話、世の中には「なぜ潰れないのか」と思う商売、店は結構多い気がする。どこの商店街も見回せば、「どうして潰れないのか、見当もつかない」店の一つ二つは必ずあると思うのだ。
自分の家の近く(住宅街)にも、小規模といってもまだ足りない、つつましい商店街があるのだけれど、そこの煎餅屋さんと婦人服店(主に高齢者向け中心)については、これまで一度も客が買い物をしているのを見たことない。以前は夜間と土日しか前を通らなかったせいか、とも思っていたけれど、昼間に前を通っても結果は同じ。どちらも販売商品の単価もそう高くはなく、人ひとりが暮らす程度の金額ですら、売上が立っているとは到底思えないのだが。
常識的な範囲で推測するならば、店での売上はもとより期待していない人の経営、たとえば年金受給者が半分趣味で店を続けている(婦人服の方は高齢の方なのでこれっぽい)とか、家族の誰かが宝くじでひと山当てたとか(可能性は低いが)。なにかしらの「理由」は必ずそこにあるのだろう。
大学生の頃、家庭教師として一年間、小さな呉服屋の息子さんの勉強を見たことがあるのだけれど、ここの店も見事なくらい物が売れている気配というものがなかった。にもかかわらず、家庭教師を雇うだけあり、この家庭は結構裕福であった。常々不思議に思っていたが、さすがに直接は聞けなかったので、ある時懇意の床屋さんにこのことを思い切って質問してみた(だいたい床屋さんというのは町の情報源なのだ)。
床屋さんによれば、自分の住んでいた平塚市は、今でこそ凋落激しいが、戦後の復興期には神奈川県中央部でも有数の商業都市で、県下からの買い物客で大変にぎわっていたという。大手資本チェーンもない時代であったので、個人商店はどこも相当な利益を上げたようだ。その利益で彼らの多くは土地を購入し、アパートや駐車場経営を併せて始めた。どうみても儲からない店が潰れないのは、ほとんどが所有の地所から利益を得ているから、ということらしい。
ちなみに床屋のおじさん情報によれば、この呉服屋の月売上、少ない月は自分のアルバイト代に達しないことすらあったらしい。
まだまだ社会を知らない学生であったけれど、この話には、世の中いろいろな「仕組み」があるのだな、と妙に感心した覚えがある。奇しくもバブル経済はこの直後くらいから台頭し始めるわけだが、その後この呉服屋がどうなったのかはわからない。
さおだけ屋に限らず日常、自分たちの身の回りにも、それぞれにかならず何かしらの理由というものが存在する。そういうことをあれこれ思案めぐらすこと、それはあの時以来、散歩の楽しみのひとつだ。どんなにさえない(失礼!)商店街、そこにも「理由」はかならず存在する。
本屋で目を通したので、表題に対する答えはある程度知っているけれど、他人の「商売」を邪魔するわけにもいかないので、興味ある方は直接本を手にとってみてください。
(もっとも明確な解答というほどのことは書いてはいないけれど…)
さおだけ屋に限らない話、世の中には「なぜ潰れないのか」と思う商売、店は結構多い気がする。どこの商店街も見回せば、「どうして潰れないのか、見当もつかない」店の一つ二つは必ずあると思うのだ。
自分の家の近く(住宅街)にも、小規模といってもまだ足りない、つつましい商店街があるのだけれど、そこの煎餅屋さんと婦人服店(主に高齢者向け中心)については、これまで一度も客が買い物をしているのを見たことない。以前は夜間と土日しか前を通らなかったせいか、とも思っていたけれど、昼間に前を通っても結果は同じ。どちらも販売商品の単価もそう高くはなく、人ひとりが暮らす程度の金額ですら、売上が立っているとは到底思えないのだが。
常識的な範囲で推測するならば、店での売上はもとより期待していない人の経営、たとえば年金受給者が半分趣味で店を続けている(婦人服の方は高齢の方なのでこれっぽい)とか、家族の誰かが宝くじでひと山当てたとか(可能性は低いが)。なにかしらの「理由」は必ずそこにあるのだろう。
大学生の頃、家庭教師として一年間、小さな呉服屋の息子さんの勉強を見たことがあるのだけれど、ここの店も見事なくらい物が売れている気配というものがなかった。にもかかわらず、家庭教師を雇うだけあり、この家庭は結構裕福であった。常々不思議に思っていたが、さすがに直接は聞けなかったので、ある時懇意の床屋さんにこのことを思い切って質問してみた(だいたい床屋さんというのは町の情報源なのだ)。
床屋さんによれば、自分の住んでいた平塚市は、今でこそ凋落激しいが、戦後の復興期には神奈川県中央部でも有数の商業都市で、県下からの買い物客で大変にぎわっていたという。大手資本チェーンもない時代であったので、個人商店はどこも相当な利益を上げたようだ。その利益で彼らの多くは土地を購入し、アパートや駐車場経営を併せて始めた。どうみても儲からない店が潰れないのは、ほとんどが所有の地所から利益を得ているから、ということらしい。
ちなみに床屋のおじさん情報によれば、この呉服屋の月売上、少ない月は自分のアルバイト代に達しないことすらあったらしい。
まだまだ社会を知らない学生であったけれど、この話には、世の中いろいろな「仕組み」があるのだな、と妙に感心した覚えがある。奇しくもバブル経済はこの直後くらいから台頭し始めるわけだが、その後この呉服屋がどうなったのかはわからない。
さおだけ屋に限らず日常、自分たちの身の回りにも、それぞれにかならず何かしらの理由というものが存在する。そういうことをあれこれ思案めぐらすこと、それはあの時以来、散歩の楽しみのひとつだ。どんなにさえない(失礼!)商店街、そこにも「理由」はかならず存在する。













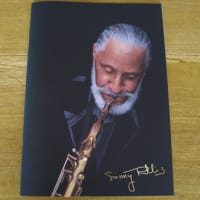






実際、美容院(床屋さん同様)に2ヶ月に1回は情報収集に行く感があります。
自分も立ち読みしちゃえば良かったですw
でもつい気になっちゃう題名に
表意を呈して借りてみます。