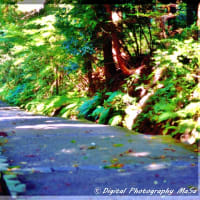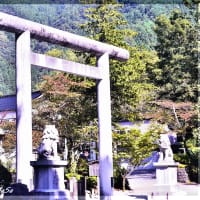イメージカット

※001-東口・夜景

※002-

※003-加賀てまり

※004-再興九谷焼・吉田屋窯

▲⇒概略 【吉田屋窯について!】 吉田屋伝右衛門・よしだや でんえもん
古九谷の制作中止から約100年後、大聖寺の城下町に住む富裕な商人であった彼は、九谷焼、なかでも
青手古九谷の復活を強く願い、1824年に、自らの財産を投じて古九谷の窯の隣に磁器制作のための窯を
築きました。その窯は、彼の屋号 (店の名) にちなんで「吉田屋窯」と呼ばれ、古九谷に迫る芸術性と
品質で、当時の富裕層や知識人から好評を博しました。
しかし、採算を度外視した品質の追及は吉田屋窯の経営を苦しめ、経営建て直しのために交通の便が
良い山代地区に窯を移したものの、7年後の1831年には閉鎖に追い込まれました。
山代の吉田屋窯は閉鎖直後、現場の支配人であった宮本屋宇右衛門みやもとや うえもんへ引き継がれ、
「宮本屋窯」として再開します。
この窯の初代・須田菁華が、陶芸家・美食家で知られる北大路魯山人に対して陶芸を教えたそうで、
お店の入口には魯山人が彫った刻字看板が掲げられています。
※005-大樋焼

▲⇒概略 【大樋焼について!】
金沢の楽焼。江戸時代初期大樋長左衛門の創始にかかる。茶道具を主に作り,赤黄色のいわゆる飴釉が特色。
大樋焼は、ロクロを使わない手びねりとヘラで、ひとつひとつ作られます。保温に富み軽くて暖かみがある
風合いの器は口当たりが柔らかで、お茶に広く利用された事も頷けます。
京都の楽家から、楽焼きの黒や赤を使うことを禁止され、独自に飴釉という釉薬の効果を利用した独特の
発色が特徴で、土作りから本焼きまでの、一貫作業で作られています。
※006-県立・音楽堂から・・・

・
・