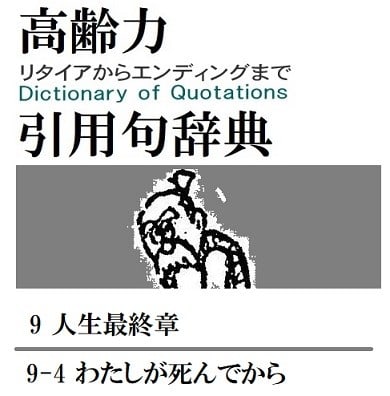
9-4 わたしが死んでから
982 寺山修司の墓
私は肝硬変で死ぬだろう。そのことだけは、はっきりしている。だが、だからと言って墓は建てて欲しくない。
私の墓は、私のことばであれば、充分。
■長尾三郎『虚構地獄 寺山修司』講談社・1997
983 友人の訃報
友人や知人の死に際しても、それほど大きなショックは受けない。「あ、先にむこうへ行ったのか」と、いう感じなのだ。
浄土とか、天国とかいう向こう側が、ひょいと白線をまたげばいけそうな実感があるのである。
■五木寛之『新・風に吹かれて』講談社・2006
984 追悼文
いずれにしても、深い悲しみにひたってばかりいることは許されず、いや応なくそのひとの人生のこし方と、正面切って向きあわないことには追悼文は書けない。
同時にそれはおのれ自身が過ごしてきた道のりに、点検をせまられることでもある。だからだろうか、追悼文を書き終えたとき、きまって言いようのない寂蓼感に襲われる。
■矢野誠一『さようなら――昭和の名人名優たち』日本経済新聞出版社・20130
985 患者の死の語録
個々の患者の死の語録を残すことは、誰からも顧みられることなく、無名のままこの世を去った人々への挽歌として意味があるのではないか。
■小堀鴎一郎『死を生きた人びと――訪問診療医と355人の患者』 みすず書房・2018
986 涙
現実に起こってしまったことはしょうがない、死んだ人は生き返らない。人が涙するのは、そこに後悔があるからだ。受け入れて前向きにあきらめる。自分が終わらせない限り、嫌でも明日がやって来る。
■安藤モモ子『0.5ミリ』幻冬舎・2011
987 あの世へ行きかけている人
ひどく輪郭のくっきりとした幽霊の話なんて、あまり耳にしない。逆に、地下鉄やスーパーの中で、静かに横に立っている人の顔がはっきりしなかったら、それはあの世から来たか、あの世へ行きかけている人なのかもしれない。
■工藤美代子『ノンフィクション作家だってお化けは怖い』KADOKAWA・2015
988 墓
〔プロテスタントのクリスチャンだった父は〕母が亡くなった後、納骨とかにいっさい行かないんです。墓参りもしない。なぜかっていうと、「ママはそんなとこにいない」と言うんです。
それがまあ、自分の死の直前になってから「お母さんとおなじ墓に入れてくれ」と言いだし、さらに「墓参りにも来てくれ」と言いだした。やっぱりそれって、浄土真宗のDNAなんですかね? なんなんだ、あれは(笑)。――上野千鶴子
■山折哲雄・上野千鶴子『おひとりさまvs.ひとりの哲学』朝日新聞出版・2018
989 死の豊穣さ
あまりに当たり前すぎて誰も言及しないのであろう。再構成の中で残された人は耐え、育ち、大きくなり、新しい世界を築いていかざるを得ないのである。〔…〕
誰の死も「新しき世界」をつくり出していくための、豊かな源泉である。死は「喪失」ではなく、個人だけでなく、社会にとって発展のきっかけであり創造なのであると言える。そこに「死の豊穣さ」ともいうべきものがあるのではあるまいか。
■中澤正夫『死のメンタルヘルス――最期に向けての対話』岩波書店・2014
990 その人抜き
誰の死でも、その人の属していた「世界」へいろいろな影響を及ぼし、変化を与える。よい影響か、悪い影響かは問題ではない。「惜しい人を失った」でも「やっと死んでくれてすっきりした」でもいいのである。
「変化が来る、その人抜きの再構成がはじまる」ことが見落とされているのではあるまいか?
■中澤正夫『死のメンタルヘルス――最期に向けての対話』岩波書店・2014
991 魂でもいいから
この世に存在するのはモノだけではない。ある人を慈しめば、慈しむその人の想いも存在するはずだ。この世界を成り立たせているのは、実はモノよりも、慈しみ、悲しみ、愛、情熱、哀れみ、憂い、恐れ、怒りといった目に見えない心の働きかもしれない。
だからこそ人の強い想いが魂となって、あるいは音となって、あるいは光となってこの世にあらわれる――。なんてことを、僕は夢うつつに妄想しながら、被災地で起こった不思議な体験のことを振り返っていた。
■奥野修司『魂でもいいから、そばにいて――3・11後の霊体験を聞く』新潮社・2017
992 別の死を呼ぶ
死は、残された者たちの人生に影をさしこませる。その死の成り立ちようが、痛ましければ痛ましいほど、人々は深く傷つき、自らを責め、生きる意欲を奪われ、その苦しみは、また別の死の呼び水にもなり得る。
■西川美和『永い言い訳』文藝春秋・2015
993 あの人、生きているんだっけ
お葬式に伺ってお別れをしたのに、ふとわからなくなることがあります。あれ? あの人、生きているんだっげ、亡くなったんだっけって思うことが。それでいいんじゃないかなあ。
曖昧なままのほうが、いつでもまた、会えるような気がするじゃない。
■吉田日出子『私の記憶が消えないうちに――デコ 最後の上海バンスキング』講談社 ・2014
994 原節子という伝説
平成27年9月5日、原節子という伝説を生き切った会田昌江は、95歳でその生涯に幕を下ろした。半世紀にも及んだ隠棲の末に。
その死は故人の固い遺志によって、およそ3カ月のあいだ、世に知られることはなかった。
■石井妙子『原節子の真実』新潮社・2016
995 夕鶴となりて
〔姉の〕辺見じゅんの死を報されてより、気仙沼市、南三陸市を経て仙台に入るまでの問、辺見じゅんの死を悼む挽歌があふれるように生まれてくる。辺見じゅんのイメージは、彼女が中学時代に演じた木下順二の「夕鶴」である。
夕鶴となりて旅立つ野分かな
汝がゆく花野の涯に父が待つ
天の水飲みて夕鶴躯(み)を反らす
もともとは歌とは、神と人に「訴える」ことに由来する。私が辺見じゅんにできる鎮魂のありかたとしては、彼女に対する挽歌を詠むことだけであろう。
■角川春樹『夕鶴忌――一行詩集』文学の森・2013
996 人生の記録
たとえ、思い出がつまっている写真や記録などを捨てたとしでも、自分のなかの記憶としての過去は残っていますものを捨てただけのことで、過去を捨てたなどという大袈裟なことではないと思うのです。
もし忘れてしまうような思い出なら、自分にとって忘れていい、必要ないものでしょう。必要な人生の記憶は自然に残っています。
人生の記録なんて後から捏造していくものだと思っています。
■中崎タツヤ『もたない男』飛鳥新社・2010
997 償いの方法
憎むべき犯人が、死刑になって処刑されることで癒される遺族も確かにいるだろう。他方、悲しみの分母の大きさに比べるとほんの僅かかもしれないが、犯人の真の更生が、遺族の慰藉に繋がる面もあることは否定できないのではないだろうか。
「犯人に償ってもらいたい」という言葉。その償いの方法は、「死」であるべきなのか、「更生」であるべきなのか──。深く、重い問いかけである。
■堀川惠子『死刑の基準──「永山裁判」が遺したもの』日本評論社・2009
998 悼むということ
たぶん、悼むというのは「欠落」を意識することである。あの人を失ってしまった!と痛切な思いで意識すること、それが悼むということなのだ。
だが、人はやがて忘れていく。なぜなら、忘れることなしに前に進むことはできないからだ。
■沢木耕太郎『ポーカー・フェース』新潮社・2011
999 二度目の死
人の死による「欠落」は永遠に埋めることはできないが、やがてその「欠落」を意識する人が誰もいなくなるときがやって来る。
必ず、いつか。そのとき、死者は二度目に、そして本当に死ぬことになる。
■沢木耕太郎『ポーカー・フェース・新潮社・2011
1000 再び歩き出す
親しい人を失った時、もう歩き出せないはどの悲哀の中にいても、人はいつか再び歩き出すのである。
歩き出した時に、目に見えない力が備わっているのが人間の生というものだ
■伊集院静『別れる力――大人の流儀3』講談社・2012
1001 死後を信じない
死後を信じない人に無理して死後を信じさせようとするほど無駄なことはない(笑) ――山折哲雄
■山折哲雄・上野千鶴子『おひとりさまvs.ひとりの哲学』朝日新聞出版・2018
1002 死後の世界
ちなみに、ぼくはけっこう死後の世界を信じている。〔…〕死ぬことは全然怖くない。
逆にパスポートをもらって新しい世界に行けるわけだからちょっと楽しみかな。向こうの世界はどれくらい発展しているんだろう。きっと元の世界にその様子を知らせたいと思うでしょうね。
■椎名誠『ぼくがいま、死について思うこと 』新潮社・2013
1003 待っているのは「無」
問題は死んだあとだ。どうなるのか、何かが待っているのか、それともいないのか。ほんとに光のトンネルを抜けると花畑があって、死んだ自分の血族がおれを待っているのか。臨死体験者は皆同じことを言うが、おれは信じてない。断末魔の一瞬の幻覚だ。〔…〕
痛くて無惨な思いのまま死なないように、脳が最後の大サービスで幻覚を見せてくれるシステムがDNAに組み込まれてるんや。実際に待っているのは「無」。おれは、そう思っているのだが、
■中島らも『異人伝――中島らものやり口』講談社・2007
1004 一方で別な考えも
一方で別な考えも持っている。〔…〕
「地球生命体の総合意識」みたいなものがあって、成層圏内から地下何十キロくらいまでの分厚さで地球全体を包んでいる。個体生命は死ねば肉体から放たれて、その集合意識に帰っていく。「個」から解放される。新しい生命はその集合体から個体に移る。
■中島らも『異人伝――中島らものやり口』講談社・2007
1005 土に還る時
「やがて土に還ろう。そう思った時、人は孤独ではなくなります。そういうものです。いずれ、宋江殿にもわかる時が来る」
「そうでしょうか?」
「土とは、不思議なものです。懐かしくなってくる。癒すのです、なにかを。いや、多分、孤独を」
「穆紹殿は、孤独ではありますまい?」
「老いとは、孤独なものなのですよ、宋江殿。出来のいい息子がいようが、やさしい娘がいようが、同じことです。ひとりで土に還る時を、待つ日々なのですから。その時、癒してくれるものを持つのは、その人の人生が豊かということにならないでしょうか」
■北方謙三『水滸伝04道蛇の章』集英社・2007
1006 自然に還る
自然に還るということは、いったんは白骨になるんだけれども、それがやがて粉末になり分解されて土に還る。土のなかで新しい生命、つまり植物、樹木、草、花、そういうものになっていく。変化して。その栄養分になって、新しい生命のもとになっていく。
そういう意味での輪廻、転生。そういうところにふっと気がついて、〔…〕。それで気持ちが非常に落ち着いたんです。――山折哲雄
■山折哲雄・上野千鶴子『おひとりさまvs.ひとりの哲学』朝日新聞出版・2018
1007 会えてよかった
いつの間にか時が過ぎ、亡くなった人もあります。
わたしはあの世を信じてはいませんが、やがてさきに逝った人のいるところでもし会えたら、そのとき、あなたに会えてよかった、と言おうとおもっています。
■安野光雅『会えてよかった』朝日新聞出版・2013
1008 死ぬとは
死ぬとは、先に亡くなった一番大切な人にまた会えること。
大事なのは、その時まで生き切ること。久しぶりに会うのだから、いろんな話をしてあげないといけない。暗い話はだめ。喜ばれない。
素敵なみやげ話をたくさん持っていくために、その時まで精一杯生き切るのだ。
■西山厚『仏教発見!』講談社・2004
(了)









