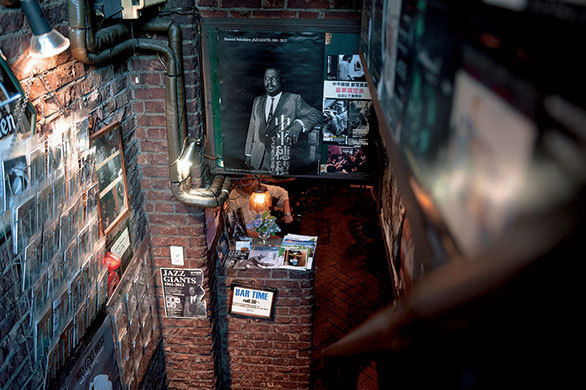
Robert Johnson- Crossroad
CREAM Crossroads 1968
CROSSROAD
十字路へ行ってひざまずいた
十字路へ行ってひざまずいた
天の神様、どうかこの可哀想なボブをお助けください
ああ、十字路に立って車を止めようと手を振った
十字路に立って車を止めようと手を振った
誰も俺に気がつかず、みな通り過ぎてゆく
ああ、日が沈み、闇が俺を取り囲む
ああ、闇が俺を取り囲む
俺を愛してなぐさめてくれる女は、ここじゃ一人も見つからなかった
走れ、走れ、それで友達のウィリー・ブラウンに言ってやるんだ
走れ、走れ、それで友達のウィリー・ブラウンに言ってやるんだ
神様、十字路に立ち尽くす俺はこのまま沈んでいってしまいます
親父の会社で働いて居た頃。前のblog記事でも書いたが、バンドをやっている、 女の子がパートのアルバイトとして会社に来て居た。その子は変わった子で、「プエルトルコの子とヴェトナムの子とシンガポールの子とで昨日、働いたのよ。」とか、「昨日さあ、ライヴの打ち上げでライブハウスの楽屋の通路に居たら、『レイジーキル』のベーシストがさあ、私のベースを蹴って行ったんだ。考えられる?頭来ちゃうわよ。」「アパートの隣の部屋の白人がさあ〜〜ジャズだと言ってピアノ弾くんだけどさあ、無茶苦茶なのよ。」働きに来ているのか、音楽の話をしに来ているのか解らない。
終いには、「〇〇君は私のバンド聴きに来てくれたけど、〇〇さんは来てくれないじゃない!!」と私に言う。段々と図に乗ってくる。私もバンドでブルースとかジャズを演奏していたが、私のバンドのメンバーは、ボーカルの〇〇が、仕事場に来たといって、怒って居たぐらいだ。もっとも、私がブルースハープで、本来は歌も歌うのがいいのだけど、当時は自信がなくて、中央大学出身の21歳の男をボーカルとして居た。芸大を出たベースとドラムは可成り上手くて、まさにプロだった。私が19歳の時に2人共30歳だった。丁度ベーシストの奥さんが、私と同じ拓殖大学出身で、話が盛り上がった。何時もスタジオでの練習の帰りに居酒屋の「村さ来」でビールとツマミのおかずを注文して、皆んなで音楽談議に花を咲かせていた。そのベーシストの奥さんはライブハウスで演奏するときにも、何時も見に来ていて、私は「自分もこんな奥さんを持ちたいなぁ」と思って居たぐらいだ。中央大学出身の男は、「自分は大学に入ってから音楽を聴いたんだ。皆んなみたいに、勉強をしなくて音楽を聴いていたのとは訳が違う」と言っていて、ベースとドラムは鼻で笑っていた、「あいつ、あんなこと言っているけど、英語の歌詞分かって歌っているのかねぇ...」練習中にボーカルが歌っていると。「おい、お前さあ、チャパティーって言ってるけど、なんだそれ〜〜」「そう聞こえるよ」「へ〜〜、そう」「一度レコードの歌詞良く読んでみな!」
しかし不思議と私には皆んな何も言わなかった。多分歳が若い事で多目に見られていたのだろう。ハープの腕前もまだまだだったのにだ。此の間、探したらその当時の練習中のオーディオ・テープが出て来た。今、改めて聴いてみるとボーカルの歌と私のブルースハープが下手だ。。。ギタリストは同志社出身だった。暫くは京都と大阪で活動していたと言っていた。ブルースとジャズに精通して居て、テクニックは可成りあった。歳は矢張り私より上の27歳だった。ベースとドラムはプロとして活動もしていて、楽器屋でも働いていた。ギターは小さな喫茶店の経営者だった。漫画喫茶で中古レコードなども売って居た。夏になると良くアメリカにレコードを買いに行って居たので、私はアメリカ盤のブルースのレコードをよく彼を通じて買って居たものだ。ロッド・ピアッツアとかウイリアム・クラークなどアメリカ西海岸のブルース・ハーピストをそれで知った。このバンドはライブハウスで8回目の演奏をした後に、私は病気になり脱退した。その後はロックバンドに成って行ったらしい。私はあえてメンバーと連絡は取って居ない。皆んなは私が辞めると知ったら、慌てて何回も電話をくれたが、皆んな母が断ってしまった。当初私は、何で自分に電話を渡さなかったのかと怒って母に文句を言ったが。。。。今はそれで良かったと思って居る。これが1970年代後半から1980年代の半ばに掛けてです。丁度この当時、ヘビメタのバンドでリードギターを弾いていた高校時代の友人が行方不明になったと電話が掛かってきたが....その後彼がどうなったかは知らない。ところでメンバーを集めるには、音楽雑誌や、ライブハウス、果ては電柱にまでメンバー募集のチラシを張った。
当時、アンダー・グラウンドで、今で言う、インディーズ・シーンだけども、よくバンドのメンバー同士を引き合わせる人間が居た。電話で問い合わせると、すぐに各楽器をやっている人たちを紹介してくれたが、電話で話してみると、みんなロックバンドを組みたくて、ブルースは一緒にはやれないと言った話だった。1980年代になるとパンク・ロックやらテクノ・ロックが出て来て、日本でもブルースは余り良く聴かれて居なかった。まあ、私は、丁度、親父が自分の会社なら、お前も余り体のことは心配せずに働けるだろうと私を会社に入れた。処が此れが裏目に出た。先に会社に入って居た。親父の兄貴の従兄弟二人が、よく思わなかった。特にゆきかずは私に「会社は俺が次期社長になるんだ!お前はなぜ入って来た!!」私が黙って居たら。「体が悪いなら、働くな!!お前は俺の座を狙っているのだろう!!」と言うのだ。「そんな事はないよ。」と言っても、「嘘だ!これからお前をいびり切ってやるからな!!」と言う。そしてそれを実行した。初めの内は社員旅行やら忘年会やら出て居たが、私はそのうち出なく成って行った。ある忘年会の座敷で、カラオケが置いてあり、皆んなは歌を歌って喜んでいたが、私は「横浜ホンキートンク・ブルース」しか毎回歌わないので、なんだと思われていた。だから何時もベルトにフォルスターを付けてオールド・スタンバイを持歩いて居るので、まあ、仕方が無いので、アドリブで即興演奏をしてみた、カラオケのマイクを使ってカラオケに繋げて吹いたのだけども、そうしたら皆んな、呆気に取られて、「今の何だ、バッハか?」「いやぁ、ジャズだろ?」親父が「こいつが、今吹いたのはブルースですよ。」と言ったら丁度、食料品メーカーの人も来て居て、驚かれた事があった。従兄弟のゆきかずは、ハーモニカを見せろと言い、「穴が10個しか無いのに、よくあんな音が・・・」と、皆んな当時はブルースハープなんて聴いた事が無かったらしい。私ぐらい吹ける人は山程居る。当時は知っている人でも、単に小さなハーモニカで、良くフォーク・ミュージシャンがピーピー吹いているのを知って居るぐらいだったらしい。従兄弟が「なんて曲だ」と聞くので「アドリブだよ」と言ったら「アドリブってなんだ?」と言うので「即興演奏」と言ったら「けっ!!」と言っていた。
実はバンドを辞めた後、一度、京王線の明大前にあったライブ・カフェでセッション的なことは2、3度やった事がある。会社で外回りから帰って来て、在庫を片付けて居たら。誰かがチャイムを鳴らす。出てみたら、ギターを抱えた人で、「君、 〇〇さんでしょ。」と訊く。「そうだけど、何の用、此処は職場なんだから、困るよ。」と言うと「一度一緒にやらない?」と言うので、私は「俺は・・・」と言い掛けたら「じゃあ、仕事が終わるの何時?」と訊いてくるので「5時半だけども」と言うと「いつも会社に居るの?」と聞くので、「今日はたまたま、居たけど、いつもは外回りだから居ないよ。」と言ったら「喫茶店で終わるまで待って居る」と言うので。「それじゃあ、明大前のジャズ喫茶「マイルス」で待っていて、仕事が終わったら行くから」と言って置いて、仕事が終わってから言ってみるとその人は店に居て、手を振った。「何?どう言うことなの?」と訊いたら。彼はライブ・ハウスで二人のディオでブルースを演奏していて、メンバーを探していると言うので、「俺のことをどうして知ったの」と訊いたら「渋谷のライブハウスで前にあんたのメンバー募集の張り紙を見て知っていたから」と言う。話は、ジャズ喫茶だからご法度だったのだけどもマスターに許しを貰って、ウイスキーの水割りを頼み、ソニー・ステットのLP「ディープ・ルーツ」をリクエストして話をして見たら「一週間後にちょうど明大前のライブ・カフェでライブがあるんだけど、ハープ探していてさぁ、」と言う。「俺は下手だよ。話聞いているんでしょう?」と言っても「だってライブハウスで吹いていたんだから」と押し切られて、1回切りならと言って、セッションという形で吹いた。始めギター二人で弾いていて、途中から3曲ばかり吹くと言った具合だ。店に行って見ると、結構大掛かりなPAシステムがあって、ミキサーがやって来て。「ぶっつけで行くからな」と言う。後で知ったのだがこの二人組みはフライング・レコードからレコードを出して居たそうだ。
二人が演奏して居る間に客から「ハーモニカ見せて」と言われた。なぜか年配の人が多かった。女の人が手に取って、「随分と小さいのね。」と言っていた。自分の出番になると、まあ、アンプはPAシステムなので、ダイナミック・マイクロフォンを渡されて、これで吹けと言われた。一応、自分のグリーンバネットを持って行ったのだが、それは使うな、此れを使えと言う。仕方が無いのでそれで吹いた。全てアドリブだったのでうまく吹けたか如何かは自分では解らないが、年配の客は喜んでいたので「まあ良いかな・・・」と思った。その後、この二人から連絡があったが、私は電話に出なかった。母が居ないと言ったらしい。話を戻す。寒いのでトレンチコートを着て会社に行って、ロッカーの中のハンガーに掛けていると。パートの女の子が黙ってジッと見て居て、「何時も同じ格好しかしないのかと思ったら、コート着て来たのか。」と言う。何時もの様にピッキングをして。時間が来たので帰り。翌日になったら。その子がダボダボの白いコートを着て入って来て、ロッカーのハンガーに掛けて居た。慌てて古着屋で買ったらしい。「なんだかなぁ...」と思った。まあ、今回の話はこの位にして置きます。此処まで読んでくれてありがとう。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ー 原田芳雄さんの思い出。ー
下北沢に原田芳雄さんは住んでいた。毎年12月の終わり頃に原田邸で餅つきをやっていた。いろんな人が来て居た。芸能人は勿論の事。近所の人たちも来ていた。一度だけ餅つきに参加した事がある。餅つきには、大人餅と子供餅があったと思う。私は芳雄さんを兄貴と慕って居た。勿論本人に言った事は無かったけど。
はじめ私は松田優作を好きになった。そして優作が芳雄さんを尊敬していると知ってから、彼の映画「反逆のメロディー」「やさぐれ刑事」「君よ憤怒の河を渡れ」などをミニシアターで見て、ファンに成って行った。1980年代はライブハウスで彼のブルースを聴いた。歌が上手い。ライブに行くと会場にはいつも原田芳雄の格好をして居る、そっくりさんが結構いたものだ。私も芳雄さんが来て居るアメカジやらを真似て着て居た。1990年代に成ると芳雄さんの映画が立て続けに公開された。聞く処に寄ると、1980年代は映画から遠ざかって居たそうだ。

Yokohama Honky Tonk Blues
原田芳雄 ブルースで死にな
原田芳雄さんの「無宿人御子神の丈吉シリーズ」のPAL盤DVD。



1990年代は「われに撃つ用意あり」「シンガポール・スリング」「浪人街」「寝取られ宗介」2000年代に「ざわざわ下北沢」「鬼火」それから変わった処では「パーティ7」などの映画に出演している。どれも滅法面白い。私は特に若松孝二監督と組んだ「われに撃つ用意あり」「シンガポール・スリング」「寝取られ宗介」「キスより簡単」が好きな映画だ。若松監督との思い出もある。丁度、2011年公開の「11・25、自決の日!三島由紀夫と若者たち」を見に行った時だ。若松孝二の名は昔から知っていた。『ピンク映画の黒澤明』と言われていた。ピンク映画はセックスシーンがある。要するにお色気映画だ。しかし若松孝二の作品は単なるポルノではない。制約としてのセックスシーンはあるがそれで見せる映画ではない。どれも低予算映画なれども若松孝二の反骨精神、いや反逆精神か、それが漲って居る。でも私は実はピンク映画時代の若松監督の映画のDVDは「胎児が密漁する時」「腹貸し女」「新宿ジャック」ぐらいしか持っては居ない。どれも強烈な作品ですが。。。
「11・26、自決の日。三島由紀夫と若者たち」のトーク・ショーにて撮影。


若松孝二は震災後に何を撮ったのか?
でも。私は若松監督が、一般映画を撮るようになった頃からの作品をよく観て居る。交通事故で死ぬまでに撮った映画だ。「飽食」「17歳の風景・少年は何を見たのか」「実録・連合赤軍浅間山荘への道程」「キャタピラー」「11・26、自決の日 三島由紀夫と若者たち」「海燕ホテル・ブルー」そして遺作と成った「千年の愉楽」などです。「11・25、自決の日・三島由紀夫と若者たち」を当時既に認知症だった母を連れて見に行ったのだが、トーク・ショーが上映後にあって、主演の井浦新さんやらと若松監督のトークが聞けたのだけれども。私は拍手をしていたら、監督が気付いて、時間も押しているからと行って次回作の「千年の愉楽」の予告編を掛けたのだけども、映画館の暗闇の中で予告編が掛かる前に、ふと人の気配がして横を向いたら、監督が温和な笑顔で立って居た事があった。その時に私は立ち上がり握手をして。サインをパンフレットにして貰った。監督はその時、「東電を叩く映画を作るよ。」と言って居たが、新宿の道を横断中に左からきたタクシーに跳ねられて亡く成ってしまった。芳雄さんはその前に映画「大鹿村騒動記」の舞台挨拶に車椅子で現れてから、間も無く亡くなって居る。二人は今は天国で映画を撮って居る事だろう。
ピンク映画時代の逸話を映画にした映画「止められるか、俺たちを」は4月にDVD発売されます。詳しくはこの記事の前の私のBlogで詳細を乗っけています。
~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『火の魚』
さて、原田芳雄さんの晩年のTVドラマです。あまりの評判の為、1時間余りながら劇場公開もされました。DVDはAmazonで購入出来ます。名作ドラマです。海外の賞も受賞しました。下の映像はダイジェストです。この映像だけで判断するのではなく、レンタルで良いので見て下さいね。
Image of 火の魚
瀬戸内・大崎下島を舞台に、世間から取り残された孤独な老人と、
時を慈しむように生きる若い女性が、心を通わせていく「命」の物語。
【ストーリー】
広島の小さな島から届けられる物語。テーマは「命の輝き」。島に住む老作家・村田省三(原田芳雄)のもとに、原稿を受け取るため東京の出版社から女性編集者・折見とち子(尾野真千子)が通ってくる。小説家と編集者は、年は違うがプロ同士。たがいに一歩も譲らず、丁々発止のバトルが繰り広げられる。あるとき小説の想定を、燃えるような金魚の「魚拓」にしたいと思いついた村田は、折見に魚拓を作ることを命じる。魚拓を取るには、金魚を殺さなければならない。小さな命をめぐって、二人の間にさざ波が立つ。
やがて村田は、折見の“秘密”を知ることになる…。
【キャスト】
原田芳雄、尾野真千子、高田聖子、岩松了 ほか
【スタッフ】
原作:室生犀星
脚本:渡辺あや
音楽:和田貴史
監督:黒崎博
<受賞歴>
★平成21年度(第64回)文化庁芸術祭大賞
★第36回放送文化基金賞優秀賞、演技賞(尾野真千子)、脚本賞(渡辺あや)、演出賞(黒崎博)
★平成21年度芸術選奨文部科学大臣新人賞(演出:黒崎博)
★ヒューゴ・テレビ賞奨励賞
★第50回モンテカルロ・テレビ祭・ゴールドニンフ賞(テレビ映画部門)
★第62回イタリア賞・単発ドラマ部門・最優秀賞(イタリア賞)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
「ケロベロス・地獄の番犬」
同じ押井守の作品である『紅い眼鏡』の続編。物語は前作の続きではなく、冒頭部の都々目の国外脱出から、帰国するまでの中間に当たる。
低予算であった前作から大幅にスケールアップしており、前作では3体しか製作されなかったプロテクトギアは、本作では2000万円の予算をかけてケルベロスの頭部の数にちなみ50体が造られた。香港や台湾での長期ロケも敢行され、香港では銃器メーカー寶力道具有限公司の協力により日本では不可能な実銃による撮影が行われた。
「ストーリー」
荒廃と腐敗にまみれた近未来都市・東京。従来の自治体警察の治安力をはるかに越えた組織的な犯罪がはびこる中で、「首都警」こと首都圏治安警察機構が生まれた。首都警は次第に強力な権力を発揮するようになり、外部からの批判も高まるが、核部隊ケルベロスの批判は激しかった。そしての50名の特機隊からなるケルベロスが解体の危機に瀕する中で何人かが反乱を起こした。乾もその一人だったが、彼らの力も治安部の膨大な力の前では無力に過ぎず、ただ一人国外逃亡を果たした都々目を除いて、全員鎮圧されてしまう。三年後、出所した乾は、都々目の居所に関する情報を得て出国する。乾にとって都々目は兄と慕うほどの存在だった。謎めいた白服の男の手引きで、乾は都々目のアジトを訪ねたが、そこには都々目の姿はなく、彼の愛人だという少女・タンミーがいた。都々目の行方を追い、旅に出る二人と、その後を密かに追う白服の男。やがて思いがけない場所で都々目と再会した乾は、しばらくそこで幻想的な日々を送るが、次第に都々目の裏切りという真実か明らかになる。それを知って激しいショックを受ける乾。そんな時、白服の男によって、彼らに攻撃を仕掛けてくる特殊公安部を相手に、乾はプロテクト・ギアを身につけ、ただ一人破滅に向かっていく。そして、そんな乾の最後を見届けた都々目は東京へと舞い戻るのだった。
Stray Dog (映画本編です)
主を失った犬の放浪。女に拾われた犬の放浪。犬が最期に選んだ主とは一体なんだったのか。ケルベロスサーガ全般に、言える事ですけど、彼らは前提からして敗者と言うか、「もう必要がない。」と言う烙印を押されてしまって居る訳ですが。そんな彼らがそれでも何か行動を起こそうとする。それで別に何かが変わる訳でも無いのだけど……とにかく、客観的に観てお薦めって映画では全く無いんです、でも。しみじみ「いいなぁ」と思えますね。押井さんは、とにかく広角レンズをローアングルで撮る撮影が楽しくて仕方なかったとの事。押井監督に言わせると、野良犬の目線で撮った映画だそうだ。「紅い眼鏡」の方は哲学的と言うか、この「ケロベロス・地獄の番犬」は一遍の「詩」見たいな映画。「紅い眼鏡」の前日談だけども、この映画だけ観ても解ります。
ILC Supportersスペシャルトークショー「押井監督×山下教授」篇
押井守 ✕ 神山健治 対談 (2009年)
「押井守の論考」
さて、われわれはまず押井守の世界をどこから、どのように読み始めるべきなのだろうか? 正直なところ、領域をいちはやく特定することは大変困難である。押井守の作品世界に内在するテーマは、ひどく広範囲にわたり、また尚且つその深さにおいても非常にさまざまな水準に及んでいる。たとえばある者は『ビューティフル・ドリーマー』に古代中国思想の問題意識を見いだしたろう。またある者は『天使のたまご』の中に、フロイトやメルロ=ポンティのいわゆる“肉の存在論”のほのかな香りを嗅ぎ取ったかも知れない。『紅い眼鏡』にファウス卜的逃走や60年代イデオロギー闘争の世代の思想的背景を感じた者、『御先祖様方々歳!』の背後にレヴィ=ストロースの親族構造論の片鱗を見た者、パトレイバー『劇場版』に象徴言語の隠喩によってなる超越諭的な言語ゲームを垣間見た者、『迷宮物件/FILE-538』にホフスタッターの不思議な論理の存在を感じた者……いったいわれわれはどの先達に教えを請えばよいのだろうか。
押井守が現在の形で注目を集め始めたのは、TVシリーズ「うる星やつら」におけるオリジナルのエピソード『みじめ!? 愛とさすらいの母!』から、というのが現在もっとも支配的な説である。この作品において押井氏はずいぶんと苦言を受けられたそうだが、マニアックなものの見方をするファンの間ではその評価は可成り上がったらしい。たしかに、その内容は、すくなくともゴールデンタイムに放映されたTVシリーズアニメとしては、大変ハードな問題を扱っている。現実と夢の不可分性を論じたこの作品は、それ以降の押井守作品の作品性を方向づける原基的なものであった。じっさい、それ以降の押井守作品の評論を読むと、その殆ど全てがこの作品の固有の問題地平を、それ以降の作品のものと無差別に近い扱いで論じている。
だが実際のところ、この段階の議論には限界がある。現代に生さているわれわれは、整備されたマニュアルがないと新しい行動を起こすことをためらいがちだが、この傾向は残念なことに“思考”の面に最も顕著にその例を見ることができる。考えなくてもよい場合、われわれは思考を休む。どう考えてよいかわからない時はなおさらである。大抵の人は押井作品の中に、何か漠然と「高度な思考」を嗅ぎとるが、数の観念の未熟な未開人が両手指の数以上をすべて「タクサン」として総括してしまうように、多くの観賞者はそれを「むずかしいテーマ」として総括する。彼はそれ以上考えることをしない。そしてそんなとき彼の自我を守るのは、「作品は“感性”で観るものさ」という常套旬である。
シュペングラーの詩的な記述で有名な、崖から落ちる瞬間の人間の脳裏を横切る瞬時の回想は、実は蓄積されたあらゆる記録から打開策を検索しようとする脳の最後の情報処理機能だという説がある。新しい方法がない、あるいは必要ないとき、われわれはいままでの経験の範疇と方法とで考えようとする。だがこのとき、われわれが超個人的な技術的思考に到達する確率は、がっかりするほど低い。
押井守の作品と対決するためには、あなた個人の限られた思索の歴史を超えた“方法”が不可欠である。そのマニュアルはあるにはあるが、図書館へ行く労力と、はげしい退屈に対する覚悟が必要である。そこで此処ではまず、ひとつの技術的思考方法と、“知”のフィールドがそこに至った軌跡をおおざっぱに記すことにする。大学等で専門的な研究をされた諸氏には退屈な記述となるだろう。その場合は読みとばしていただいて結構である。
〜存在と意識〜
われわれは一般に、周囲をとりまく日常的な《世界》を、客観的・公開的な環境世界として無条件に信じ、疑わない。こういった素朴な認識態度は“自然的態度”や“素朴実在論”などとよばれる。
しかし一方、一見自明とも思えるこうした客観的世界を無条件に信じず、主観的認識を中心に素朴な実在論に疑問を唱える立場がある。世界の成立根拠を客観的な実在に置かず、あくまで意識と意識に映ずる表象に求めるという思想群である。こうした立場は内省論、懐疑論、観念論等とよばれ、時代・地域に関係なく常に人類の思想史上に現れる傾向にある。なかでも近代以降に限定すれば、特にヨーロッパにこの思想的傾向が強い。
そもそも近代人のこうした思考習癖は、デカルトのコギト以降“意識”に対する興味が特別な重要性を帯びてきたことに大きく由来するだろう。意識自身にとって“意識”は比較的透明性をもっているのに対し、意識の“外”の世界は常に不透明性を帯びている。バークリーやフィヒテのように主体の意識の内部に認識の王国を築く没世界的な内省論にしろ、デカルト自身やデイヴィッド・ヒュームのように主体の認識の不完全性からただ眼前に広がる世界の実在を信じ得ず、意識それ自体の内部と外部とにそれぞれの世界を創造し、その双方の間に絶望的な断絶を設けてしまった二元論的な懐疑主義にしろ、その深層構造を同じくする知の場からきわめて自然に産み出される思考と言うことができよう。またこういった視点から考えた限り、空間の認識にとどまらず時間の認識にも同様の知的態度を見ることができる。すなわち、客観的な時間の存在を完全に、あるいは条件つきに否定し、時間の成立根拠をそれを認識する主体に由来するとする思想である。西洋哲学において、アウレリウス・アウグスティヌスに一つの源流をもとめられるこの思想もやはり近代思想史にその姿を現し続けている。カントールによる時空間の実在性の証明もこれらの思想群を沈黙させるには至ってはいない。
こうした知的態度の対立の根底には、存在と意識の対立の思考習慣がある。
伝統的な哲学では、意識や精神は神からの付与をその由来とし、広く“存在”の中に含まれるものであった。この“存在”は総括的に第一哲学としての形而上学において語られ、精神と存在とは対立するものとしては捉えられてはいなかった。はるかな時間を経、中世から近代に移ろうとする時代、デカルトの「懐疑」という方法において初めて《意識》は《存在》の従属物以上の地位を与えられることとなる。のちに実存哲学の先駆と称された“我”の発見は、人類の思想史中最もドラマティックな瞬間であった。だがそれは同時に、人間がまさに死にゆく神の呪いを受けた瞬間でもあった。オリュンピカに記された悪夢において雷鳴とともにデカルトを襲ったのは、“悪意の霊”に象徴される涜神の意識と、自身の所業に対する激しい不安と怖れであったという。そしてその時より始まった、存在と意識のトートロギーに満ちた関係を明らかにしようとする近代西洋哲学の必死の試みは、独断と懐疑との峡をあてもなく彷徨することとなる。
この問題は、カントが「コペルニクス的転換」ののちに慎重に提示した紳士的な説明で、ひとたびは結論づけられたかに見えた。だがその結論すら、多くの不徹底さを残していた。結局、存在と意識とのリアルな関係論の総合的な理論化は、カントの後に現れ“近代”を終焉せしめたヘーゲルの巨大な体系の出現を待ってすら完全には成し遂げられなかった。そしてその近代最後の激突は皮肉にも、へーゲルに挑むマルクスとキェルケゴールという三つの弁証法の中に発現するのである。
ヘーゲルの体系は、意識の論理によって成っている。デカルトはコギトという“意識”によって“存在”に懐疑をとなえ否定したが、ヘーゲルにおいて“存在”は“存在の意識”であって、意識による存在の否定はすなわち“意識”による“存在の意識”の否定、つまり意識による意識の自己否定という矛盾の構造を展開する。“存在の意識”は意識であるとともに在在であるから、自己自身を自己の対象として外化する。しかし同時にやはりそれは意識でありつづけることによって自己を自己へと統合する。このダイナミックな発展の構造がへーゲル弁証法の基本原理である。
これは“意識”の体系でありながら、存在論としての形而上学の形式をとる独特の体系である。だが、近代最大の体系であるヘーゲル論理学も、やはり真に総合的な“存在”の論理を解明しつくすには至らなかった。その一つの現れとして、ヘーゲル形而上学の方法に対するマルクスの攻撃的な評価はあまりにも有名であろう。また、現実的な“生”のカテゴリーとして“実存”の問題を提出し、質的弁証法によって観念論としてのへーゲル体系を此判したキェルケゴールの立場も忘れるわけにはいかない。
しかし、自らの方法に“科学”を標榜し、唯物論の弁証法を展開するマルクスの立場は、つまるところすべてをプロトコル命題に還元しようとする論理実証主義と同様、存在の深層を知らずただ此岸的事実の総体を読む“ただの”唯物論であった。また逆に、世界公開性と、主体が物理的次元で依存せねばならないはずの客観的存在を見失い、なおかつ彼岸者である神にのみ救済を求めねばならなかったキェルケゴールも、やはり不完全であった。真理の真相は、存在と意識、主体と客体を、高次の次元よりともにつらぬく“何か”にあった。究極の真理を夢見つつ、果たすことなく消えていった哲学者の幾人かは、ぼんやりと、しかし確実にそれを“見て”いた。押井守も、いまそれを見ている。
〜意志の哲学〜
科学の歴史は進歩の一途をたどってきた訳ではない。現代の科学的世界は人類にとって二度目の経験であり、その間には明らかな退歩の歴史があった。
科学的思考法の最初の発達は、紀元前約600年のイオニアで始まった。世界を秩序あるものとし、論理と実験を武器に世界の真相に迫るその態度は、現代の方法と大変よく似ていた。それは数100年のうちに衰退し、アレキサンドリアの崩壊とともに失われた。そののち、長い中世の暗黒が歴史を覆っていく。人類がこの成果を再び手にするのにはルネッサンスの時代を侍たねばならなかった。哲学の歴史にも、きわめて似た事情を見ることができる。
イオニアの科学が栄えていたころ、哲学の追及は世界の真相に対してなされていた。存在の実相こそ哲学的思索の変わらぬテーマであった。ある人物の出現を境に、哲学は“存在の実相”から離れることになる。それは必ずしも退歩ではなかったかもしれない。だがそれはある意味で“堕落”であった。その人物は、ソクラテスだった。
二ーチェは、哲学を堕落せしめた張本人としてソクラテスを糾弾する。この“自ら名乗る愚者”によって、人類の知は存在そのものの意味を語る“大地の思惟”を忘れ、矮小な“道徳”を云々するようになった。以来、人類が再び存在の思惟を取り戻すには近代の到来を待つことになる。
存在の真相の思惟が人類の思想史に再びその姿を見せたのは、19世紀を持った近代の終盤の時代であった。実在と現象の二元論が激しく交錯している時、それは“意志の哲学”という奇妙な思想の形をとって現れた。
アルトゥール・ショーペンハウエルの“盲目的な生への意思”は、激しい批判を経てニーチェの“権力への意志”の思想を生む。だがそれらの思索の背後には、イマニエル・カントの“物自体”があった。
マルクスがカントの哲学を批判した「不可知論」という嘲笑的な評価は、あまりにも広く知られている。だが、このときマルクスのおかした過ちについてはそれほど広く知られてはいない。“存在の思惟”はマルクスの時代の射程を超えたものだった。そして何よリマルクスは「嘲笑わねばならなかった」。嘲笑うことこそが、みずから起こした宗教に対する彼の開祖としての最も誠実な儀礼行為だったのである。
カントの“物自体”の思想は、つまるところカテゴリー論である。カントは思惟の形式を「分量」「性質」「関係」「様相」の四つの群から成る十二の範疇(カテゴリー)に分け、理性の可能的経験の領域と、その限界を示唆することに取り組んだ。この仕事は、理性の理論を確立し、宇宙の涯や時間の限界の問題に一つの解答をもたらした。だがその成果の本質は、後のハイデッガーの展開した存在論的差別の方法論に通ずるものであった。すなわちそれは哲学史にとって、単なる実在と現象の二元論を超越した、高次の存在論の可能性を開示する“事件”だったのである。“物自体”に対するニーチェの心酔、『カント・ブーフ』にみられるハイデッガーの評価は、この点にその由来をもっている。〔補遺 こういったカントの思惟は、ただ思弁的、形而上学的な段階の議論に留まるものではない。この思索は、あらゆる学術や文化の局面にその現実的な発露の例を見ることができる。たとえば言語学的哲学における世界とシンボルの乖離、行動主義的な心理学における性向と行動の関係論、経済学における産業的部分と企業的部分の弁証法、格闘技における勝負と勝敗の不一致、キリスト教における救済と原罪の思想──人間の認識領域は現象界に限られており、物自体を直接認識することはできない。人間が宇宙空間における光線を直接見ることができず、ただその反射によってしかその存在を知ることができないのと同様に時間や空間などを直接認識しえず、ただその内的存在物(即ち現象)によってそれを認識するしかないという“認識力の限界”こそ、人類の悲劇の大きな原因なのである。また、このことはひとつの思考実験を生んだ。もしも、人間の認識力にこのカテゴリーを超越する能力があったら? 感覚的知覚に依存し、現象の世界のみに束縛された悟性に、存在の実相を直接感じとることのできる認識力があたえられたら?……おそらくその者は現在の人間とは認識論的に次元のまったく異なる存在者となるだろう。
自らをカントの正当な後継者とするショーペンハウエルは、残念ながらあまりに“詩的”だった。“存在の真相”をいちはやく見抜いたその『意思と表象』の哲学は、しかし彼自身の望むようには評価されなかった。だがその悪魔的な魅力に満ちた形而上学は、超時代的な天才を出現させた。ひそやかに死への誘惑を囁くショーペンハウエルの哲学に対する激しい憤りとともに、ニーチェは現れた。その“権カへの意志”の思想は、存在の本質を求める古代の思索を復活させた。二十世紀最大の思想家マルティン・ハイデッガーも、知の考古学者ミッシェル・フーコーも、大地の思索者ツァラトゥストラの弟子だった。
そして時代は、“近代”の終焉を迎えようとしていた。
19世紀末、物理学は混迷の時代を迎えていた。ニュートン力学に対するマッハの無謀とも思える挑戦は、近代物理学の根底を問いなおすものだった。彼の比較物理学の提唱は、皮肉の意味をこめて『物理学的現象学』と呼ばれた。また数学界においても、新しい知的潮流が起こっていた。デーデキントの無限小解析やカントールの集合論などをその例とする数学的思考の算術化の傾向である。
これら思想的流派の知的運動は、近代までの世界を何らかの意味において裏打ってきたプラトン主義の思考習慣を打ち破る胎動であった。「証明の背後の何ものかではなく、証明が証明するのだ」というヴィトゲンシュタインの言葉に顕されるように、知は自らを“構成”する。それは、“現代”の到来を意味していた。
時を同じくして、哲学の世界にもひとつのエポックが訪れようとしていた。カントールの同僚のひとりが、数学の思考法を哲学に持ち込んだ。彼の名は、エドムント・フッサールといった。彼は、物理学のマッハからその学派の名称を借用した。それまで何らかの形で“芸術的”な様相をすら持っていた“哲学”を、彼は「厳密に学問的な方法」によってあらたにシステム構築しようとした。彼はその知的運動を、誇り高い自負とともに『現象学』と名づけた。
現象学は、記述の哲学である。それはどこまでも冷静に、的確に、あらゆる諸科学が暗黙のうちに認め問わないその根底にまで立ち戻って記述する一種の科学哲学である。したがってそれは、あらゆる認識の大前提となる“意識”の、その“指向性”という根源的な性質が向かうもの、すなわち“直感に原的に与えられた事象”としての《現象》をその固有の対象とする。そのとき、われわれが自然的態度のもとにひたっている歴史、文化、伝統的な思考習慣、諸科学からの理論や知識、個人的および主観的なものの見方などといった各種のイドラ、さらには世界そのものを在りとする存在定立一般をすら問題対象の外部へ置く。それは“括弧入れ”と呼ばれる思考技術の一方法であり、“判断中止”(エポケー)とも呼ばれる。それはあたかも、複雑な外科手術が、各器官の有機的関連の維持に対する十分に注意深い配慮のもとに、麻酔され、切開され、処理されるのによく似ている。この思考実験的な方法を、方法論的に“還元”と呼ぶ。
この“還元”は、世界の実在を疑うデカルト的懐疑とは異なり、世界への関与や関心から一時的に身を引くことにより自然的態度においては到達し得なかった認識と世界の真の関係に迫ろうという思考技術である。だが同時にこれは、世界と主体の関係を超越的に理解するための技術でありながら、世界と主体の関係そのものを一時的にしろ問題の外に置くという矛盾を内包している。したがってこの思考作業は、段階的に、精密に、注意深く進められる。まず「形相的還元」においては、眼前に提示された対象の本質的把握がめざされ、次いで“主観”の領域を主題とする「現象学的還元」では没個人的な“私の”世界構成としての自我論的構成が問題とされ、さらに「間主観的還元」において多数主観の共同主観的構成による普遍的な対象の客観性が確保される。〔補遺 単純な見方をすれば、作品『天使のたまご』はこの“現象学的還元”の段階から“間主観的還元”にいたる知的フィールドにおいて語られる「現象学的作品」であるという理解も極端な誤りではなかろう。しかしそもそも、アニメーション等映像メディア上で語られる芸術は、それ自体現象学的要素を強く持っている。虚構であることを前提としつつもその作品世界を感覚対象とする態度は、(不徹底ではあるが)ある意味で明らかに現象学的な思考技術としてのエポケーであり、ひとつの還元である。また特にアニメーションは、非実在的(irreal)な“絵”でありながら、それが動き、声を発することによって「意味を付与され」、「生気を吹き込まれ」、“指向的対象”として構成される。これは、やはり非実在的で客観的な色や音、すなわち「色のごとき或るもの」といった“感覚の色”や“感覚の音”などの材料的成分から成る、いわゆる“ヒユレー的契機”が、“ノエシス的契機”によって「意味を付与され」、「生気を吹き込まれ」て“指向的対象”としての“ノエマ”として構成されるという“現象学的還元”の説明とほぼ一致する。
またこの場合、声優の存在はきわめて大さな意味を持つ。知覚感性論における“外”の原初的指標は「眼」と「声」によって啓発されるが、特にデリダの指摘によれば、自己現前性を出発点とする明証性は音声記号中心主義に起因するのである。
現代においてこうした例は、映画のスクリーン、テレビの液晶スクリーン、コンピュータのCRT等の中に非常にしばしば見ることができる。これは、フッサールの時代にはまだあまり見ることのできなかった情況である。すなわち現代は、過去のいかなる時代にもまして現象学的な時代だと言える。そういった意味で、現象学的視点は見直されるべきなのかもしれない。以下述べることとなるが、フッサールのこの思考技術は、(必ずしもフッサールの意図どおりの形でなしに)さまざまな知的潮流に受け継がれていく。アメリカの実在論および自然主義哲学、ヨーロッパの実存哲学、また心理学をはじめとするその他の精神諸科学、そして各種の視覚的芸術。タルコフスキーや押井守も、この影響下にある。このことはこの文の重要な主張のひとつである。
フッサールの試みは、極端な見方をすれば要素論的な“観照の記述”の学であり、一種の思考技術である。それは眼前の世界に無秩序に広がるままにされていたさまざまな存在物を、いったん全体化し、排去することによって得られる「もの」、すなわち現象学的残渣としての純粋な意識と、それに指向的統一を与える“ノエマ(意味)”および“ノエシス(意味付与作用)”などに関する厳密な記述を目的としていた。だがそれは結局の処、その名の示すとおりあくまで“現象の学”であった。このあとヨーロッパの知的潮流は、フッサールの思いもかけぬ方向へ フッサールのこの思考技術は、思いがけない効果を生もうとしていた。眼前的な存在物の排去という操作は“世界”に被われていた自己意識から、それを被う対象的存在を剥ぎ取リ、その内部の深淵を剥きだす結果を生んだ。それによってもたらされたのは、自己意識と対象的存在との背後に共通に横たわり、その深殻に見え隠れる“深淵的存在”の示唆と、それの周囲に漂う“不安”の概念であった。ここにおいて思想史は、M・ハイデッガーの出現という決定的な事実を刻む事となる。
〔補遺 かつて“存在の思惟”への到達をはたした哲学を検討したとき、ひとつの方法上の共通点を見いだすことができる。それは意識に映ずる現象からの“存在”への接近が、人間の能力として保証されること、言葉を変えれば、人間という存在者そのものが、深淵的存在へといたる認識の現実的通路として重要な意味を擁しているということである。たとえばカントは、因果律に規定された現象界においては保証され得ない人間の本質的自由を、唯一確保できる方法として、現象界から物自体への意識の超越を説いた。そして此処で注目すべきなのは、その超越が人間の遂行行為(カントにおいては定言命法による道徳的格率の遂行)によってなされうるという考えである。同様にニーチェにおいても、精神の革変によって向かうべき“超人”がやはり深淵的存在への鍵を握っている。フッサールの弟子たちが、現象学的方法とキェルケゴールの遺産である“実存”の融合へと向かったのはこうした必然性があったのかも知れない。また逆に言えば、人類の思想史が“存在”へのアプローチのためにこの“実存”の概念に到達するまで、数千年の歳月を要した訳である。
われわれ目の前に与えられているテキストは、あくまでも単なる「存在するもの」である。それは“存在者”もしくは“存在物”であって、けっして“存在”そのものではない。ハイデッガーの指摘によれば、従来の哲学における観念論や実在論の論争は、どちらもこの“存在するもの”と“存在”の差異を不明確なままに展開された、下位の議論であるという。すなわち、世界所属的なレベルにある“存在するもの”を、いかように──たとえば内省論的な観念論の立場からであろうと、唯物論的な実在論の立場からであろうと──解釈しようとも、それは存在論的無差別をおかしたオブジェクト・レベルの議論にすぎない。存在そのものについての論及は、存在するものについての議論とは峻別されねばならない。これが“存在論的差別”である。
こういった存在論への手がかりとしてハイデッガーは、人間の存在への研究、すなわち現存在の実存論的分析論を具体的方法とする解釈学的現象学を提唱した。そして押井守は、ハイデッガーのこの方法から出発した。押井守作品群との関係については、いちいち述べることはしない。読者諸君自身の記憶と思考力をもって、その方法論的相似性を読み取っていただきたい。
 |
存在と時間〈上〉 (ちくま学芸文庫) |
| クリエーター情報なし | |
| 筑摩書房 |
 |
押井守論―MEMENTO MORI |
| クリエーター情報なし | |
| 日本テレビ放送網 |
-------------------------------------------------------------------------------
ブルース・ハープ。なんと麗しい楽器だろう。私は数十本かのブルースハープを所有している。ハーモニカ吹きにはこの気持ちは分かるだろう。大体がすぐに壊れる楽器でもある。ブルース・ハープは人によって全く違った音色が出る。同じと言う事が無いのだ。口の形、歯が無いと言った事でも、音色は変化する。また、ギターやらピアノと違って誰にでも容易く演奏出来ると言う利点がある。音色は同じ管楽器のサックスに似て居るかも知れない。ブルースハープはその小ささから、携帯用に適して居る。私は何時も腰のベルトにフォルスターを付けて、持ち歩いて居る。何時、如何なる時にも吹けるようにだ。経験上学んだ。しかし最近は練習の時間が中々取れなくて、思い出した時に、アドリブを吹くといった具合だ。この間は演歌を吹いてみた。吹いて見ると結構面白かった。さて、最近話題になって居るブルース・ハーピストです。
注目のブルースハーピスト。『ビック・ピート』
Big Pete - That ain't it - Live
Big Pete & Little G Weevil,Pribojszki Mátyás,Szabó Tamás-Jam
ビック・ピート『ライブ・アット・ブルースナウ』
ディープで野太いハーモニカにクールなテナーヴォイスで、オリジナルを中心にジュニア・ウェルズ、ハウリン・ウルフ、ビッグ・スモーキー・スムーザーズなどの名曲を存分に聴かせる。ゲストに、キッド・ラモス、モンスター・マイク・ウェルチ、アンソニー・ジェラーシ等を迎え、オールドスクールなシカゴ&ウェストコースト・ブルース・サウンドを完全再現。スイスで行われた“ブルース・ナウ”フェスにて収録。
<プロフィール>
ビッグ・ピートはオランダ出身のブルース・ハーピスト。23歳という若さで、98年に亡くなったウェストコーストの伝説のハーピスト、レスター・バトラーへのトリビュートバンドのフロントマンに抜擢。ヨーロッパをツアーし、その名を知らしめた。その後、2004年にザ・ストライクス名義の『バスルーム・アコースティックス』でCDデビュー。その後も、バックボーンズやM.O.C.T.(メン・オブ・コンシダラブル・テイスト)などの人気バンドで数枚のアルバムをリリースしており、名実ともに母国オランダのブルース・シーンでは、トップアーチストとして認められている。2010年には、アメリカ西海岸を代表するブルース集団、マニッシュ・ボーイズのアルバム『シェイク・フォー・ミー』に招かれゲスト参加。それを足掛かりに2011年ソロ・アルバム『チョイス・カッツ』で全米デビューを果たす。その後、デルタ・グルーヴ主催の“ハーモニカ・ブラスト”ツアーでロッド・ピアッツァ、ミッチ・カシュマー、アル・ブレイクなどと全米を回りその名を世界に知らしめた。2017年には、再びレッド・デヴィルズのリユニオンツアーでヨーロッパを周っている。
発売は2019年3月22日の予定
-----------------------------------------------------------------------------
裏切りの街角 甲斐よしひろ
桑田佳祐 - 東京
CRAZY KEN BAND タイガー&ドラゴン
サザンオールスターズ「いとしのエリー」by 桑田研究会バンド
みずいろの雨/八神純子
2012 サーカス :: Mr. サマータイム
Hirota Mieko - Ningyo no ie 弘田三枝子 人形の家
ブルーライトヨコハマ いしだあゆみ
山崎ハコ ざんげの値打ちもない
クリスタルキング 大都会
帰って来たヨッパライ












