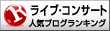ムハマドとヤング、二人の美意識が作り出した豪華なソウル・シネマ。
僅か一夜という刹那の時間に繰り広げられた一大叙事詩、そんな印象を強く感じさせた。ザ・ミッドナイト・アワーという名に違わぬ真夜中の光景を濃密に描いた80分。内なる襞にジワジワと張り付くようなディープな質感と小気味とグルーヴを併せ持ったビート、ソウルとハートウォームの両面を醸し出すヴォーカルワーク、上質の華やかさを注ぎ込んだホーン&ストリングス……。地上の街の灯を大きく包み込んだ静謐な夜空に次々と星が瞬き始めるかのごとく、各プレイヤーがその夜景を司る夜の支配者となって、夜の街や風景、その夜を過ごす人たちの機微を細やかに描き出していく。
格好つけてロマンティックな物言いをしたら、こんな風になるだろうか。このステージを体感し胸に去来したのは、ライヴというよりも一編の映画を見終えたような心持ちだった。軸となるのはレイドバックしたソウルな音鳴りだが、ヴィンテージ感はあっても古めかしいという感覚がないのは、時は過ぎれど、夜も人も本質的な部分では同じだという普遍的なところにしっかりと音がフォーカスしていたからかもしれない。
ア・トライブ・コールド・クエストとしてはもちろん、ディアンジェロやエリカ・バドゥらのプロデューサーとして、ラファエル・サディーク(トニ・トニ・トニ)やドーン・ロビンソン(アン・ヴォーグ)らとのルーシー・パールのメンバーとしても知られるアリ・シャヒード・ムハマドと、60~70年代サウンドを現代に邂逅させる手腕でデルフォニックスやビラルらの作品を手掛けるプロデューサーのエイドリアン・ヤングがコラボレーションしたプロジェクト、ザ・ミッドナイト・アワーの来日公演は、プロジェクトを始動させた2013年から5年をかけて映画のサウンドトラックのようなアルバム『ザ・ミッドナイト・アワー』を完成させたというタイムリーな時期でもあったが、期待以上の興奮をもたらしてくれた。

ヒップホップ・シーンで活躍していたムハマドだが、ソロ作『シャヒーデュラ・アンド・ステレオタイプス』では生演奏によるクールなソウル・アルバムを仕立て、また、ジャズ・ヴィブラフォン奏者のロイ・エアーズとの来日公演も果たしたことでも分かるように、元来ソウルやジャズへ接近していた人物。70年代前後の音を現代へ回帰させる手法でソウル・アルバムをプロデュースしてきたヤングと出会い、ケミストリーを起こすことは時間の問題だったのだろう。今回のアルバム『ザ・ミッドナイト・アワー』同様、電子ピアノ(フェンダー・ローズ)をはじめベースやドラム、ストリングス、ホーンなど生演奏に拘った布陣で、東京の夜を彩った。そのうちホーン・セクションとストリングスの計4名は日本人を配した。これはホーンとストリングスは現地で調達するというヤングの意向なのかどうかは分からないが、ヴァイオリンの越川歩と柳原有弥、アルトサックスの橋本和也、トランペットの真砂陽地はヤングの期待に十分応える演奏を披露してくれた。特に終盤で見せた、ステージ前方で繰り広げられた真砂のトランペットとヴォーカルのカロリナのマウストランペットとの掛け合いは、フロアを大いに焚き付け、興奮の渦をもたらした。
寡黙にベースプレイを続けるムハマド、スパンコールのタキシードを身に纏いながらホーン&ストリングスに1曲ごとにイントロ前に指揮振りをするヤング、ユニークなパフォーマンスで味わい深い粋なギターを奏でるジャック・ウォーターソン、そしてカッという乾いた音とグルグルと矢継ぎ早に刻むビートをクールな面持ちで変態的に繰り出すデヴィッド・ヘンダーソンが、日本人ホーン&ストリングスとともに夜の帳から真夜中へと時を移すかのごとくのインストゥルメンタルを30分奏でた後に登場したのが、白のステッチがあしらわれたカジュアルドレス姿のカロリナと真っ赤なタキシードジャケットに身を包んだローレン・W・オデンのヴォーカル陣。旧き良きソウル・ミュージックの趣向になぞらえた、ハートウォームでハッピー・テイストのデュエットを仲睦まじく。ア・トライブ・コールド・クエスト『ボニータ・アップルバム』のネタとなったランプ(RAMP=ロイ・エアーズ・ミュージック・プロダクション)の「デイライト」も披露していた。

当初は美声というよりもコクのある声質で語りかけるように歌うカロリナとあくまでもレディをエスコートするというスタンスでアプローチするオデンというカップル・デュエットでスタート。シネマティックな架空のサウンドトラックというザ・ミッドナイト・アワーの音楽性コンセプトに合わせたか、やや声圧が弱いかと思っていたが、二人での掛け合いが熱を帯び、また、それぞれがヴォーカル・ソロをとるようになると、軟なテイストは一変。カロリナは、スティーヴィー・ニックスやジャニス・ジョプリンあたりの70年代の女性ロック・ヴォーカル然とした意志の強さとミニ・リパートンもちらつくスウィートネスを湛え、オデンはソウルというよりもリズム&ブルース、もっといえばロックンロールによく見えるファットなヴォーカルでフロアの熱気をさらに上昇させる。時には咄嗟に最前席の女性の手を取り、見つめ合って愛を問いかけるように歌う場面も。
その熱に感化されたか、「ソー・アメイジング」などでアリとパートチェンジしてベースを弾いていたヤングは、ステージ上でチャック・ベリーよろしく“ダックウォーク”を披露したかと思えば、そのノリのままステージを降りてフロアを巡り(観客の横に座って)ベースをかき鳴らすというサプライズも。メロウに深く沈んでいた夜を“マスカレード”な大人の夜の賑わいへと一変させていく。甘美ながらもそれだけでない、自我や渇望する欲のようなものも捉えた人間味に溢れたパフォーマンスは、まさに生命力がたぎるステージへ。生演奏でそれを具現化し、響かせているところに、彼らのこだわりと矜持が垣間見えた。

静と動、人間の欲と抗えない自然。一夜という短い時間に生まれる理性と欲望、あらゆるものをヴィンテージなフィルターを通して、フロアに集った“今”の時空にいる人とをリンクさせていく。映画的な音楽とは言ったものの、もっと言えば、壮大な戯曲が眼前で展開しているといった方がいいかもしれない。それが冒頭の“僅か一夜という刹那の時間に繰り広げられた一大叙事詩”という印象として強く残ったのだと思う。
さまざまな場面を目の前で展開していったが、終わってみればあっという間。時間にしては刹那だが、意識としては濃厚にして芳醇。ソウル・ミュージックに回帰しながらも、これまでにないステージの在り方を浮かび上がらせたマジックアワー。早くも次回の来日に期待するのも止むを得ない、胸躍るステージだった。

◇◇◇
<MEMBER>
Ali Shaheed Muhammad(b)
Adrian Younge(key)
Loren W.Oden(vo)
Karolina(vo)
Jack Waterson(g)
David Henderson(ds)
Ayumu Koshikawa(vn)
Yuya Yanagihara(vn)
Kazuya Hashimoto(as)
Yochi Masago(tp)


◇◇◇