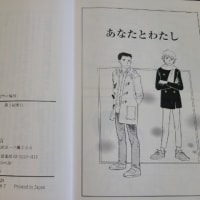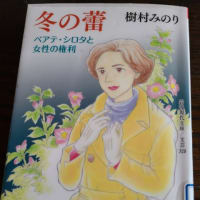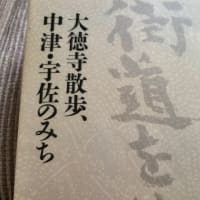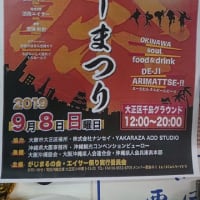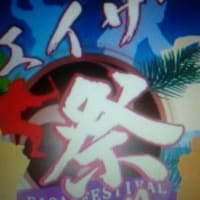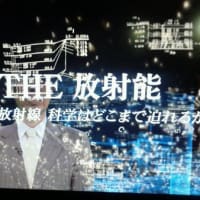写真は左からNo.⑦⑧⑨。 ⑦⑧は初版のカバーデザインだが、
⑨は増刷で、後に統一されたデザインとなっている。
おきなわ文庫(ひるぎ社)ラインナップ
No. 書名 副書名 年 著者・述者
01 近代沖縄の寄留商人 1982 西里 喜行
02 八重山・島社会の風景 1982 真栄城 守定
03 御教条の世界 -古典で考える沖縄歴史 1982 高良 倉吉
04 近世沖縄の肖像 ㊤ -文学者・芸能者列伝 1982 池宮 正治
05 〃 ㊦ 〃 〃 〃
06 宮古・地域開発の胎動 1982 真栄城 守定
07 西表炭鉱概史 1983 三木 健
08 沖縄の無産運動 1983 安仁屋 政昭
09 沖縄戦を考える 1983 嶋 津与志
10 もうひとつの沖縄戦 -マラリヤ地獄の波照間島 1983 石原ゼミ
11 島の未来史 1983 岩井 康彦
12 近代沖縄の鉄道と海運 1983 金城 功
13 沖縄と中国芸能 1984 喜名 盛昭
14 尖閣列島 1984 緑間 栄
15 沖縄の心を求めて 1984 石田 穣一
16 おきなわ歴史物語 1984 高良 倉吉
17 南島地名考 -おもろから沖縄市誕生まで 1984 田名 真之
18 沖縄の子どもたち -小児科医のカルテより 1985 安次嶺 馨
19 八重山戦後史 1991 大田 静男
20 南海の歌と民俗 -沖縄民謡へのいざない 1985 仲宗根 幸一
21 早川元・沖縄県知事日記 昭和四十六年 1985 野里 洋
22 ヤマピカリャーの島 -西表島の自然と人間 1985 小野 紀之
23 沖縄の県民像 -ウチナンチュとな何か 1985 沖縄地域科学研
24 近代沖縄の糖業 1985 金城 功
25 伊平屋島民民俗散歩 1990 上江洲 均
26 沖縄の文化 -美術工芸の周辺から 1990 渡名喜 明
27 わが故郷(しま)アントゥリ -西表・網取村の民俗と古謡
1986 山田 武男
28 レダの末裔 -アイルランド・ポリネシア・沖縄 1986 米須 興文
29 おきなわ歴史物語 続 1988 高良 倉吉
30 格差から個性へ 1987 真栄城 盛定
31-1 戦後沖縄の通貨 ㊤ 1989 牧野 浩隆
-2 〃 ㊦ 〃 〃
32 沖縄気象歳時記 1990 伊志嶺 安達
33 南島の民俗文化 -生活・祭り・技術の風景 1987 上江洲 均
34 オキナワ マイラブ 1991 黒川 修司
35 空手の歴史 1987 宮城 篤正
36 わたしの沖縄体験 -国境のある島にて 1988 桑原 守也
37 宮古風土記 1992 仲宗根 将二
-1 宮古風土記 (新)㊤ 1997 〃
-2 〃 ㊦ 〃 〃
38 沖縄の踊り 1991 真久田 巧
39 金門クラブ -もうひとつの沖縄戦後史 1988 金城 弘征
40 嘉永六年の奄美 -解説『嶋中御取扱御一冊』 1989 山下 文武
41 南の島の新聞人 -資料にみるその変遷 1988 南風原 英育
42 サンゴ礁の渚を遊ぶ -石垣島川平湾 1989 西平 守孝
43 沖縄の豚と山羊 -生活の中から 1989 島袋 正敏
44 沖縄の民間信仰 1992 窪徳 忠
45 おきなわ感懐録 -ある日銀マンのメモワール 1989 佐々木 信行
46 福州琉球館物語 -歴史と人間模様 1990 多和田 真助
47 首里城入門 -その建築と歴史 1991 首里城研究グ
48 首里城物語 1991 真栄平 房敬
49 琉球漢詩選 1991 島尻 勝太郎
50 糸満アンマー -海人の妻たちの労働と生活 1992 加藤 久子
51 つらねの時代 1990 仲程 昌徳
52 崎山節のふるさと -西表島の歌と昔話 1990 川平 永美
53 考古学からみた琉球史 ㊤ -古琉球世界の形成 1991 安里 進
54 西表炭鉱夫物語 1990 三木 健
55 沖縄福建交流顛末記 1991 高橋 俊和
56 中国琉球交流史 1991 徐 恭生
57 考古学からみた琉球史 ㊦ -古琉球から近世琉球へ
1991 安里 進
58 戦後動員とジャーナリズム -軍神の誕生 1991 保坂 広志
59 87-91年リポート 沖縄の基地 1992 鳥取部 邦夫
60 ドイツ人のみた明治の奄美 1992 ドゥーダーライン
61 琉球政府 -自治権の実験室 1922 大城 将保
62 沖縄・医の風景 1992 平田 亮一
63 おばあちゃんの自然生活志 1992 山田 雪子
64 八重山の芸能 1993 大田 静男
65 占領27年 為政者たちの証言 1993 宮城 悦二郎
66 沖縄ことばの散歩道 1993 池宮 正治
67 シマおこしの構図 1993 真栄城 守定
68 沖縄の保健婦たち 1994 沖縄県保健婦-
69 アイルランド断章 1994 米須 興文
70 ボルネオ・サラワク王国の沖縄移民 1994 望月 雅彦
71 琉球歌劇の周辺 1994 仲程 昌徳
72 発言・沖縄の戦後50年 1995 高良 勉
73 ウシ国沖縄・闘牛物語 1989 仲程 昌徳
74 戦後沖縄の社会史 -軍作業・戦果・大密貿易の時代
1995 石原 昌家
75 沖縄ことばの散歩道 (続) 1995 池宮 正治
76 近世先島の生活習俗 1996 玉木 順彦
77 沖縄の時代 1996 松島 朝彦
78 沖縄新民謡の系譜 1996 大城 学
79 サシバ日和 -美島・伊良部 1997 謝花 勝一
80 「沖縄」批判序説 1997 高良 倉吉
81 ケービンの跡を歩く 1997 金城 功
82 秋霜五〇年 -台湾・東京・北京・沖縄 1997 郭 承敏
83 沖縄の自己検証 -鼎談「情念」から「論理」へ 1997 真栄城 守定
84 近世沖縄の素顔 1998 田名 真之
85 `95`~98 新・沖縄レポート 1998 比嘉 良彦
86 沖縄「韓国レポート」 1998 宮里 一夫
87 沖縄・宮古のことわざ 1998 佐渡山 正吉
88 三線のはなし 1999 宜保 栄治郎
89-1 名勝「識名園」の創設 ㊤ -琉球庭園の歴史 2000 古塚 達郎
-2 〃 ㊦ 〃 〃 〃
90 私の見た沖縄経済 -ある日銀マンの沖縄へのラブレター
2000 沼波 正
91 沖縄イニシアティブ -沖縄発・知的戦略 2000 大城・高良他
92 沖縄の神社 2000 加治 順人
93 沖縄長寿学序説 2001 秋坂 真如
自家製の資料
「おきなわ文庫」
出版地:沖縄県那覇市 出版社:ひるぎ社 出版年:1982年~(このリストでは某図書館の登録年で、増刷年を含む)
「おきなわ文庫」はNo.93まで出版されたらしい。No.31、89は2分冊、No.37は旧版に加えて2分冊の新版が別に存在するようなので、全部で97冊(以上)のシリーズであったようである。検索してみると、沖縄でも全巻を揃えている公共の図書館は見当たらない。
ひるぎ社がどうなったかの情報はnet上ではみつからなかったが、秋田市「無明舎」の安倍さんの「あんばいこうの沖縄レポート」(2000年)があって、ひるぎ社富川さんの「資金があればね、金さえあれば企画はいっぱいあるし、すぐにも利益を上げてみせるんだけど、先立つもんが...」という言葉が記録されている。
どなたか、何らかのかたちで、「おきなわ文庫」をまた続けていただけないのだろうか・・・?
⑨は増刷で、後に統一されたデザインとなっている。
おきなわ文庫(ひるぎ社)ラインナップ
No. 書名 副書名 年 著者・述者
01 近代沖縄の寄留商人 1982 西里 喜行
02 八重山・島社会の風景 1982 真栄城 守定
03 御教条の世界 -古典で考える沖縄歴史 1982 高良 倉吉
04 近世沖縄の肖像 ㊤ -文学者・芸能者列伝 1982 池宮 正治
05 〃 ㊦ 〃 〃 〃
06 宮古・地域開発の胎動 1982 真栄城 守定
07 西表炭鉱概史 1983 三木 健
08 沖縄の無産運動 1983 安仁屋 政昭
09 沖縄戦を考える 1983 嶋 津与志
10 もうひとつの沖縄戦 -マラリヤ地獄の波照間島 1983 石原ゼミ
11 島の未来史 1983 岩井 康彦
12 近代沖縄の鉄道と海運 1983 金城 功
13 沖縄と中国芸能 1984 喜名 盛昭
14 尖閣列島 1984 緑間 栄
15 沖縄の心を求めて 1984 石田 穣一
16 おきなわ歴史物語 1984 高良 倉吉
17 南島地名考 -おもろから沖縄市誕生まで 1984 田名 真之
18 沖縄の子どもたち -小児科医のカルテより 1985 安次嶺 馨
19 八重山戦後史 1991 大田 静男
20 南海の歌と民俗 -沖縄民謡へのいざない 1985 仲宗根 幸一
21 早川元・沖縄県知事日記 昭和四十六年 1985 野里 洋
22 ヤマピカリャーの島 -西表島の自然と人間 1985 小野 紀之
23 沖縄の県民像 -ウチナンチュとな何か 1985 沖縄地域科学研
24 近代沖縄の糖業 1985 金城 功
25 伊平屋島民民俗散歩 1990 上江洲 均
26 沖縄の文化 -美術工芸の周辺から 1990 渡名喜 明
27 わが故郷(しま)アントゥリ -西表・網取村の民俗と古謡
1986 山田 武男
28 レダの末裔 -アイルランド・ポリネシア・沖縄 1986 米須 興文
29 おきなわ歴史物語 続 1988 高良 倉吉
30 格差から個性へ 1987 真栄城 盛定
31-1 戦後沖縄の通貨 ㊤ 1989 牧野 浩隆
-2 〃 ㊦ 〃 〃
32 沖縄気象歳時記 1990 伊志嶺 安達
33 南島の民俗文化 -生活・祭り・技術の風景 1987 上江洲 均
34 オキナワ マイラブ 1991 黒川 修司
35 空手の歴史 1987 宮城 篤正
36 わたしの沖縄体験 -国境のある島にて 1988 桑原 守也
37 宮古風土記 1992 仲宗根 将二
-1 宮古風土記 (新)㊤ 1997 〃
-2 〃 ㊦ 〃 〃
38 沖縄の踊り 1991 真久田 巧
39 金門クラブ -もうひとつの沖縄戦後史 1988 金城 弘征
40 嘉永六年の奄美 -解説『嶋中御取扱御一冊』 1989 山下 文武
41 南の島の新聞人 -資料にみるその変遷 1988 南風原 英育
42 サンゴ礁の渚を遊ぶ -石垣島川平湾 1989 西平 守孝
43 沖縄の豚と山羊 -生活の中から 1989 島袋 正敏
44 沖縄の民間信仰 1992 窪徳 忠
45 おきなわ感懐録 -ある日銀マンのメモワール 1989 佐々木 信行
46 福州琉球館物語 -歴史と人間模様 1990 多和田 真助
47 首里城入門 -その建築と歴史 1991 首里城研究グ
48 首里城物語 1991 真栄平 房敬
49 琉球漢詩選 1991 島尻 勝太郎
50 糸満アンマー -海人の妻たちの労働と生活 1992 加藤 久子
51 つらねの時代 1990 仲程 昌徳
52 崎山節のふるさと -西表島の歌と昔話 1990 川平 永美
53 考古学からみた琉球史 ㊤ -古琉球世界の形成 1991 安里 進
54 西表炭鉱夫物語 1990 三木 健
55 沖縄福建交流顛末記 1991 高橋 俊和
56 中国琉球交流史 1991 徐 恭生
57 考古学からみた琉球史 ㊦ -古琉球から近世琉球へ
1991 安里 進
58 戦後動員とジャーナリズム -軍神の誕生 1991 保坂 広志
59 87-91年リポート 沖縄の基地 1992 鳥取部 邦夫
60 ドイツ人のみた明治の奄美 1992 ドゥーダーライン
61 琉球政府 -自治権の実験室 1922 大城 将保
62 沖縄・医の風景 1992 平田 亮一
63 おばあちゃんの自然生活志 1992 山田 雪子
64 八重山の芸能 1993 大田 静男
65 占領27年 為政者たちの証言 1993 宮城 悦二郎
66 沖縄ことばの散歩道 1993 池宮 正治
67 シマおこしの構図 1993 真栄城 守定
68 沖縄の保健婦たち 1994 沖縄県保健婦-
69 アイルランド断章 1994 米須 興文
70 ボルネオ・サラワク王国の沖縄移民 1994 望月 雅彦
71 琉球歌劇の周辺 1994 仲程 昌徳
72 発言・沖縄の戦後50年 1995 高良 勉
73 ウシ国沖縄・闘牛物語 1989 仲程 昌徳
74 戦後沖縄の社会史 -軍作業・戦果・大密貿易の時代
1995 石原 昌家
75 沖縄ことばの散歩道 (続) 1995 池宮 正治
76 近世先島の生活習俗 1996 玉木 順彦
77 沖縄の時代 1996 松島 朝彦
78 沖縄新民謡の系譜 1996 大城 学
79 サシバ日和 -美島・伊良部 1997 謝花 勝一
80 「沖縄」批判序説 1997 高良 倉吉
81 ケービンの跡を歩く 1997 金城 功
82 秋霜五〇年 -台湾・東京・北京・沖縄 1997 郭 承敏
83 沖縄の自己検証 -鼎談「情念」から「論理」へ 1997 真栄城 守定
84 近世沖縄の素顔 1998 田名 真之
85 `95`~98 新・沖縄レポート 1998 比嘉 良彦
86 沖縄「韓国レポート」 1998 宮里 一夫
87 沖縄・宮古のことわざ 1998 佐渡山 正吉
88 三線のはなし 1999 宜保 栄治郎
89-1 名勝「識名園」の創設 ㊤ -琉球庭園の歴史 2000 古塚 達郎
-2 〃 ㊦ 〃 〃 〃
90 私の見た沖縄経済 -ある日銀マンの沖縄へのラブレター
2000 沼波 正
91 沖縄イニシアティブ -沖縄発・知的戦略 2000 大城・高良他
92 沖縄の神社 2000 加治 順人
93 沖縄長寿学序説 2001 秋坂 真如
自家製の資料
「おきなわ文庫」
出版地:沖縄県那覇市 出版社:ひるぎ社 出版年:1982年~(このリストでは某図書館の登録年で、増刷年を含む)
「おきなわ文庫」はNo.93まで出版されたらしい。No.31、89は2分冊、No.37は旧版に加えて2分冊の新版が別に存在するようなので、全部で97冊(以上)のシリーズであったようである。検索してみると、沖縄でも全巻を揃えている公共の図書館は見当たらない。
ひるぎ社がどうなったかの情報はnet上ではみつからなかったが、秋田市「無明舎」の安倍さんの「あんばいこうの沖縄レポート」(2000年)があって、ひるぎ社富川さんの「資金があればね、金さえあれば企画はいっぱいあるし、すぐにも利益を上げてみせるんだけど、先立つもんが...」という言葉が記録されている。
どなたか、何らかのかたちで、「おきなわ文庫」をまた続けていただけないのだろうか・・・?