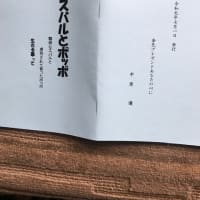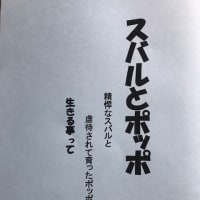スバルの生い立ちはそれほど悪くは無かった。スバルが 花さんの所に来たのは生まれて三ヶ月の時。孫の忠志がどうしても猫を飼いたいと言うので、知り合いの獣医さんに情報を提供してもらって、札幌から小樽まで行って貰ってきたのだ。本当は、アメショーをくれると言う事だったが、行ってみるとアメショーはもういなくてミックスの白色と薄茶色のトラ猫を貰う事になった。何とも可愛いぬいぐるみのような子猫だった。
スバルは花さんの息子と、その嫁、そして孫の忠志と四人暮らしだったが、まもなく息子の海外の転勤で、猫と花さんがそのままその家に残る事になった。もしスバルがいなければ、花さんも一緒に外国へ行っていたのかも知れなかったが、花さんは高齢で足も悪かったので慣れない外国生活よりも、数年後に息子たちが帰国するまで日本に残る事になったのだ。
結局、数年で帰国すると思っていた息子家族は、十年たっても日本へは戻れなくて外国を転々と回っていた。
花さんはスバルと二人暮らしになった時に、スバルを去勢して外にも出すことにした。自分の足が動かなくなったときはスバルの面倒をみることが出来無くなるから、なんとか一人で生き延びて欲しいと考えたからだ。
スバルは朝ごはんを花さんに貰うと外出するようになった。夕方になって家へ戻るとニャーニャーと外で会ったことを花さんに話した。花さんは猫語が分かるかのように、そうかい、そうかい、と聞いてくれる。夕飯を食べ終わると花さんのベッドに上がり寄り添って一緒に寝た。
半年も経つとスバルは、ねずみ、小鳥を銜えて来て庭にいる花さんの目の前でバリバリと音をたてて食べるようになった。花さんは「偉い偉い」とスバルを褒めて身体をきれいに拭いて家に入れた。大怪我をして帰ったこともあるが、スバルはすくすくと育ち立派に成長していった。
十年経ったある日、花さんは庭で倒れて、その後遺症で右半身が動かなくなり、言葉も話せなくなって、救急車で運ばれて三ヶ月入院後、そのまま施設に入ることになった。
スバルは外猫になった。
ポッポは、スバルのおかげで、飼い主の虐待から逃げる事が出来て、外猫になった。
キティは、老人施設に入る飼い主から突然捨てられて途方に暮れていたところをスバルに助けられた。
クロは、どこからか来てスバルについて歩いた。
そしてクロの紹介でクーちゃんと言う生まれた時から外猫の、ちょっと気の強い雌猫と知り合いになった。気が強い筈だった。子供を産んだ後だったのだ。スバルは獲物を捕ってはクーちゃんに運んだ。
ポッポは飼い主から虐待されて、痩せこけて、眼もほとんど見えなくて目やにだらけだった。ポッポはいつ飼い主が追いかけて来ないかと怯えて、夜は魘されてあまり眠れない。
キティは飼い主に捨てられたと、しくしくと泣くけれど、ポッポは
「でも、今まで可愛がられていたんだろう?まだいい方だよ。僕なんか、飼い主が機嫌悪いといつも八つ当たりされて、壁に投げられる、殴られる、引きずり回される、ご飯を貰えない、罵声をあびる。でも、僕が悪いからだと思っていた。醜いし、頭は悪いし、声はガラガラだし。窓越しにスバルが来て教えてくれたんだ。悪いのは君じゃないと。花さんが倒れた日、スバルは涙をためて僕の所へ来た。帰る家が無くなったと言うんだ。でも花さんの事は恨んでいない。こうなる事は分かっていた。だけど、花さんが恋しいよー。と泣くんだ。
一緒に来てくれるかい?と頼むので、自分の事よりもスバルがかわいそうになり、渾身の力で窓を開けて家を出て、スバルを追いかけた。」
そこまでキティに言ったポッポは、もしや。と思った。半分は本当に泣いていたのだろうけれど、半分は、僕を助ける演技?
ポッポはスバルに助けられて自由になったが、この醜い風貌だから、だれも撫でてはくれないし、食べ物もくれない。心までも醜くなりそうになる。かわいい子猫を見て
「まあ、可愛い猫ちゃん」
と、子供連れの家族は足を止めてだっこするのに、ポッポを見ると、
「汚い、触るんでない、病気がうつるよ。」
と憎しみの眼差し。ひどいときは、蹴られたり、水でっぽうで水攻めにあったりする。生きてる資格ないよとも言われる。人を疑わないスバルは人の足に寄り添って頬をすりすりさせて、喉を鳴らしているが、怒る人や嫌がる人は誰もいない。それを見ていると,羨むより自分が情けなくて、どうして自分はこんな運命なのだろうと悲しくなり萎縮してしまうのだ。。
スバルはポッポに
「僕は花さんに大きな愛情をたくさん貰った。誰の事も恨まなくて済んだし、愚痴を言う必要もない。君は、やっと自由をつかんだのに、今までと同じ心のレベルで生活していくつもりかい?僕は君が好きだよ。君は他人の痛みを知っている。」
ポッポは好きだ。などと言われたことが無かったから、素直に受け入れる事ができない。今まで受け入れて許せば、二倍になった失望が待っていたのだから。
寒い冬がやってきた。極寒の二月。
ねずみもいない。すべての猫がお腹を空かせている。生ごみをあさりたくてもカラスが恐い。
クーちゃんは、また子供がお腹にいる。こんな冬に?スバルはクロ、キティ、よたよたのポッポと一緒にエサを探しに歩く。以前エサをくれた家があるとクーちゃんが教えてくれた。
スバルが初めに偵察に行った。ベランダにパンくずが置いてあり数羽の鳥たちが食べている。スバルが近づくと鳥たちは一斉に飛び立った。スバルがベランダの手すりに手をかけたその時、手が手すりに凍りつき剥がれなくなった。氷点下二十度である。寒い上に吹雪いて来て、間もなく猛吹雪になった。
隠れていたクロ、キティ、ポッポは身動きが取れない。
スバルの体力は次第に消耗してきた。強い睡魔が襲った。
スバルは夢うつつで花さんが庭で倒れた時を思い出していた。
花さんは庭のウツギの花が白、ピンク、赤に鮮やかに見事に咲いている所に倒れた。スバルは叫んだ
「花さん、花さんー」
スバルが目を覚ますと、暖かい暖炉の前に、花さんがいつもくれたキャットフードがあった。花さん有難う。迎えにきてくれたんだね。」
スバルは、男女の争いの声で夢から覚めた。
「この猫も飼うつもり?家で二匹飼ってるだけでも大変なのに、」
「二匹飼うのも三匹飼うのも同じだって。」
「うちの箱入り猫ちゃんたちは怖がるでしょう。雄猫よ。あら、でも去勢しているわ。きっとどこかの飼い猫なのよ。きっと。」
「わかった。この猫が元気になったら、外に出してやろう。」
男女は窓の錠をガリガリひっかいているスバルに気が付いた。スバルは、ポッポの様に虐待でもされたら大変だと思って
「出してくれー、出してくれー」
と、叫び続けた。男女は根負けしてスバルを外に出した。
「また、おいでねー。」
と、男の声がした。
あれからスバルは毎日その家に通っている。その家で寝泊まりしている。食事をもらえるので体力もついて、春にはねずも鳥も捕ってポッポ達に運んだ。その家の飼い主の事をスバルはおとうさん、おかあさんと呼ぶようになっていた。お父さんと、お母さんはいつも喧嘩をしているけれど、本当は仲がとても良いのだと嬉しそうに話すので、ポッポ達も喧嘩の内容を聞くのが楽しみになっていた。
数年が経ちスバルも、クロもキティもクーちゃんも、もう年を取ってきた。
人間でいえば六十二歳くらいだ。スバルのおかげで食べ物にありついてはいる。外猫の寿命は五十才だから長生きではあるが、確実に年は取っている。ポッポはまるで猫の仙人みたいに骨と皮だけでこの世の者とは思えない変な貫禄がついてきた。
ある日スバルが血だらけで鶏肉をくわえてやってきた。
スバルは、恐怖に顔をひきつらせている。
「誰にやられたんだ。」
ポッポは昔の虐待されていた自分を思いだし、頭のてっぺんまで震えが止まらない。
「人間だ」
「やはりそうか。」
「生ごみをあさっていたらやられた。」
「もう家からは出してもらえないかも知れない。今度ケガをして帰って来たら外には出さないとおとうさんに言われていた。」
「スバル帰るのか?」
「僕はやっぱり人間が好きだ。寄り添う人間が必要だ」
「こんな目にあっても?」
「あの家の人たちは良い人だよ。」
「そうだな。」
その日からは、スバルは外に出ることは無かった。いや一度だけ
天気の良い日におとうさんと玄関の外にいるのを見かけた。スバルの足元はよろけて、走る力はもうないようだった。目もあの時ののギラギラしたきつい目では無く、優しい目をしていた。お父さんに抱かれると、青い空をながめ、ポッポ達を探す様子もなかった。
ポッポの方では、困った事が起きていた。二匹の雄と雌の子猫が迷い込んできた。この子猫たちも、飼い主の事情で捨てられたのだ。
ノルウェージャンフォレストキャットに良く似た長毛種である。
二匹はやんちゃ盛りで、怖いもの知らずにじゃれ回るので目が離せない。
ポッポ達は話し合って、スバルのいる家に二匹を入れることにした。
二匹を玄関の用具入れに押し込むことにした。用具入れは棚になっていて、一番下の植木鉢の受け皿が重ねて置いてある隙間に比較的おとなしい雄猫を押し込んだ。もう一匹の雌猫はお転婆でなかなか棚に入ろうとせず、ダンスを踊るように跳ねながらどこかに行ってしまった。
棚に入った方の雄猫は直ぐに飼い主に見つかり、家の中に連れて行かれた。
スバルは家に来た子猫の臭いがポッポやクロや、キティやクーちゃんの臭いだったから、事情をすぐに呑み込んだ。その時スバルはすでに歩くのも息をすることも辛かったのだが、自分でトイレを足し、食事もやわらかいのを少しだけ食べた。
子猫はよほどお腹がすいていたらしく、「此処はどこ?怖いよー。」と泣きながらも、食事を夢中で食べた。スバルはよろけながら子猫に寄り添い
「大丈夫だよ。良い子だね。」
そういって、身体をなめた。子猫はスバルにじゃれつき背中に乗ったりした。スバルは怒る事も無く子猫に寄り添った。
そして一週間後おかあさんの帰りを待っていたスバルは、おとうさんとおかあさんの腕の中で亡くなった。
人間に傷つけられた傷が悪化して亡くなったのだ。
おとうさんとおかあさんは、スバルが死んだら泣き続けるだろう、暫くは食事も喉を通らないだろうと話していたのに、この子猫のおかげで泣く暇さえなかった。
この雄猫は、レイと名付けられた。レイは食べるのが下手で、お皿から食べ物を全部こぼしてしまうし、おしっこも所構わずするので、バッグや枕、服、何もかもをビニール袋に入れなければならなかった。三ヶ月経った時に去勢の手術をしてからは、おしっこを所構わずすることは無くなった。この三ヶ月飼い主はスバルの死を悲しむ余裕は全くなかったのだ。
スバルが亡くなった事は、移動火葬車が来て、箱に入れた菊の花で飾ったスバルの亡きがらを抱えて出てきたおかあさんの姿を見たとき分かった。ポッポ達は車を囲んで陰から見ていた。火葬されて骨壺に入ったスバルに
「お前が、僕達より早く死ぬなんて思わなかった。」
「お前が一番幸せだと思っていたのに。」
「おまえは、本当は、一番さびしがり屋なのかも。」
「おまえは、一番愛情に飢えていたのかも」
「おまえが、一番綺麗な心を持っていた。」
「お前は裏切らなかった。」
「お前は、精悍だった。」
「おまえは、憎めないやつだよ。」
「お前が大好きだ。」
「スバル―!」
ポッポは声を上げて泣いた。みんなも声を上げて泣いた。
おとうさんとおかあさんが泣けなかった分だけ泣いた。
一年経って、レイの妹は厳しい冬を超えて、白い美しい毛並みも黒く汚れ、眼も攣りあがって怖い顔になっていた。ポッポ達は自分たちの限界を知っていた。身体が大きくなってきたこの子をもうかばいきれない。ポッポ達は最後の賭けに出た。
スバルが亡くなったおとうさんとおかあさんの家に、この子を
入れよう。
まずクーちゃんが玄関で
「くーくー」
と、呼びかけた。気が付いたおかあさんが
「スバルの為に買っておいたペースト状のニャグニャグが余っているからあげるわ」
と、くれた。
「くーくーと泣くから、あなたの名前はクーちゃん。」
次にポッポが玄関からちょっと離れた隣の塀に座った。
今度はおとうさんとおかあさんが気が付いた。
「ずいぶん汚い猫だなあ。目やにだらけだよ。こっちにきたら洗ってやるんだけどなあ。」
「名前、決めたわ。ポッポちゃん。スバルのごはん持ってくるから待っててね。」
「ずいぶん可愛い名前付けたねえ。」
「名前くらい可愛くいないと」
ポッポは2回もご飯をもらった。
次に、キティが玄関の階段の真ん中に座った。
「見てみろよ。この猫の背中の模様。般若みたいだね。前世でひどい目にあってその怨念。」
「まさか。この猫ちゃんはキティ。かわいい名前がいいよ。」
次にクロが家の前をうろうろ何往復もした。
「黒い猫ねえ。黒い猫は縁起が良いと言うねえ。」
「だけど、普通過ぎて面白みが無いわ。名前はクロでいいわ。」
そう、猫の名前はおとうさんとおかあさんが名付け親なのだ。
それまではみんな、ただの名無しの野良ちゃん。
「ずいぶん言いたいこと言ってくれるなあ。」
「だけど、名前付けてくれたよ。ねえポッポちゃん。」
「なんだい?キティちゃん。」
「私はクーちゃんだって。」
「僕はクロ。そのまんま。」
お互い、とても嬉しそうだ。
最後にポッポたちは女の子を連れて、家の前を歩いた。薄汚れた猫に交じってノルウェージャンフォレストキャットらしき雌猫は一際美しく輝いて見えた。
「あら、レイにそっくりな猫ちゃん。ねえ、あなたちょっと来てちょうだい。レイの親?兄弟?」
「ありゃりゃ、本当だ。こりゃ困ったぞ。飼わないわけ行かないだろう。」
「あなたねえ、うちに猫三匹いるのよ。四匹飼えるわけないでしょ。あなたのおこずかい、三万円から二万円に減らすわよ。」
「まあまあ、そのことは後で。おい、お前、入るかい?この家の子になるかい?」
玄関のドアを開けて手招きをすると、そのねこは、踊るように飛び跳ねながら家の中に入った。」
残された猫たちは、ほっとして
「これで肩の荷が下りた。」
「僕達も中に入れてくれないかなあ。」
「無理に決まってるだろう。」
「私はごめんだわ。今更家猫になるなんて。」
あれから三年、レイとキラリはとても仲良く暮らしている。
この家に初めからいる二匹の猫、ミーと琥珀とは仲良くないけれど。
あれから、ポッポ、キティ、クロ、クーちゃんの姿を、誰も、一度も見かけた者はいない。
ポッポは一〇〇歳になった。
それぞれ忙しい人生だったけど、過ぎてしまえば、一つの物語として終わる、それだけの事かもしれない。
だけど、心も体も出来上がる大切な幼少期に虐待は受けたくなかった。と、今でも思うのである。