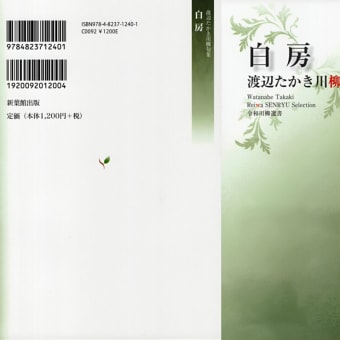□本日落語二席。
◆三遊亭遊馬「居残り佐平次」(寄席チャンネル『粋 らくご』)。
国立演芸場、平成30(2018)年12月16日(「三遊亭遊馬独演会」)。
この日の落語会は、もう一席が「品川心中(上下)」。つまり、ともに品川での廓噺という、なかなかめったに聞けない趣向であった。自分は、寄席チャンネルで両席をばらばらに録り、しかも半年ほど間隔をあけて聞いたので、せっかくの趣向はお楽しみが半減したかもしれない。
「居残り佐平次」というと、このネタの抜群のおもしろさに比して、演者が古来苦慮してきたのが落げである。本来の「おこわにかけた……ごま塩」は、語句の意味から言って現代に通じにくいのと、さほどスマートではないために、どうしても落語家としてはかえたくなるところなんだろう。
三代目春風亭柳好、九代目桂文治、柳家小三治、立川談志など、次々と独自の落げが考案され、なかには、五代目古古今亭志ん生や古今亭志ん朝のように、落げをつけないという向きもある。
自分としては、立川談志家元の、「あんな野郎に裏を返されたら……」がいちばんスマートだと思われ、もっとも好きな落げである。ただし、これは、仕込みを入れなかった場合、落語などを通じて吉原のことを知らない聞き手にはわからないというのが欠点だ。
今回、遊馬は独自に考えたと思われる落げをつけていた。佐平次が去ったあと、廓の主人が「あいつ(佐平次)が来てから、うちの売上はあがる一方だった」と言い、「残りものには福がある」で落げである。
なるほどわかりやすくはある。「裏を返されたら……」の落げに比べると、スマートさはないが、もしかすると、今後も継承されるかもしれない。
◆五代目桂米團治「本能寺」(J:COMテレビ『特別番組 桂米團治独演会』)。
大阪梅田サンケイホールブリーゼ、令和2(2020)年7月23日(「サンケイホールブリーゼ米朝一門落語会シリーズ 2020桂米團治独演会」)。
◆三遊亭遊馬「居残り佐平次」(寄席チャンネル『粋 らくご』)。
国立演芸場、平成30(2018)年12月16日(「三遊亭遊馬独演会」)。
この日の落語会は、もう一席が「品川心中(上下)」。つまり、ともに品川での廓噺という、なかなかめったに聞けない趣向であった。自分は、寄席チャンネルで両席をばらばらに録り、しかも半年ほど間隔をあけて聞いたので、せっかくの趣向はお楽しみが半減したかもしれない。
「居残り佐平次」というと、このネタの抜群のおもしろさに比して、演者が古来苦慮してきたのが落げである。本来の「おこわにかけた……ごま塩」は、語句の意味から言って現代に通じにくいのと、さほどスマートではないために、どうしても落語家としてはかえたくなるところなんだろう。
三代目春風亭柳好、九代目桂文治、柳家小三治、立川談志など、次々と独自の落げが考案され、なかには、五代目古古今亭志ん生や古今亭志ん朝のように、落げをつけないという向きもある。
自分としては、立川談志家元の、「あんな野郎に裏を返されたら……」がいちばんスマートだと思われ、もっとも好きな落げである。ただし、これは、仕込みを入れなかった場合、落語などを通じて吉原のことを知らない聞き手にはわからないというのが欠点だ。
今回、遊馬は独自に考えたと思われる落げをつけていた。佐平次が去ったあと、廓の主人が「あいつ(佐平次)が来てから、うちの売上はあがる一方だった」と言い、「残りものには福がある」で落げである。
なるほどわかりやすくはある。「裏を返されたら……」の落げに比べると、スマートさはないが、もしかすると、今後も継承されるかもしれない。
◆五代目桂米團治「本能寺」(J:COMテレビ『特別番組 桂米團治独演会』)。
大阪梅田サンケイホールブリーゼ、令和2(2020)年7月23日(「サンケイホールブリーゼ米朝一門落語会シリーズ 2020桂米團治独演会」)。