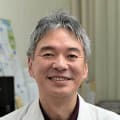記事は次のとおり。
大病院と中堅病院、収益力の二極化くっきり 帝国データ調査
http://sankei.jp.msn.com/life/body/100925/bdy1009252025001-n1.htm
2010.9.25 20:23【産経新聞】
年間総収入が30億円以上ある全国の民間病院事業者で、平成20年度までの3年間の最終損益が判明した法人のうち、3期連続で黒字を確保した法人が5割あまりある一方、3期連続で赤字に陥った法人も1割弱あったことが、信用調査会社「帝国データバンク」のまとめで分かった。赤字法人はすべて中堅事業者で、診療報酬の引き下げや特定の大病院の“ブランド化”が進んだ中、民間病院の経営で二極化が顕著となっている実態が表れた。
同社は、兵庫や岡山の大規模病院が昨年、相次いで民事再生手続きを申請したことなどを受け、医療法人や社会福祉法人、財団法人など全国803事業者の決算状況を調査した。
その結果、20年度(21年3月期)が前期より増収となったのは66%の530法人で、規模が大きい法人ほど増収の割合が高かった。
また、過去3年間の最終損益が判明した547法人のうち、3期連続で黒字を確保したのは55%の301法人。逆に3期連続で赤字だったのは8・2%の45法人で、すべて年間総収入が300億円未満の中規模事業者だった。
帝国データバンクは「長く続いた診療報酬引き下げのほか、患者の大病院志向が高まり、中規模以下の安定経営が難しくなっている」と分析している。
一方、全国に144ある国立病院は20年度、約7割が黒字を確保。しかし、地方自治体が運営する公立病院は、逆に約7割が赤字となった。
(記事ここまで)
対象は年間30億円以上の収入(収益ではない)がある民間病院事業者ということなので、中規模以上の病院ということになる。対象にならなかった小規模病院の経営状態がどうなのかは、ちょっと気になる。
それはさておき、19年度と比べて20年度が増収になったのは、規模が大きい法人に多かったと書いてある。平成20年4月には診療報酬改定がおこなわれており、記事には書いていないがそれによる影響はあるだろう。その他に日本版DPCの導入促進が進んだこと等も、大規模法人の方が増益になったことに関係があるかもしれない。
調査時点で過去3年間の最終損益が判明した547法人の中で、3期連続で赤字になったのは45法人であり、その全てが年間収入300億円未満の法人だったという。30~300億円の収入といえばもの大きい金額ではあるが、医療は出ていくお金も大きいのと、医療法で「医療は非営利である」と定められていることもあり、どの医療機関も収益(内部留保)は一般企業に比べれば非常に薄く、効率化が難しい中規模以下の病院は、慢性的に赤字になっている病院が多い。
解説記事もある。
民間病院収益二極化、診療報酬下げが直撃 “医療弱者”へ悪影響も
http://sankei.jp.msn.com/life/body/100925/bdy1009252054002-n1.htm
2010年9月25日【産経新聞】
民間の大規模病院と中小病院で、経営状態が二極化している実態が明らかになった。背景には、政府が長らく続けてきた診療報酬の引き下げによる「淘汰の誘導」や、高評価を得る優良病院への患者の集中があるとみられる。ただ、明治以来日本の医療の中心を担ってきた民間病院の減少が進めば、患者の選択肢の狭まりや、地方の高齢者など“医療弱者”への悪影響も懸念される。
厚生労働省の統計によると、平成2年に1万を超えていた全国の病院数は、22年3月末時点で約8700施設に減少した。
その大きな要因となったのが、診療報酬の改定だ。22年度は全体で0・19%の引き上げとなったものの、自民党政権が続いた21年度まで、10年連続で計7%も引き下げられた。
大阪市の中堅病院院長は「今後(診療報酬引き下げを)意図的にやれば、病院経営の淘汰はさらに進む。国は民間病院を整理し、公立病院を残すことしか考えていない」と憤る。
この院長は「僻地医療を公立病院だけで支えられるのか」と警鐘も鳴らす。実際、民間病院が破綻した地域では、公立病院も医師不足から診療科が減り、結果的に住民が地域内で必要な診療を受けられなかったり、選択肢が狭まったりするケースも表れている。
一方、都市部の大病院も安泰とはいえない。東京都心で約500床を抱えるある総合病院は、最高水準の医療体制が高く評価され、著名人も数多く利用するが、本業である医業損益は赤字で、不動産の運営益で全体の黒字を確保しているのが実情だという。
医療関係者は「模範的な医療を提供しても、赤字経営は避けられないという事実に、国も国民も気づいていない」と指摘している。
(記事ここまで)
この解説記事は、「民間病院を淘汰するような医療政策で、公立病院を優遇していると大変なことになる」という論調で書かれている。あれ?最初の記事の最後には、国立病院は7割が黒字だけど、地方公立病院は逆に7割が赤字だって書いてあったよね。ということは、大阪市の中堅病院院長は「民間病院が被害者だ」と言っているけど、地方公立病院も被害者で、国が加害者なんじゃないの?
ついでに言えば、国立病院の7割は黒字だと書いてあるが、昔あった国立病院・療養所のうち採算性の悪いところはいわゆる「国立病院立ち枯れ作戦」により淘汰されており、約4割減少した。さらに2004年から「独立行政法人国立病院機構」に移管され、2011年からは職員が非公務員型に移行するなど、どんどん絞り込まれている。そして、国立がん研究センター(旧国立がんセンター)などのナショナルセンター病院は、研究などでも日本の中心となるべき病院群であるが、どこも予算不足に苦しんでいて研究もままならず、中で働いている医師は丁稚奉公のような働きぶりを余儀なくされている。
前の記事では「民間の中では大規模病院が有利」と書いてあったが、この解説記事の後半では一番有利なはずの都市部の大病院も安泰とはいえないと書いてある。ここで取り上げられている病院が、都市部大規模病院の代表的な姿であるかどうかはわからないが、そうであったとしたら、この2つの記事を合わせると、どこでどんな医療をしたとしても医療機関の経営は厳しいということになるのではないか。
そして、今年の4月におこなわれた診療報酬改定も、プラス改定とはいうもののわずか0.19%のプラス。後発医薬品の導入促進などのマイナスを入れたら実際にはマイナス改定だといわれている(もっとも、この数字自体にあまり意味が無いのではないかという気がして、以前このブログにも書いたが)。しかも今年の改定では、大学病院など大病院が一息つけるような改定になっていて、中小病院はより厳しい経営環境に置かれている。
中小病院や診療所の医師の高齢化、経営が苦しい病院は医師不足も深刻であるなどから考えると、地域に密着して親しまれ、地域の人に頼りにされてきた医療機関の淘汰は、これからぐんぐん進んでいくのかもしれない。地域によってはすでに地域内で必要な診療を受けられないところも出てきているが、地方だけでなく都市部でもそういう地域が出てくる日も、遠くはないのかもしれない。
↓このメアド欄はセキュリティが低そうなので、書かない方が無難です↓
最新の画像もっと見る
最近の「ニュースへコメント」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事