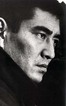● 人間は、生まれたときから「美意識」を持っているのだそうだ。
ところが、その美意識を大人になって失ってしまうのは何故なのだろう。
思うに、「美」は「魂」によって左右されるのだ。
子供の清らかな魂は、吸い取り紙のような感性を持っている。
人間の世界の様々な出来事を取り込む。
その結果、逆に本来の「美意識」を忘れてしまうだろう。
● 少年老い易く 学なり難し
一寸の光陰 軽んずるべからず
時は移ろい悠久の流れは、水の流の如く止まることなし。
既に、光陰人生の旅は、「 白秋 」も半ばを迎える。
「少年老い易く」は夢現のうちに過ぎ、真実を実感する。
「学なり難し」は更に真実と知り、己の非才と未熟を嘆く他なし。
「一寸の光陰」を思えば残光わずかなり。その先は無限の闇か・・。
「軽んずるべからず」と知るも、志に反し意のままにならず。
われ至りて、「棺覆っても定まらず」との予感に心定まらず。
この先に続くは、遙かに遠い「1人旅の細き道」なり。
風は枯葉を巻いて胸に吹き。心細さこの上なし。
振り返る昔は「後悔」と「無念」の夢跡。
願うは、いつの日か顔知らぬ父母に会えることのみ。
心は寒く、体は冷たく、傷は更に深く悲しけれど。
今しばらくの生命の炎を燃やさん。
われは我なり、他人にあらず。老兵なれど未だ枯れず。
独りなれど、最後の気力振り絞って道を歩かん。
道に光を、1杯の酒、花1輪は見果てぬ夢か・・。
● 人間は自然界の一部の存在である。
人間そのものも、大いなる自然だが、自然そのものに矛盾ははない。
だが、自然を自分なりに解釈しようと考えると、頭の中に矛盾が生じる。
果てはパニックになってしまい、何がどうなのか結論が出せないままでいる。
結局のところ、自分の頭の程度では理解できない。
いうなれば、自然とは、「コスモ(秩序)」の反対の、「カオス(混沌)」だと云う他はない。
● 願わくは 花の下にて春死なむ その如月の 望月の頃
西行法師(1118-1190)
平安末期から鎌倉初期の歌僧で俗名/佐藤義清(のりきよ)である。
もと北面の武士で23歳で謎の出家、陸奥から四国・九州まで諸国を旅した。
述懐歌にすぐれ「新古今集」では最高の94首が入集している。
家集「山家集」、聞書「西公談抄」がある。
「撰集抄」は仮託だが後世の西行観に大きな影響を与えた。
西行は、如月(2月)の望(もち)の日・15日の満月の頃、花(山桜)の下で、
死にたいと願い、この歌に心を込めた。
陰歴2月は現代の中春の頃に当たる、桜の季節である。
又、2月15日(望の日)はお釈迦様の「入滅の日」でもある。
西行は、建久元年(1190)2月16日願い通り没している。
河内の国(大阪府南河内郡)の弘川寺で、享年73歳の生涯を終えた。
西行の願いの通り、河内の国は、絢爛たる桜の満開の頃であったことだろう。