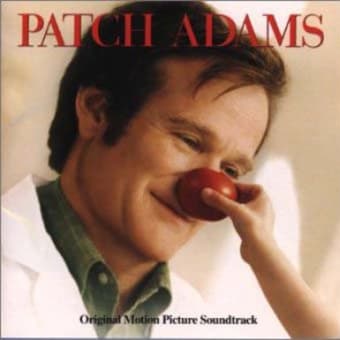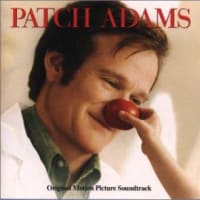この写真は建国前のエルサレムにあるBab-es-Silsilehと呼ばれるものでHerod's Templeへの西の入り口の門である。反対側にある泉はベツレヘム近くのソロモン(管理人注:ソロモンはダビデとバテシバの間に生まれた二人目の子ども)の池からの水を水源とする。この門の左はダヴィデ街でありエルサレムで最もにぎわいをみせる。
『旧約聖書はどこもおもしろい。いや、考えさせられる。モーセの出エジプトやノアの洪水やソロモンの伝説のように、歴史と虚構がどのように交じったかを読むのもスリルがあるし、ユダヤの預言文学のレベルを他の古代宗教とくらべるのも興味が尽きない。イザヤ書・エレミア書・エゼキエル書を読んだときは、「そうか、これがユダヤの言霊か」と合点した。
その一方、約束の地カナーンを誓った民族共同体イスラエルがどのようにユダヤ民族のなかの理念として定着していったかとか、古代ヘブライ社会やヘブル語がどんな表現レベルをもっていたのかということを見るのも、興奮させられる。しかし、文学的にも哲学的にも、また神学的にも心理学的にも共通する深さをもつ問題を鋭く提示しているところというと、なんといっても『ヨブ記』なのである。ゲーテはこれをもとに『ファウスト』を発想したし、ドストエフスキーはここから『カラマゾフの兄弟』全巻を構想した。』(松岡正剛氏の「ヨブ記」から)
ヨブ記とは
ヨブへの答え オリーブの木
ヨブへの答え 全能者よ,わたしに答えよ!
ヨブへの答え 知恵の女神ソフィア
ヨブへの答え 神の非道
ヨブへの答え 教会と精霊の答え
話のついでですが......
「バビロンあるいは,バビロニアはバグダッドの南方約90キロの地点にユーフラテスをまたいで広がる。長谷川三千子氏はこう指摘している。「カナンの地」は,イスラエルの民にとって,故郷と呼ぶべき類の地ではなく,そもそも,それは事実の上から言っても,彼らの故郷ではなく,それは,カナンの人々(注:現在のパレスティナ)が住みつき,根づいた土地なのである。
イスラエルの民の「カナンの地」との関係は,徹頭徹尾ヤハウエ神に依っている。この地はヤハウェ神によって示され,命じられ、約束されたことによってのみイスラエルの民と結びついているのであり,それ以外の形で結びついてはならないのである。......ヤハウイストの生きていた時代と推定される起源前十世紀頃という時代は,ティグリス川上流の二ムロデやコルサバードに発掘されたジグラドは,ちょうど紀元前十世紀,九世紀ごろに新築または再興されている。広い意味では,ヤハウイストはまさにジグラトと同時代の人間だったのである。」とまあこんなことで。
白痴の第2編第4でムイシキン侯爵は言っていました.....宗教的感情の本質というものは、どんな論証にもどんな過失や犯罪にも、どんな無神論にもあてはまるものじゃないんだ。そんなものには、何か見当ちがいなところがあるのさ。いや、永久に見当ちがいだろうよ。そこには無神論などが上っ面(うわっつら)をすべって永久に本質をつかむことができない、永久に人びとが見当ちがいな解釈をするような、何ものかがあるんだ......,と。永久に見当違いで人は一生を送るのです(爆)。この世に実体というものはありませんから,はい。」
松岡正剛・金と魔術から
『ドイツの小都市シュタウフェンの市役所の広場のそばに「獅子亭」がある。1539年、この宿泊レストランで特筆すべき死亡例があったことが建物の外壁に告知されている。こういうものだ。
「西暦1539年、この獅子亭においてファウスト博士なる奇妙な黒い魔術師ありて、悲惨なる死を遂げたり。ファウスト博士なる男が存命中、ひたすら義兄弟と呼びし悪魔の長の一人メフィストフェレスなる者が24年間にわたる契約の切れし後、ファウスト博士の首の骨をばへし折り、その哀れなる魂を永劫に地獄に引き渡せりと言い伝えらる」。
16世紀ヨーロッパに出入りしていたファウスト伝説がどういうものであるかは諸説があるが、ファウストが「黒い魔術」すなわち「錬金術」に長けていたことだろうことは、どの伝説にも共通する。「人造の金」の精錬に夢中になって各地を渡り歩き、その魔術的技能を吹聴してさまざまな貴族にその腕を信じこませていたらしいことも、各種ヴァージョンが伝わっている。シュタウフェン男爵が手元不如意になったときも、ファウストは自分の錬金術が役立つと信じこませていたらしい。
シュタウフェンはファウストが死んだ(殺された)とされる土地である。そのためその後、ファウストをめぐる噂はさまざまに尾鰭をつけ、人々はこの男を悪魔メフィストフェレスと契約を結んだファウスト博士として結像させていった。
ファウスト伝説が最初に書物になったのは、1587年にフランクフルトで出版された『ヨハン・ファウスト博士の歴史』だった。斯界では通称「ファウスト本」とか「ファウスト・ヒストリア」と呼ばれる。ヒストリアとは「事実にもとづいた歴史」のことをいう。この書物を印刷・出版した業者がヨハン・シュピースだということもわかっている。
この「ヒストリア」のなかでは、ファウストはワイマール近郊のロート村に生まれたことになっている。敬虔な農民の子だったらしく、ウィッテンベルクの富裕な伯父のもとに引きとられると、学生時代をへて順調に神学博士となったのだが、やがて心変わりして魔法や魔術の研究に傾斜していったとある。
ついで神学者から転向して医学博士を名のり、各地を訪れては万能医者としての治療や助言にあたるうち、想い深まってある森で悪魔を呼び出すことにした。おそらく験霊(ポルターガイスト)に挑んだのである。
首尾よく悪魔の霊が呼び出され、何度かの会合を重ねるうち、この霊はその名をメフィストフィレスと言い、大悪魔ルシファーに仕えるガイスト(霊)であることがわかった。メフィストフィレスとはどうやら「光を好まない者」という意味だった。
それが気にいったファウストはメフィストフィレスと契約をしたいと言い出し、もし自分の欲望が叶えられればキリスト教も知識も拒否し、メフィストフィレスに自分の生涯を提供すると申し出た。何かと引き替えに魂を売ったのだ。かくてここにファウストと悪魔の代理人との前代未聞の契約が結ばれたのである。
ファウスト伝説には、そのほかいろいろのエピソードが交じっていく。曰くニュルンベルクで錬金術師として活躍した、曰くフランクフルトの見本市で貨幣の両替を繰り返していた、曰くバンベルクで魔法でこしらえた豚を売った、そのほか云々侃々諤々。
さて、いまさらいうまでもなく、このような話の展開をもつファウスト伝説が、その後、ゲーテ(970夜)のレーゼドラマ『ファウスト』の下敷きになったわけである。
しかし、ゲーテは伝説を下敷きにはしたものの、『ファウスト』をかなり独特の物語にしていった。ゲーテが生涯にわたって抱えたテーマのすべてを注ぎこもうとしたからだ。そのため1773年に着手していながら、死ぬ直前の1831年までの60年を費やしたほどだった
今夜は『ファウスト』を案内するところではないので、詳しいことは何も書かないが、ゲーテがファウストという主人公に何を託したかという仕込みは肝腎な点なので、かんたんに言っておく。
ゲーテはファウストを、哲学・法学・医学・神学を研究しつづけながらも“学問と現世の空虚”にたどりついてしまった学者として設定した。
そして、そのファウストが自身の可能性に失望して一度は毒杯を手にするものの、その瞬間に反転して「さらなる尊大」に向かって自己の極大に酔いたくなったというふうに、話をつくった。
ファウストが至高の存在に向かって「不遜な実験」にとりかかり、神秘や魔法の世界に入って「自身の偉大な証明者」になろうとしていると、設定したわけだ。
で、それでどうなったのか。そうした不遜なファウストのところへ、黒犬に姿を変えたメフィストフェレスがやってくる。やがてその恐るべき全容をあらわすメフィストに、しかしファウストはほとんどたじろがない。それどころか、自分の野望は尋常一様なことでは成就しがたいと思っていたので、メフィストの登場は渡りに舟だったのである。
こうして、かの難解きわまりないファウストとメフィストフェレスの問答になっていくのだが、あれこれの挙句、メフィストが「賭け」を持ち出し、ファウストがその悪魔との「契約」に挑むというふうになっていく。メフィストが「私があなたの家来となって願いを叶えるから、あの世では逆の関係にしよう」と持ちかけると、ファウストは死後のことなどどうでもいいので、「おまえが私を納得させ、満足させたなら、私は最後を迎えていい」と言う。そういう危険な内容の契約に変えるのだ。
ついでにそのあとの展開を書いておくと、ファウストとメフィストの契約が成立すると、手初めにメフィストはファウストを見ちがえるように若返らせ、少女グレートヒェンに惚れさせる。グレートヒュンは本名をマルガレーテといった。
970夜にも少々説明しておいたように、グレートヒェンはどんな器用なこともできない少女だが、愛することだけを知っている。そういう可憐な少女だった。ファウストは恋に落ち、胸を焦がし、その本来の活力を失っていく。辛うじてメフィストのはからいで結ばれるのだが、それならその愛でこそメフィストの契約を破棄できたはずなのに、ファウストにはもはやアニメーション(アニマ・モーション)がエマネーション(流出)につながらない。
そうこうしているうちに、この関係を責めるグレートヒェンの兄がファウストの手にかかって死んだ。一方、グレートヒェンは眠り薬の量を誤って母親を殺してしまう。それどころか、ファウストとのあいだに生まれた子を水没させて殺し、牢屋に入れられ獄死する。
茫然とするファウストをメフィストはハルツ山地のブロッケン山の「ワルプルギスの夜の宴」に連れ出し、なにもかもを忘却させようとするのだが、ファウストにはグレートヒェンの面影がどうしても消えない。事態はしだいに行き詰まってくる。
その後、ファウストはしばらく落ち着きを取り戻すのだが、そこへメフィストがまたまた罠をかけ、ファウストは美女ヘレナと恋に陥り、二人のあいだに男児オイフィリンが生まれる。詩の化身となったオイフィリンが地下世界に行くと、ヘレナもこれを追う。この先の話はおもしろいのだが、また、省略しておこう。
ファウストはいつしか100歳になっていた。それでも最後の命の火を燃え上がらせて、新たな社会の建設に立ち向かう。もはや魔術の力を借りるまでもない。メフィストを振り切るかのように、「止まってくれ、おまえは実に美しい!」と叫ぶと、ついに最期を迎える。
ニヤリと笑ったメフィストは契約に従ってファウストの霊を手に入れようとするが、天使たちがこれを阻み、墓の中のファウストの魂はグレートヒェンの霊に導かれて天高くのぼっていく‥‥。』以下略.....
【参考情報】
(1)ファウスト伝説は「ファウスト・ヒストリア」以降、ゲーテ以前にも、ゲーテ以降にもさまざまな物語になっている。たとえばクリストファー・マーロウの『ファウスト博士の悲話』(1588)では、ファウストは悪魔と結んで科学の権化に向かっていくという物語になり、レッシングの『ファウスト博士』では理知を昇りつめたファウストは魂の救済力をもったともされた。
しかし最も特異なのはトーマス・マン(316夜)の『ファウスト博士』で、ぼくはこれには脱帽した。参った。次項(2)にかんたんな案内をしておく。驚かないように。
(2)トーマス・マンの傑作『ファウスト博士』(1947)には副題がある。「一友人の物語るドイツ作曲家アドリアン・レーヴァーキューンの生涯」だ。これでわかるように、この物語は音楽家の壮絶な宿命を友人が語っているという体裁をとる......と松岡氏は語っているが管理人の関心はトーマス・マンがゲーテの死後100年にあたる1932年3月21日に,ワイマール市の公会堂で行われたとされるマンが58歳の時の講演記録「作家としてのゲーテの生涯」の方にある。次の記事で要約してみよう。

松岡正剛のフリーメーソン
ベートーベンの『第九』の第4楽章「合唱」はシラーのオードの言葉でできている。シラーがクリストフ・ケルナーのもとに身を寄せていたときに、フリーメーソンの精神を讃えるために書いたオードだった。
ベートーベンもフリーメーソンに好意をもっていたが(本書では会員だということになっている)、モーツァルトはおそらくメーソンそのもので、父やハイドンにフリーメーソン入会を勧めただけでなく、『魔笛』全曲をフリーメーソンの精神の表現だとみなしていた。
モーツァルトだけではない。音楽家でいえばリスト、シベリウスから現代ジャズのカウント・ベイシー、デューク・エリントン、ルイ・アームストロングもフリーメーソンだったようだ。 本書の巻末に載っている興味津々の「フリーメーソン人名録」によると、フリーメーソンの歴史を知らない者には驚くべき人物の名が次々にあがっている。
その一部を掲げると、たとえばモンテスキュー、ヴォルテール、サド侯爵、メーストル伯爵、カサノヴァ、ゲーテ、ヘルダー、ラクロ、レッシング、アレグザンダー・ポープ、ウォルター・スコット、フランクリン、ジョージ・ワシントン、ハイネ、ジェンナー、ステファヌ・マラルメ、モンゴルフィエ兄弟、ジュール・ヴェルヌ、オスカー・ワイルド、コナン・ドイル、マーク・トウェイン、ジョルジュ・デジメル、シャガールらもフリーメーソンだったということらしい。
うーん、ハイネ、マラルメ、ワイルドもそうなのか!
フリーメーソンについては誤解が渦巻いている。ぼくも何が本当なのか、さっぱりわからない。だからここでは本書に書かれたこと以外はいっさい触れないことにするが、「この本は堅い」と評判の本書だって、すべて"事実"が記述されているのかどうか、ぼくにはまったく保証できない。
しかし、フリーメーソンがヨーロッパの職人幻想と理神主義と共同体思想とを動かしてきたことは、誰しもが認めるところである。問題は、むしろなぜ誤解に包まれたのかというほうにある。
フリーメーソンの起源は14世紀を溯らない。
それ以前にも何かの前身があったと思いたいところだが、せいぜい鏝と直角定規とコンパスを重視する石工(メーソン)を中心とする職人組合があったということだけで、それ以外のことはわからない。
おそらくフランスの記録にのこる「巡歴職人団」のようなものがどこかで職人組合と重なってきたのであろう。だから、グノーシスやカバラや、テンプル騎士団やヨハネ騎士団とフリーメーソンをつなげる線はまったくないと見てよいらしい。 だいたいフリーメーソンはアングロサクソン起源なのである。ここから「実践フリーメーソン」とよばれる集団が生まれていった。かれらは長きにわたって書き継いだ『古き義務』という規則書兼祈祷書兼伝説集のようなものをもっていて、それが何度も断片的に写本されて各地に伝わった。
その、各地にできた拠点を「ロッジ」とよび、ロッジに登録されたメーソンを「公認メーソン」とよぶ。ロッジの活動がしだいに異なってくると、1717年にロンドンの4つのロッジの代表者が集まってロンドン・グランドロッジを設立した。1723年には「フリーメーソン憲章」も発表する。これがのちにエイシャント・グランドロッジ(古代派)とよばれる潮流で、のちの「近代派」と対立したらしい。二つの和解は1813年のことだったという。すなわちオベディエンス(分派)時代である。
このイギリスのロッジのうち、フランスに流れてきたフリーメーソンがある。これがのちに「思弁フリーメーソン」とよばれる流れで、折からのヴォルテールらの啓蒙主義に縦横に結びついた。フリーメーソンの活動が爆発していくのはここからである。
したがって、本書でもしばしば注意書きが出てくるのだが、フリーメーソンは錬金術とも薔薇十字運動ともほとんど関係がなかったということになる(ポール・ノードンの『フリーメーソン』ではヘルメス思想や薔薇十字思想とフリーメーソンは関係をもっていたとされている)。
それでもフリーメーソンが誤解されたのには、いくつかの理由がある。第1には、その参入儀式のせいである。イニシエーションとよばれる。実際にはレセプションという程度のものだと本書では解説されているが、外からみればイニシエーションが秘密結社特有のものだろうという感想になる。
第2にはフリーメーソンが誤解されるのは、エルサレムの神殿を起源とする神殿幻想や各地のロッジの象徴的装飾性などにみられるように、視覚的シンボルを重視するところにある。本書にはそうしたシンボルが所狭しと挿入されていて、それらを見ているとフリーメーソンが秘密結社で神秘主義に酔っているとしか見えなくなってくる。
第3に、フリーメーソンは誰がメンバーであるかということを長らく公表してこなかった。むろん自分からも言い出さない。これはどうしても怪しく見える。日本でいえば西周や津田真道がオランダでフリーメーソンに入会しているのだが、このことは多くの日本人にとっては未知なことなのである。
これだけ揃えばフリーメーソンに関する噂はいくらでも飛び火する。どうもフリーメーソン側もこのような噂が出ていくこと自体を放っておくようなところがあった。
ところが20世紀になって、フリーメーソン側もそうもしていられなくなったのである。
フリーメーソンが現代社会のなかで、ある程度明白な活動を見せるようになったのは、ヒトラーやムッソリーニやフランコがフリーメーソンの活動を禁止しようとしたからだった。フランコ時代にはかなり処刑者も出た。
こうしてフリーメーソンは第二次大戦後は活動の一部をおもてに出すようになってきた。集会もニュースになった。1971年のパリ・コミューン100周年記念開放白会、1987年にミッテラン大統領がエリゼ宮にフリーメーソン代表団を迎えて演説をしたことなどは、かなりよく知られたニュースであった。ちなみにミッテラン大統領はフリーメーソンにかなり親近感を抱いていたようで、本書によると、エマニュエリ社会党第一書記、デュマ外務大臣、ジョックス国防大臣などの側近がフリーメーソン会員だったらしい。
いま世界中には約800万人ほどのフリーメーソン会員がいるという。これからフリーメーソンがどんな活動をするのか知らないが、そろそろ日本でもフリーメーソン情報が解禁されてもいいようにおもわれる。
ところで本書は「知の再発見」双書のうちの一冊である。ぼくはこの双書が好きで、翻訳が出る前に目ぼしいものはフランスからとりよせていた。
いまは戸田ツトム君の念入りのレイアウトによって大半が日本語で読めるようになっている。手軽な双書であるけれど、その図版の選択の精度、一定の叙述水準、資料の提示の仕方など、かなり編集的な充実がはかられている。お薦めだ。
参考¶フリーメーソンについては怪しげな解説書も少なくないが、以下のものはなんとか読める。ただし各書ともに少しずつ"事実関係"が違っているので注意。ポール・ノードン『フリーメーソン』(白水社文庫クセジュ)、マンリー・ホール『フリーメーソンの失われた鍵』(人文書院)、吉村正和『フリーメイソン』(講談社現代新書)、湯浅慎一『フリーメイソンリー』(中公新書)、W・カーク・マクナルティ『フリーメーソン』(平凡社「イメージの博物誌」)、キャサリン・トムソン『モーツァルトとフリーメーソン』(法政大学出版局)など。
ベートーベンの第九とFEMA CAMP
松岡氏は本の中の知識だけなのでフリーメーソンはそんな生やさしいものではない。
NEW WORLDへの序章