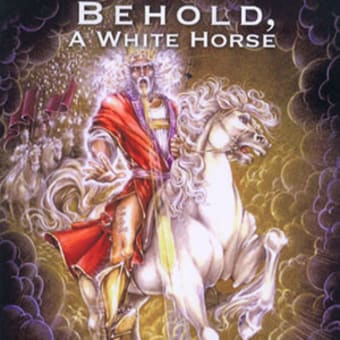http://blogs.yahoo.co.jp/alternative_politik/30408045.html
約束の地・・・
アブラハムが神に導かれた土地・・・
モーセがイスラエルの民をエジプトから連れていこうとした土地・・・
エルサレム、エリコ、ベツレヘム、ヨルダン
これら聖なる地すべて・・・
レバノン在住の学者カマール・サリービーによれば・・・、
2000キロも南、サウジアラビアの西・・・
アシール地方に存在する地名であるという。

旧約聖書が語る神に選ばれし民族の物語は、
今日のイスラエルではなく・・・
モーセの後継者ヨシュアが占領した約束の地も、
パレスチナではなくアシールであり、
ダビデとソロモンはアラブの王であり・・・
彼らの聖なる地エルサレムは
メッカとイエメン北部の間にある紅海沿岸地域、
アッシール地方であったというのだ。
本シリーズはカマール サリービー著の「聖書アラビア起源説」を検証するものなのだが、彼の著書の内容について少し触れておく必要があるかもしれない。
彼の主張のバックボーンは、「地名」だ。
旧約聖書に記載されてある800以上もの地名のうち、ほぼ大部分がアラビア半島南西部で発見することができるという。それもただ、同じ名前・由来の名前があるのではなく、物語の関連、旅の行程などを照合した時の関連性もある。その半面、パレスチナに確認できる地名はごくわずかで、物語の中での説明と現実の地理との照合には困難を有するものばかりだという。
これまで数多くの聖書学者が古代イスラエル王国の痕跡や旧約聖書の軌跡をパレスチナに探してきた。
しかし、これまで何一つ決定的となる証拠を見つけることは出来なかった。
なぜか?
サリービーはこう言うだろう。
間違った場所を探しているのだよ・・・ と。
では、間違ってしまった原因は何か?
それはヘブライ語が間違って翻訳されたからだ。
議論を進める前に、「翻訳の問題」が登場するので、少し「聖書アラビア起源説」から引用しよう。問題の発端は、そもそも子音文字で書かれたヘブライ語の聖書に対し、後世の人間が間違った形で母音付加を行ったために起きたことにあるという。
私の論旨は、ヘブライ語聖書が、今まで一貫して誤って解釈され続けてきたのではないかという考えのうえに成り立っている。
(中略)・・・ヘブライ語は、紀元前5、ないし6世紀頃に、日常語として使われなくなった。そのため、ヘブライ語聖書を理解するためには、伝統的なユダヤ教の聖書解釈を受け入れるか、あるいは、ヘブライ語に密接な関係をもつ現存のセム語から手引きを得るか、のいずれかしかない。現存のセム語には、アラビア語とシリア語(現代シリア語)があるが、後者は古代アラム語の名残である。P21
(中略)
前述したように、初期の形態のヘブライ語聖書は、子音文字で綴られたものであった。それは西暦6世紀頃から9世紀もしくは10世紀にかけて、当時パレスチナやバビロニアのマソラ学者が考案した独特の母音記号によって音読できるものとなった。これはいいかえると、この母音付加を行ったマソラ学者たちが、1000年以上にわたり話されていなかった言語を再建した、ということである。彼らは自らの母国語がアラム語かアラビア語かにかかわらず、知識のおよぶ限りにおいてその母音付加を行った。P60-61
しかし、この問題は聖書だけにとどまらない。楔形文字で記録されたバビロニアやアッシリアといったオリエント世界の記録も、聖書の記述に適合させるように解釈され、都合の悪い記述に関しては無視されてきた。
サルゴン2世の軍事遠征
一般的な歴史では、例えばサルゴン2世はシリア方面に軍事遠征を展開し、「紀元前721年にはイスラエル王国(オムリ朝)を滅ぼしてその上層民を帝国各地に強制移住させ、他の地方の住民をイスラエルに入植させた(ウィキペディア)」というものである。

旧約聖書の「列王記」には、イスラエル王国を滅ぼしたのは「アッシリアの王」としか書かれておらず、シャルルマネセル5世であったようにも記述されている。旧約聖書外典トビト書では、シャルマネセル5世の時に捕囚があったと記されているそうだが、現在も議論を呼んでいる。
しかし、サリービーは、著書「聖書アラビア起源説」にて、実際にアッシリア軍は
「タイマーを通り南西アラビア半島のアシール地方を攻めた」
・・・という主張を展開している。
たとえば、そのほんの一例が、サルゴン2世の地名表の冒頭部分である。そこではこのアッシリアの王は自らを「サ・ミ・リ・ナ(smrn)と全ビト・フ・ウム・リ・ア(hmry)の征服者」と称している。しかしこれは、「サマリア」(ヘブライ語でsumrwn)、「オムリ」(ヘブライ語のmry)の家を指すものではない。もちろん、アシールにはオムリのイスラエル王国が存在していたし、その地方には聖書にあるなそのままの地名「サマリア」が今日も残っている。
実際にここで述べられているのはジーザーン地方のジャバル・ハループにあるアッサルマイン(srmyn)と呼ばれる村であり、アブー・アリーシュにあるヒムラ-ヤ(hmry)という名の村である。
この文献には、さらに多くの地名があげられており、このことからサルゴン2世が、地理的な区分としてのアシール全域、すなわちターイフからイエメンの国境地帯にまでおよぶアラビア半島西部全域を支配していたことは明らかである。

たとえばジーザーン地方では、王は「ムス・ク(msk)の王、ミ・タ・アを追い払った」とあるが、ここでいわれている場所は、アブー・アリーシュの東、アーリダ丘陵地帯にある村落ムスクー(msq)のことである。
リジャール・アルアマでは、王は「アス・ドゥ・ドゥ(sdd)を略奪した」とあるが、ここで語られているのは、「南部人」(聖書では「ベニヤミン人」と呼ばれ、アラビアの古典詩ではバヌー・ヤーミン(ymn)とうたわれている)のことである。この人々は、「海」(ym)に住んでいたのではなく、ワーディ・ナジュラーンから広漠たる砂漠にかけて広がるヤーム(これもym)という地域に住んでいた。
さらにターイフ地方で、王はム・ス・リ(msr)とラ・ピ・フ(rph)を「うち破った」とあるが、これはそれぞれ今日のアール・マスリー(msr)とアッラフハ(rph)のことである。このほかにも王は「タ・バ・リ(tbl)」のすべてを皆殺しにした」とあるが、これは今日のワーディ・タバーラのことであり、ヒ・ラク・ク(hlk)は今日のアルハリーク(hlq)を指すのである。それからその近くで、王は「ハ・ザ・アト・ア・ア(hz`t)の王ハン・ノを、捕虜にすると宣言した」ともある。
この ハ・ザ・アト・ア・アは、これまで「ガザ」(ヘブライ語ではzh)を指すものと考えられていた。しかし、それはフ・ウム・リ・アがオムリ(mry)を指すのと同じくらい筋道のとおらない解釈である。実際には、その語が指すものは、古代アラビア半島西部の一部族フザーア(hz`t)であり、この部族の末裔は、今なお彼らの本来の故郷である南ヒジャーズ地方(メッカからターイフにかけて)に住んでいる。
さらにこのフザーアの領域から南へおよそ200キロ行ったところで(「七日間の行軍で」という刻文から算出)、サルゴン2世は、「イ・ア(`y`)」の国の7人の王を服従させた」とあるが、この場所は、アシール沿岸地方にある今日のワーディ・イヤーア(`y`)である。
このように、地表名にあるいくつもの地名が、そのままアラビア半島西部に残っているのに、どうして学者たちはその地名表が、アッシリアによるシリアとパレスチナの征服の記録であるという考えに固執するのであろうか。シリアとパレスチナには、そうした地名はどこにもないのである。
ふむ。
『聖書アラビア起源説』では、サバ王国とアッシリアの朝貢関係については取り上げていないのだが、時代的にはアッシリアとサバ王国の朝貢関係についても説明がつくと思うのだが・・・。
次はサバ王国の方・・・に目を向けてみよう。
http://blogs.yahoo.co.jp/alternative_politik/30423248.html
前回の記事の最後に次はサバ王国の方・・・に目を向けてみよう
・・・と書いたのだが、その前に寄り道しようか・・・。マタ…
新アッシリア時代のサルゴン2世の遠征が、「聖書アラビア起源説」の著者サリービーの言う通りタイマーを通って南西アラビア半島のアシール地方を攻撃したのであれば、動機は説明できるだろうか?
旧約聖書にはサルゴンの名が一度だけ登場する箇所がある。イザヤ書第20章1節だ。
「アッシリヤの王サルゴンによって派遣された最高司令官がアシュドデに来て、アシドドを攻め、これを取った年」
これは一般的には紀元前711年頃にサルゴン2世がパレスチナで起こった蜂起を鎮圧する際、反アッシリヤ同盟に加わったアシドドを、最高司令官を通じた報復攻撃によって、滅ぼしたとされている。アシドドという土地は、ヨシュア記第13章3節によれば・・・
ペリシテ人の土地の一つだ。
エジプトの東のシホルから北へのびて、カナンびとの属するといわれるエクロンの境までの地、ペリシテびとの五人の君たちの地、すなわち、ガザ、アシドド、アシケロン、ガテ、およびエクロン。(ヨシュア記第13章3節)
従来推測されているペリシテ人の町の位置
旧約聖書では、士師の時代から王国の時代まで、この地でイスラエル人と永遠の敵であるペリシテ人との激しい戦いが繰り広げられる。しかし、結局のところ彼らがどこからやってきて、どこへ行ったのかは定かではない。
サリービーは著名な聖書学者K・A・キッチンの言葉を引き合いに「ペリシテ人とは、旧約聖書に出てくる民族のなかでは、最もなじみの深い存在でありながら、同時に最も正体の分かりにくい民族でもある」と述べている。
このペリシテ人は聖書中のいくつかの章句には「ケレテ人(krty)」としてあらわされている。そのため、ペリシテ人とはかつて地中海のクレタ島に住み、後のパレスチナの西南部を制圧して、そこに住みついた謎の「海洋民族」であるという説が信じられてきた。
ラムセス三世の治世(紀元前1186年~紀元前1155年)には「海の民」と戦争が勃発しており、その「海の民」と呼ばれた連合軍の参加民族としてチェケル人、シェクレシュ人、デネン人など伴にペリシテ人とみられる民族(Peleset)が述べられている。

旧約聖書の世界において、彼らはどんな民族だったのか?
ここで、契約の箱の物語と巨人兵ゴリアテと戦ったダビデの物語を紹介しておこう。
契約の箱
モーセの十戒が刻まれた石板が収められている契約の箱は、映画「インディージョーンズ 失われたアーク」でも取り上げられた。この映画の最後のシーンで、ナチス軍が今や契約の箱の蓋を開けようとする時に、インディーは昔の恋人マリアンに言う。
「絶対に目を開けちゃだめだ!
時代は紀元前11世紀頃、イスラエルの地に若き士師(民族指導者)が誕生した。彼の名はサムエル。彼は幼いころから契約の箱があるシロの祭司エリに仕え、寝床にあって神の言葉を聞き、そして成長して主の預言者として認められるようになった。
ある時、イスラエルの民は理由もなく隣国ペリシテに戦争をしかけ、逆に約4千人が討ち死にするという事態になってしまう。大敗を喫したイスラエルの長老たちは話し合い、シロから契約の箱をもってくれば神の力が得られるだろうと、使者を送り契約の箱を運ばせた。
契約の箱がイスラエル軍の陣営に到着するとペリシテ軍は動揺した。この時「イスラエルの全軍が大歓声をあげたので、地がどよめいた。」と記録されている。
しかしながら、逆にペリシテ人は一致団結し、最後までイスラエルと戦うことを決意した。
その結果、イスラエル軍は再び大敗し、今回は戦死者3万を数えただけでなく、「契約の箱」をペリシテ人に奪われてしまった。
ペリシテ人を検索すると....(身長が3メートルもあったそうだ)
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%9A%E3%83%AA%E3%82%B7%E3%83%86%E4%BA%BA&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=

ペリシテ人はさっそく奪った契約の箱をアシドドという都市に運び、ダゴン神殿に納めたとされる。
管理人注:聖書ものがたり・サムエル記
http://angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/134.html

『「主の箱」はサミュエル記の時代ペリシテ人によって返還されキルヤルト・エアリム(Kirjath-Jearim)のエルサレムから9マイルにあるアブ・ゴシュ(Abu Ghosh)の村にあるアビナダム(ABINADAB)の家に運ばれた。』

『Jaffaの南,アシュケロン(Askelon)の北からほどなくのところに地中海からわずか3マイルのところにアシュドト(Ashdod)の村がある。「ペリシテ人は神の箱を奪い,エヘン・エゼルからアシュドドへ運んだ。ペリシテ人は神の箱を取り,ダゴンの神殿に運び入れ,ダゴンのそばに置いた。(サミュエル記Ⅰ第5章1~2節)

『ダヴィデはそれらを脱ぎ去り,自分の杖を手に取ると,川岸から滑らかな石を五つ選び,身につけていた羊飼いの投石袋に入れ,石投げ紐を手にして,あのペリシテ人に向かって行った。(サミュエル記Ⅰ第17章40節・ダヴィデとゴリアト)』
ダヴィデとゴリアト
http://megalodon.jp/2009-0318-0311-45/angel.ap.teacup.com/gamenotatsujin/316.html
『ダゴン(Dagon)は、古代パレスチナにおいてペリシテ人が信奉していた神。名前の由来はヘブライ語のダーグ(魚)ともダーガーン(穀物)ともいわれる。 父親はエル。伝承によってはバアルの父とされる。魚の頭をもつ海神と考えられてきたが、近年の研究では農耕神であった可能性も強い。ガザとアシトドに大きな神殿があった。
旧約聖書によれば、ペリシテ人はイスラエルと戦い、勝利して契約の箱を奪ったとき、アシトドのダゴンの神殿にこれを奉納した。翌朝、ダゴンの神像は破壊され、ペリシテ人は疫病に悩まされたため、ペリシテ人は賠償をつけて契約の箱をイスラエルに返したとされる。破壊された神像は頭と両手が切り離されて魚のような体の部分だけが残っていたという。 近世ではミルトンの『失楽園』において、「海の怪物」とされ、悪魔の一人に数えられている。ここではすでにダゴンは上半身が魚の半魚半人の姿をもつものとされる。』(Wiki)』
「キルト・エアリムの人々はやって来て,主の箱を担ぎ上り,丘の上のアビナダムの家に運び入れた。そしてアビナダムの息子エルアザルを聖別して,主の箱を守らせた。」(サミュエルⅠ第7章1節)
ところが翌朝、アシドドのペリシテ人達が起きてみると、契約の箱の前にダゴン神が倒れていたという。そして、次の日もダゴン神が倒れており、更にダゴンの頭と両手は切り取られ、胴体だけが残されていたという。その後、アシドドの町には疫病が広がり、契約の箱をガテに移送することになる。
すると、今度はガテの町の人々に疫病が広まり、しかたなく契約の箱をエクロンに移す。すでにアシドドとガテの噂を聞いていたエクロンの人々は、箱の持ち込みを拒否した。
そこで領主たちは、ダゴンに仕える祭司たちと相談し、雌牛に繋がれた荷車に契約の箱をのせると、雌牛は子牛の方へは向かわず、イスラエルの町ベト・シェメシュに向かって行った。
こうして契約の箱は7か月ぶりにイスラエルの地に戻ってきた。
ペリシテ人達は国境までついてきて、箱が無事にイスラエル領に入っていくのを見届けてから、帰って行った。
しかし・・・ これで物語は終わらない。
7か月ぶりに契約の箱がイスラエルに戻ってくると、ベト・シェメシュの人々は喜んだ。
ところが
ヤハウェはこの町の人々で契約の箱を覗いた者があったので、ベト・シェメシュの人々のうち70人を殺した。
契約の箱の中を見てはいけないのである。
だからインディーは目をつぶったのだ。
ダビデとゴリアテ
契約の箱事件の後も、イスラエル人とペリシテ人の争いは続いた。ダビデとゴリアテの戦いは「第一サムエル記」第17章に記されている。
ペリシテ軍はエフェス・ダミムに陣を敷き、サウルの率いるイスラエル軍はエルサレムの南西にあるエラの谷に陣を敷き対峙した。
ペリシテ陣営からゴリアテという巨漢の戦士が現れると「勇者を一人出して一騎討ちで決着をつけようではないか。もしお前たちが勝てばペリシテはお前たちの奴隷となる。もし俺が勝てばお前たちはペリシテの奴隷となれ」と40日間、朝と夕の2回にわたって先の言葉でイスラエル兵たちを辱めた。しかしイスラエル兵はゴリアテに恐れをなし、戦いを挑もうとする者はいなかった。
この話を、イスラエル軍に参加していた兄に食料を送り届けるために陣営を訪れていた、羊飼いのダビデが聞くと憤り、サウルにゴリアテの退治を申し出た。サウルは初めは難色を示したが、他に手段がなかったため、ダビデの出陣を許可した。
サウルは自分の鎧と剣をダビデに与えたが、ダビデは「慣れていないので歩くこともできないから」とそれらを身に着けず、羊飼いの武器である杖と、投石器と、川で拾った滑らかな5個の石という軽装でゴリアテに挑んだ。
ゴリアテは「さあ来い。おまえの肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう」と嘲ったが、ダビデは
「お前は剣と槍を頼りに戦うが、私はお前がなぶったイスラエルの戦列の神、万軍のエホバの名を頼りに戦う。戦いは剣と槍の力で決するものではないことを人々は知ることになるだろう。これはイスラエルの神の戦いである」
と返答した。これを聞いたゴリアテはダビデに突進した。ダビデは袋の中から1個の石を取り出し勢いよく放つと、石はゴリアテの額に命中し、うつ伏せに倒れた。ダビデは剣を所持していなかったため、ゴリアテに近寄って剣を奪い、首をはねて止めを刺した。

ペリシテ軍はゴリアテの予想外の敗退により総崩れとなり、イスラエル軍はダビデの勝利に歓喜の声をあげた。イスラエル軍は敗走するペリシテ軍を追って、ガテやエクロンまで追撃して勝利を収めた。この戦いによりダビデの名声は広まり、サウルの側近として仕えるようになった。
このゴリアテは、身長は6キュビト半(約2,9メートル)もあったというが、その描写はギリシアの重装歩兵にそっくりだという。
サムエル記上 第17章
5節: 頭には青銅のかぶとをかぶり、身にはうろことじのよろいを着けていた。よろいの重さは青銅で五千シェケル。
6節: 足には青銅のすね当てを着け、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。
7節: 槍の柄は機織の巻き棒のようであり、槍の穂先は、鉄で六百シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。
イメージ 9これを見る限り先程のペリシテ人が海の民であり、ギリシアやクレタに由来する民族であるという説はがぜん信憑性を帯びてくるのだが、同じような格好ということであれば、アッシリアの兵隊なども似たような格好をしていた。
・・・ただ、こうした重装歩兵の姿がギリシアやアッシリアに確認されるのは、紀元前7世紀頃のことであるので、いずれにしてもダビデの時代には存在しなかったと考えられる。つまり、後世で編纂される際に少し脚色されたのだと考えられているのだ。
しかし、サリービーによれば、ペリシテ人もイスラエル人とともに住んでいた多数のアラビア半島西部の住人のなかの一部の人びとであり、彼らの居住地は紅海沿岸に限らず、内陸部のワーディ・ビーシャ流域にもおよんでいたらしいということである。
ペリシテ人の宗教や慣習は明らかにイスラエルのものとは異なっていた。へフライ語聖書では、とりわけペリシテ人を名指して、彼らは「割礼をうけない」と述べている箇所がある(士師記第14章3節、15章18節、サムエル記上第14章6節・・・・略)。彼らはその地方のさまざまな神を信仰していたが、なかでも特別な崇拝の対象となっていたのは、「ダゴン」という神であり、それを祭った神殿は「ガザ」と「アシドド」にあった(P262)
この「ガザ」と「アシドド」は、ペリシテ人が住んだアシール沿岸地方の主要都市のうちの2つにあたり、それらは以下のとおりである。この「ダゴン」の神殿は、その五都市の近郊に今なお残っている。
ガザ = zh
これはワディ・アダムにあるアッザ(zh)である。その近郊には、ダグマーという村がある。さらにこのほかにもダグムという名の村が、ワーディ・アダム流域をはじめとして5つある。アシール沿岸地方には、このほかに「ガザ」に相当する地名が3つある。すなわち、マジャーリダ地方のアッザ、バルラスマル地方のアール・アッザ(ガザの神の意、紛れもなく「ダゴン」のこと)、およびビルクの近くのアッズである。
アシドド(sdwd)
これはリジャール・アルマアのスドゥード(sdwd)で、その山頂にはまた、ダルワート・アール・ダグマー(dgmすなわち「ダゴンの神の頂き」の意)という村がある。このほかにもアラビア半島西部には、いくつかの「アシドド」がある。すなわちジーザーン地方のシダード(sdd)、メッカ地方のシャディード(sdd)である。またターイフ地方にあるシダードの近くには、ダグ-マ(dgm)という名の村がある。
アシケロン、ガテ、そしてエクロンの位置については『聖書アラビア起源説』をご参照ください。
ダゴンについてはこちら↓
→ http://blogs.yahoo.co.jp/alternative_politik/29456072.html
もし、ダゴンの神殿がアラビア半島西側のガザとアシドドに存在しているというのであれば、すでに紀元前2000年頃から商業都市マリやシリア地方などの、メソポタミアの都市で崇められてきたダゴンが発祥なのだろうか?
海の民がオリエント世界を席巻していた頃、都市マリやエブラを中心として、ユーフラテス川流域にはダガンを冠する人々の名前が数多くあり、特にマリではダゴンとして確認される名前のうち35%が集中している。
つまり、アラビア半島西部にとって、ダゴンは外来の神であるのかと考えなければならないのか?
いや、もしそれを言うのであれば、ペリシテ人が海洋民族である可能性も消えるだろう。確かにシリア地域でダゴンが崇拝されていていただのだが、クレタ島やギリシアでダゴンが崇拝されていたという形跡はあるのだろうか?
ペリシテ人(Wiki)
ペリシテ人、あるいはフィリスティア人(ヘブライ語:p'lishtīm>ギリシア語:Philistînoi>ラテン語:Philistīni>英語:Philistines)とは、古代カナン南部の地中海沿岸地域周辺に入植した民族群。アシュドド、アシュケロン、エクロン、ガザ、ガトの5つの自治都市に定着して五市連合を形成していた。古代イスラエルの主要な敵として知られ、聖書の『士師記』や『サムエル記』で頻繁に登場する。特に、士師サムソンの物語や、戦士ゴリアテと戦ったダビデの物語などが有名である。
現在のヨーロッパ諸語では、ペリシテ人とは「芸術や文学などに関心のない無趣味な人」の代名詞として使用される。
また、パレスチナ(Palestina)は「ペリシテ人の土地」という意味だが、パレスチナ人とペリシテ人は、直接の関係はない。
起源
ペリシテ人の起源を物語る資料は、文献史学的にはエジプト新王国期の記録や旧約聖書に見られ、また考古学によっても興味深い情報が得られている。
これらの情報から、ペリシテ人は紀元前13世紀から紀元前12世紀にかけて地中海東部地域に来襲した「海の民」と呼ばれる諸集団を構成した人々の一部であり、エーゲ海域とギリシアのミケーネ文明を担った人々に起源を持つとする説が有力である。
文献史学
聖書の記述によれば、ペリシテ人はアブラハムの時代にはすでにカナンの地に定住していたとされるが、この時代のペリシテ人へ言及した文献は聖書を除いて他に存在しないため、その起源については諸説存在する。
聖書の記述では、彼らのルーツはハムの子ミツライム(エジプト)の子であるカフトルの子孫であるとされ、「カフトル島から来たカフトル人」と呼ばれている(『創世記』10:13-14、『申命記』2:23)。さらにこれを裏付ける記述は、『エレミヤ書』47章4節にも存在する。したがって、ハムの子カナンを始祖とするカナン人とは異なる氏族であったとされる。
カフトルが実際にどの地域を指しているのかについても諸説あるが、紀元前12世紀頃までに、すでに鉄の精製技術を有していたことなどから、クレタ島、キプロス島、あるいはアナトリア地方の小島の1つであった、などの候補が挙げられている。今日ではクレタ島であるとの見解が示されることが多い。
また、ペリシテ人の築いた都市国家の王はセレンと呼ばれ、これはギリシア都市国家のテュランノス(僭主)と同一起源の語彙と考えられている。
考古学
ペリシテ人の残した遺跡から出土する彩文土器は、紀元前12世紀初頭のミケーネ3C式土器と同じ起源を持つと考えられている。またペリシテ人の築いた都市の都市計画はヘレニズム・ローマ都市を思わせる規則性を有している。