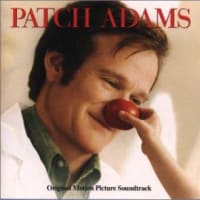https://blog.goo.ne.jp/0345525onodera/e/11130d9592cc07d50ffbebcee9c6387c
http://web.archive.org/web/20160907054036/http://www7.plala.or.jp/machikun/mataibara.htm
受難曲に関心がある方のみご覧ください。

イエスかバラバか?
それゆえ、あなたがたは行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、わたしがあなたがたに命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさい。見よ。わたしは、世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。(マタイ 28 章 18-20 節)
マタイ24章は終末の預言か?
ピラトから「バラバか、イエスか」と問われて、民衆はためらうことなくバラバを選んでしまった。正義の人、あれほど民のためを思い、つくした人を民衆はあっさり見捨てて、なんと極悪人であるバラバの釈放を求めてしまった。分厚い聖書の中でもこのシーンほど、キリスト教というものの本質を示している部分はないだろう。
もし、このときにピラトが民衆のひとりひとりに個別に同じことを聞いたら彼らはなんといっただろうか。おそらくは皆が「釈放されるべきはイエスである」と言ったことであろう。民衆一人一人はおそらく善良であり、またイエスの善行を良く知っていたと思われる。だから少しでも冷静に考えればこの「イエスかバラバか」という選択肢自体が無意味なものであり、イエスのような人が磔刑に処せられるはずがないのである。
私は聖書のこの場面を読むたびに、第一次世界大戦のことを考える。第一次大戦がなぜあんな世界規模の戦争になってしまったのか、ということについてはいまだに定説がないらしい。要するに誰もわからないのだ。ただ言えることは誰もがあの戦争があんな世界中を巻き込む大戦争になるとは思っていなかった、ということだ。
あの戦争が世界大戦となった原因の一つは当時網の目のように張り巡らされていた諸国間の同盟関係である。ではなぜ同盟というものがあったのかといえばそれは自国の安全保障のためであろう。国家間の安全弁としての諸同盟が逆に大戦争の原因を作っていたのである。
多くの人が犠牲になる世界大戦など、望む者はいないだろう。(一部の人の利益となる局地戦争ならばそうでもないだろうが)誰も望む者がいない大戦争を結果的に人類は選んでしまった。第一次大戦はまさに20世紀のバラバである。人類は「バラバを!」と叫んだ民衆の時代から少しも進歩してはいないのである。
第二次世界大戦に関しては第一次世界大戦の戦後処理の必然の結果だと言われている。ヴェルサイユ条約であれだけ過酷な戦後賠償をドイツに求めれば窮鼠ネコを噛む、ドイツ人は生きるためには何をするかわからない、ということは当時の識者の一部では理解されていた。(J.M.ケインズなどがその代表) しかし、この時点でも人類はバラバを選んでしまったのである。ヴェルサイユ条約もまた人類にとってのバラバであったのである。
日本の歴史でいえばバラバとなったのはあの悪名高き、日独伊三国軍事同盟であろう。現在から振り返ればあの条約を推進した松岡洋右などは悪の権現のように言われているが、彼にしてみればあの条約こそが日本の安全保障に必須と考えていた訳である。松岡洋右を擁護するわけではないが、彼は外相という立場にあって必死になって日米戦争回避の道をさぐっていたのである。
結果的にはあの軍事同盟が日米関係の命取りとなり、日本は太平洋戦争に突入してしまった。アメリカとの戦争を本気で考えていた日本人は当時でもほとんどいなかったと思う。陸軍とてあくまでも仮想敵国はソ連であり、それもできればソ連との直接対決は国力から考えて避けたい、と考えていたのである。
日本人はあの時代、まさにバラバを!と叫ぶ民衆と同じだったのである。少しでも冷静に考えれば、アメリカやソ連などと戦争などして勝てるわけがない、ということはわかるはずだ。(日露戦争はニコライ王朝末期で共産党革命が進んでいたロシアという特殊条件のもとでかろうじてひろった勝利であったのである)
さて、太平洋戦争後の日本はバラバを選ばずにうまくやってきたのであろうか。確かにこの50年以上、日本人は戦争とは無縁で生きてきた。その間に経済大国ともなった。しかし、小さなバラバはやはり無数に存在し、常にバラバを!と叫んでいる状態にあるのは戦前と変わらない、と思う。戦争という一点に集中しないだけで、さまざまな局面で私達はバラバをつい選んでしまっているような気がする。たとえばレンアイなどをする時、ある女にとってイエスとなるような存在のオトコとバラバのようなオトコがいてそれぞれから求愛されたとすると、結局多くの女はバラバたるオトコを選んでいるような気がする。
かつて私は公務員をしていた。そこには労働組合があった。みんな組合のやっていることは何かおかしいんじゃないか、と思いつつ、仲間はずれになるのを怖がり、表面的な人間関係を保つために、適当に組合活動をやっていた。当時私は「ははあ、組合というのはバラバだな」と思っていた。まわりがバラバ、バラバ、と叫んでいる状況では自分も保身のためにバラバを!と言ってしまうのだ。あの本物のバラバの釈放を要求した民衆たちもまた内心はこんなんでいいんだろうか、と思いつつ、つい勢いにのって「バラバを!」と叫んでしまったのではないだろうか。
キリスト教はまさに人間のこのような弱さを前面に押し出して考える思想である。人類はつねにイエスを十字架につけ、バラバを釈放してしまう特性を持っている。現代でも無数にいるバラバを前に、私達はどのように生きていったらよいのであろうか。
マタイ受難曲のページへ
前ページへ
ここよりペテロの否認に続いて第2部の2回目の山場となる。物語はピラトによる尋問が続き、民衆は正義の人イエスか、極悪人バラバかどちらかの選択をせまられることになる。
バッハのこの場面を比較的淡々と進めている。(これは後の「バラバを!」の一語を効果的に演出するための布石である) エヴァンゲリストとピラトが交互に出てきて物語をすすめる。まさに嵐の前の静けさ、という雰囲気である。
それにしてもピラトはなぜこの選択を民衆にさせようとしたのだろうか。エヴァンゲリストがまさに語っているように、当時の慣習では祭りの際に、一人を磔刑に処するときは一人を釈放することがあったらしいが、その判断は裁判官がやらずに民衆にまかせていたのだろうか。
さて、第13小節よりピラトの妻の代理人がやってきて彼女の妻の言葉を伝える。「あなた、お願いだからこの正義のお方には関ってほしくないの。このお方のことで今日夢でずいぶんとうなされましたのよ。」
これはまさしく女のカンというやつなのだろう。もし自分のダンナがこの裁判でイエスを十字架にかけてしまうようなことがあるとのちのちまずいことになる、と思ったのである。しかしピラトの妻も所詮は俗っぽい女性の一人にすぎない。決して「民衆のいうことは無視して正義の人、イエスを無罪にしてください」とは言わなかったのである。
あくまでも自己保身の一環として要するに当たらずさわらずでいこうと思っただけなのだ。面倒になりそうなことに関りになるのを避ける、という一番人間として卑しい行為に出たのである。ただ女の直感というものは本当にすごいものであると思う。いつの時代でも。
ところでこのピラトの妻の言葉は曲がCdurに転調してから始まっている。そのために彼女の言葉はエヴァンゲリストとピラトとの間の語りとは一線を画した感じになり、はっきりと浮き出て聞こえるのである。そして最後はgmollとなり、彼女の不安な気持ちを和声の変化が象徴している。
このピラトの妻の入りはカデンツが終わらないうちに始まっている。ここのところは、カデンツが終了してからピラトの妻の言葉が入るように修正した演奏もあるようであるが、やはりここは楽譜通り、カデンツの終了とともに彼女の言葉が入るように演奏したほうがよい。(和音も合ってるし) それにより、はやくダンナに私の思いを伝えたい、という彼女のはやる気持ちがうまく表現されるからである。
さて和音はgmollから再びAdur系へと戻り、場面はまた前に引き戻される.いよいよ民衆がバラバかイエスか、究極の選択をせまられる時が来たのである。・・・・・・・・・結局民衆はバラバを選んでしまった。これぞまさに人間のもつ原罪、キリスト教の究極であると思っている。これに関しては「バラバを選んだ人類のページ」をお読みください。
バッハはマタイにおいては「Barrabam!」のわずか半小節で終わらせている。(下譜)
通常ここは民衆が口々に「バラバ!バラバ!」と叫ぶ様を表現して、かなり長い対位法で歌われるところである。(ヨハネでもそうだ) バッハは発想をまったく変えたのである。ところでここで、ヨハネの同じ場面を聴いてみましょうか。
人類はイエスという正義の人を十字架にかけ、バラバという最悪の男をゆるしてしまった。これ以上の罪があるだろうか。人類みんながそう思うのならばいっそのこと、ひとことで終わらせてしまえばよいではないか、というまさにコロンブスの卵的発想である。
これが絶大なる効果をもつこととなった。人類の罪が「Barrabam!」この半小節に凝縮されることとなったからである。この曲がこれまで淡々とすすんできたのもまさに聴くものをしてその関心をこの半小節に集中させようという意図であったのである。
この「Barrabam!」がつよい印象を与えるのには秘密がある。まず第一はこの前の拍からの関係である。通奏低音をみるとA→オクターブのDisとなっており、減5と増4が重なっている。これにより、聴く者は意外な和声進行に驚くのである。
第二には、いうまでもなくこの部分が減七になっていることである。減七はこれまでにもたびたび出てきた。いずれもかなり感情が高まった状態で出現してきている。この和音はつねに解決を必要とし、これだけを聞かされる聴衆は無意識のうちに解決を欲するのである。解決されないうちはその焦燥感がずっと続くため、まさに手に汗握る状態が持続するのである。
その解決はつぎのエヴァンゲリストの言葉により2小節あとでemollとしてなされる。第三としてはDis上の減七→H上の七の和音への変化である。「Barrabam!」が終わった次の第31小節に入ると和音の最高音はC→Hと変化し、結果的に和音はH上の七の和音の第一転回形へと変化するのである。
これにより、「Barrabam!」のところの和音はあたかもその最高音CがHを根音とした九の和音のような効果をかもし出すのである。そのため、聴衆はますます解決への渇望を余儀なくされるのである。以上の3点により、この「Barrabam!」はその異様な雰囲気の醸成に成功しているのである。
管理人注:これらは人間社会の男女の間違いそのものです
イエスかバラバか、民衆はピラトに問われて明快にバラバを選んだ。ピラトは民衆よりは少しは知性があったのだろう。この民衆の選択に危険なものを感じたのにちがいない。以後、ピラトは自己保身に走り、なんとか民衆にその責任を持っていこうとする。そして「ならば私はこのイエスに対してはどのように対処すべきか」と民衆に問う。自分で判断するのではなく、できるだけ民衆に判断させ、あとで何かあったときの逃げ道を作っておこう、という腹である。
民衆は問われてイエスを「十字架につけよ!」と叫ぶ。バッハはこれをバスから始まるフーガとして作曲した。このフーガはただものではない。下譜のようにこのテーマには減4と減5が含まれており、アクセントの移動も行われ、民衆のすごみを感じさせるものである。フーガは下からわきあがるマグマのように膨れてきて最後はフル合唱になって爆発して終わる。短いながらこの合唱には煽動された民衆のパワーが炸裂しているのである。
この合唱は曲が進むにつれ、♯の数が増大してくる。♯はいうまでもなく十字架の象徴である。これは楽譜をつらつら眺めていると実感できる。
伴奏はおおむね合唱をなぞっているが、フルートだけはは独自の旋律を与えられている。これまでも民衆の軽薄さの象徴として使われてきた軽妙なフルートだが、ご多分にもれず、この曲でもピッピッとやっている。(当然ピッコロを併用すべきだろう) おもしろいのは最初の4小節は1stと2ndが別の旋律を吹いていて、第5小節から一緒になっている点である。おそらく最初の4小節は合唱がまだバスとテノールしか入っておらず、声部が足りないのでフルートを2パートに分けて声部を補っているのであろう。それ以上の深い意味はないように思う。またバスと通奏低音も途中で(第3~5小節)別の旋律になる。これはバスが興奮のあまり高い音域になるために低音が不足するための措置である。
ところでこの「十字架につけよ」はヨハネでも出てくる。ここでマタイとヨハネにおけるこの言葉に対する音楽的扱いの違いについてまとめておきたいと思う。マタイにおいては上述のように、フーガと減5度などを使った音程によって民衆のパワーを表現している。これに対し、ヨハネにおいてはまったくちがったやり方でそれを表現しているのである。ヨハネにおいては下譜のように、フーガは用いずに、フル合唱の対位法にて始まる。特徴は掛留音の効果的使用である。掛留音については掛留音のページを参照していただきたいが、要するにわざと不協和音を作ることにより、「十字架につけよ」という民衆のパワーを表現しているのである。
このコラールでは前曲を受けて、イエスの受けた理不尽な刑罰をのろっている。そのために冒頭の「Wie wunderbarich ist doch diese Strafe!(なんと驚くべき刑罰であろう)」のところではでは独特の工夫がこらされている。旋律は第3や第25番のそれと同一のものなのであるが、この冒頭の「なんと驚くべき」の言葉を表現すべく、和声はなんと最初から転回された形で始まっているのである。(こういう例は他のコラールにはない)和音としては第3番と同じhmollなのであるが、こちらはH上の七の和音となっており、バスがDis音から始まるために、第1転回形となるのである。さらにはアルトがAから始まるために、ソプラノと長2度の不協和音を形成し、これもまたこの不穏な和音の形成に一役買っている。また、バスは最初の4音が半音階で上昇しており、※のところでは減七和音となっているために、「おどろくべき」のところが不気味に響くのである。(下譜参照) 上記のような効果により、このコラールは他にはない独特の世界を作っている。
↓h上の七の和音第一転回形 
←半音階上昇→
このコラールはしたがって前曲とのつながりが大事である。前曲がHdurでピカルディ終止で終わったあとにコラールがそのまま休まずに入ってくるのが望ましいのである。第54番と55番はひとつの曲であるとの認識が必要なのである。だから入りもあまり小さい音でない方がよい。ある程度大きい音量で入り、後半になるにつれてピアノにしていった方が良い。