沖縄県那覇市では、2009年10月30日(金)~11月1日(日)に首里城祭が開催されます。
・伝統芸能の宴
平成21年10月30日(金)~11月1日(日)
場所:首里城公園下之御庭(無料区域)
琉球王朝時代、首里城において生まれた「琉球舞踊・組踊」
「古典音楽」が披露されます。
金・土は10時~17時 日は10時~11時30分
・冊封使行列・冊封儀式
平成21年10月31日(土)
冊封使行列 11:50~12:00 冊封儀式 12:00~13:10
場所:綾門大道~守礼門~下之御庭(冊封使行列)
首里城正殿前御庭(冊封儀式)
「冊封」とは、中国皇帝が周辺諸国に使者を派遣し、その国の王を任命する儀式です。

首里城展示資料より
・琉球王朝絵巻行列 平成21年11月1日(日)
場所:那覇市国際通り 12:30~14:30
歴史史実をもとに国王・王妃行列、冊封使行列に伝統芸能行列を加え、華やかさを演出しながら総勢約1,000人により構成されます。
中国皇帝が冊封のために派遣した使節団は、冊封の式典が行われる日に、冊封使(さっぽうし)の宿舎である天使館から首里城まで行列を行いました。
その行列は、琉球王国側からは三司官が出迎え、琉球側、中国側とで行われました。
この行事の再現が「琉球王朝絵巻行列」です
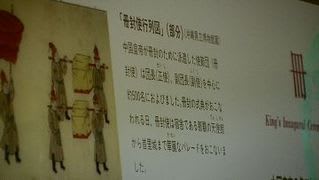
首里城に展示されている冊封使行列の図

これも首里城展示のものですが、「江戸上り行列図」か忘れました
沖縄県立博物館・美術館の博物館1階・常設展(総合展示)のコーナーに冊封使行列図などが詳しく展示されていたと思います。
2007年10月28日(日)の琉球王朝絵巻行列の様子です。
12時半から国際通りを久茂地の県庁側から出発し牧志・安里の方面へ行列が向かいました。

国王王妃行列の始まりです

三線が続きますが、実際の行列ではこれはなく、演出のためのものです

行列の先触れをする先導が続きます。
先導は、後ろの鞭(警護に使う)、火矢(爆竹を鳴らす)、旗、路次楽(行列で演奏される音楽)の責任者です

旗はいろいろあり、「令」字旗は中国の皇帝の命で来ていることをつげます。
他に国王や冊封使の行列に彩りを添える飾りの旗もあります。

赤涼傘(りやんさん)は傘の一種で国王が行列する時に揺らしながら行進し、目的地に着くと立てて飾ります。

首里城に展示されている赤涼傘(りやんさん)
赤涼傘の次に儀じょう(武器を持った一団)、大親(ウフヤ:国王や王妃の行列時に三司官の一人が大親になり行列全体の指揮をとる)が続きます。

黄涼傘(りゃんさん)は揺すりながら行進し、琉球では赤と黄の二種ですが、中国では白、青、藍など各種の涼傘が出ます。

いよいよ国王様がやってきました

国王が外出時に乗る乗物をチューといい、敬ってウチューまたはウチューイといいました。

これを担ぐ人をウチューフといいます。

一般公募で選ばれた国王役の方です

役とは言え、このように担がれ、「余は満足じゃ 」みたいな気分になれるのでしょうか?
」みたいな気分になれるのでしょうか?
それとも緊張してそれどころじゃない?

お次は王妃様

王妃も外出時にはウチューに乗りました。

これを担ぐ人は国王と同じで首里の農民があたり、女官が周囲を固めました。

王妃も一般公募で選ばれました

女官の次に摂政(王子の位。国王に次ぐ国政の責任者で、国王の兄弟や王族から任命された、赤地浮織冠)が続きます。
次に三司官(士族の最高の位、行政の責任者、紫冠)が続きます

「粛静」(静かにするように!)のプラカードを実際もっていたとのこと

中国皇帝使節団の冊封使(さっぽうし)行列です。
総勢400人ほどの人員が約半年間琉球に滞在したそうです。

巡視旗は見回って実情を調べる意で役人の権威づけるものとして必ず出しました。
虎旗、人物旗、龍旗、雲旗とともに正使を褒め、行列を飾り整え、冊封使行列にしか見られず、琉球側にはありません。

黄涼傘、赤涼傘ともに儀礼的な傘。

冊封正使・副使は皇帝の名代として来琉しているので、冊封をうけるまでは、国王も下手で絶えず拝啓して迎接しました。
琉球国王は明・清の2代にわたって中国皇帝の冊封を受けました
清時代は正使が満人、副使が漢人という組み合わせが多かったそうです。

朝鮮、越南、琉球等の付庸国の国王が新たに即位する際、それを認める勅書や王冠等をたずさえ、冊封使(さっぽうし)が派遣されました。
中国から琉球へ冊封使として来たのは、武寧9年(1404年)が最初で、尚泰王の慶応2年(1866年)の最後まで22~24回来琉したそうです。

伝統芸能行列が続きます。
若衆(十代の士族の少年、若衆踊りはみずみずしい生命感を歌い上げ、琉球王朝芸能の華であり、御冠船踊りの中心をなしました。)は色気がありますな
中国皇帝より与えられた冠を国王にかぶせる儀礼があり、御冠船の名のおこりは、使節の乗船がこの冠を持参してくることに由来するそうです。

行列の最後尾で待機中の四つ竹の方々。
戴冠の儀式の後、盛大な宴が催され、そのときの余興芸能として数々の芸能が組まれ沖縄独特の演劇である組踊、あるいは琉球舞踊、三味線音楽などはこのために発達したものであり、この芸能を称して御冠船踊りと称することもあるそうです。

同じく待機中の旗頭、エイサーの方々。
本来は(琉球王国時代)この行列に国王・王妃は参列していませんが、華やかさをもたせるために国王・王妃を出演させているとのことです。
さすがにメインを張るだけあり、ウチュー(神輿みたいな国王の外出時の乗り物)に乗った国王・王妃の姿は荘厳でした。
琉球舞踊(四ツ竹、若衆踊り)やエイサー、空手・古武道に旗頭、太極拳、龍舞などの多数の伝統芸能行列も行われるので必見と思います。

これは「首里城公園 新春の宴」(1月1~3日)での国王様と王妃様
国王様と王妃様は元旦早々、公務でお忙しいのであります(笑)
追加
沖縄県立博物館・美術館2周年記念イベント
『琉球古典音楽の調べ』
2009年11月1日(日) 午前9時・正午
沖縄県立博物館・美術館 エントランスにて開催
【演目】
1、 合奏曲「渡りざう・瀧落菅攪」
2、 古典音楽斉唱「かぎやで風節」(9時)
「こてい節」(正午)
3、 古典音楽斉唱「なからた節・瓦屋節・しやうんがない節」
4、 古典音楽独唱「干瀬節・子持節」(9時)
「仲風節・述懐節」(正午)
5、 古典音楽斉唱「道輪口説・中作田節」
6、 創作曲「梯梧」作:大城 貴幸
歌・三線・箏・笛・胡弓・太鼓などによる演奏
エントランスホールでの開催にて無料公演とのこと
・伝統芸能の宴
平成21年10月30日(金)~11月1日(日)
場所:首里城公園下之御庭(無料区域)
琉球王朝時代、首里城において生まれた「琉球舞踊・組踊」
「古典音楽」が披露されます。
金・土は10時~17時 日は10時~11時30分
・冊封使行列・冊封儀式
平成21年10月31日(土)
冊封使行列 11:50~12:00 冊封儀式 12:00~13:10
場所:綾門大道~守礼門~下之御庭(冊封使行列)
首里城正殿前御庭(冊封儀式)
「冊封」とは、中国皇帝が周辺諸国に使者を派遣し、その国の王を任命する儀式です。

首里城展示資料より
・琉球王朝絵巻行列 平成21年11月1日(日)
場所:那覇市国際通り 12:30~14:30
歴史史実をもとに国王・王妃行列、冊封使行列に伝統芸能行列を加え、華やかさを演出しながら総勢約1,000人により構成されます。
中国皇帝が冊封のために派遣した使節団は、冊封の式典が行われる日に、冊封使(さっぽうし)の宿舎である天使館から首里城まで行列を行いました。
その行列は、琉球王国側からは三司官が出迎え、琉球側、中国側とで行われました。
この行事の再現が「琉球王朝絵巻行列」です
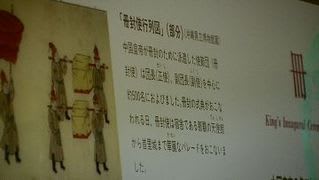
首里城に展示されている冊封使行列の図

これも首里城展示のものですが、「江戸上り行列図」か忘れました

沖縄県立博物館・美術館の博物館1階・常設展(総合展示)のコーナーに冊封使行列図などが詳しく展示されていたと思います。
2007年10月28日(日)の琉球王朝絵巻行列の様子です。
12時半から国際通りを久茂地の県庁側から出発し牧志・安里の方面へ行列が向かいました。

国王王妃行列の始まりです

三線が続きますが、実際の行列ではこれはなく、演出のためのものです


行列の先触れをする先導が続きます。
先導は、後ろの鞭(警護に使う)、火矢(爆竹を鳴らす)、旗、路次楽(行列で演奏される音楽)の責任者です

旗はいろいろあり、「令」字旗は中国の皇帝の命で来ていることをつげます。
他に国王や冊封使の行列に彩りを添える飾りの旗もあります。

赤涼傘(りやんさん)は傘の一種で国王が行列する時に揺らしながら行進し、目的地に着くと立てて飾ります。

首里城に展示されている赤涼傘(りやんさん)
赤涼傘の次に儀じょう(武器を持った一団)、大親(ウフヤ:国王や王妃の行列時に三司官の一人が大親になり行列全体の指揮をとる)が続きます。

黄涼傘(りゃんさん)は揺すりながら行進し、琉球では赤と黄の二種ですが、中国では白、青、藍など各種の涼傘が出ます。

いよいよ国王様がやってきました


国王が外出時に乗る乗物をチューといい、敬ってウチューまたはウチューイといいました。

これを担ぐ人をウチューフといいます。

一般公募で選ばれた国王役の方です

役とは言え、このように担がれ、「余は満足じゃ
 」みたいな気分になれるのでしょうか?
」みたいな気分になれるのでしょうか?それとも緊張してそれどころじゃない?

お次は王妃様


王妃も外出時にはウチューに乗りました。

これを担ぐ人は国王と同じで首里の農民があたり、女官が周囲を固めました。

王妃も一般公募で選ばれました


女官の次に摂政(王子の位。国王に次ぐ国政の責任者で、国王の兄弟や王族から任命された、赤地浮織冠)が続きます。
次に三司官(士族の最高の位、行政の責任者、紫冠)が続きます

「粛静」(静かにするように!)のプラカードを実際もっていたとのこと

中国皇帝使節団の冊封使(さっぽうし)行列です。
総勢400人ほどの人員が約半年間琉球に滞在したそうです。

巡視旗は見回って実情を調べる意で役人の権威づけるものとして必ず出しました。
虎旗、人物旗、龍旗、雲旗とともに正使を褒め、行列を飾り整え、冊封使行列にしか見られず、琉球側にはありません。

黄涼傘、赤涼傘ともに儀礼的な傘。

冊封正使・副使は皇帝の名代として来琉しているので、冊封をうけるまでは、国王も下手で絶えず拝啓して迎接しました。
琉球国王は明・清の2代にわたって中国皇帝の冊封を受けました
清時代は正使が満人、副使が漢人という組み合わせが多かったそうです。

朝鮮、越南、琉球等の付庸国の国王が新たに即位する際、それを認める勅書や王冠等をたずさえ、冊封使(さっぽうし)が派遣されました。
中国から琉球へ冊封使として来たのは、武寧9年(1404年)が最初で、尚泰王の慶応2年(1866年)の最後まで22~24回来琉したそうです。

伝統芸能行列が続きます。
若衆(十代の士族の少年、若衆踊りはみずみずしい生命感を歌い上げ、琉球王朝芸能の華であり、御冠船踊りの中心をなしました。)は色気がありますな
中国皇帝より与えられた冠を国王にかぶせる儀礼があり、御冠船の名のおこりは、使節の乗船がこの冠を持参してくることに由来するそうです。

行列の最後尾で待機中の四つ竹の方々。
戴冠の儀式の後、盛大な宴が催され、そのときの余興芸能として数々の芸能が組まれ沖縄独特の演劇である組踊、あるいは琉球舞踊、三味線音楽などはこのために発達したものであり、この芸能を称して御冠船踊りと称することもあるそうです。

同じく待機中の旗頭、エイサーの方々。
本来は(琉球王国時代)この行列に国王・王妃は参列していませんが、華やかさをもたせるために国王・王妃を出演させているとのことです。
さすがにメインを張るだけあり、ウチュー(神輿みたいな国王の外出時の乗り物)に乗った国王・王妃の姿は荘厳でした。
琉球舞踊(四ツ竹、若衆踊り)やエイサー、空手・古武道に旗頭、太極拳、龍舞などの多数の伝統芸能行列も行われるので必見と思います。

これは「首里城公園 新春の宴」(1月1~3日)での国王様と王妃様

国王様と王妃様は元旦早々、公務でお忙しいのであります(笑)
追加

沖縄県立博物館・美術館2周年記念イベント
『琉球古典音楽の調べ』
2009年11月1日(日) 午前9時・正午
沖縄県立博物館・美術館 エントランスにて開催
【演目】
1、 合奏曲「渡りざう・瀧落菅攪」
2、 古典音楽斉唱「かぎやで風節」(9時)
「こてい節」(正午)
3、 古典音楽斉唱「なからた節・瓦屋節・しやうんがない節」
4、 古典音楽独唱「干瀬節・子持節」(9時)
「仲風節・述懐節」(正午)
5、 古典音楽斉唱「道輪口説・中作田節」
6、 創作曲「梯梧」作:大城 貴幸
歌・三線・箏・笛・胡弓・太鼓などによる演奏
エントランスホールでの開催にて無料公演とのこと











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます