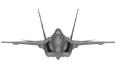アサギマダラの渡りが教える飛行思想
滑空による風上移動距離は、揚抗比の改善のみならず、高度を上げることでも伸ばすことができる。アサギマダラは昆虫であるが故、その渡りにおいては動力源が制限されているので、上昇気流を使って上昇していると考えられている。しかし上昇気流のない海をも渡ってくるので上昇気流だけでは不十分で、強い風を利用した上昇飛行も考えられる。従ってアサギマダラは翼面積の増大ではなく、強い風力エネルギーで高度を上げる方法を選択し、翼を紙のように薄くし抗力を小さくすることで実現していると考えられる。それが紙飛行機の様なチョウが、推進動力もないのに季節風に向かって2000kmもの距離を渡るエコ飛行の秘密である。
アサギマダラの渡りが教える機体構造思想
揚力や抗力は相対気体流速度の二乗と翼面積に比例した力になる。従って強風下でも飛行できるコンパクトな機体にすれば、特段に翼面積を大きくしなくても同じ揚力が得られるし、抗力も小さくできる。推進動力を効率化するために翼面積を大きくしたり、グライダーのように高アスペクト比の長い翼としたりする機体設計もあるが、機体重量と機体強度との戦いと、風に弱くなるという欠点がある。アサギマダラの思想は強い風力エネルギーを利用するので、吹き飛ばされないように紙のように薄くて、コンパクトな設計である。しかし揚力の増大ではなく、抗力の最小化の方を選んだことで、こちらは無風状態では落下してしまうというリスクを負う。
今の航空機は大気圏での飛行のために翼面積を大きくする設計である。その分抗力も大きくなって強風が吹くと欠航となる。しかしアサギマダラは強い風が吹くほど逆に有利である。
地上に近い対流圏では無風状態が存在するが、上空15000m付近の成層圏では、逆に上昇気流は期待できないけれど、無風状態の無い年中強風領域となっている。従ってアサギマダラにとって成層圏での飛行は不可能だが、そこの領域に限定した飛行機は、揚力が小さくても落下し続けることはなく、長期間の安定した滞空が実現できると考える。



強風を利用する思想 翼面積を利用する思想
繁殖のためとはいえ強風に吹き飛ばされず、逆に強い季節風に突き進むための構造で、しかもそのための動力を使っている気配さえない。
つまり羽ばたきによって強風に立ち向かうのではなく、強風で得られる揚力により上昇し、その位置エネルギー使って風上に移動しているのである。
何億年もの自然環境のもとで淘汰され続け、そこで生き残った生き物には全くといって無駄なところがないとつくづく感じ入ってしまう。
戦闘機の設計も無駄なところは徹底して切り取る設計であろうから、期せずして最新戦闘機の正面から見た構造はアサギマダラとそっくりであった。
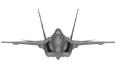

滑空による風上移動距離は、揚抗比の改善のみならず、高度を上げることでも伸ばすことができる。アサギマダラは昆虫であるが故、その渡りにおいては動力源が制限されているので、上昇気流を使って上昇していると考えられている。しかし上昇気流のない海をも渡ってくるので上昇気流だけでは不十分で、強い風を利用した上昇飛行も考えられる。従ってアサギマダラは翼面積の増大ではなく、強い風力エネルギーで高度を上げる方法を選択し、翼を紙のように薄くし抗力を小さくすることで実現していると考えられる。それが紙飛行機の様なチョウが、推進動力もないのに季節風に向かって2000kmもの距離を渡るエコ飛行の秘密である。
アサギマダラの渡りが教える機体構造思想
揚力や抗力は相対気体流速度の二乗と翼面積に比例した力になる。従って強風下でも飛行できるコンパクトな機体にすれば、特段に翼面積を大きくしなくても同じ揚力が得られるし、抗力も小さくできる。推進動力を効率化するために翼面積を大きくしたり、グライダーのように高アスペクト比の長い翼としたりする機体設計もあるが、機体重量と機体強度との戦いと、風に弱くなるという欠点がある。アサギマダラの思想は強い風力エネルギーを利用するので、吹き飛ばされないように紙のように薄くて、コンパクトな設計である。しかし揚力の増大ではなく、抗力の最小化の方を選んだことで、こちらは無風状態では落下してしまうというリスクを負う。
今の航空機は大気圏での飛行のために翼面積を大きくする設計である。その分抗力も大きくなって強風が吹くと欠航となる。しかしアサギマダラは強い風が吹くほど逆に有利である。
地上に近い対流圏では無風状態が存在するが、上空15000m付近の成層圏では、逆に上昇気流は期待できないけれど、無風状態の無い年中強風領域となっている。従ってアサギマダラにとって成層圏での飛行は不可能だが、そこの領域に限定した飛行機は、揚力が小さくても落下し続けることはなく、長期間の安定した滞空が実現できると考える。



強風を利用する思想 翼面積を利用する思想
繁殖のためとはいえ強風に吹き飛ばされず、逆に強い季節風に突き進むための構造で、しかもそのための動力を使っている気配さえない。
つまり羽ばたきによって強風に立ち向かうのではなく、強風で得られる揚力により上昇し、その位置エネルギー使って風上に移動しているのである。
何億年もの自然環境のもとで淘汰され続け、そこで生き残った生き物には全くといって無駄なところがないとつくづく感じ入ってしまう。
戦闘機の設計も無駄なところは徹底して切り取る設計であろうから、期せずして最新戦闘機の正面から見た構造はアサギマダラとそっくりであった。