身近にいるAくんは、「う~ん、それってどうなんですかねえ」的なものの言い方が、悪いクセになってしまっている。
どうして悪いクセかというと、なにも考えていない人間でも、いちおう意見は述べたらしき匂いだけは残せる、とてもイージーな詐術だからだ。その場に匂いはつけられるのだが、中身はあるかを吟味するとすぐに、全くないのが分かる。果汁0%。むしろアイデアを出しあう場などでは、代案を持たないのに「う~ん、それってどうなんですかねえ」しか言わない、意見があるふりをする者が混じると、かなりのマイナスになってしまう。
昨日、これから書くワン・ビンの新作を見た後、数人で意見交換になり、僕が「おそらく、貧しい環境にあってもひたむきに、無心に生きる少女たちの強さに感動しました、という受け止められ方がメインなのだろう……」と言ったら、すかさずAくんが「う~ん、それってどうなんですかねえ」と入ってきた。
Aくんはドキュメンタリー業界の関係者と認知されたい希望を強く持っているので、ひとが集まる場に顔を出すのが大好きだ。特に、話題作のマスコミ試写を見た者同士が公開前に感想を述べ合う。そんなサロン的な場に身を置くことは、〈関係者っぽいフンイキ〉を味わうにはもっとも最適で手軽だから、大好物みたい。ワン・ビンの新作ともなると、ますます。
しかし僕は、ちょっとイラッとして、話しかけないでくれと身振りで制した。「どうなんですかとは、どういう?」と意見を求めたところで、はかばかしい返事が返ってこないことが、Aくんとの約1年のつきあいでよく分かっていたからだ。
Aくんをいけにえのようにしてしまってスマナイことだが(Aくんとは誰かも詮索せんでください)、彼に限った話ではない。浮かぶのは、
「ドキュメンタリーって、どうして、いつから、意見があるふりをする者でも居心地のいい世界になってしまったのか?」
という疑問だ。
プレスリリースを引き写し、てにをはを変えて、「深く考えさせられる。」と締めればドキュメンタリー評は一丁あがり。ものの見事に、誰でも「ふり」ができるようになった。もちろん、「興味深い。」と差し替えてもいいし、「まずは(画面の事象に)出会う、ということ。」などともったいつけてみせてもいい。いずれにせよ、なにを考えたのか、なにを興味深く捉えたのか、までは書くことはほぼ求められないので、いくらでも逃げられる。要点を噛み砕く努力をしなくても、自分のものの考えかたを開陳して叩かれるリスクを負わなくても、安心して近づけるのが現在のドキュメンタリーの周辺だ。
そこで僕は、「犯人はダイレクトシネマ説」を、ちょっと唱えちゃうのである。
『三姉妹~雲南の子』
2012 フランス=香港 監督ワン・ビン
5月25日よりシアターイメージフォーラムほか全国順次ロードショー
配給ムヴィオラ
http://moviola.jp/sanshimai/
どんな内容かをざっくり説明すると、まず、現代のドキュメンタリー映画の最重要人物のひとりである、ワン・ビン(王兵)の最新作である。
とはいえ、ワン・ビンの映画はほとんど見たことがないので、まあ、そういう評判の方です、としか僕には言いようがない。ワン・ビンが一躍名を高めた9時間超の大作『鉄西区』にしても、すこしは見たことがある気がしていたのだが、前述した昨日のおしゃべりで、どうも違うドキュメンタリーの印象とゴッチャにしているのが分かった。ヤレヤレだ。僕の場合はAくんとは逆で、知識と鑑賞本数がさっぱり足りない。
で、そのワン・ビンが、雲南省の寒村に暮らす、3人の姉妹を撮った作品がこれ。
家にいるのは、インイン(10歳)、チェンチェン(6歳)、フェンフェン(4歳)の3人だけ。母親は家出して、父親は出稼ぎに出ているからだ。近所におばさん一家とおじいさんがいて、3人に野良仕事を手伝わせたり、食事を出したりしているが、基本、3人はなんとか姉妹だけで生活している。
この暮しが、圧倒的に貧しい。働かなければ生きていけない土地で、学校の勉強だけがほとんど唯一の娯楽。おばさんの家にはテレビがあり、そこに写る番組はきわめて珍しいはずなのだが、あまりに自分たちとの暮らしに接続がないので、インインたちにはなんとなく眺める以上の実感がない。
ちょっと横道に逸れるが、この、ときどき現れる、インインたちがボンヤリとテレビを見ている場面には、写真家・朝海陽子が撮った〈テレビを見ている最中の家族〉のポートレイト・シリーズを思わせるところがあって面白い。(2011年に写真集『sight』として発表)
http://www.akaaka.com/blog/bl-110114-sight.html
『三姉妹~雲南の子』を見ると、カメラがよくもここまで貧しい村の内部に入り込めた、といったんは感心する。しかし、自分たちの暮らしに接続がない=そのカメラで映し出された自分たちが不特定多数に見られることまで、想像の意識が及ばない、となると、実は警戒をすみやかにとき、密着することは意外と困難ではなかった気もする。
朝海の写真は、家族がみなでテレビのなかに没入する瞬間を捉え、間接的に、完全に無心の家族の肖像(いわゆる素の状態の夫婦の距離、子どもの居場所など)を抽出した。一方、この映画の場合は、テレビを見たところで自分とは関係なく、没入しようがなく、それでもおばさんたちが見ているからしかたなく一緒にテレビを眺めている長女インインの姿によって、インインを映画の幼きヒロイン足らしめる、ある強さを浮かび上がらせる。誰もアテにできない場所で、甘えかたも知らず、自分がどれだけ貧しいのか、どんな孤独を抱えているかの自覚も無いまま、おばさんの家ではいつも壁際にポツンと立っている。
おばさんのほうは世知があるので、テレビの内容が分かる。しかし、対象化の意識はやはりどこか素朴なため、こわい場面になると、ワーッと両手で顔をふさいだりする。つまり、おばさんのほうが女の子のような無邪気なきもちでテレビという「社会の窓」をたのしみ、インインは、「社会の窓」の存在そのものに気持ちがいかず、むしろ退屈して、外に出る。
そう、この映画でワン・ビンは、ある特殊な空間にいる少女のたましい、尊厳を日記形式で描いたのだ。実はきわめて高度に文学的な作品なのだ、と言うことはできる。
インインのゴホンゴホンとくりかえす咳き込み、ついぞ着替えない、着たっきりの汚れて変色したパーカーは、少女の、第三者からするとかなり絶望的な、大人に庇護されない状況の悲惨さを伝えて余りあるのだが、大人のように働かなければ生きていけないなかで、ついに周囲とうちとけないインインの、悲しい、淋しいという感情をまだ知る前の姿には、ある清潔感が生まれる。見る人の多くは、常に仏頂面で働くインインの姿から、無垢の観念性、少女の一時期だけが持つ聖性を見出すことになる。泥と家畜の糞まみれのパーカーのロゴデザイン、「LOVELY DIARY♫」が、おあつらえのスピリット・タイトルのように読めてくる。
劇的な場面は、2人の妹がいちど父親の出稼ぎ先に引き取られ、インインだけが村に残される時期に訪れる。
インインに前にぶたれたことを根に持つ女の子が、おかあさんと一緒にいるところでインインと出くわし、さあここを先途とばかり、おかあさんに聞こえるように大きな声で「どうして私をぶったのよ!」とインインを責めるのだ。ガキんちょなりのズルい計算をきかせたこの女の子の、にくったらしさが何ともかわいくて、悶絶ものの場面。偶然が入り込んでドラマを転がしてくれる、ドキュメンタリーのいちばんおもしろい瞬間だ。さてそのピンチをインインがどう切り抜けるかは、公開後に見てもらうとして。絶対の庇護者=おかあさんの存在を笠に着た子との対照エピソードによって、さらに、母親を知らないインインの孤独と清潔な強さが引き立つようになっている。
思うままに、こういう解釈をしてみると、『三姉妹~雲南の子』はかなりの傑作ではないかという気がしている。おそらく、(自分で言うのもなんだが)1本の映画のクリティックのための目先としては、まあ、質の高い部類に入るだろう。
実際、ワン・ビンが、この映画でまさにダイレクト・シネマ的な、自然主義的スケッチを貫くことに勝算があったことは確かだと思う。
まだ半分は夢の中にいる年齢であるインインの妹たちの無邪気さ、ヤギやイヌたちとほぼ同レベルで張り合って生きているコロッコロとした小さな生命力ぶりは、誰にとっても見ていて快い。多くのドキュメンタリー愛好家は、あまりに貧しい村の生活を生々しく見せられると、どう言っていいか分からない。なので、子どもたちの無心さを慈しむ……な方向に読後感をまとめたい意識が働く。そして、それが可能なようなかたちへ向けて周到に、ワン・ビンは映画を完成させている。長女が宿している聖性云々という僕の解釈も、まあなかなかもっともらしく、批評家っぽいことを言えているようで、基本はあくまでワン・ビンが敷いたレールの上にある。インインと女の子の喧嘩も、違う時に撮って、編集時にうまいこと時系列を無視して組み替えたかもしれない。
ここからが、マクラの話につながる。つまりはなんかね、そうやって気持ちよく解釈できてよいのかと思うのだ。
ダイレクトシネマ、自然主義的リアリズム、観察映画、などいろいろ称することができる昨今のドキュメンタリー映画を、ここで思い切って十把一絡げにすると、ナレーションやテロップによる誘導のない、または最小限にとどめられたスタイルが、高い評価のポイントとして共通する。同時にその価値観においては、観客にこう見てほしい、という作り手の意志が露骨に表に出ない。「とにかく臨場の意識で、予断を持たずカメラを向けました。そこに何があるかは、観客ひとりひとりにゆだねたいのです……」と語ることが、作り手の誠実さとみなされる。
僕は数年来のこうした評価価値に則る人、「あの映画は、くだらないテレビと違って、ナレーションやテロップがない。だからスバラシイ」式の誉め方をする人をことごとく、申し訳ないぐらいに冷たく、他愛がない、と思ってきた。理由は単純で、そういう人のほとんどが、編集の作為は語らないし、気づかないからだ。それに「テレビと違って」と、テレビをわざと落としながら引き合いに出して無理に映画を高尚に誉めようとするセコさが、本業・番組構成作家としては、不快だった。
巧い人ならば、ナレーションやテロップがなくても、編集でストーリーやキャラクターを望む方向に寄せて、見る人の気持ちを誘導することができるのだ。さらには、「ナレーションやテロップを一切付けておりません」という断りを無添加食品の表示のように利用しながら、思うままに編集したものをナチュラルなイメージに仕立てる人もいる。そういう、したたか系の横綱がフレデリック・ワイズマンなのだと言い切ってもいい。
もちろん、その手法を、いたずらに否定するものではない。映画によってリアルな現実をありのままに見た、という気分になれる知的喜びも、広義にはちゃんと映画のエンタテインメント要素に入っている。
ただ、直接的・具体的イメージを作り手が丸ごと渡し、観客が丸ごと受け止める、という現代ドキュメンタリーにおける美しい約束事には、どうしても(それでも、どんなものでも編集加工はされているんだぜ?)という破れ目は常に付きまとうし、「あえて観客にゆだねる」的な麗句も、作り手と見る側、両方のハードルを低くする、甘やかすことにつながっているのではないかと、どうしても感じちゃうのだ。
「ワタシたちはこの問題についてこう思う。ついては、観客にもそれだけの理解を求めたい!」式のドキュメンタリー映画は、1990年代ぐらいには、本当に見ていて苦痛だった。作り手の左翼思想に深みがなかったりする場合は、目も当てられないものになる。しかし、そういう映画に対する時には「ボクはこの映画、好きじゃない。どうしてかというと、これこれこうだからだ」と自分の軸でモノを言わねばならない緊張感があった。「う~ん、それってどうなんですかねえ」的な感想は、なにも言っていないのと同じ、とハッキリしていた。
「あえて観客にゆだねる」式は、その点、とてもラクだ。お互い、なにか言う必要がない。絵画における抽象画の時代のように、音楽におけるフリージャズの時代のように、ドキュメンタリー映画周辺のことばも、「解釈や分析よりもまずは感じること。」とか、「出会うことから始める、ということ。」みたいな、ふりだしに戻る相対的物言いのほうが、この数年は強かった。「う~ん、それってどうなんですかねえ」しか言えないひとでも、気安く見ることができるようになったし、よく知ってる風な顔ができる。これはゼロ年代になってからのドキュメンタリーの、良い点・悪い点あわせて、いちばん大きな(フィルムからビデオになったとの同じ位の)変化ではないか。
絶賛されるに十分な『三姉妹~雲南の子』を見て僕が感じた微かな不満は、あまりに現在いちばんよいとされているドキュメンタリーの作り方に則り、良く出来すぎていないか? 自分の考えを底に沈め過ぎていないか? だった。
インインたち村人たちが、移民の漢族なのか、少数民族なのか(雲南省は中国で最も少数民族が多い)、判然としないのがやや、もどかしかった。おばさんの被っている青いつばつき帽子から、ナシ族ではないかと思ったのだが、確証は持てない。ここらは、公開前に幾つも出てくるだろう監督インタビューを読んで確認したい。
雲南省には数年前、一度だけ番組の取材で行ったことがある。まさにインインたちのその後にあたる、全村移住で観光都市の集合住宅に住み、毎日、きまった時間に観光地へ出かけて伝統舞踊や歌を披露し、当局から収入を得ている少数民族を麗江で撮影した。
農家のおじさん、おばさん感がまるだしなナシ族の善人夫婦にその場で頼み、住宅まで入り込んだ。腹が減っていないかといろいろ出してくれる、本当に素朴ないい人たちだったが、そのぶん、真新しい住宅とのギャップはすごかった。「村を離れた時の気持ちは?」と時間を置いて3回聞いたが、3回とも、「こんな快適な場所に住めるようになって幸せです」という答えだった。漢族の通訳は、夫婦に対していやに態度が大きく、「もういいでしょう。こんなところよりも、撮影してほしい素晴らしい場所はたくさんあります」と、明らかに途中から不機嫌だった。
中国は中国人の国(あるいは共産党員の国)という単純な認識が、あっさり崩れたのはこの時だ。大部分を占める漢族と、少数民族の国だった。
雲南省そのものは、自然と天然資源の宝庫。実はものすごくゆたかな地だ。しかし、近代化の視点で切れば、中国で最もインフラ整備の行き届かない、貧しい省ということになる。本当は肥沃な土地なのに、年貢を米で払うという江戸時代の一律の決まりを主君が呑んでしまったため、米がとれない→飢饉→貧しいというイメージが明治以降も定着してしまった青森県と、近いところがある。
僕は雲南省のいいところ、経済発展のさなかのようすも見てきたので、ワン・ビンがこの、並はずれて貧しい村とたまたま出会い、スケッチのようにカメラを回したとはちょっと考えにくい。それ相応の、わざわざこの村まで赴き、撮る狙いはあったと思っている。同じ中国とはいえ、ワン・ビンにとっても、雲南省はビジターの視点ではじめて捉えた場所だろう。そこらへんの態度をもっと示してくれないと、この村のリアルな貧しさが、まるでおとぎ話の遠い村のような抽象性をまとい、意味合いが相対化されてしまうと感じた次第。
ただ一方で、ワン・ビンはそこもよく検討し、踏まえたうえで、主観を沈めたのかもしれないとも思う。
おそらく今、中国で指折りに貧しい、拝金主義のはの字も浸透しようがない地域をえらんで撮影した。ひとりっ子政策がさすがに行き詰っている国を舞台に、帝政ロシア崩壊前夜に書かれたチェーホフの戯曲の題名をなぞらえたタイトルにしてみせた。
アイロニーという名のビーンボールは、これだけ投げれば十分ではないか。後は、ワタシが撮り、スムーズに、見やすい形に編集したそのものを、ただ見てくれ。ワン・ビンがもしもそう言うならば、これはこれで、かなり僕はハハーッ、よく分かりました……と納得するのである。



















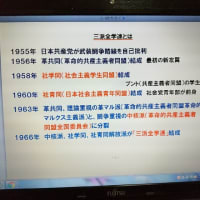
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます