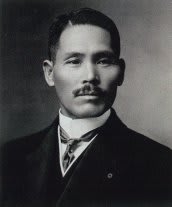石坂・潤野の合戦
天正十年は織田信長が全国制覇の寸前に惜くも本能寺に敗死した年であり、信長の遣業をうけついだ秀吉が全国統一の偉業をなしとげたのが天正十八年(一五九二)である。
これをみても天正年間がいかに戦国争乱の時代であったかが知られよう。
まさに統一直前の終盤戦が各地に展開された時代である。
九州においても
大内、
大友、
龍造寺が九州各地の小豪族を配下に従えて九州全島の支配を三分して争った時代である。
天正の後年になっては
毛利,大友,
島津が北部九州の争奪に激しい戦いをくりかえしたようである。
特に早くから筑前地方を支配してきた大友は,南九州を領有した島津の侵略を受けて筑前・筑後一帯を防衛するのに懸命であった。
粕屋郡の立花山に居城をもつ立花は大友の勇将であり、古処山に城を構えた秋月は、島津北進の先鋒であった。
このような形勢の中で
秋月と
立花との間に嘉穂盆地の争奪戦がくりかえされたのは天正十年の前後数年間にわたったようであるが、立花山と秋月との間にあった私たちの村が戦禍の災難から逃れることができようはずもない。
次に抄録する記録は戦火に明けくれたそのころのようすが生々しく伝えられたものである。
立花家文書
天正九年十一月六口於穂波表合戦の砌、戸次伯耆入道雪家中之衆、分捕高名、或被疵戦死之着到,令披見言乞
県史(1の下)
これは大友が秋月と戦った大友方の勇将立花道雪に与えた書状で部下将兵の功績と負傷者,戦死者の名簿を披見したと書いたものである。
横大路文書
前之六日・穂波郡潤野原合戦之刻・最前被砕被刀疵之由候,感悦無極候,必配当矯,何様可賀之候,恐々謹言、
天正六年十一月十一日統虎 道雪 横田伊豆守殿
(県史1の下)
前の書状は立花道雪,宗茂の父子が配下の臣横田伊豆守に与えた軍忠状である。
すなわち重傷にも屈せず奮戦した働き振りはまことによろこびにたえない。
戦い終わって賞を行う際には必ず賞讃することをわすれないと感激をこめて書いたものである。
同じ十一月の潤野合戦に負傷しながらも奪戦した
薦野増時にも同様の軍忠状をおくつているが、天正九年十一月(一五八二)潤野の一帯を戦場にして北上する島津の先鋒秋月軍と大友勢力防衛の先陣立花軍との間に激突がくりかえされたときのことである。
この戦いによって寺院も神杜も焼き払われたが再興のいとまもなかったであろうし、兵火によってやきはらわれた民家に佇むうちのめされた村人の悲惨な有様が目にうかぶようである。
日本全国がそうであったように私たちの村もこのころの戦火で焦土と化してしまつたのではなかろうか。
かってそれ以前に栄えたと思われる
明星寺をはじめ村内の寺杜もそのころを境にして全く昔日の面影をとどめるものもないまでに焼失してしまったようである。
そのような戦禍の惨状が秀吉の島津征伐の終るまで続いたとおもわれる。
秀吉が
大隈城に到着して秋月をくだしたのは天正十五年四月二日(一五八七)のことである。
当時の戦況を九州紹運記には次のように述べている。
鑑連公、紹蓮公御両家の人数を以って穂波郡へ打出石坂守龍野へ御陣被成賀麻穂波両郡を放火し引き退く処に秋月より八千の人数を指出し……紹蓮公御白身御長刀をめされ早やかかれ者共と御声を励し切り懸らせ給えば・……槍を入れ太刀を合せ或は組合い差違え黒煙を立て、(九州紹運記)こうして秋月八〇〇〇人の兵に対して立花,高橋の連合軍も六〇〇〇人の兵を繰り出して八木山、潤野の線に合戦を展開した。
ついに秋月方の七〇〇人を討ち取って粕屋郡に引き上げたと記している。
鑑連公とは立花道雪のことである。
このときの合戦に高橋紹蓮の嫡男統虎公が十六才にて初陣かくかくたる武勲をたてたとも書いている。
統虎はこの後
立花道雪にみこまれて道雪の養子となり、後には朝鮮の役にも勇名をはせた筑後柳河藩主立花家の祖先
立花宗茂である。
戦国の勇将
立花宗茂十六才の若武者振りもさることながら、その日の合戦の思い出は彼にも終生忘れることのできない追憶となったであろ。
村内各所に伝えられる城跡や古戦場はいずれもそのころのつわものどもの夢の跡である。
八木山千人塚のいい伝えも天正九年十一月(一五八二)の激戦の語り草のようである。
天正十五年六月(一五八七)遠征終った
秀吉が九州諸大名の領地を定めここに九州の兵乱は全く鎮定した。
そして筑前一国と筑後の一部は
小早川隆景が領有することになった。
それにしても私たちの村にとって天正の戦禍はなにもかも村全体を一変してしまったようである。
踏みにじられた平和な生活をとりもどすために祖先の人たちの不屈の一鍬一鍬は焦土の中に新しい村を再建してぎたのである。
鎮西村再建の時代であり、むしろ今日の私たちの村の新しい出発の時代となったようである。
豊前覚書(弓箭物語柳川国初日記トモイウ)
元和元年二月城戸豊前守清種の著述
道雪(立花)様紹運(高橋)様御人数天正八年慶辰九月上旬=石坂=而御両家之御人数御もやひ被成、穂波郡の内潤野原御打出、御両殿様御すわり被成候。
左様御座候処=秋月衆八千程にて朝辰の時分御陣所へ攻掛申候間、御両殿様急ぎ馳向候へと上意ニ候へ共、大橋京林被申上候分=時悪戦敷候間御据り場=引受御鑓被侯へと被申上半、無程敵近参候間、先手之衆堪兼突掛り可申と被仕候処、大橋京林さいふり時は京林へまかせられ候へと被申候間三段程之田之間を隔て据候所へ実かり申候間、早時分死候と被申=付て据場立候へ則鑓打むかひ其まま御突崩し、はじと申村迄三里追打被成、秋月殿内歴々の侍三五〇余御打捕被成候、御両殿様彼頸実見被成頸見塚三ツ京林つかせ被てより、御両殿様御時宣を被成候て、先道雪様御腰物御脱勝時御上候てより、追付紹運様御腰物御脱御勝時御上候てより惣勢一度二刀ヲ脱キ御勝時を上候刻ハ天地も響き雷電稲妻の如く夥敷事無比類侯。
誠に弓矢八幡摩利支天かと、御両殿様御事申すべく、左候てより石坂之様二御引被成候。
八木山へ御陣被成、惣勢二被仰渡候分い、人別ニ炬ヲ誘候へと被仰付候間、何も相誘申候由申上へ、大祖山の峯より宝満迄彼炬むらもなくり、灯候へと御意候間、八木山御陣所より宝満まで四里之道灯流申侯ヘバ、味方見申てさへ夥敷候間、秋月面より見申候ハ、御両家の御人数存之大勢御座候由、批判仕候由承候。
翌日巳の刻ニ御両殿様御参舎被成候而、御誤合被遊候てより、紹運ハ葉山の内嶺通り宝満之様二御帰陣被成候。道雪様ハ石坂より金出通御被成候右御語合之義統虎(立花宗茂)ヲ道雪様御養子可被成様二風聞申候。
八木山・石坂の戦い
「石坂の戦い」は、「筑前国続風土記」に「八木山村古戦場」として記述がある。
この合戦は「立花統虎」の初陣として知られている事から、統虎中心に記載する。
「八木山合戦・石坂合戦」が正しく同一の戦いであったかは確認できない。
「統虎」が立花城に入った頃は「戸次道雪」の「立花姓」はまだ許されてはいなかった。
「道雪・統虎」が正式に立花姓を継ぐのは天正十年十一月十八日以降である。
「柳川立花家」の史料によれば「道雪」は生前「立花氏」は用いず「戸次道雪」を通し、死後に「立花道雪」と呼ぶように為ったとしている。
「統虎」は永禄十年十一月十八日(一五六七)豊後国国東都甲荘、屋山(八面山)の北麓、長岩屋松行川沿いの吉弘館「筧城」で「吉弘鎮理」の嫡男として誕生した。幼名は「千熊丸」。
吉弘氏の本城は「屋山城」であったが、平時は麓の館(筧城)に居た。
この館(やかた)のあった場所ははっきりとしないとされる。長岩屋松行川の辺りであったことには違いないようであるが、堀の内あたり、吉弘氏の菩提寺「金宗院跡」など云われている。弟に「統増」がいる。
元亀元年五月、父「高橋鎮理」は筑前国豊満山、岩屋城城督として入り、「高橋鎮種」と歴代大蔵系高橋氏の偏諱(いみな)「種」をつけ「鎮種」更に入道して「紹運」と号す。
この時千熊丸は三歳であった。
千熊丸は子供の時から体大きく、がっしりしていたと言う。弓矢撃ちにも長け、物事に動じず、状況判断や機転はすばやかった。
何事においても同じ歳の子供はおろか年上にも負けなかったと言う。
「千熊丸」は持って生まれた武将としての天性のものを備えていた。
この嫡男に「紹運」は吉弘家の行く末の安泰を感じていた。
この「千熊丸」の器量は「道雪」も見て取っていた。
「道雪」「紹運」は親子程も歳は違ってはいたが、武将として相通ずるものがあり盟友関係にあった。
千熊丸は元服して名を「統虎」と改める。
天正九年八月十八日「道雪」は、「戸次・高橋」の絆をより強固にする事こそ、筑前牽いては大友を安定させる道と、「紹運」に「千代」への婿養子を申し出る。
「老将道雪」の、このたっての依頼に、「紹運」は統虎を「千代」の婿養子とする事を了承する。
立花山城へ入った「統虎」はその年の初冬、天正九年十一月六日「秋月種実」との八木山「石坂合戦」に、両父「道雪・紹運」と共に初陣する。
この「石坂の戦い」は何度と無く熾烈をきわめた、大友、秋月の戦いの中でも、この穂波郡内(穂波郡は、古くは穂波屯倉・ほなみのみやげ、と云った)最大規模の戦いと言っていい。
多くの者が討ち死しそれを弔った「千人塚」が八木山本村に、残されている。
筑後国生葉郡井上城「問註所鑑景」は従来大友に従っていた、しかし
秋月種実が力つけ大きくなると「種実」に通じる。
この事態に同族
「問註所統景」は大友に救援要請。
豊後より「朽網統暦」が到着する。
これを支援し、秋月の兵力を分散撹乱するため「道雪、紹運」の両将は「初陣の統虎」へ伴い鞍手より「嘉麻・穂波」方面に軍を進めたのである。
ところが「朽網」は突然豊後へは引き返えしてしまう。秋月種実も井上城へと篭る。
憤懣やるかたない
「道雪・紹運」は、秋月の領地、飯塚片島、潤野、大日寺一帯に火を放ち蹂躙する。これに「種実」は、急遽兵五千騎あまりで大友軍を追討する。
この合戦に初陣の「統虎」のいでたちはまさに「武者絵」を見る如くであった。
煌びやかな唐綾縅の鎧、前立て勇しく兜の緒をきりっと締め、金象嵌に鹿皮の尻鞘の太刀を佩き、矢筒背高に負い塗籠めの強弓手に、栗毛の駿馬に乗り凛々しい武者姿であった。
この戦いの発端は前記の如く、鞍手方面から打って出た「戸次道雪、高橋紹運」勢が、飯塚、嘉麻一帯を蹂躙したことに端を発した。
追討してきた「秋月」勢に大友勢は激しく襲い掛かり序戦は、大友勢は秋月の首級三百を挙げる。
初陣に臨んだ統虎は、馬を下りると何を思ったか「自分についてくる者は来い」と紹運の本陣より三町も離れて陣を構えようとした。驚いた統虎の傅役(もりやく)「有馬伊賀守」は「本陣を離れては敵に付入られ危ない、紹運さまの陣へお戻り下さい」と諫めた。
これに統虎は「敵が大勢でも如何ほどのことはない、父と一緒に動いては、我に従う者も父の勢と共に進退して、我の下知には従わなぬではないか。
ここは、我の計りごとに任せよ」これに傅役(もりやく)伊賀守は「この機あって戦慣れした者でさえ考えもつかぬ事、年端も行かぬ初陣の者にしては人並みを勝れた知略である、天性の武将の才能を備えておられる。
ここは「統虎様」の計略通りいたそう」と百五十騎ほどを統虎につき従った。
戦いは熾烈を極めた。
建花寺川(けんげじかわ)の谷筋の急坂を攻め上がって来た秋月勢に「紹運」は至近まで引き寄せ、一斉に「鉄砲」「弓矢」を撃ちかけたので、秋月の先鋒が次々倒れ先陣の七百が怯んだ。
これに「紹運」機今と自ら大太刀振るい切り込んだ。
秋月勢はこの「高橋勢」の勢いに石坂下に落ちる。(現在も、石坂の下あたりを坂の下という)
これに秋月の二陣壱千騎が犇めき合って攻上ってきた。
「紹運」も更に気力振るって切りまわる。
そこへ静かに伏せていた「統虎」の一五〇騎は秋月の横を突いて打って出た。秋月の後陣参千も攻め上がり、紹運の千五百との間に激しい合戦となった。
双方に戦死者も増えた。この状況の中、初陣「統虎」は鎧を揺るし秋月雑兵を倒すが秋月勢が群がるように統虎に迫っていた。
有馬伊賀守も必死に統虎を守ろうとするが自身も方々に太刀傷受けていた。
この有馬へむけ秋月の剛の者「堀江某」なる者が討ち懸ろうとした。
これに気付いた統虎、強弓に矢を番え「堀江」に向け放つと、矢は堀江の利き手に見事命中、子供の頃から小鳥も射落としたという統虎の弓の腕は確かであった。
それでも手負いの「堀江」秋月でも名を為す兵(つわもの)「統虎」に組討で懸る。
しかし体力に勝る統虎はこれを一気に取り押さえる。
そこを統虎に従っていた「萩尾大学」が首級上げる。
戦いは、「戸次道雪」の伏せ兵壱千余りが林から一気に懸ったので秋月勢は総崩れとなって敗走する。
この「秋月種実」に「
戸次道雪・
高橋紹運」初陣の「統虎」の争った「
八木山石坂の戦い」、大友三〇〇、秋月七六〇、併せ壱千体越える戦死者だす壮絶な合戦であった。
中でも、「統虎」は知略のある陣立で軍勢を調え「初陣」を存分に戦い、優れた武将としての片鱗をみせた。
翌年「立花統虎」と姓を改め、以後戦国の世を戦い抜く。
八木山石坂古戦場について
中世八木山とは、現在「千人塚(皐月GC:竜王コース近く)」のある本村付近を指した。
筑前続風土記によれば八木山氏と云う地頭がいたようである。
当時、この付近は人里遠く山深いところであった。
篠栗へ下る直前に山伏谷という所があるが、この地名の由来は、この辺りに山賊が出没し、山伏せを殺していた事に由来すると言う。
風土記には「石坂は八木山村の東にあり」とある。
嘉摩、穂波郡の諸村は眼下にあって佳景、田河郡(田川)まで見通せることが書かれている。
筑前続風土記に「石坂の戦い」は書かれていないが、石坂を取り上げて書いた事は、当時からこの場所が大変な通行の難所であった事が覗える。
只、筑前国続風土記の書かれた頃の「石坂」が今日と同じであれば、石坂は黒田長政の入国後「黒田如水」によって開かれたと路筋と言う。
元の路は「北方の山さがしき所にありて」とあって、「人馬のわづらひおおく」とあり、このためこの難所を避け、如水が今の石坂を開いたのである。
石坂の上には茶屋があり、如水の逗留した茶屋は、代々年貢が免除されたという。
いまある「茶屋」の地名はその名残り。
当時は二本の松ノ木があったと書いているが、今残っていないようだ。
風土記の記述が正しいとすれば、戦国時代の路は今の石坂より北、飯塚へ流れる建花寺川の上流谷筋(蓮台寺)から山に取り付き、鎮西カツラの木のある辺りの上尾根を迂回したと見られる。
(当時も建花寺川と呼んだかは分らないが、川の名称は中世は違って居た。
遠賀川は、このあたりは「嘉麻川、下って直方川、更に木屋瀬川、と呼んだ)仮に、激戦地がこの戦いの戦死者埋葬した「千人塚」の説明板の記述にあるように「八木山展望台」辺りだとすると、合戦時ここは大変な急斜面、比高もあり攻め上がるは相当困難である。
こうして地形を見ると「石坂」と言っても、直接その場所指すのではなく、主戦場は十数町北の山地から、千人塚にかけてと見られ、石坂はその総称ではなかったか。
この戦いの戦死者葬った「千人塚」の位置からして、急坂急崖を千体もの死体集め、三十町も離れている所まで運び埋葬したとは思えない。
八木山氏宅址と八木山殿墓
八木山の老松神杜の杜地前に八木山氏の宅址という所があり、中村に八木山氏の先祖の墓という所がある。
墓という所は高さ60cmで1.5m四方の盛り土に小さい祠がたっている。
土地の人は地主様といっている。
(私が行ったときは、見当たらなかった・・口枯れたのか・新しく立ち代ったのでは?)
八木山千人塚(鎮西村誌)
天正年間筑前国は、豊後大友氏の立花城「戸次道雪」、岩屋城「高橋紹運」と筑前筑後の諸将との対峙が熾烈を極めていた。
その中でも「秋月種実」は弘治三年七月十九日(一五五七)「戸次鑑連」率いる大友軍に古処山を攻められ父「文種」が自刃に追い込まれる。
当時十三歳の「種実」は家臣に守られ、かろうじて逃れ中国「毛利元就」のもとへ逃れる。
天正に入り(天正四年前後)「種実」は古処山城を奪回帰参する。古処山に戻った「種実」は、父の仇敵大友に常に対峙、休松、柴田川、八木山、岩屋、立花など各地で大友軍と戦う。
天正九年十一月「戸次道雪・高橋紹運」は大友に反旗した筑後国生葉軍井上城「問註所鑑景」をめぐって、支援する「秋月種実」を撹乱するため、五千騎にて秋月領「嘉麻」「飯塚」に討って出る。
大友勢は「潤野」「大日寺」一帯に火を放ち、稲穂を刈るなど蹂躪。
これに秋月種実は同じく五千騎で追跡。
篠栗と飯塚の間「八木山石坂」で「紹運」「秋月」が激戦となる。
その中「道雪」の伏せ兵千騎が秋月勢に襲いかかり、秋月勢は総崩れとなった。
この戦いを「八木山石坂の戦い」または「八木山村古戦場」という。
この合戦の戦死者、秋月七百六十、大友三百、あわせ千人を越えた。
「千人塚」は「石坂合戦」で戦死した両軍の死体を集め葬った所と言う。激戦地は三十町ほど東「石坂」とされるが、このあたりも主戦の激戦地であったのではないか。
古戦場の近くには様々に戦死者を弔う塚や地蔵塔があるが、この「千人塚」は 実数で千体を埋葬したか分らないが、まるで古墳の様に丘陵をなし大きい。
恐らく延長は四〇m近く、幅も二五m高さ7~8m近くある。戦国のものとしては九州では一番大きな塚であろう。
八木山とは古くはこのあたりを指していた。
異説:石坂の戦い「八木山村古戦場」
この項は別途「石坂の戦い(統虎初陣)」にて紹介した「戸次道雪、高橋紹運」「秋月種実」の争った石坂八木山合戦を「筑前国続風土記・巻之二十五」版をもとに書き上げたものである。
この戦いの発端は、大友氏旗下筑後井上城「問註所鑑景」が秋月に寝返ったことから、同長巌城城主で一族の「問註所統景」救援に「大友宗麟」が豊後直入郡山野城「朽網宗暦」を派遣したことに起因する戦いである。以下「風土記」を読み替え一部書き足した。
中世、筑前国穂波郡八木山村は「上村・下村」の二村に分かれていた。
その「上村」に「城ガ尾」と云う山がある。
この山は南方の高山である「龍王嶽」に続く低山である。(こん日この山の場所は、はっきりとはしない、風土記の文面より、現八木山小学校の南あたりに位置しているようである)
天正の頃「立花山城」の戸次氏の軍勢が「城ガ尾山」へ取上り占拠したので「秋月種実」の軍勢が責めて来たのだという。
これに「薩摩勢」も援軍出し戦ったが、この合戦で双方に多くの兵が討ち死を出した。
その死骸を埋めた場所が「城ガ尾」の西にあって、今も「千人塚」と呼んでいる。
天正九年十一月、豊後大友家の軍勢が筑後国生葉郡に侵入撃ち出た折「秋月種実」はこれを迎え撃つため、上座郡(かみつあさくら)に出張って対峙するとの情報が「道雪、紹運」の下へ入った。
これに立花山城の「戸次道雪」岩屋城「高橋紹運」は、両家の軍勢併せ都合五千余騎を引き連れ、秋月の軍勢を遮り分断させるための撹乱作戦に出たのである。
両将は秋月領内深く、嘉麻郡飯塚片島辺りまで押し入り、周辺悉く火を放ち焼き払い蹂躙した。
しかし対抗する秋月勢との出合いは無かった。
天正九年十一月六日やむなく、道雪、紹運の両将は嘉麻より一旦陣を引くこととした。
一方秋月方は「種実」が上座(かみつあさくら)に出陣中、留守のこともあって「道雪、紹運」両将相手に、平な場所での戦いは勝算は望めない。
敵が引く時山道の狭い切岸や、陣形のままならぬ場所に追い懸けて討ち取るべく、兼ねてより秋月旗下の臼井、扇山、茶臼山、高の山、馬見山の各城代共と僉議(せんぎ)を重ねてあった。
このため、秋月方はたちまち五千余人が集まり「戸次、高橋両軍」勢の引きいく跡を追い懸けて行った。
しかし「道雪、紹運」は少しも騒がず、敵に構うことなく「足軽」共を殿(しんがり)に立て、遠矢を放ち秋月勢の付け来るの防ぎ、静々(しずしず)引き退いていった。
これを見た秋月勢は、俄かに競うように追討してきた。
「道雪、紹運」は八木山の東の坂にて(石坂を指すと見られる)、先陣・後陣、一気に取って返し突き懸けていった。
秋月旗下の士たちも、暫くはこれを支えて戦っていたが、終に(遂に)こらえられず坂下へと引き落ちて行くところを「道雪」「紹運」の軍勢はこれを追い詰め、穂波郡の土師(はじ・現嘉穂郡桂川町土師)まで凡そ三里余(一二km余 それにしても「道雪、紹運」両将にしては、何故これほど敵領地の中深追いしたのであろうか)追い詰めた。
この間、秋月勢は一度も押し返すことが出来ず、「道雪、紹運」は敵首二百三十あまりを討ち取った。
「道雪、紹運両将」も今はこれまでと、閑(しずかに)引き返そうとした時。秋月(距離からして、おそらく古処山城、又は小石原城)」にいた留守居の家老達が、この事態を聞きつけ、上野四郎右衛門、坂田市之丞、井豊前、城井、長野、上原らの勢五千余人が、上座出陣に催促され着陣を終えたばかりであったことから。秋月の家老達はこれを引きつれ、臼井坂を打出し、屋山原(弥山原・現飯塚市弥山)より「土師」に至っていた
「大友軍」の横合より突き懸っていった。
これを見て、引きかけていた秋月勢は俄かに力を得て合流、秋月勢都合八千八百余人は一気に、取って返し「道雪、紹運」勢へ反撃を開始した。
これにはさすがの「道雪、紹運」も、朝からの合戦に人馬共に疲れており、対し秋月方は新手が加わり大軍となっていたので、戦いを避け引き退くことになった。
秋月勢は勢いに乗って、引き遅れた大友勢を追い詰め三百余人を討ち取る。
秋月の将「上野」「坂田」は、「種実」に従い長年軍功のある者達で、敵の取っ手返し易い広場では、遠矢、鉄砲を撃ちかけ閑に追い、取って返し難い切所では鬨(とき)を作って討ち懸かった。
これには勇将もって知られた「道雪、紹運」も一度も取って返すことが出来なかった。
しかし、さすがの両将、この後兵を統率糟屋郡へと難なく引き上げたのである。
秋月勢も今はこれまでと、八木山より引き返し追討した首四百余りを八木山村の東の嶺に切りかけて秋月へと引き上げた。
城ガ尾」「千人塚」とはこの時のことである。
参考資料 筑前続風土記
筑前戦国史・引用 吉永正春 著
日本図誌大系 九州 Ⅰ