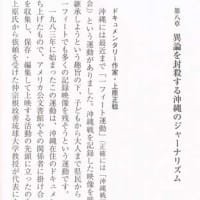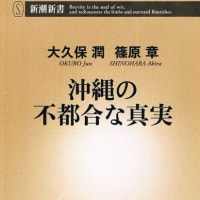「百度(モモト)踏み揚がり」の本当の意味
さて、今日は読者も芝居などで良くご存知の15世紀の悲劇の女主人公「百度踏み揚がり」(ももとふみあがり)を解明しよう。
「おもろ」に登場する名前だが、「珍妙な意味の長すぎる名前」だ。「おもろさうし」には「ももと、ふみ、あがり」と三つの言葉からなることが示されている。梵語辞典には「ももと」と結びつく表記はない。だが、諦めるには早過ぎる。ウチナー風に「ムムチュ」と発音してみると、あった!「mumucu」が出てくる。意味は「聖仙の名」つまり「ムムチュ神」のことだ。
「ふみ」は「bhūmi」ブーミすなわち聖地。「あがり」は「agrya」アグリャすなわち「最高の」だ。サンスクリットの修飾語は前に置いても、後ろに置いてもよい、というかなり自由なものである、ということを知っておこう。
この三つを組み合わせれば「mumucu bhūmi agrya」ムムチュ ブーミ アグリヤすなわち「最高の聖地の女神」となる。
「百度踏み揚がって、最後に天辺から落ちて死ぬ」なんて「土俗」な名前ではなかったのだ。
「むむと、ふみ、あがり」とは「最高の聖地の女神」のことであり、歴史に登場するにふさわしい名前だったのだ。
尚泰久の娘 ムムチュ ブーミ アグリャ「最高の聖地の女神」が嫁いだのが「勝連」(かっちん)の「きむたかの阿麻和利」だが、勝連(かっちん)は「khacārin」(カチャーリン)すなわち飛ぶ鳥、あるいは(空中の守護神)を起源とする。「きもたか」を胆高とわかったようでわからない解釈が定着しているが、「きもたか」は実は「cintaka」(チンタカ)で「思慮深い」を意味する梵語だ。「阿麻和利」についてはもう少し研究が必要だから、ここでは述べない。
長らくお待たせしました。許(ユル)ちうたびみそーれー。アッと驚く梵語の研究を再開します。先ず初めに、数人のお互いに関係のない人たちから梵語を起源とするウチナー口の講座を開いてほしいとの要望が出てきました。今、そのつもりで動き始めたが、どれだけの人たちがどのような講座を望んでいるのか知ることが先決だ。提案があれば遠慮なくメールで申し出てください。
メールは
タイトルに「ウチナー口」と入れて下さい。
uehara.shonen69■gmail.com
■は@に置き換えてください。迷惑メール防止のための処置です。
上記メールアドレスに対し、営業および広告宣伝等のメールを送らないようにお願いします。