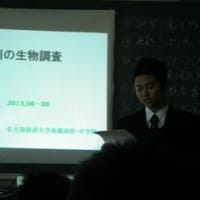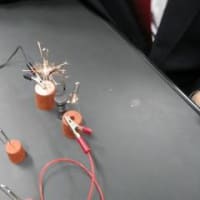11月17日(木)
カイガラムシのきれいな写真が撮れました。
カイガラムシとは、カメムシ目ヨコバイ亜目腹吻群カイガラムシ上科に分類される昆虫の仲間です。
つまり、大きく言うとカメムシの仲間です。
口(ふんという)は、植物に刺すような口になっていて、植物の葉の師管の溶液を吸って生きています。
カイガラムシにはいろんな種類がありますが、今回大発生したカイガラムシはヒラタカタカイガラムシ
と思われます。
オモト、カトレア、カンキツ類、キミガヨラン、シンピジューム、ソテツ、デイゴ、トベラ、バナナ、
バラ、ヤブニッケイなど極めていろんな植物につく昆虫です。
卵嚢を作らず産卵された卵はすぐに孵化します。
雄は見られず、雌だけで発生します。
テントウムシやヤドリコバチの仲間が天敵で、自然ではこの天敵がカイガラムシの大発生を抑えています。
しかし、職員室の中は天敵が侵入することも少ないために大発生したのだと思います。
成虫は体長3~4mm。日本では主に温室害虫の仲間だと言われています。

コチョウランの葉の左上に茶色い楕円の物体が付いています。
これがカイガラムシです。

拡大するとこのようになります。
カイガラムシの左下を見ると、葉から蜜が出ているのがわかります。
これは、カイガラムシをふきっとた後から出てきました。
つまり、カイガラムシが葉の師管の中の糖分を主食にしている証拠です。

マクロモードで写真を撮りました。
脚のような模様が分かるでしょうか。
これで虫の仲間だと言うから驚きです。
カイガラムシのきれいな写真が撮れました。
カイガラムシとは、カメムシ目ヨコバイ亜目腹吻群カイガラムシ上科に分類される昆虫の仲間です。
つまり、大きく言うとカメムシの仲間です。
口(ふんという)は、植物に刺すような口になっていて、植物の葉の師管の溶液を吸って生きています。
カイガラムシにはいろんな種類がありますが、今回大発生したカイガラムシはヒラタカタカイガラムシ
と思われます。
オモト、カトレア、カンキツ類、キミガヨラン、シンピジューム、ソテツ、デイゴ、トベラ、バナナ、
バラ、ヤブニッケイなど極めていろんな植物につく昆虫です。
卵嚢を作らず産卵された卵はすぐに孵化します。
雄は見られず、雌だけで発生します。
テントウムシやヤドリコバチの仲間が天敵で、自然ではこの天敵がカイガラムシの大発生を抑えています。
しかし、職員室の中は天敵が侵入することも少ないために大発生したのだと思います。
成虫は体長3~4mm。日本では主に温室害虫の仲間だと言われています。

コチョウランの葉の左上に茶色い楕円の物体が付いています。
これがカイガラムシです。

拡大するとこのようになります。
カイガラムシの左下を見ると、葉から蜜が出ているのがわかります。
これは、カイガラムシをふきっとた後から出てきました。
つまり、カイガラムシが葉の師管の中の糖分を主食にしている証拠です。

マクロモードで写真を撮りました。
脚のような模様が分かるでしょうか。
これで虫の仲間だと言うから驚きです。